- 領収書
領収書はもう紙で保管しない!電子保存のメリットや注意点、手順を解説
公開日:
更新日:
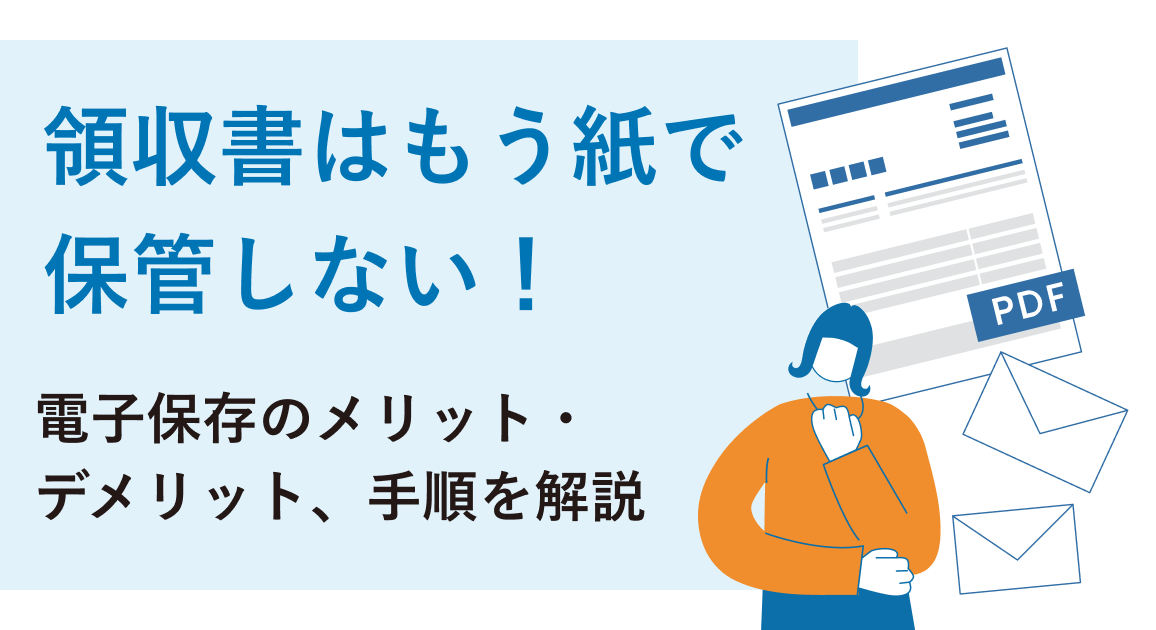
領収書の保管、もう紙で管理するのは限界…と感じていませんか?
保管スペースの問題、紛失のリスク、検索の手間など、紙での領収書管理には多くの課題がつきまといます。
そこで近年注目されているのが、領収書の電子保存です。
電子保存によって、業務効率化、コスト削減、セキュリティー強化など、多くのメリットを享受することができます。
本記事では、電子帳簿保存法の解説や具体的な電子保存方法など、領収書電子保存に関する情報をわかりやすく解説します。
領収書の電子保存に対応!経費精算システム
領収書の電子保存とは?
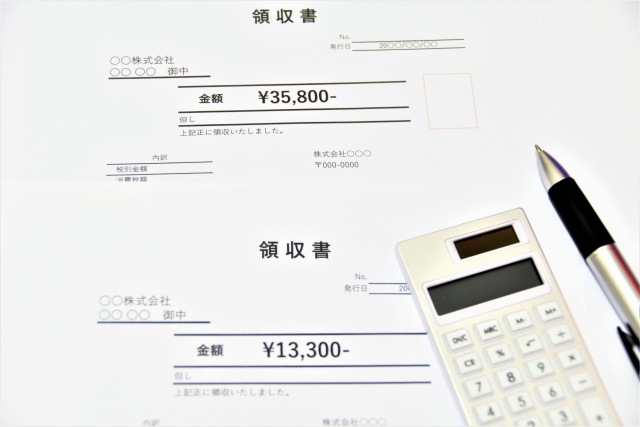
領収書の電子保存とは、紙の領収書をスキャンしたり、電子データで受け取ったりした領収書を、一定のルールに従って電子データとして保存することです。
電子帳簿保存法において、電子保存には「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」という3つの区分があります。
このうち電子帳簿等保存は、会計システム等を利用して作成した帳簿などに関する内容です。スキャナ保存は、紙の領収書をスキャンして、電子データに変換して保存することを指します。電子取引データ保存は、メールやシステム上でのやり取りで受け取った書類の保存に関する区分です。
どちらの形式も、一定の要件を満たすことで法律上有効な領収書として認められます。
領収書を電子保存するメリット

領収書の電子保存には、業務効率化やコスト削減など、さまざまなメリットがあります。ここでは以下の4つを紹介します。
- 業務効率化
- 保管スペースの削減
- 働き方の選択肢が広がる
- その他のメリット
参照:国税庁「電子帳簿等保存・スキャナ保存【令和 5年 11月配信】」
1.業務効率化
電子保存の最大のメリットは、業務効率化です。
受け取った領収書を紙で保管している場合、必要な領収書を探すのに時間がかかることが少なくありません。しかし電子保存なら、キーワード検索や日付・金額での絞り込みなど、さまざまな方法で簡単に検索できます。
また、電子保存では紛失や破損のリスクも軽減できます。紙の領収書は、ついうっかり捨ててしまったり、災害で失われたりする可能性がありますが、電子データなら簡単にバックアップを取っておけるためです。
さらに、電子データは共有が容易なため、経理担当者だけでなく、営業担当者など、必要な人がいつでもどこでも領収書を確認できます。これにより、承認作業や経費精算などの業務フローがスムーズになり、業務効率化につながります。
2.保管スペースの削減
紙の領収書の保管には膨大なスペースが必要です。法人の場合、領収書は原則として7年間の保管が義務づけられているため、年数が経つほど、また取引量が増えるほど領収書の量も膨れ上がり、保管場所の確保や整理整頓に悩まされることになります。
こうした悩みから解放してくれるのが電子保存です。
電子データはほとんどスペースを占有しないため、オフィスのスペースをより有効に活用できます。以前は領収書の保管に使っていたエリアを他の用途に転用することで、業務の拡張につながる可能性があります。
またオフィススペースを効率的に活用できるようになれば、オフィスの縮小や移転といった選択肢も視野に入れることができ、コスト削減効果を期待できます。もちろん、領収書を保管するためのキャビネットやファイルなどの備品購入費も不要です。
3.働き方の選択肢が広がる
領収書の電子保存は、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を実現してくれます。
従来の紙媒体での管理では、領収書の確認や処理のために出社する必要がありました。
しかし電子保存なら、自宅や外出先からでもスマートフォンやパソコンで領収書を確認・承認できるため、テレワークを導入しやすくなります。
また領収書を探す手間や、承認のために書類を回覧する時間が削減できるため、業務効率が向上し、残業時間の削減にもつながるでしょう。
結果として、従業員のワークライフバランスが向上し、より生産性の高い働き方が実現できます。
4.その他のメリット
領収書の電子保存には、ほかにもさまざまなメリットがあります。
税務調査対応がスムーズに
電子帳簿保存法に準拠したシステムを使用して領収書を管理することで、税務調査への対応が迅速になり、法令遵守の負担を軽減できます。
証拠の信頼性が向上
紙媒体に比べて、電子データはデータの履歴を確認できるため、証拠としての信頼性が向上します。
災害時のデータ保護
電子データのバックアップを適切に管理することで、災害時のデータ損失を防ぎ、事業継続計画(BCP)対策として有効です。
環境負荷の低減
ペーパーレス化により紙資源を節約し、環境への負荷を軽減するとともに、SDGsの目標達成にも寄与します。
領収書を電子保存する際の注意点

領収書の電子保存には、いくつかの注意点があります。事前にこれらの注意点を押さえておくことで、スムーズに電子化を進められるでしょう。
電子帳簿保存法への対応
電子帳簿保存法では、領収書を電子保存するための要件が定められています。
たとえば、スキャナ保存の場合、解像度やファイル形式など、細かいルールに従わなくてはなりません。これらの要件を満たしていないと、電子保存が認められず、税務調査などで思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
また企業によっては、電子帳簿保存法に対応するために、新たなシステムの導入や運用が必要です。
領収書の電子保存をする際は、こうしたコストや手間も十分に考慮する必要があります。
セキュリティー対策
領収書には、顧客情報や取引先情報など、重要な情報が含まれている場合があります。そのため領主書を電子保存する際は、情報漏えいのリスクを十分に考慮し、適切なセキュリティー対策を講じることが重要です。
具体的な対策としては、たとえばアクセス制限やデータの暗号化、ウイルス対策ソフトの導入などが挙げられます。
セキュリティー対策を怠ると、情報漏えいが発生し損害賠償や企業の信用失墜といった深刻な問題を引き起こす可能性があるため、十分な注意と対策が求められます。
システム導入・運用
領収書の電子保存には、専用のシステムが必要になることがあります。どのようなシステムを導入するにせよ初期費用やランニングコストが必要なため、予算の確保が欠かせません。
また、システムの運用には専門的な知識が必要になる場合もあります。自社の人材で運用できるのか、あるいは外部に運用を委託するのかなど、運用体制についても検討が必要です。
これらの注意点に加えて、自社の業務フローに合ったシステムを選ぶことも重要です。導入前にトライアル期間を設けるなどして、事前に使い勝手を確認することも重要です。
領収書を電子保存するための要件

領収書を電子保存する際は「真実性の確保」と「可視性の確保」という、2つの要件を満たす必要があります。
ただしこれらの要件は、取引先からどのような形態(電子データ、もしくは紙媒体)で領収書を受け取ったかで異なります。
電子データで受領した場合
電子データで受領した領収書は、電子帳簿保存法に基づく電子取引として扱われます。電子取引の領収書を電子保存する場合、以下の要件を満たすことが必要です。
真実性の確保 | 可視性の確保 |
|---|---|
以下の要件のいずれかを満たすこと
| 以下の要件すべてを満たすこと
|
参照:国税庁「電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 (令和6年6月)」
真実性の確保
真実性の確保とは、電子データが真正なものであることを証明できるようにすることです。
自社や取引先の実態に応じて、上の表にある4つの要件のうち、いずれかを満たすかを決める必要があります。
可視性の確保
可視性の確保とは、保存している電子データをいつでも、速やかに確認できるようにすることです。
すべての企業は、原則として上の表にある3つの要件すべてを満たさなければなりません。ただし検索要件だけは、小規模事業者で、かつ税務職員によるダウンロードの求めに応じることができる場合は不要とされています。
紙媒体で受領した場合
紙媒体で受領した領収書を電子保存することを、スキャナ保存といいます。スキャナ保存には、重要書類と一般書類で異なる要件があるため注意が必要です。
- 重要書類(資金や物の流れに連動する書類)…契約書、納品書、請求書、領収書など
- 一般書類(資金や物の流れに連動しない書類)…見積書、注文書、検収書など
真実性の確保 | 可視性の確保 |
|---|---|
以下の要件すべてを満たすこと
| 以下の要件すべてを満たすこと
|
参照:国税庁「電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】 (令和6年6月)」
真実性の確保
スキャナ保存の真実性の確保には、電子取引よりもさらに細かい要件が定められています。領収書は電子帳簿保存法の重要書類にあたるため、これらの要件すべてを満たす必要があります。
可視性の確保
可視性の確保要件は電子帳簿保存法に基づく電子取引の場合と似ていますが、元となる紙データとスキャンした電子データの関連性を確認できるようにしておく必要があります。
電子保存した領収書を効率的に管理するには

電子保存した領収書を効率的に管理するには、領収書管理サービスの利用がおすすめです。
領収書管理サービスは電子帳簿保存法に対応しており、スキャンデータの保存や検索、承認ワークフローなど、領収書管理に必要な機能が備わっています。
また、データの共有も容易になるため、関係者間での確認や承認作業がスムーズに進み、業務効率化につながるでしょう。領収書管理サービスのなかには自動仕訳機能や会計ソフトとの連携機能など、付加価値の高い機能を備えたシステムもあります。
これらの機能を活用することで、領収書処理にかかる時間を大幅に短縮し、より重要な業務に集中できるようになります。
まとめ
領収書の電子保存は、業務効率化やコスト削減、コンプライアンス強化など多くのメリットをもたらします。
クラウド経費管理サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。
全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。
Bill One経費の特長
- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる
- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結
- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合
- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応
- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止
- カードごとの利用限度額設定が可能
- 1か月あたりの利用限度額が最大1億円
- カードごとの利用限度額設定が可能
- 年会費・発行手数料無料
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください

3分でわかる Bill One経費
立替経費をなくし、月次決算を加速する
クラウド経費管理サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。


