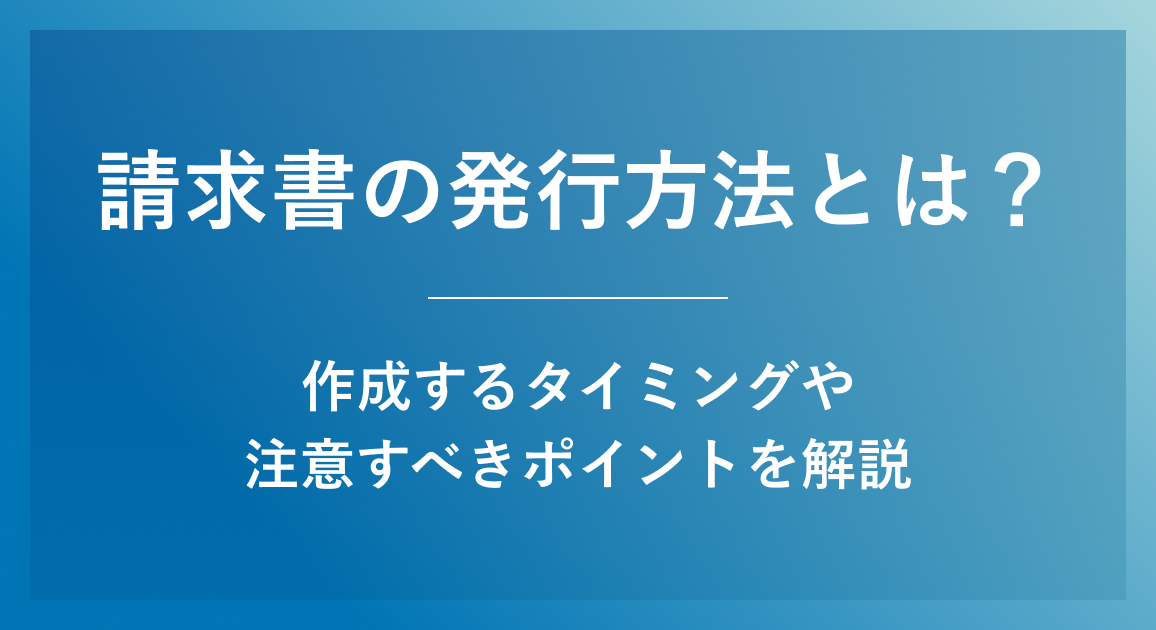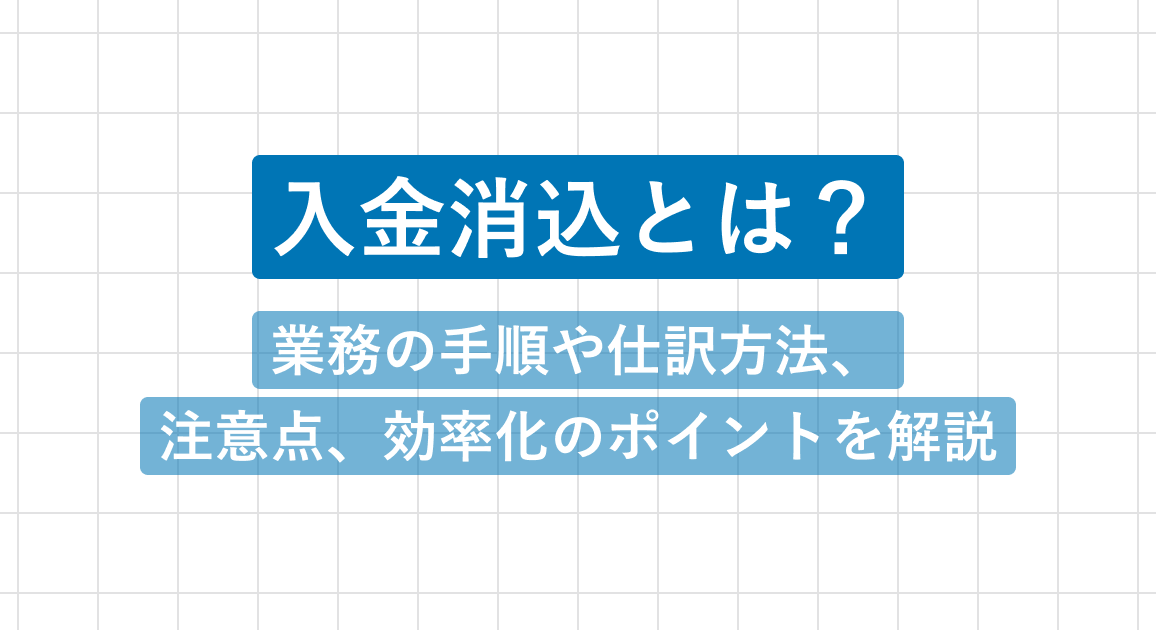- 請求書
請求書払いとは?流れや、請求側・支払い側のメリット・デメリットを解説
公開日:
更新日:
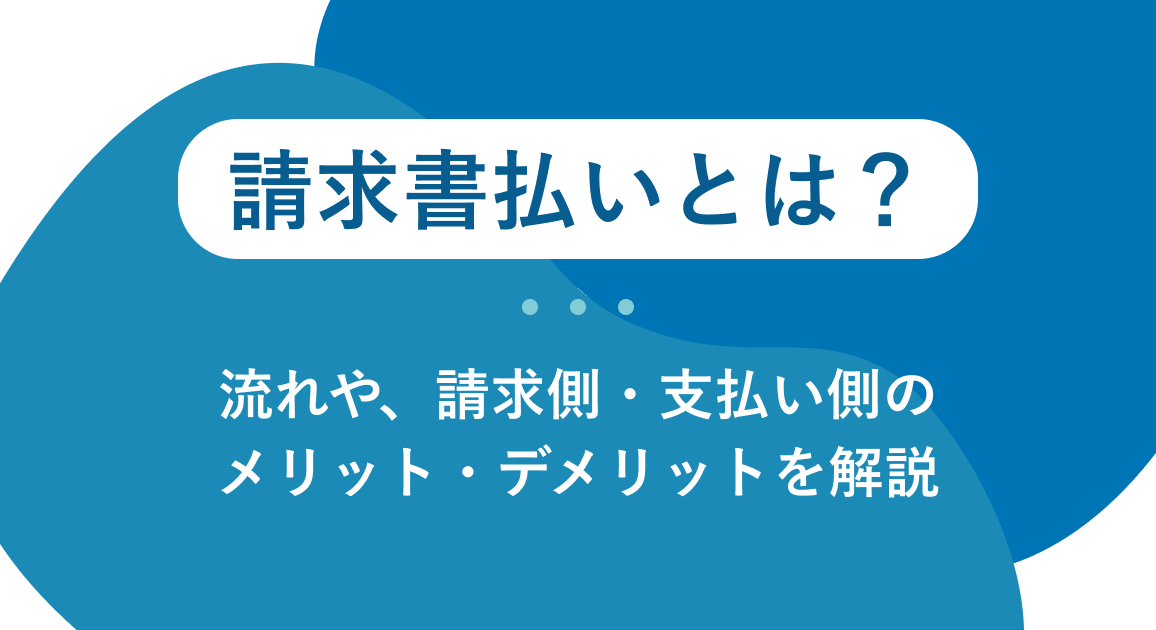
企業などで採用されている「請求書払い」は、請求側・支払い側それぞれにコスト削減や業務効率化といったメリットのある取引方法です。しかし、デメリットやリスクについても理解しておかないと、思わぬトラブルが発生する可能性もあります。
そこで今回は、請求書払いの概要から、作成~支払いまでの流れ、採用によるメリット・デメリットについてご紹介します。合わせて、請求書払いで気をつけるポイントも解説しているので、ぜひご覧ください。
債権管理業務を効率化
請求書払いとは

請求書払いは、商品やサービスを先に提供し、後日設定された期日に代金が支払われる「掛売り」のことで、与信取引の一つです。与信取引とは、取引相手に対して信用を供与し、その信用に基づいて事前に商品やサービスを提供することを指します。
与信取引は互いの信用に基づいて取引が成立するため、未払いのリスクも伴います。そのため、信用関係が構築できていない新規の取引先とは、請求書払いの代わりに料金の都度払いや前払いといった支払い方法が選ばれる場合もあります。
請求書払いは、法人や個人事業主間のビジネス上の取引(BtoB)では一般的な方法ですが、企業と一般消費者との取引(BtoC)においても多く利用されています。例えば、ECサイトの購入代金をコンビニ払いで支払う方法などがそれに当たります。
また、近年では地方税や固定資産税、都市計画税の納付書をスマートフォンで読み取り、オンライン決済ができるアプリも登場しています。一般企業相手ではありませんが、こちらも請求書払いの一種です。
請求書払いの流れ

請求書払いの具体的な流れは、以下のとおりです。
- 与信審査
- 請求書の発行と送付
- 入金消込
- 未入金の催促と代金の回収
それぞれの手順について、詳しく解説します。
1.与信審査
請求書払いが可能かどうかを判断するため、請求を行う企業が取引先の支払い能力を事前に評価します。評価のためには自社で定めた「与信管理規定」に基づく「与信基準」を満たすことが求められます。
与信審査では、取引規模に応じて請求書払いの可否だけではなく、与信限度額の設定も重要です。これは、与信限度額を高くしすぎると不良債権のリスクが増加し、反対に低く設定し過ぎると良い取引機会を逃し売り上げが減少する恐れがあるためです。
取引先の事業成績や市場シェアを定期的にチェックし、未回収リスクがなく、かつ取引の機会を最大化できるよう、慎重な審査を行いましょう。
2.請求書の発行と送付
商品・サービスの納品後に請求金額が確定したあとは、請求書を作成します。請求書の必要項目は以下の通りです。
- 書類作成者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
- 請求書番号
- 振込先(振込先の口座情報・振込手数料なども記載)
- 支払い期限
※適格請求書を発行する場合には登録番号などが必要
請求書には決められたフォーマットはありません。ExcelやWord、会計システム、もしくは手書きのいずれでも作成できます。作成後は、記載内容に漏れがないかを確認して、発行・発送しましょう。
3.入金消込
期日内に代金を回収したら、入金消込を行います。これは、請求書と入金額の一致を照合し、正確な債権残高になっているかを確認する作業のことです。
入金消込はExcelで管理するのが一般的ですが、取引数が多くなると目視による作業が複雑化し、手間がかかります。そのため、業務の効率化を目的として、入金消込の工程を自動化しているケースもあります。請求書払いをはじめとする後払い制度では、取引時には売掛金として処理され、代金回収と同時に入金消込で正確な入金と債権残高を確認することで、業務の効率化を図っています。
4.未入金の催促と代金の回収
期日内に入金消込が完了しない場合には、取引先に対して催促や代金回収を行います。
まずは取引先に支払い意思の有無を確認することが大切です。入金忘れや請求書の紛失のような簡単なケースであれば、営業担当から取引先に連絡を取ることで迅速に解決することが多いでしょう。しかし、取引先の財務状況が悪化したり、悪意のある不払いに発展したりするケースもあります。その際には支払い督促や差し押さえなどの法的手続きが必要です。
取引先の信用評価と与信限度額の決め方

請求書払いを始めるには、取引先の信用調査・与信限度額の設定が必要になります。
ここでは、どのように行うのかについて解説します。
定量分析と定性分析の実施
取引先の信用評価をする際には、「定量分析」と「定性分析」の2つの観点から行うことが重要です。
定量分析では、公開されている財務諸表や企業の売り上げデータなど、具体的な数字を基に評価を行います。定性分析は、企業の評判や経営者の姿勢、将来性といった数字に表れない要素を見極めることが目的です。
これら2つの分析を組み合わせることで、取引先の信用状況をより正確に把握できます。片方だけでは偏った見解になりやすいため、バランスよく評価を進める必要があります。
ビジネスモデルのチェック
取引先の信用評価を行う際には、ビジネスモデルの分析も欠かせません。単に事業内容を確認するだけでなく、仕入れや販売の方法も確認しましょう。また、業界特有の商習慣がある場合は、そちらも考慮することが重要です。
特に初期投資が大きいビジネスモデルでは、収益化までに時間がかかる可能性があるため注意が必要です。取引先のビジネスの安定性や将来性を総合的に評価しましょう。
与信限度額の設定方法について
与信限度額を設定する際には、業務に必要な取引額を設定する一方で、リスクも慎重に考慮しなければなりません。自社の利益を守るためにも、無理のない範囲で確実に回収できる額に設定することが重要です。
適切な与信限度額を見極めるには下記を確認します。
- 取引先の純資産
- 取引先の仕入れ債務(買掛金、支払い手形の額)
- 自社の売掛債権
請求書払いのメリット

請求書払いのメリットについて、請求側と支払い側、それぞれの立場から紹介していきます。
【請求側】請求書払いのメリット
請求側目線での請求書払いのメリットには、以下のようなものがあります。
- 決済業務を効率化できる
- 販路の拡大が期待できる
決済業務を効率化できる
請求書払いには決済業務を効率化し、会計処理のミスを減らすメリットがあります。
一定期間ごとの一括支払いのため、請求書と回収確認をまとめて処理することができ、決済業務が効率化されます。
業務負担が軽減されることにより、経理担当者の心的負担の軽減、業務精度の向上も期待できるでしょう。請求書払いの導入は、自社・取引先双方の決済業務を簡単にし、効率化に寄与します。
販路の拡大が期待できる
掛売りを主な取引方法としている企業は多いため、掛売りを導入することで販路の拡大が期待できます。
実際に商品やサービスの納品後に支払い期日が設定されていることが、請求書払いの特徴です。買い手は支払い期日までに資金を準備すれば良いため、資金不足でも取引が可能になります。売り手にとっては現金取引のみよりも買い手を増やすチャンスが広がるのです。
【支払い側】請求書払いのメリット
支払い側目線での請求書払いのメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 計画的な資金運用が可能となる
- 支払い業務が効率化できる
- 事業成長の機会を得られる
計画的な資金運用が可能となる
支払い側からみた請求書払いのメリットの一つに、資金管理をより計画的に行えるという点があります。
現金払いのような都度の取引で支払う必要がある場合、毎回資金状況をチェックする必要が生じます。しかし、請求書払いでは一定期間の取引を一括で支払うため、一度の資金確認で済みます。加えて、納品から支払い期日までの猶予期間があるため、資金繰りに余裕を持たせることが可能です。
支払い業務が効率化できる
請求書払いは、あらかじめ定めた期間中であれば、何度取引を行っても支払いを一度にまとめられるので、支払い業務が効率化されます。経理作業の手間を大幅に削減できるとともに、銀行振込で支払いをする場合は振込手数料などのコストを削減することもできます。
事業成長の機会を得られる
先にも挙げたように、請求書払いは支払い期日までの猶予があります。そのため、資金不足でも大規模な取引が可能です。
現金払いでは資金が手元にない場合、事業の成長に必要な大きな投資ができません。しかし請求書払いなら自社の資金繰りと支払い期日を考慮しつつ、資金がない状態でも成長につながる取引が行えます。
請求書払いのデメリット
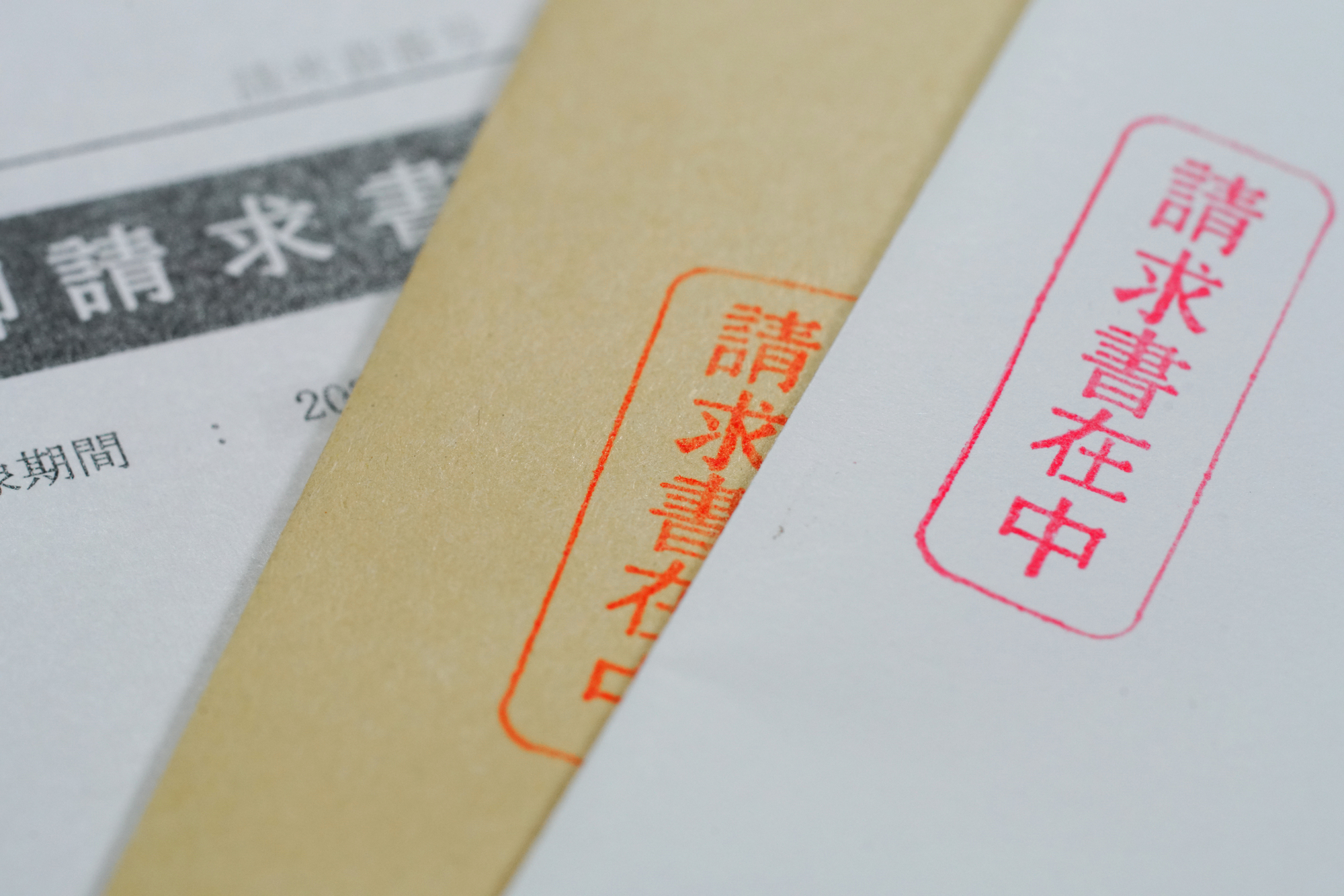
前述の通り多くのメリットがある請求書払いですが、効果的に活用するためには、デメリットについても知っておきましょう。
請求書払いのデメリットについて、請求側と支払い側、それぞれの立場から紹介します。
【請求側】請求書払いのデメリット
請求側目線での、請求書払いのメリットは以下のとおりです。
- 債権回収が不可能となるリスクがある
- 資金繰りに悪影響が及ぶ可能性がある
債権回収が不能となるリスクがある
後払い制度である請求書払いには、債権回収が不能となるリスクがあります。決済をその都度行わないため、取引先が経営不振などに陥れば未回収が発生し、大きな損害につながります。
このリスクを管理するために欠かせないのが、与信審査の徹底です。未回収の場合の資金繰りへの影響や貸し倒れリスクも考慮し、自社での請求書払いの厳格な基準を設けることが大切です。
資金繰りに悪影響が及ぶ可能性がある
請求書払いは、納品直後にすぐ代金を回収できるわけではないため、自社の資金繰りに影響を与える恐れがあります。特に資金に余裕がない企業が支払い期日の入金を前提に計画している場合、入金の遅延や回収不能が経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、資金繰りに課題を抱える企業は、保証金の受領や請求書払いの基準を設けるなどの対策が必要です。実際に、リスク回避のために取引先企業の規模や資本金次第では、請求書払いを認めない企業もあります。
与信審査などの負担が大きい
請求書払いにおいて、取引相手の信用を確かめるためには与信審査が不可欠です。しかし、与信管理には多くの時間、労力、費用がかかり、そのすべてが請求する側の負担になります。
加えて、審査後に取引が成立しないケースもあります。その場合は、調査に投じた手間やコストが回収できないため、これもデメリットの一つといえるでしょう。
【支払い側】請求書払いのデメリット
支払い側目線での、請求書払いのデメリットは以下のとおりです。
- 支払いの遅延・漏れにより信頼性を失うリスクがある
- 取引が中断される場合がある
- 与信審査の受け入れが発生する
支払いの遅延・漏れにより信頼性を失うリスクがある
請求書払いでは商品やサービスの納品後、支払い期日までの期間が存在します。この間に請求書を紛失したり、支払い日を忘れてしまい、遅延が発生したりする可能性もゼロではありません。
頻繁な支払い遅延は取引先との信頼関係を損ね、取引停止につながるリスクがあります。請求書の管理と、期日内の支払いを徹底し、取引先との信頼関係を維持しましょう。
取引が中断される場合がある
取引相手の方針変更により、予期せず取引が中断することがあります。請求書払いは信用に基づく取引であり、先に挙げたように請求側には債権回収が不能となるリスクがあります。
これに対応するため、企業は取引相手の選定に特定の基準を設けることが多いです。特に、個人事業主のように取引条件が変更されやすい場合は、取引停止のリスクが大きいといえるでしょう。請求書払いに大きく依存している企業は、サービス利用の中断により大きなダメージを受けるため、予備の計画を準備しておくことが重要です。
与信審査の受け入れが発生する
企業によって異なる与信調査では、調査員が直接会社を訪問し、業務や設備、経営状況を確認したり、決算書類の提出を求められたりすることがあります。
これらの手続きに時間を費やしても、最終的に契約が拒否されたり、取引の不成立、取引額を下げられたりする可能性などがあります。
与信審査に対する心理的な抵抗や取引不成立による自信の喪失も、請求書払いのデメリットといえるでしょう。
請求書払い以外の支払い方法

企業間の取引では請求書払いが一般的ですが、他にどのような支払い方法があるのかを確認しておきましょう。
口座振替
口座振替は、銀行口座から自動で代金が引き落とされる便利な支払い方法です。賃貸料や公共料金など、継続して利用するサービスでよく使われています。
この方法を用いることで請求側は代金を確実に回収でき、請求業務に時間をかけずに済みます。また、長期利用者を確保しやすくなる点もメリットです。支払う側も口座に残高があれば入金の手間が省け、クレジットカードの登録も不要です。
しかし、請求側には手続き開始や入金に時間がかかるというデメリットもあります。支払う側は振替日前に口座に十分な残高を確保しておかないと、未入金扱いになることがあります。
クレジットカード決済
クレジットカード決済は、個人取引でよく使われる一方で、最近では企業間取引でも少額の取引を中心に利用が増えています。
この方法には請求側・支払う側双方にメリットがあります。請求側にとっては、代金を確実に回収でき、請求業務の効率化が図れます。支払う側は、購入後すぐに支払いを行わずに済み、経費の一元管理やポイントの獲得も可能です。
その反面、デメリットもあるので注意が必要です。請求側はクレジットカード加盟店になる必要があり、決済手数料が発生します。支払う側はカードの限度額が決まっているため、高額取引には不向きです。
請求書の未払いが起こる3つの原因

取引先が増えると、請求書の未払いが発生することがあります。請求書に対して未払いが発生するのは下記の3つの原因があります。
- 自社側の手違い
- 取引先のミス
- 意図的な支払い遅延
それぞれについて解説しましょう。
理由1.自社側の手違い
請求書の未払いが発生する原因の一つは、自社側のミスです。例えば、経理が受注を正しく把握しておらず、請求書を送っていなかったり、誤って別の取引先に送付してしまうケースがあります。また、支払い期日を誤って記載することも未払いの原因となります。
代金が入金されていないからといって、すぐに取引先に問い合わせるのは適切ではありません。まずは、自社の手違いがないかを確認しましょう。
理由2.取引先のミス
取引先のミスによって請求書が未払いになることがあります。例えば、支払い期日を勘違いしていたり、請求書が正しい部署に届かず処理されなかったり、誤って請求書を捨ててしまうケースなどが考えられます。
このような取引先側のミスが判明した場合は丁寧に催促し、いつまでに入金できるかを確認することが大切です。請求書の書式が分かりにくかったり、期日が明記されていなかったりするなど、請求側にも問題がある可能性もあるため、高圧的な態度は取らず、冷静で真摯な対応を心がけましょう。
理由3.意図的な支払い遅延
取引先が資金繰りに苦しんでいる場合、意図的に支払いを遅らせることがあります。また、経営が悪化して債権が回収できない「貸倒れ」に至ることもあります。
こうした状況に対応するには、早めに催促を行うことが大切です。倒産や資金ショートが発生してからでは、手遅れになります。中には、督促を何度行っても支払いがなく、事務所を訪問したら既に閉鎖されていたという例もあります。悪意を持って支払いを拒む企業も存在するため、取引前に与信管理を徹底することが重要です。
未払い請求書に対する催促手順

貸倒れが発生すると企業にとっては大きなダメージとなり、取り戻すのは容易ではありません。そうした状況を防ぐためにも、請求書に対して未払いが発生した場合の対処法を確認しておきましょう。
- 自社の確認作業を行う
- メールや電話で催促する
- 正式な催促状を送る
- 督促状を送付する
- 法的措置を検討する
STEP1.自社の確認作業を行う
未払いの請求書に対して催促を行う前に、まずは自社側で確認作業を行うことが重要です。請求先の間違いや、請求内容の不備、請求書の送付忘れなど、自社側のミスが原因で未払いが発生している可能性があります。
取引先によっては請求書が正しく受理されないと支払いができないルールを設けている場合もあるため、請求書が自社へ届いているか、内容に誤りがないかを確認する必要があります。
また、取引先からのクレームが原因で支払いが滞っているケースも考えられます。こうした場合に催促を急いで行うと、さらに状況を悪化させる恐れがありますので、まずは慎重に問題の有無を確認してから適切な対応を取ることが大切です。
STEP2.メールや電話で催促する
未払いが確認できたら、次に取引先に連絡を取って催促を行います。メールや電話などでコンタクトを取り、未払いの理由について確認しましょう。
連絡方法は、状況に応じて最適な手段を選ぶことが大切です。ただし、電話では履歴が残らない可能性があるため、証拠として残るメールでのやり取りがおすすめです。
取引先の事情によっては、話し合いの上で新たな支払い期日を設定するなど、対応を検討しましょう。
STEP3.催促状を送る
期日までに代金が支払われない場合は、催促状を送付します。催促状には、「〇月〇日までに未払い金の支払いをお願いします」といった具体的な支払い期日を明記しましょう。催促状は正式な書面として扱うため、社印や角印を押します。
催促状を送付することで、未払い債権に対して催促をしたという事実を残すことが大切なので、簡易的な方法でも問題ありません。
STEP4.督促状を送付する
支払いが催促状の期日までに行われない場合、次のSTEPとして督促状を送付します。催促状と督促状は似ていますが、督促状はより強い警告を含む書面です。この際には「〇月〇日までに支払いが確認できない場合、法的手続きを取らせていただきます」といった明確な期限と措置を示す文言を含めましょう。
また、督促状は内容証明郵便で送付することが重要です。郵便局が送付の事実と内容を証明してくれるため、裁判に発展した場合でも有利に働きます。
STEP5.法的措置を検討する
代金未払いが続き、再三の催促にも取引先が応じない場合、法的措置を検討する必要があります。これは取引先との関係に大きな影響を与えるため、慎重に判断するべき最終手段です。
一般的な法的措置としては、支払い督促や民事調停の申し立て、さらに強制執行や少額訴訟などの手段が考えられます。どの手段を選ぶかは状況に応じて適切に判断し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
請求書払いで請求側が気を付けるポイント
最後に、請求側から見た請求書払いで注意すべきポイントとして、次の3点を紹介します。
- 会社の角印を押す
- 事前に契約内容を確認する
- 継続して与信審査を行う
会社の角印を押す
請求書への捺印は法律上義務付けられているわけではありません。しかし、偽造防止やビジネスマナーの観点から、印鑑を使用しないと請求書が受理されない取引先も存在するため、注意しましょう。
通常、請求書には会社の角印が用いられ、法務局に登録した丸印や銀行印の使用も一般的です。ただし、重要な印鑑の頻繁な使用は摩耗や紛失のリスクを増加させるため、耐久性のある角印が適切です。また、請求書の修正に訂正印は原則使用できません。
事前に契約内容を確認する
請求書払いでは取引開始前に、振込手数料の負担をどちらが担当するか、支払い期日はいつか、といった契約内容を、お互いでしっかりと確認することが重要です。
一般的には振込手数料は支払い側が担当し、この点を請求書に明記すると、のちのトラブルを防げます。支払い期日はほかの取引先と同様に設定し、統一することで管理が容易になり、ミスを防げます。
定期的に与信審査を行う
取引先の経営状態は日々変動しているため、定期的な与信審査が必要です。一度行ったからといって審査を怠ると、取引先が赤字や倒産危機にあることに気付かず債権の未回収リスクが高まります。
取引額の増加や信用状況の悪化に応じて、与信限度額は最低でも年に一度見直しましょう。適切な与信枠の管理は、未回収や貸し倒れを防ぐために不可欠です。
まとめ
本記事では請求書払いについて解説しました。請求書払いは、企業間取引で一般的な支払い方法です。ただし、信用取引であるため与信管理や限度額の設定が重要です。貸倒れが発生すると企業にとって大きなダメージとなるので、事前の確認や未払いへの早急な対応も大切になります。
このように、取引先が増えるにつれて与信管理や請求書の発行、入金消込などの管理コストが増加します。取引数が増加しても、正確性と効率を落とさず対応可能な仕組みを作ることが重要です。
「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。
入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。
Bill One債権管理の特長
- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行
- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理
- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能
- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能
- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結
請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、 企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。


3分でわかる Bill One債権管理
リアルタイム入金消込で、現場を強くする
クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。



執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。