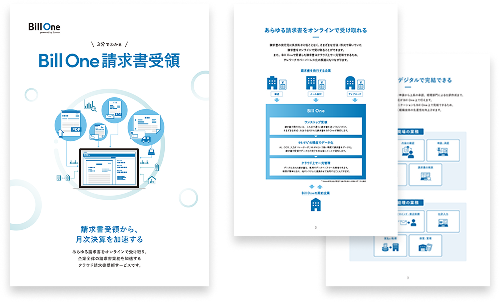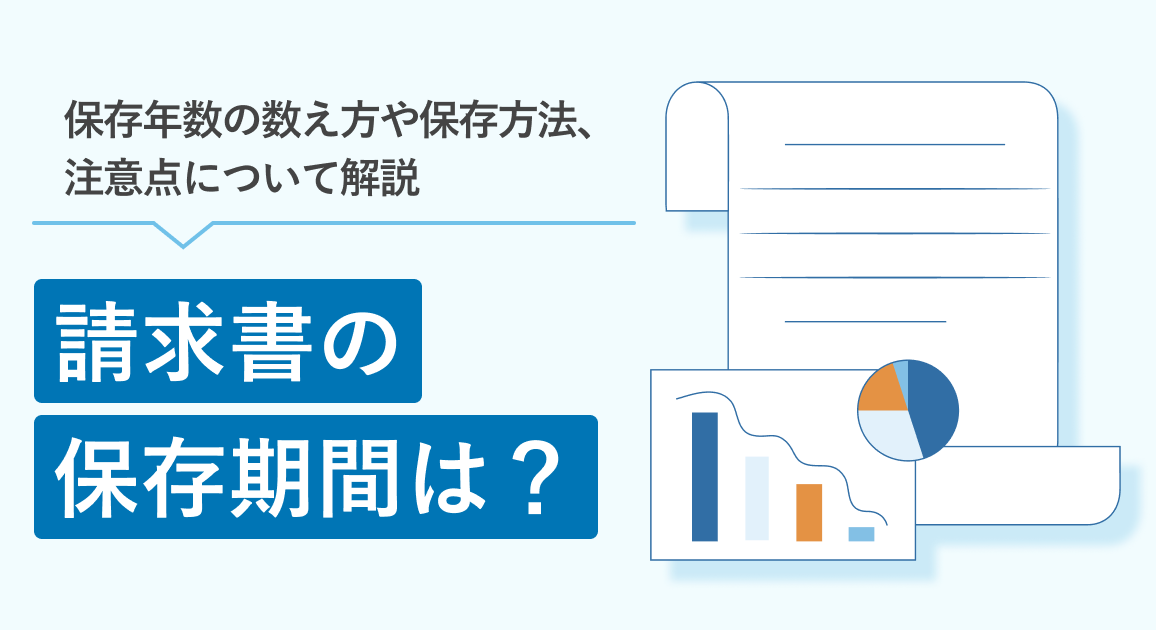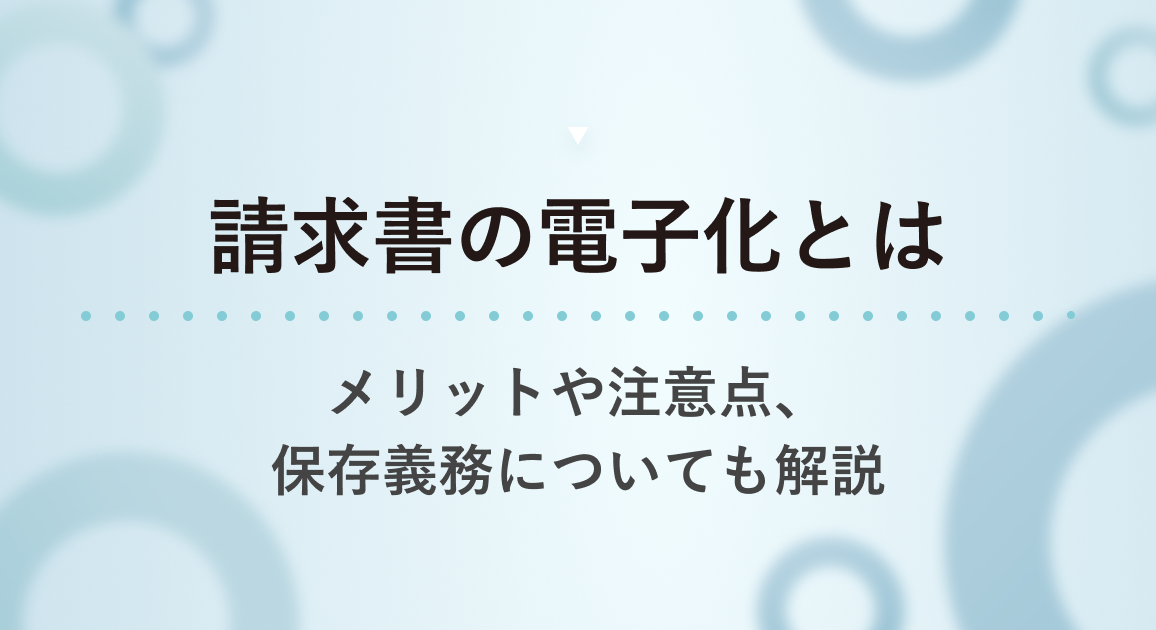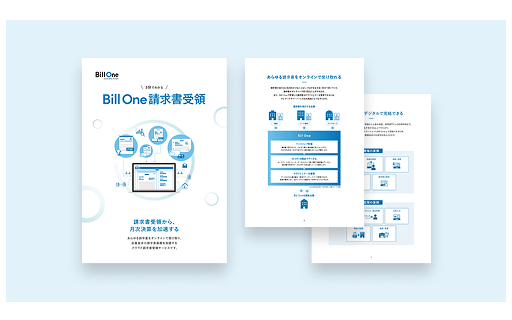- 請求書
請求書の書き方|インボイスのポイントや請求書発行に関するマナーを解説
公開日:
更新日:
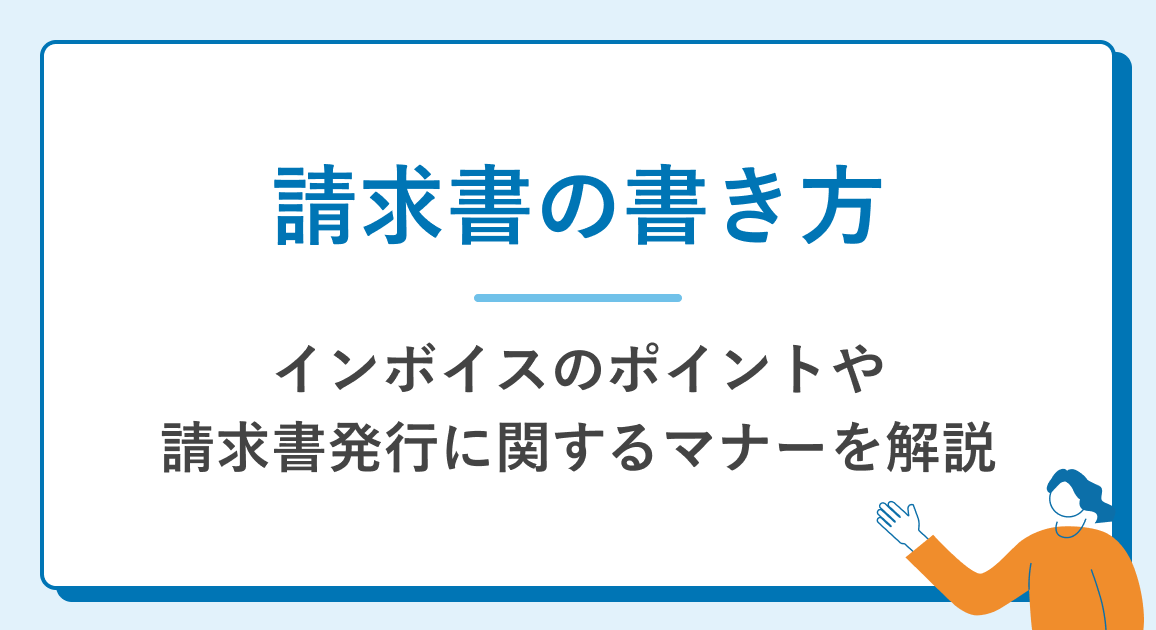
請求書の書き方で押さえるべき重要なポイントが、記載項目とマナーです。
請求書の記載項目はインボイス(適格請求書)とそれ以外で違いがあり、記載項目に漏れがあると適切な請求書およびインボイスと認められない場合があります。また、請求書の書き方についてマナー違反をしてしまうと、取引先とのトラブルになる恐れがあるため、慎重に書かなければなりません。
今回は請求書の書き方について詳しく解説します。
請求書の書き方|インボイス(適格請求書)とそれ以外で記載項目が異なる

請求書を作る上で最も大切なのが、記載項目の漏れを起こさないことです。記載項目に漏れがあると必要な情報を伝えられない恐れや、請求書としての効力を持たない恐れがあるため注意しましょう。
なお、請求書の記載項目はインボイス(適格請求書)とそれ以外で違いがあります。基本的な記載項目に加え、インボイスならではの記載項目が存在するイメージです。
基本的な記載項目とインボイスの記載項目それぞれについて詳しく解説します。
基本的な記載項目
インボイスとそれ以外の請求書すべてに共通する基本的な記載項目は以下の通りです。
- 請求書の宛先
- 発行者の情報
- 請求日(発行日)
- 取引年月日
- 取引内容
- 金額
- 振込期日
- 振込先
- 請求書番号
- 備考
それぞれ書き方や注意点について詳しく解説します。
1.請求書の宛先
請求書の宛先として、交付先(受取側)の氏名または名称を正確に記載します。請求書の宛先について以下の3点に注意が必要です。
- 正式名称を略さず書く。「(株)」などの略称を使わない
- 法人宛の場合は「御中」、個人宛の場合は「様」をつける
- 法人に属する特定の個人が宛先の場合、個人名への敬称のみつける。「御中」「様」の併用はしない
なお交付先の住所の記載は必須ではなく、氏名または名称のみで特に問題はありません。
2.発行者の情報
請求書の発行者(交付側)の情報として、発行者の氏名または名称は必ず記載する必要があります。その他に記載する情報として以下の例が挙げられます。
- 住所
- 電話番号
- FAX番号
- メールアドレス
前項で紹介した請求書の交付先に関する情報と同様、発行者側についても氏名または名称のみでも問題ありません。ただし商慣習として、発行者側については住所等も記載するケースが多くみられます。
3.請求日(発行日)
請求日(発行日)は請求書を作成した日そのものではなく、経理の締め日に合わせるケースもあります。例えば月末締め翌月末払いの場合、請求書を発行したのが翌月の頭であっても、請求日は月末にするイメージです。取引先とのトラブルを防ぐためにも、請求日に関するルールについて確認するのが安心です。
なお、和暦・西暦の書き方に法的な決まりはありません。ただし両方が混在しないよう、どちらかに統一することが前提となります。
4.取引年月日
実際に商品やサービスの提供が行われた日を取引ごとに記載しましょう。取引年月日の書き方も和暦・西暦の決まりは特にありませんが、前項で紹介した請求日の表記方法に合わせるのが一般的です。
5.取引内容
取引内容として、引き渡した商品・サービスの名称や数量を記載する必要があります。項目が多くなりすぎる場合は「一式」表記を使ってまとめることも可能です。ただし、あまりまとめすぎると具体的な取引内容がわかりにくくなってしまうため、バランスに注意する必要があります。
6.金額
請求書に記載するべき金額として以下の4つが挙げられます。
- 取引ごとの金額
- 小計(税抜の合計額)
- 消費税の額
- 合計金額
合計金額は取引先から支払ってもらう金額のため、小計・消費税の下だけでなく、目立つ位置にも記載する必要があります。請求書の真ん中やや上あたり、請求書の宛先と請求内容の間あたりに記載するのが一般的です。
7.振込期日
振込期日は事前に請求先とすり合わせをする必要があります。西暦・和暦は、これまでに紹介した請求日や取引年月日の表記と合わせましょう。
8.振込先
振込先の口座情報を記載します。記載内容にミスや漏れがあるとスムーズな支払いができず請求先の手間が増えてしまう恐れがあるためご注意ください。
振込先情報として記載する項目を紹介します。
- 金融機関名
- 支店名
- 口座種別
- 口座番号
- 口座名義
支店名は支店コードも記載しておくと親切です。また、支店名や口座名義はフリガナも記載しておくと良いでしょう。
9.請求書番号
社内での管理用につける番号です。請求書番号を使っていない場合は記載しなくても問題ありません。
10.備考
備考欄に記載する事項として特に多いのが振込手数料に関する内容です。
振込手数料は支払い側が負担するという考え方が広く浸透しています。
これは民法第485条(弁済の費用)に基づくものであり、特段の取り決めがない場合には、支払い側が負担するのが原則です。ただし、異なる取り決めをすることも可能なため、どちらが負担するか事前に確認しておくと良いでしょう。
特に取り決めをしない場合も、トラブルを防ぐため「振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします」と記載するのが安心です。
インボイスの記載項目
発行する請求書がインボイスの場合、基本的な項目に加えて以下3つの記載も必要です。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適用税率および税率ごとの合計額
- 税率ごとに区分した消費税額等
基本的な記載項目とインボイスならではの記載項目、いずれか1つでも漏れがあるとインボイスとして認められない恐れがあるため注意が必要です。
以下ではインボイスの記載項目についてそれぞれ詳しく解説します。
1.適格請求書発行事業者の登録番号
適格請求書発行事業者の登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録申請が認められた事業者に発行される番号です。頭文字はTで、その後に13桁の番号が続きます。
適格請求書発行事業者の登録番号は登録通知書に記載されています。なお法人の場合、Tに続く13桁の番号は法人番号と同じです。個人事業主の場合はすでに登録されている番号と重複しない番号が割り振られます。
2.適用税率および税率ごとの合計額
インボイス制度の目的は、取引に適用されている税率および消費税額を正確に把握することです。そのため標準税率10%を適用した取引の合計額と、軽減税率を適用した取引の合計額の記載が必要です。
なお軽減税率対象の取引がある場合、軽減税率を適用した取引を区別できるようにする必要もあります。取引内容の商品・サービスの名称に「※」をつけ、欄外に「※は軽減税率対象です」と書くのが一般的です。
3.税率ごとに区分した消費税額等
インボイスには税率ごとの合計額だけではなく、税率ごとに区分した消費税額等の記載も必要です。例えば10%対象の取引合計が110,000円(税込)だった場合、以下のように記載します。
10%対象 | 110,000円 | (消費税 10,000円) |
インボイスを発行するためには事前に手続きが必要
インボイスを発行するためには、事前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。登録申請が受理されることで登録番号が発行されます。
申請書の提出から登録通知までにかかる期間の目安は以下の通りです。
- e-Taxによる提出:約1カ月
- 書面による提出:約1.5カ月
参照:国税庁|「各局(所)インボイス登録センターのご案内」
請求書の書き方に関するマナー

前章で紹介した記載項目に不備や漏れがなければ、請求書としての効力に問題はありません。しかし請求書の書き方に関するマナーを知らずに作成してしまうと、記載内容に問題がなくてもトラブルにつながる恐れがあります。請求書を発行する際は記載項目だけでなく、マナーについても注意するのが大切です。
請求書を発行する上で押さえるべきマナーとして以下の5つが挙げられます。
- 名称の誤りは厳禁
- 振込手数料について確認する
- 請求日や振込期日を確認し同意を得る
- 【紙の場合】押印の必要性を確認する
- 【電子の場合】紙の請求書の郵送が必要か確認する
それぞれ詳しく解説します。
1.名称の誤りは厳禁
請求書に限らず、取引先へ送付する書類において名称の誤りは厳禁です。誤字脱字を完全になくすことが理想ですが、特に相手方の名称は絶対に間違えてはいけない部分といえます。
万が一にも名称の誤りを起こさないため、相手方から届いたメールの署名などをコピー&ペーストするのも1つの手段です。その場合もコピー&ペーストであれば安心と油断せず、必ず目視でチェックしましょう。
2.振込手数料について確認する
基本的な記載項目の「10.備考」で紹介しましたが、振込手数料は支払い側が負担するのが一般的です。これは民法第485条(弁済の費用)に基づくものであり、特段の取り決めがない場合には、支払い側が負担するのが原則です。
相手方が払うものと思い込んでしまうと、トラブルになる恐れや、マイナスの印象を与えてしまう恐れがあります。気持ちの良い取引を行うためには、振込手数料について事前に確認するのが安心です。
3.請求日や振込期日を確認し同意を得る
請求書に記載する請求日や振込期日についても確認しましょう。自社の都合で決めた日付を書くのではなく、相手方に確認し同意を得ることがマナーといえます。
4.【紙の場合】押印の必要性を確認する
発行する請求書が紙の場合、請求書への押印が必要かを確認するのが良いでしょう。
請求書に押印がなくても法的な効力は変わりません。しかし請求書への押印は商慣習の1つであり「押印はあるべき」と考える人も多くみられます。
トラブルになり得る要素をなくすため、紙の請求書の場合は押印について相手方の考えを確認するのが安心です。
5.【電子の場合】紙の請求書の郵送が必要か確認する
請求書を電子データで送る場合は、紙の請求書を別途郵送する必要があるか確認するのがおすすめです。
紙の請求書と電子データの請求書はどちらも同じように効力を持ちます。そのためルール上はどちらか一方の方法で送付するだけで問題ありません。
しかし請求書の管理業務は未だ紙ベースで行われることも多いです。内容を早く確認するために一旦メールで受け取るものの、管理は紙で行うというケースもみられます。
請求書を紙と電子の両方で発行・送付する必要はありませんが、相手方に確認することで、より良い印象を与えることができるでしょう。
請求書を発行する際の注意点

請求書を発行する際に押さえるべき注意点として以下の3つが挙げられます。
- 端数処理は税率ごとにまとめて行う
- 発行した請求書は一定期間の保存が必要
- 送付の前に誤りがないか確認する
それぞれ注意するべき理由や具体的な対処法について詳しく解説します。
1.端数処理は税率ごとにまとめて行う
消費税の端数処理は取引ごとではなく、税率ごとにまとめて1回で行うのがルールです。国税庁は「適格請求書に記載する消費税額等の端数処理」について以下のように回答しています。
- 消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う
- 個々の商品ごとに消費税額等を計算し端数処理を行い、その合計額を消費税額等と記載することは認められない
- 切上げ・切捨て・四捨五入などの方法は任意のものを選べる
参照:国税庁|「適格請求書に記載する消費税額等の端数処理」
2.発行した請求書は一定期間の保存が必要
帳簿や書類には一定期間の保存が義務付けられています。受領した請求書だけでなく、自社が発行した請求書も一定期間の保存が必要です。
法人の帳簿・書類などの保存期間は原則として7年間です。ただし以下のケースに該当する年度の保存期間は10年間となります。
- 青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた事業年度
- 青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度
なお、帳簿や書類の保存期間は確定申告書の提出期限の翌日を起点に数えます。請求書を発行した年月日ではない点に注意が必要です。
3.送付の前に誤りがないか確認する
発行した請求書を送付する前に、内容に誤りがないか確認しましょう。請求書を作るときに注意したつもりでも、改めて確認すると思わぬミスが見つかるケースは珍しくありません。請求書を作成した人とは別の人がチェックすることで、ミスを見逃すリスクをさらに軽減できます。
請求書のデジタル化で発行業務を効率化

請求書は記載項目に不備や漏れがなければ、紙・電子どちらも同じように法的な効力を有します。しかし請求書の発行業務を効率化するためには、請求書はデジタル化するのがおすすめです。
紙ではなく電子をおすすめする理由として主に以下の3つが挙げられます。
- 請求書の印刷や郵送料がかからなくなるためコスト削減が可能
- 請求書業務をオンラインで完結できるためテレワークの推進につながる
- 紙の請求書を整理する作業や、保管場所を確保する必要がなくなる
まとめ
請求書の記載項目に少しでも不備や漏れがあると、請求書の効力が失われる・取引先とトラブルになるなどの恐れがあります。また、請求書のマナーを守ることも大切です。誤字脱字をしないことはもちろん、細かな事項も適時確認するよう心がけましょう。
なお、請求書は紙・電子どちらも同じように効力を持ちます。しかし請求書業務をより効率良く行うためには、請求書をデジタル化することがおすすめです。どのような方法でも良いわけではなく、請求書業務の効率化につながる機能が豊富なツールを選ぶ必要があります。
「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。
入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。
Bill One債権管理の特長
- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行
- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理
- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能
- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能
- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結
請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、 企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。


3分でわかる Bill One債権管理
リアルタイム入金消込で、現場を強くする
クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。



執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。