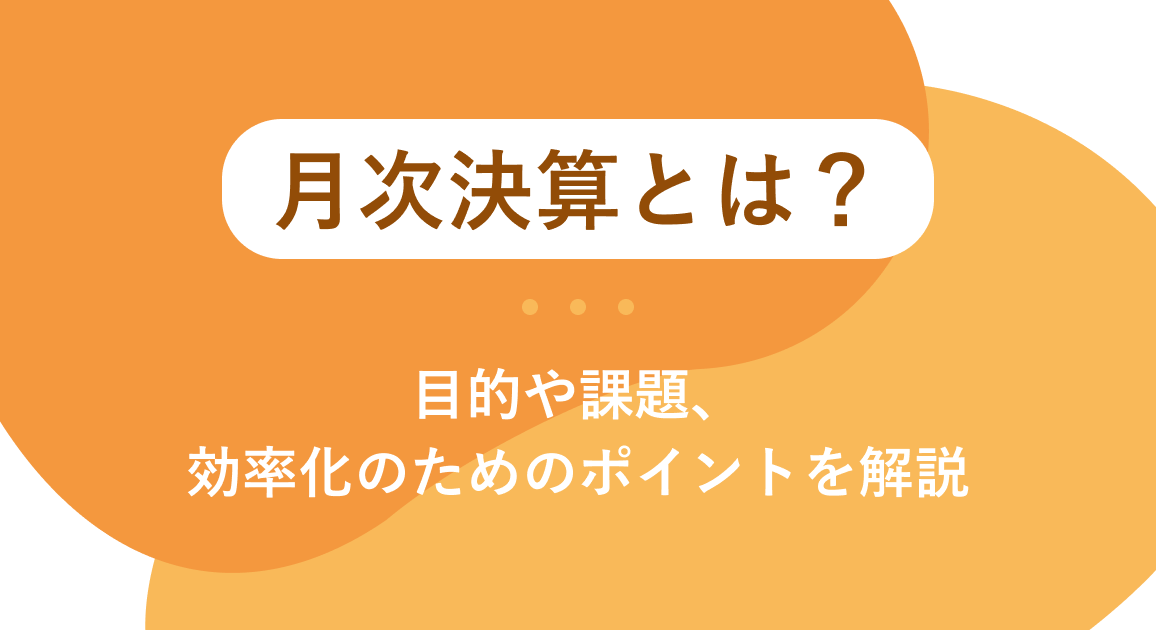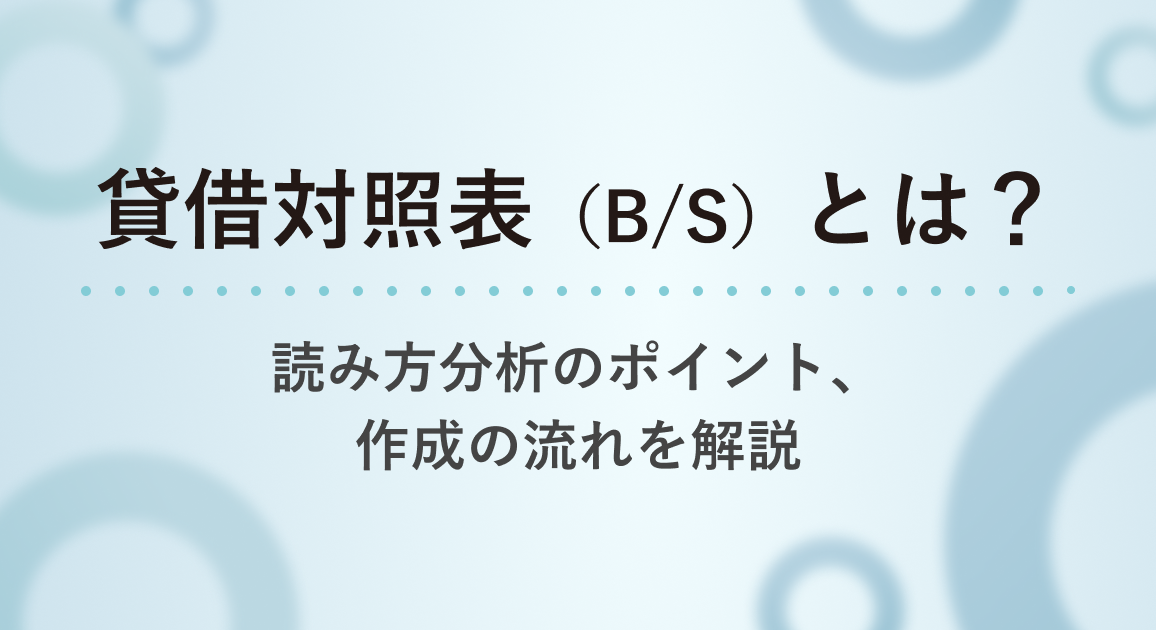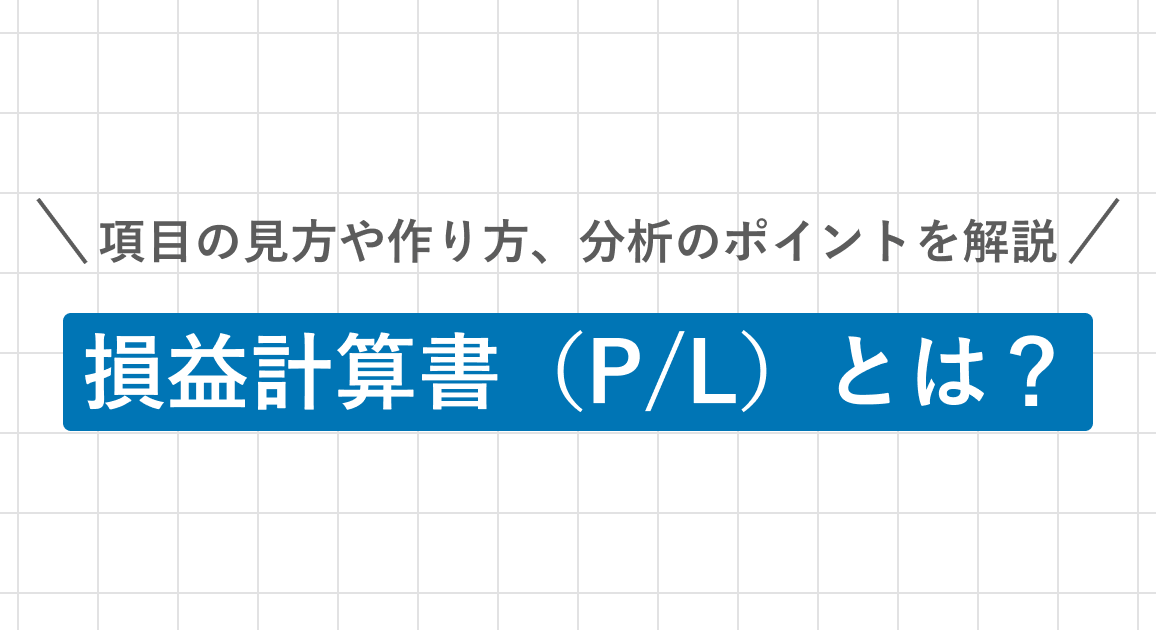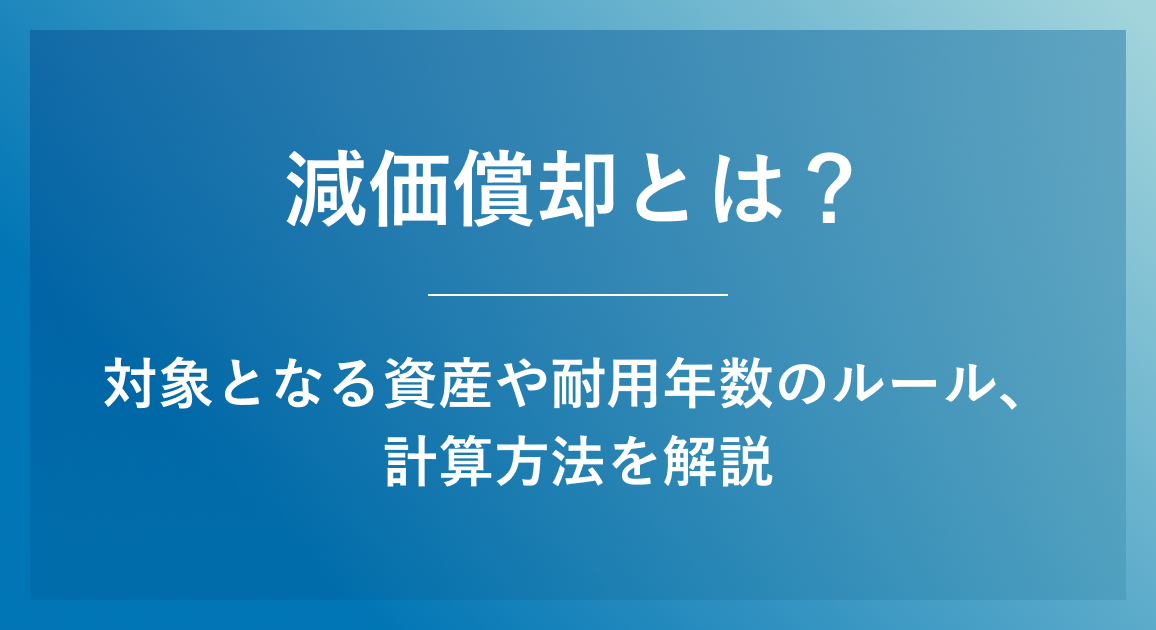- 書類その他
決算業務とは?決算業務を行う目的や時期、業務の流れや注意点について解説
公開日:
更新日:
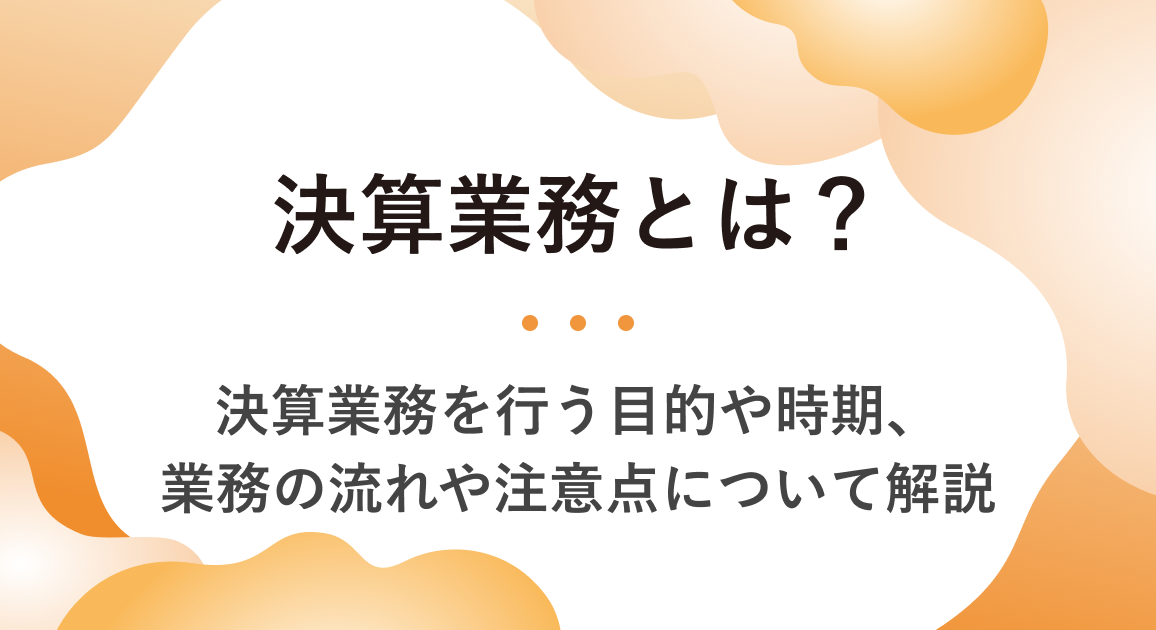
決算業務とは、一定の期間ごとに会社の業績を取りまとめて、ある時点の資産、負債、純資産を明確にする行為です。決算の結果は、経営判断や納税額の計算、投資家や関係者への報告などに利用されます。そのため、すべての企業が行わなければいけません。
また、決算は通常業務と平行して行うため、経理担当者の負担は大きなものになります。できるだけスムーズに進められるように準備をしておきましょう。
本記事では決算業務の基本から、効率よく正確な決算を行うための具体的な方法まで詳しく解説していきます。決算業務の効率化に役立ててください。
月次決算を効率化するヒントが分かる!
決算業務とは

まずは、決算業務の概要と目的を、それぞれ見ていきましょう。
決算業務とは、期間ごとの経営状況をまとめる業務のこと
決算業務とは、一定期間ごとの企業の収益や財務の状況を取りまとめる仕事です。
決算の結果は、決算書類にまとめます。
決算業務は、取りまとめ期間に応じて以下の4種類です。
- 月次決算:1カ月ごとの決算業務
- 四半期決算:3カ月ごとの決算業務
- 半期決算:6カ月ごとの決算で、上場企業は報告書の提出が必須
- 年次決算:会計期ごとの決算で、すべての株式会社の義務
年次決算は、年に一度行う決算で、本決算業務と呼ばれることもあります。損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書などの財務諸表を作成して、経営判断に役立てます。法人税や消費税などの計算と納付にも必要であるため、すべての企業に義務付けられています。
一方、月次決算、四半期決算、半期決算の実施は任意(上場企業は半期決算必須)です。
決算業務は、内容に誤りがあると納税額の計算結果が変わってしまいます。本来の税額よりも低く計算してしまった場合、意図せず脱税してしまう恐れがあるでしょう。そうなれば、追徴課税される可能性もあるため、正確に実施することが求められます。
決算業務の目的
決算業務の目的は、主に以下の3点です。
- 経営者、株主、取引先、金融機関への報告
- 納税額の確定
- 経営課題の洗い出し、改善
決算を行うことで、自社がどのような経営状態にあるのかを数字で確認できます。不採算事業の洗い出しや、新規事業参入のタイミングの検討などに役立てられるでしょう。また、決算書は融資を受ける際の判断材料などとしても利用されます。
特に年次決算しか行っていない企業の場合、納税額を決定するための決算という側面が大きくなるかもしれません。しかし、決算書からは、経営判断に役立つさまざまな情報を読み取れます。正しい分析を行うためにも、決算は正確に行うことが重要です。
決算業務を行う時期

年次決算を行う時期のことを決算期と呼びます。また、決算を行う月は決算月と呼びます。ここでは、法人と個人事業主、それぞれの決算期について見ていきましょう。
法人の場合
法人は、設立時に決算期を任意に設定できます。ただし、一度決定した決算期を変更する場合は株主総会での決議といった手続きなどが必要です。
なお、決算期は原則として1年を超えることはできません。また、決定した決算期は、通常事業年度として定款に記載します。
(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに事業年度が終了した法人)によると、年1回決算の企業では3月を決算期とする法人が最も多いです。次いで、9月と12月を決算期とする企業が多くなっています。3月決算の企業が多いのは、新年度が4月であるためでしょう。
個人事業主の場合
個人事業主は、会計期間が1月1日から12月31日までと決められているため、決算期は12月になります。
そのため、法人のように決算期を任意に決めることはできません。全事業者が12月を決算期として、2月16日から3月15日までに確定申告を行います。
決算業務の流れ
決算業務の流れを非上場や中小企業の場合と上場企業の場合に分けて、それぞれ簡単に解説します。
非上場・中小企業の場合
中小企業など非上場企業における決算の流れは、以下の通りです。
- 決算残高の確定
- 税金の計算
- 決算書の作成
基本的な流れは上場企業とさほど変わりません。それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。
1.決算残高の確定
まずは、決算日時点において、勘定科目ごとの帳簿上の残高と実際の残高が一致していることを確認しましょう。すべて問題がなければ、決算整理仕訳を行います。
決算整理仕訳とは、決算のために行う仕訳です。日常の業務の中で行う仕訳とは異なる処理が必要です。決算整理仕訳には、以下のようなものが挙げられます。
- 期末棚卸高の確定と売上原価計算
- 貸倒引当金の設定
- 減価償却費の計上
- 見越勘定の仕訳
- 繰延勘定の仕訳
- 有価証券の評価替え など
次に、勘定科目内訳明細書を作成します。勘定科目内訳明細書とは、勘定科目ごとの取引の内訳を示す書類です。勘定科目内訳明細書は法人税申告の添付書類で、すべての企業が提出しなければいけません。
勘定科目内訳明細書は、帳簿を基に作成します。帳簿に間違いがあると正確な書類を作れないため、ダブルチェックの実施や自動入力できるシステムの導入など、ミスを防ぐための対策を採りましょう。
2.税金の計算
決算残高が確定したら、税金の計算を行います。
以下の4種類の税金について、納税額の計算と納付を行いましょう。
- 法人税
法人の所得額に対して課せられる税金です。企業の規模や利益額に応じて税率が異なります。
- 法人住民税
法人の事業所がある地方自治体に対して納める税金です。法人税額を基に計算します。個人住民税とは異なり、法人が自ら計算して納付しなければいけません。
- 法人事業税
事業を営むうえで利用する、地方自治体の施設を維持するための税金です。事業の種類に関わらず納付しなければいけません。
- 消費税
本則課税事業者は、課税売上高にかかる消費税から課税仕入れ高にかかる消費税を差し引いて納税します。
税金の計算は決算残高を基に行うため、決算を間違えていると正しい計算ができません。納税額に間違いがあると、ペナルティーが課せられる恐れがあります。
3.決算書の作成
最後に、決算書を作成します。前年までと処理方法などを変えた場合は、決算書にもその旨を明記しておかなければいけません。
作成した決算書は、取締役会や株主総会で承認を受けます。なお、株主総会は通常決算日から3カ月以内に開催しなければいけません。
法人税は決算の翌日から2カ月以内が納期限で、決算報告書の添付が必要です。それまでに作成しましょう。
上場企業の場合
上場企業の決算も、基本の流れは非上場企業と同一です。ただし、上場企業は決算から決算短信や有価証券報告書など外部への報告書類を作らなければいけません。決算短信は四半期終了後45日以内に開示しなければならないため、速やかな作成が必要です。
また、上場企業に子会社がある場合は、個別決算のあとに子会社を含めた連結決算も行います。監査法人による財務諸表の監査も義務付けられており、上場企業は決算時により多くの作業を行わなければなりません。
決算前にやっておくべき業務

決算をスムーズに進めるためには、事前準備が重要です。限られた期間内で効率よく作業を終えるためには、決算前にしっかりとした準備を整えておく必要があります。ここでは、決算前にやっておくべき重要な業務7つを解説します。
- 実地棚卸の準備
- 現金の残高確認
- 預金の借入金の残高確認
- 売掛金・買掛金の残高確認
- 受取手形・支払手形・割引手形の残高確認
- 固定資産の残高確認
- 仕掛品の確認
1.実地棚卸の準備
年次決算の前には、実地棚卸の準備を行っておきましょう。棚卸をスムーズに進めるためには、まず棚卸表を作成し、各部署に配布しておきます。この棚卸表には、商品の数量や単価、原材料、貯蔵品などの情報を記入します。
さらに、棚卸の進め方をまとめたマニュアルを作成し、各部署に共有することが重要です。担当者の役割や進行スケジュールもあわせて計画し、早めに準備を整えておくことで、実際の棚卸作業が円滑に進むでしょう。
2.現金の残高確認
決算前には、現金出納帳に記載された残高と、実際の手元現金の残高が一致しているかを確認することが不可欠です。不一致がある場合は、帳簿の記載ミスや計算間違いが原因である可能性があるため、原因を特定して修正します。
万が一、原因が特定できなかった場合は、決算前に「現金過不足」という勘定科目を使って調整を行います。ただし、この科目は事業期間中のみ使用可能であり、決算時までに解消されない場合は「雑損失」や「雑収入」として処理することになります。
3.預金の借入金の残高確認
帳簿上に記載された預金の残高と、実際の銀行にある預金残高が一致しているか確認することも、重要な決算前の業務です。この確認には、金融機関から発行された残高証明書を利用します。残高証明書の日付は、決算日と一致させる必要があります。
もしも帳簿と銀行の残高が一致しない場合は、取引内容を精査し、原因を突き止めることが必要です。例えば、銀行の営業時間外の入金や、仕入れ先がまだ銀行に小切手を提出していない場合などが考えられます。
また、会社が借入金を抱えている場合は、借入金の残高証明書も確認し、帳簿と照合して正しい残高を確保しておきましょう。
4.売掛金・買掛金の残高確認
取引先ごとの売掛金や買掛金の残高が、実際の残高と一致しているかどうかの確認も、決算前にやっておくべき業務です。この確認には「取引先別売掛金管理表」と「取引先別買掛金管理表」を使用します。
もしも一致しない場合は、管理表の記入漏れがないかを調査します。それでも原因が判明しない場合は、取引先に売掛金残高確認書を送り、必要事項の記入を依頼して照合することが有効です。
また、「締後売上」や「締後仕入」の金額も確認して、明細に記入することを忘れないようにしましょう。回収が難しい売掛金や貸付金については、不良債権明細書に記入し、貸倒引当金の計上に備えます。
5.受取手形・支払手形・割引手形の残高確認
受取手形や支払手形の記入帳と帳簿の残高が一致しているかを確認します。割引手形については、現物が手元にないため、銀行から発行される割引手形の残高証明書を取り寄せて確認します。
また、手形の割引が発生している場合には、決算書に「注記事項」として記載しておく必要があります。
6.固定資産の残高確認
帳簿に記載された固定資産の金額と、固定資産台帳の金額が一致しているかを確認します。もし不一致が見つかった場合、事業期間中に取得・廃棄・売却された固定資産の記帳が漏れている可能性が考えられます。
特に、廃棄された固定資産は売却のように資金の動きがないため、見落としがちです。忘れずに確認し、帳簿を修正しておきましょう。
7.仕掛品の確認
決算前には、仕掛品が存在していないかを確認します。仕掛品とは、決算日までに完成しなかった製品のことです。未完成であるため売上には計上されませんが、加工や製造にかかった費用は棚卸資産として計上する必要があります。
事前に仕掛品を把握し、正確な決算を行う準備を整えましょう。
決算月に行う業務

決算月には財務状況を正確に把握するため、さまざまな業務を集中的に行います。ここでは、決算月に経理担当者が行うべき主な業務を4つ解説します。
- 棚卸作業
- 減価償却資産の処理
- 経過勘定の処理
- 精算表および勘定科目内訳書の作成
1.棚卸作業
棚卸作業は、在庫や資産の数量や状態を確認し、正確な評価を行うために不可欠なプロセスです。在庫の数量や品質をチェックし、それを基に適切な評価を行います。この作業をすることで売上に対する原価を計算し、在庫コストを正確に把握します。
無駄な在庫や廃棄品も正確に反映させることが重要です。
2.減価償却資産の処理
減価償却資産とは、長期間にわたって使用される設備や建物などの固定資産のことです。これらは年数ごとに費用として計上されます。
耐用年数や減価償却方法の規定に従って適切に処理しないと帳簿に誤りが生じる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
3.経過勘定の処理
経過勘定とは、現金の収支が発生した時期と収益や費用を計上する時期にズレが生じた場合に、そのズレを調整するために用いる勘定科目のことをいいます。
具体的には、未払い費用や前払い費用、貸し倒れ引当金、仮払金、仮受金などのことです。決算時にはこれらを適切に処理する必要があります。
正確に計上することで、財務の健全性を保てます。
4.精算表および勘定科目内訳書の作成
決算作業の最後には、精算表と勘定科目内訳書の作成を行います。精算表では、すべての勘定科目の貸借や現金残高の整合性を確認します。
これらの書類が正確であることが、決算の信頼性を高めます。
決算業務を行う際の注意点

決算業務をスムーズに行うために、以下の2点に注意しましょう。期限が近くなって慌てることがないようにしてください。
なるべく前倒しで着手する
決算業務は、できることから前倒しで進めていきましょう。ぎりぎりになってから対応しようとすると、経理担当者に過度の負担がかかってしまいミスの原因になります。経理以外の従業員から必要なデータがなかなか届かない可能性もあるため、余裕をもって始めてください。
経理事務の自動化や効率化を進めるのも良いでしょう。特に、職歴の浅い担当者が対応する場合は、できるだけ業務を効率化できるシステム導入なども検討してみてください。
こまめにデータの整理をする
請求データや経費データは、日頃からこまめに整理しておくと良いでしょう。
決算に必要な書類やデータが整理された状態になっていれば、スムーズに書類作成に進めます。中小企業でも、月次決算を行ってこまめにデータの取りまとめをしておくと、年次決算で慌てる必要がなくなります。
決算業務を効率化する詳しい方法を以下で紹介します。
決算業務を効率化するには

決算業務を効率的に進めるためには、日常の業務の中で計画的な取り組みが不可欠です。以下では、決算業務を効率化するための具体的なポイントについて解説します。
- 月次決算を行う
- 期限から逆算して作業する
- 会計システムを導入する
1.月次決算を行う
決算業務の負担を軽減するために有効なのが、月次決算の実施です。月次決算を継続して行っておけば、年次決算に向けての準備が整い、最終的な業務量が大幅に削減されます。
月次決算を実施することで年次決算の際に大量のデータを一度に処理する必要がなくなり、決算時のミスも防げます。また、月次決算のデータは節税対策や資金計画の見直しにも役立ちます。金融機関への融資申請の際には、すぐに提出できる報告書としても活用でき、手続きをスムーズに進める助けとなります。
このように月次決算には多くのメリットがある一方、毎月実施するのは企業にとっても大きな負担となります。Bill Oneは請求書の受領から効率化し、月次決算の実現をサポートします。
2.期限から逆算して作業する
効率的に決算業務を進めるためには、提出期限や納税期限を逆算して作業を計画することが大切です。
まずは提出する書類の締切日を確認し、それに間に合うようなスケジュールを立てましょう。問題が発生する可能性も考慮し、予備日を設けると安心です。
各作業の締切を把握し、段階的に進捗を確認しながら進めると良いでしょう。
3.会計システムを導入する
会計システムを活用することで、決算業務を大幅に効率化することができます。近年では、クラウド型の会計システムや経費精算システムを導入している企業が増えています。これらのシステムを利用すれば、日々の経理業務が自動化され、データの整合性や正確性が向上します。
システム導入によって、手作業でのデータ入力や記帳作業が削減されるため、経理担当者の負担も軽減されます。日々の業務が効率化されることで、決算時の工数も大幅に削減でき、スムーズに決算業務を進められるでしょう。
まとめ
決算業務は企業の財務状況を正確に把握し、適切な経営判断を行うために不可欠な作業です。本記事では、決算業務の基本から効率化のポイントまで詳しく解説しました。
決算業務を効率的に進めるためには、いくつかの重要な対策があります。まず、月次決算を実施することで、年間を通じて財務状況を把握し、年度末の決算作業の負担を軽減できます。次に、期限から逆算して作業計画を立てることで、時間的余裕を持って業務を進められます。さらに、会計システムを導入することで、データ入力や集計作業の自動化が可能となり、人為的ミスを減らすとともに作業時間を大幅に短縮できます。
これらの対策の中でも、特に請求書の処理は決算業務の中で大きな比重を占めています。膨大な数の請求書を正確かつ迅速に処理することは、決算業務の効率化に直結します。
この部分の効率化を図るには、インボイス管理サービス「Bill One」の導入がおすすめです。
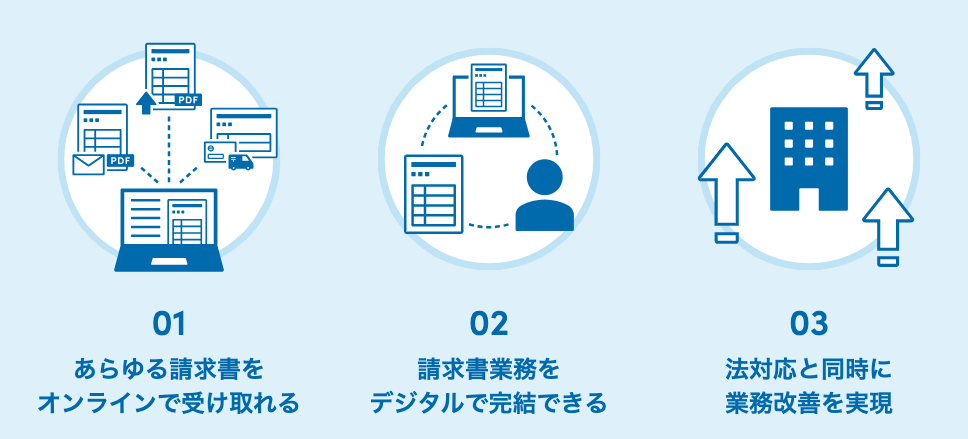
Bill Oneは、企業の請求書管理業務を効率化し、請求書の発行から受領、保管までをデジタル化することで月次決算を加速させるインボイス管理サービスです。
多くの企業が請求書管理において以下のような課題を抱えています。
- 紙の請求書の管理や紛失リスク
- 請求書の発行、受領、保管にかかる膨大な時間と手間
- 請求書データの手動入力による人為的ミスや時間的コスト
- インボイス制度や電子帳簿保存法への対応
これらの課題により、経理部門の業務負荷が高まり、月次決算の遅延にもつながりかねません。Bill Oneを導入することで、これらの課題を解決し、請求書管理プロセス全体を効率化できます。
Bill Oneが提供する主な機能と特長
- あらゆる方法、形式で届く請求書をオンライン上で受け取れる
- 受け取った請求書の申請・承認・仕訳作成まで請求書業務をデジタルで完結
- 99.9%*の精度で請求書をデータ化
- インボイス制度、電子帳簿保存法といった法制度への対応と同時に業務負荷を大幅に削減
- 請求書の発行から入金消込までをオンラインで一元管理
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill Oneは、これらの機能を通じて請求書管理業務を大幅に効率化し、企業の経理部門の負担を軽減します。請求書管理の最適化と月次決算の加速を目指す企業は、ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

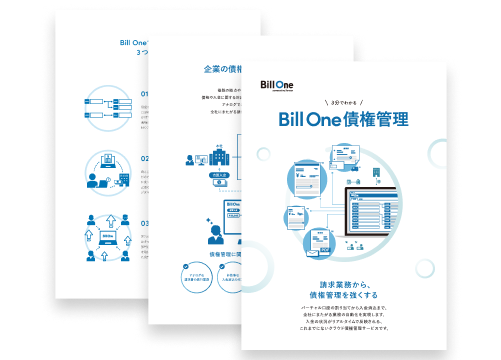
3分でわかる Bill One
「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える
経理AXサービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。



執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。