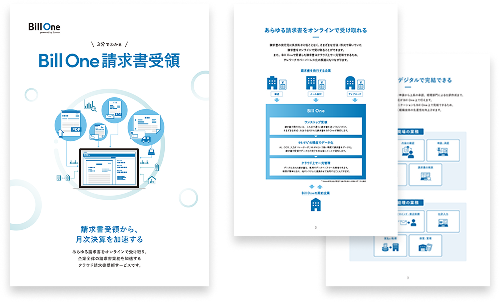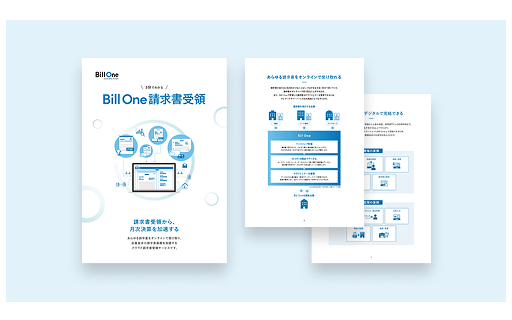- 経費精算
小口精算とは?やり方やメリットとデメリット、代替できる精算方法などを解説
公開日:
更新日:
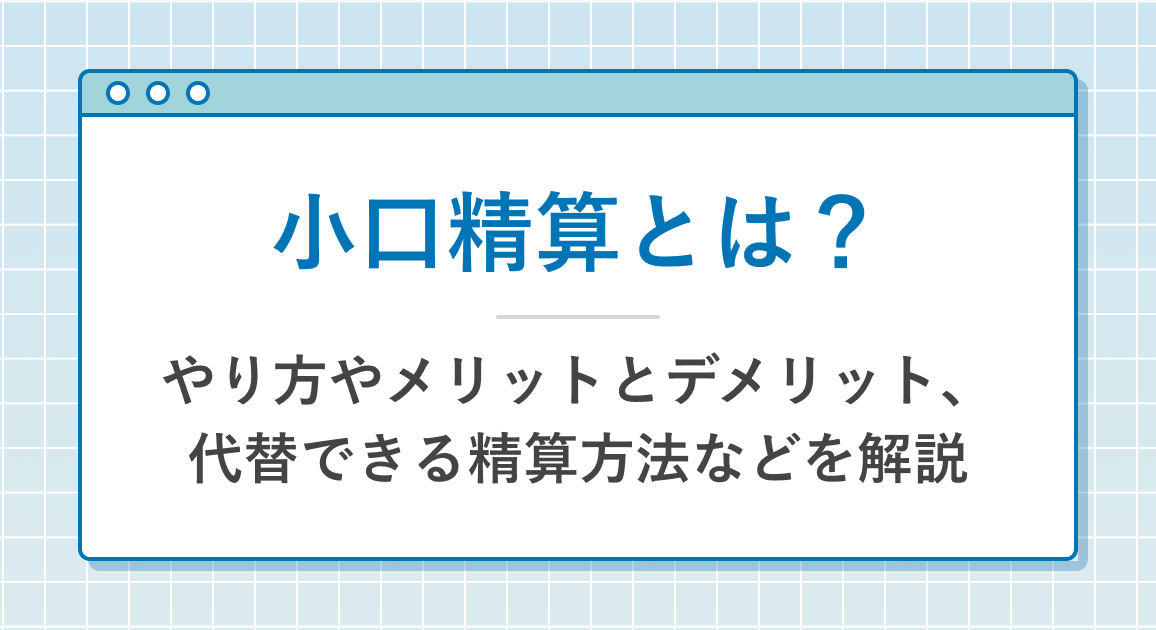
小口精算は、日常業務において発生した少額の出費を処理するための手法です。経費を立て替える従業員の負担が少なく、申請漏れのリスクが少ない点がメリットですが、その反面デメリットもあります。
本記事では、小口精算の概要ややり方について説明したうえで、メリット・デメリット、代替できる精算方法などを解説していきます。経理業務にあたる方は、ぜひ参考にしてください。
小口精算とは

小口精算とは、備品代や交通費といった少額の経費を、領収書やレシートと引き換えに、現金で精算することです。立て替えてから返金までの期間が短い点や、急な支払いにも対応できる点が特徴です。
小口精算を行うには「小口現金」が必要になります。
小口現金とは、少額で発生する経費精算のために、会社に常備しておく現金のことです。
小口精算のやり方
小口精算のやり方は以下の通りです。
- 従業員が立て替えを行った領収書またはレシートを受け取る
- 領収書を確認したあと、小口現金で精算する
- 帳簿や集計などの会計処理を行う
- 帳簿の残高と実際の現金残高が一致しているか確認する
- 小口精算は、小口現金を「小口現金出納帳」で管理するのが基本です。
経理担当者は、従業員の立て替えの精算が発生するたびに勘定科目に仕訳し、記帳しなければなりません。
また、小口精算の頻度が増えると、記帳漏れや残高の不一致が起こる要因になったり、経理担当者の負担が増えたりする可能性がある点には留意しておきましょう。
小口現金の仕訳方法

小口現金を管理する際には、経費の補充や精算ごとに「仕訳」を行う必要があります。仕訳は、どのお金がどのように使われたのかを、正確に記録するための重要な作業です。ここでは、補充時と精算時の仕訳のやり方をわかりやすく解説します。
補充時の仕訳
小口現金を補充するには「定額資金前渡制度(インプレストシステム)」と「随時補給制度」のどちらかが用いられます。ここでは、一定期間ごとに小口現金の残高が元に戻るように補充する「定額資金前渡制度」を用いた場合の仕訳の仕方を解説します。
例えば、30,000円を小口現金に補充した場合の仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
小口現金 | 30,000円 | 預金 | 30,000円 |
また、A部署から10,000円分の支払報告を受けた場合の仕訳は、次のようになります。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
通信費 | 3,000円 | 小口現金 | 10,000円 |
事務消耗品費 | 3,000円 | ||
雑費 | 4,000円 | ||
このように、小口現金を補充する際には、使われた金額とその内訳を記録します。
精算時の仕訳
小口現金から実際に経費を精算する場合も仕訳は必要です。精算する際には、どの費目にいくら使ったかを記録します。
例えば、以下のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
通信費 | 3,500円 | 小口現金 | 30,000円 |
旅費交通費 | 10,000円 | ||
消耗品費 | 12,000円 | ||
雑費 | 4,500円 | ||
このように、支払った経費が何に使われたのかを明確にすることが、仕訳の目的です。
精算は経理担当者が直接行う場合もあれば、各部署で仕訳を行い、一定の締め切り日に経理に報告することもあります。このプロセスを適切に管理することで、経理担当者の負担を軽減し、精算業務をスムーズに進めることにつながります。
小口現金を管理するときのポイント

小口現金を管理する際には、正確な運用が求められます。ここでは、小口現金を適切に管理するための重要なポイントを解説します。
- 毎日残高と記帳内容が合っているか確認する
- 小口現金出納帳は手書きでもPCでも構わない
- ルールに則って運用する
1.毎日残高と記帳内容が合っているか確認する
小口現金の管理において最も重要なことは、毎日、現金の残高が小口現金出納帳と一致しているかを確認することです。万が一、残高が合わない場合は、その原因を早急に突き止める必要があります。
記帳内容と現金残高の確認を怠ると、後で原因を探るのが難しくなります。特に週単位や月単位でまとめて確認する場合、どこで差異が生じたのかを見つけ出すのに時間がかかり、管理が煩雑になる可能性があります。そのため、毎日の確認が非常に重要です。
万が一原因が特定できない場合は、「雑損失」や「雑収入」として処理することもありますが、基本的には事前に差異が発生しないよう、こまめな確認が肝心です。
2.小口現金出納帳は手書きでもデータでも構わない
小口現金出納帳の作成方法には特に決まったルールはなく、手書きで帳簿をつけても、PCを使ってデータ管理しても問題ありません。最終的に金額が正確に把握できていればよいため、自分や組織に合った方法を選びましょう。
具体的には、手書きでノートに記帳する方法や、Excelを使用して管理する方法、さらには会計ソフトやクラウド型の経費精算システムを活用する方法などがあります。
Excelや会計ソフトを使用すると、勘定科目ごとの集計や残高の計算が自動でできるので、手作業による計算ミスを防ぎ、時間の節約にもつながります。Excelのフォーマットは、ネット上で無料ダウンロードできるものも多く、初心者でも使いやすい設計がされています。
また、会計ソフトやクラウド型のシステムを導入すれば、仕訳や経理処理を自動化できるので、帳簿管理にかかる時間を大幅に削減できます。業務の効率化が進み、経理担当者の負担軽減が可能です。
3.ルールに則って運用する
小口現金は会社のお金です。そのため、きちんと管理されなければならず、ルールに従った運用が求められます。運用の際には、あらかじめ定めたルールを徹底し、誤差が発生しないよう細心の注意を払うことが大切です。
業務に慣れてくると、つい運用ルールを簡略化したり、自分なりに変えてしまうことがあります。しかし、このような状況が続くと、ミスが生じたり、不正確な管理につながりかねません。
あらかじめ明確なルールを作成し、これをマニュアル化しておくことが重要です。さらに、マニュアルがしっかりと守られているか定期的に確認し、必要に応じて運用を見直すことも忘れないようにしましょう。
小口精算のメリット・デメリット

続いて、小口精算のメリットとデメリットをそれぞれ見ていきましょう。
メリット
小口精算のメリットは、立て替えをする従業員の負担が少ないことと、領収書の紛失や経費の申請漏れなどのリスク軽減の2つです。
月の締め日にまとめて経費精算する場合、立て替えた従業員は、返金してもらうまでのあいだ手元の現金が減っている状態になります。これは頻繁に立て替えをする従業員にとっては、大きな負担になる可能性があります。小口精算であれば、立て替えた経費をすぐに返してもらえるため、従業員の負担を軽減します。
また、支払いから精算までの期間が空いてしまうと、レシートや領収書を紛失するリスクも高まります。小口精算であれば、支払い直後から精算できるため、証憑を紛失するリスクが減ります。
デメリット
小口精算には、以下のようなデメリットも存在します。
- 経理担当者への手間、負担となる
- 申請する従業員への負担になる
- 盗難・不正利用のリスクがある
それぞれ見ていきましょう。
1.経理担当者への手間、負担となる
小口精算では、受領した領収書を確認し、現金を渡し、記帳するという作業をその都度行う必要があるため、経理担当者の負荷が高まります。
さらに、数え間違いや記帳漏れなどがあり、帳簿の額面と合わない場合には、原因追及に多くの時間を費やすことになり、残業が発生することもあります。
2.申請する従業員にとって負担になる
立て替えの頻度が多い従業員にとっても、小口精算は負担になる場合があります。
前述の通り、立て替えた経費がすぐに返ってくるという点はメリットなのですが、立て替えるたびに精算の手間がかかってしまう点はデメリットといえるでしょう。
また、直帰などの多い営業職の場合、領収書を持ち歩くことは紛失リスクにもつながります。
3.盗難・紛失の不正リスクがある
小口精算を行うには、小口現金を会社に現金を置いておかなければならないため、盗難や紛失のリスクがつきまといます。
管理を担当者一人に任せていたり、チェック体制が整っていなかったりする場合には、不正の機会を与えることにもなるでしょう。
従業員には日頃からの注意喚起を行う必要があります。また、盗難を防止するための対策も行わなければなりません。安全管理の課題が増えることがデメリットの一つになります。
小口精算に代わる精算方法

小口精算は、担当者の手間やリスク管理を行う必要があることを紹介しました。
そこで、ここでは小口精算に代わる精算方法・代替案として、以下の4つを紹介します。
- 立替経費を振り込みで精算する
- プリペイドカードを使用する
- オンラインショップを利用する
- 従業員に個別の法人カードを渡す
1.立替経費を振り込みで精算する
1つ目の代替案は、立替経費を振込で精算することです。
従業員は、月の締め日に、その月に立て替えた経費の領収書をまとめて提出します。立て替えた金額は、給与と同時に口座に振り込まれます。
この方法は、少人数の企業に向いている方法です。従業員が多い場合は経理担当者の負担が大きくなりがちです。また、立て替えている従業員にも一時的な負担を強いる点がデメリットです。
また、小口精算から振込精算に切り替えを行う場合には、事前に社内状況を把握し、周知しておく必要があります。
2.プリペイドカードを使用する
2つ目の代替案は、法人プリペイドカードを利用することです。
法人プリペイドカードとして用意したカードに、あらかじめ決まった金額をチャージしておき、経費の支払いに使用します。
チャージ金額を事前に指定できるため不正利用が防止できるほか、利用額、決済内容を確認できるなど、精算管理が簡潔になるのがメリットです。
クレジットカードには審査が必要ですが、プリペイドカードは審査が不要で簡単に発行できるため、クレジットカードの審査が通らなかった場合の手段としても有効です。
また、年会費もクレジットカードと比べて比較的安価な場合が多く、導入しやすい点もメリットといえるでしょう。
3.備品をオンラインショップで購入する
3つ目の代替案は、オンラインショップを利用して備品を購入することです。
文房具やコピー用紙などの事務用品などの消耗品を実店舗で購入している場合、オンラインショップでの購入に切り替えることで、従業員が経費を立て替える頻度を少なくできるでしょう。
支払い方法をクレジットカード決済にしておけば、購入から支払い、その後の管理といった負担を軽減できます。
また、配送を即日で行ってもらえるサービスもあるため、在庫状況を確認しながら行えば、待ち時間もそれほどかかりません。
対応商品は限られているものの、小口精算から移行しやすい手段です。
4.従業員に個別の法人カードを渡す
4つ目の代替案は、従業員に法人カードを渡し、それを使って支払いをしてもらうことです。
クレジットカード決済にすれば支払いが一本化でき、利用明細も参照できるため、帳簿の記載が不要になり、経理担当者の手間を減らすことができます。記入漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止策としても有効です。
一方、法人カードは利用額や用途を利用者ごとに細かく設定できず、発行枚数に上限があるなどのデメリットも存在します。また、カードを紛失や不正利用、なりすましなどのリスクもゼロではありません。できる限りリスクを回避できる機能を備えた法人カードを検討することも重要です。
なお、ビジネスカードの不正利用について詳しく知りたい方は、次のページを参考にしてください。
クレジットカードのリスクを回避するための注意点
法人クレジットカードを利用する際には、カードの不正利用や無駄な支出を未然に防ぐために下記のような対策を講じる必要があります。
クレジットカードの使用上の制限を設定する
法人クレジットカードを社内で使用する際には、あらかじめ利用上のルールを明確にしておくことが不可欠です。
まず、カードの使用限度額を設定し、必要以上の支出を防ぎます。さらに、利用範囲を限定し、特定の経費にのみ使用するなど、目的をはっきりさせましょう。こうした制限を設けることで、従業員がカードを使用する際にはルールに従った適切な使用が求められることになります。
月次の監査・確認プロセスの導入
クレジットカードの利用を適切に管理するためには、定期的な監査や確認プロセスを導入すると効果的です。特に月次での確認作業を行うことで、不正やミスが発生した場合にも迅速に修正できます。
クレジットカードの利用明細や小口現金の残高を毎月チェックし、すべての取引が正確で適切に処理されているかを確認します。こうしたチェックをしっかり行うことによって、不正な経費申請やミスが発生した場合にも早期の対応が可能です。
まとめ
経費の立て替えを都度精算する小口精算には、立て替えを行った従業員への負担を軽減できるメリットがあります。
一方で、日々の小口現金管理や数え間違い、記帳漏れといったミスも起こりやすく、業務の際に細心の注意を払わなければならないなど、経理担当者に負担がかかりやすいのがデメリットです。
小口精算に変わる精算方法としては、振込による立替経費の精算、プリペイドカードやオンラインショップの利用、法人カードの利用があります。
その中でもおすすめなのは、法人カードです。法人カードを全社員に配布すれば、立替払い自体を廃止することができます。
Bill One経費は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現するクラウド経費管理サービスです。

Bill One経費は、企業の経費精算業務を効率化し、立替経費をなくすことで月次決算を加速させる経費管理サービスです。
多くの企業が経費精算において以下のような課題を抱えています。
- 従業員の立替払いによる個人の金銭的負担
- 紙の領収書管理や紛失リスク
- 経費申請から承認、精算までの煩雑な手続き
- 経費データの手動入力による人的ミスや時間的コスト
これらの課題により、経理部門の業務負荷が高まり、月次決算の遅延にもつながりかねません。Bill One経費を導入することで、これらの課題を解決し、経費精算プロセス全体を効率化できます。
Bill One経費が提供する主な機能と特長
- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる
- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結
- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合
- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応
- 利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One経費は、これらの機能を通じて経費精算業務を大幅に効率化し、企業の経理部門の負担を軽減します。経費管理の最適化と月次決算の加速を目指す企業は、ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費
立替経費をなくし、月次決算を加速する
クラウド経費管理サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。