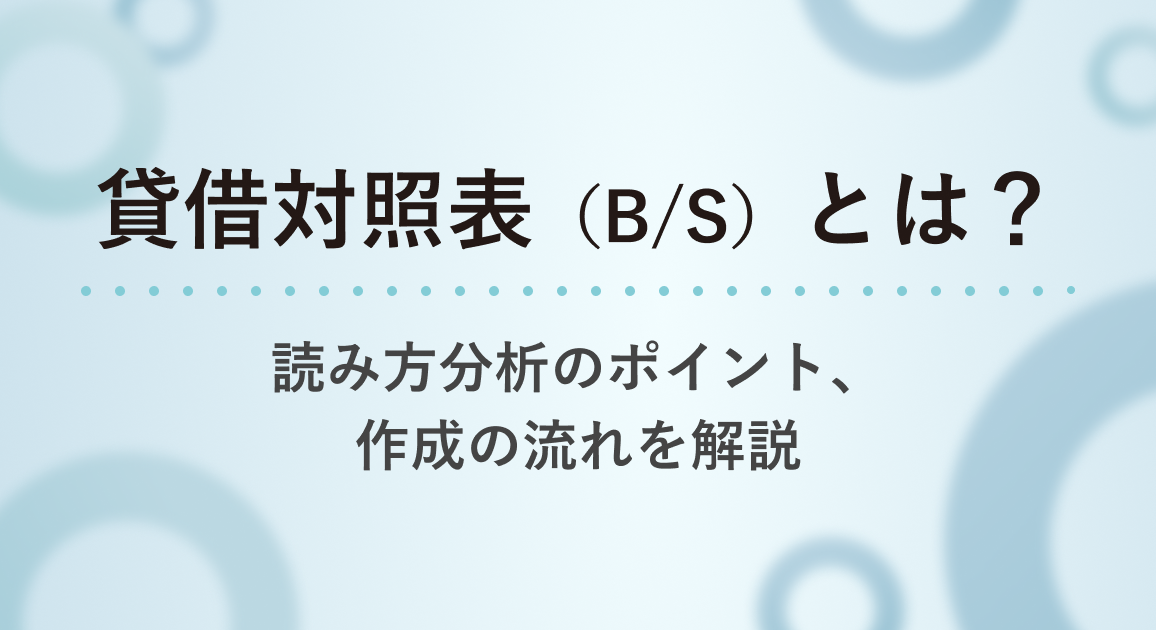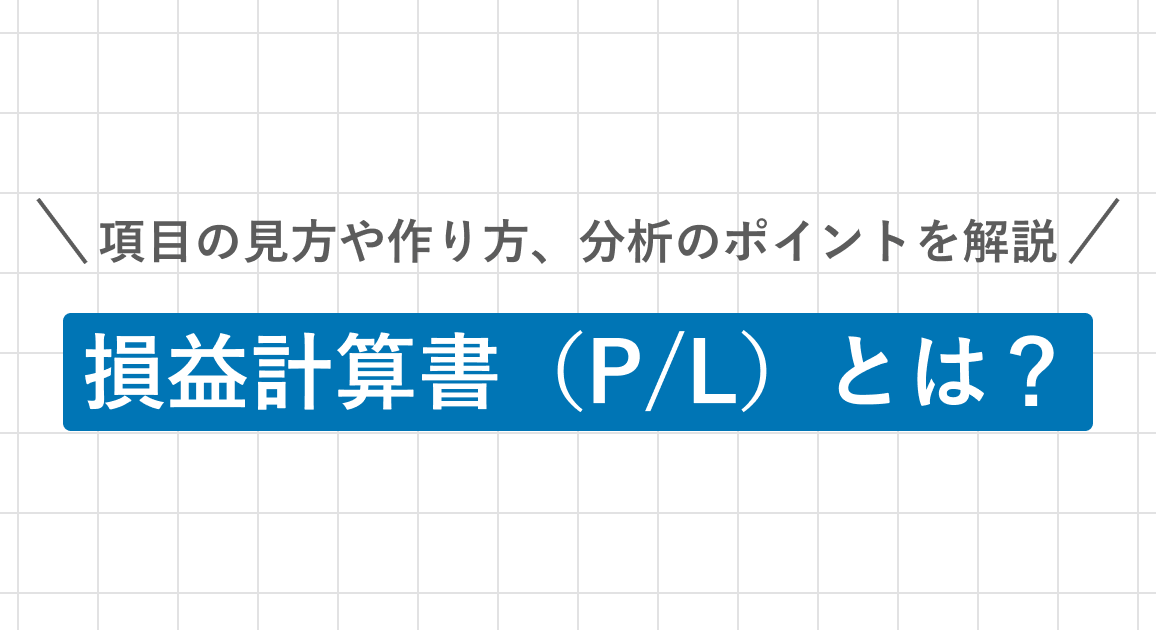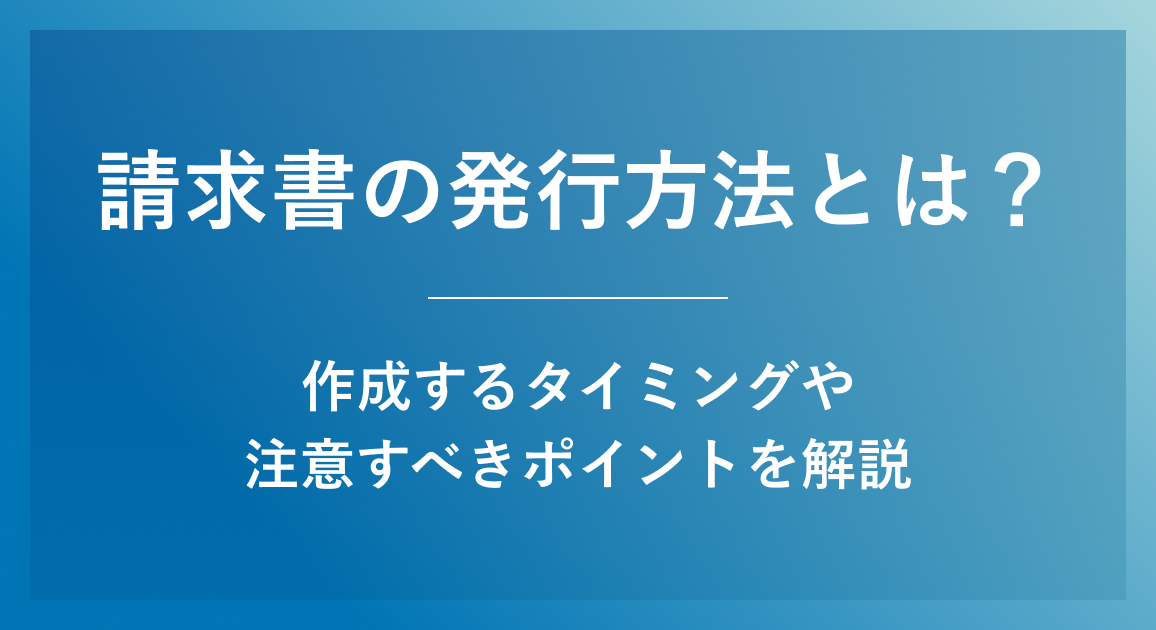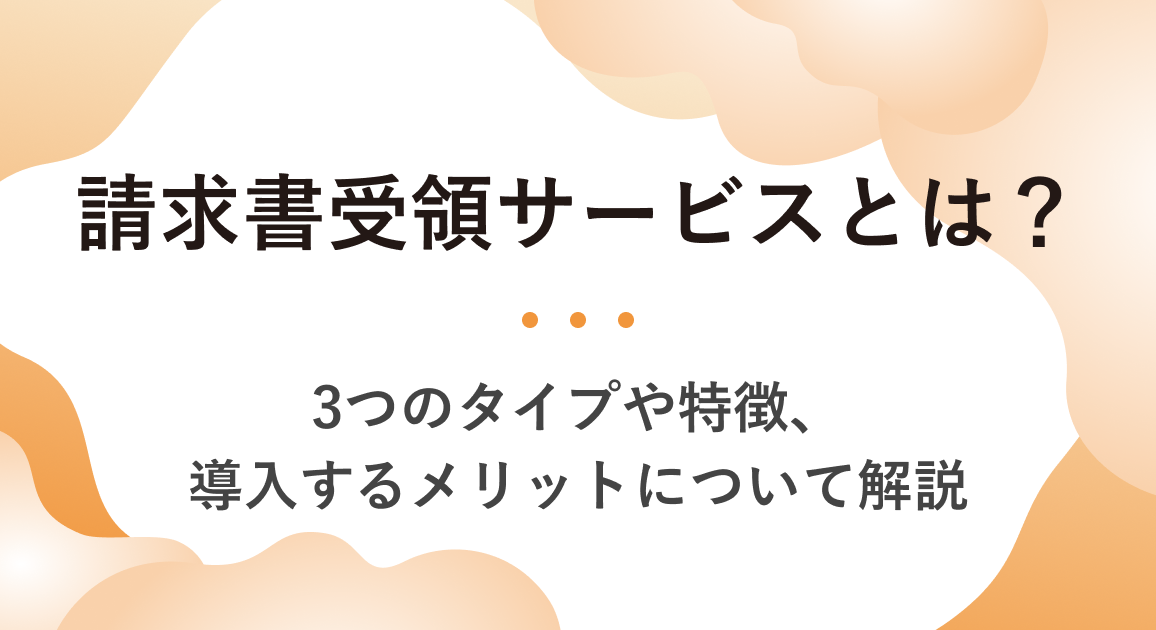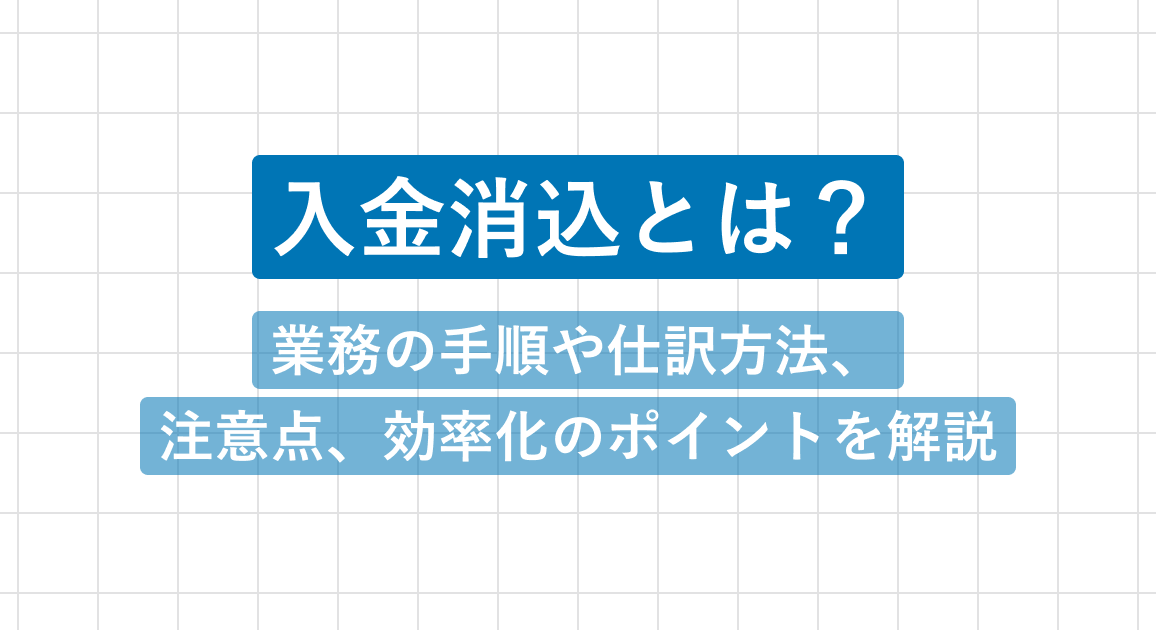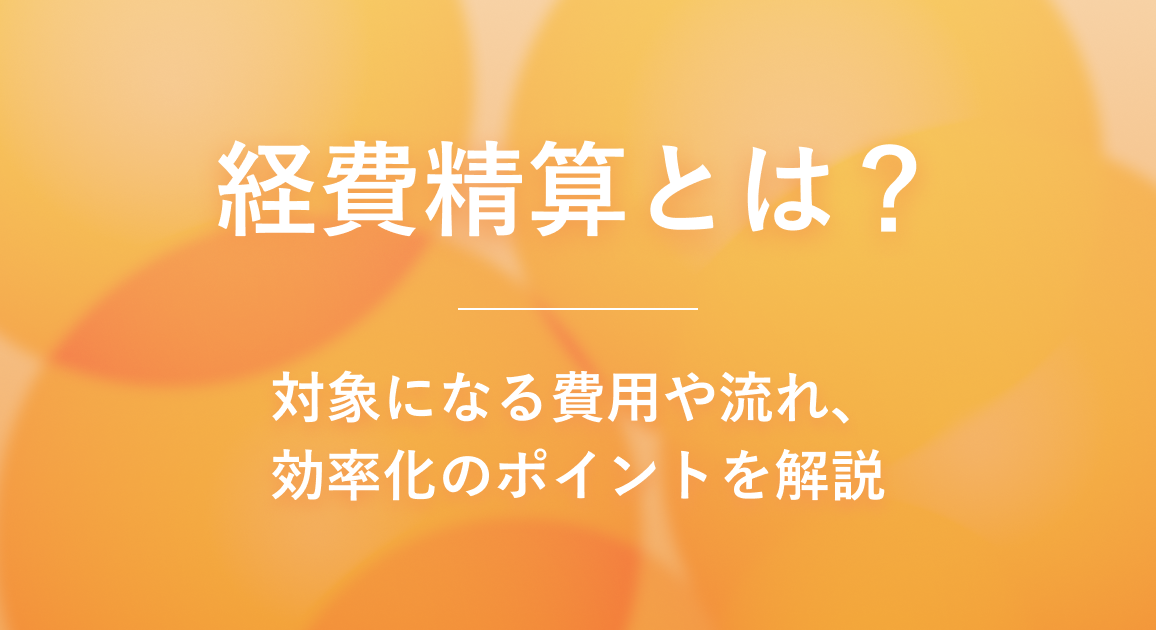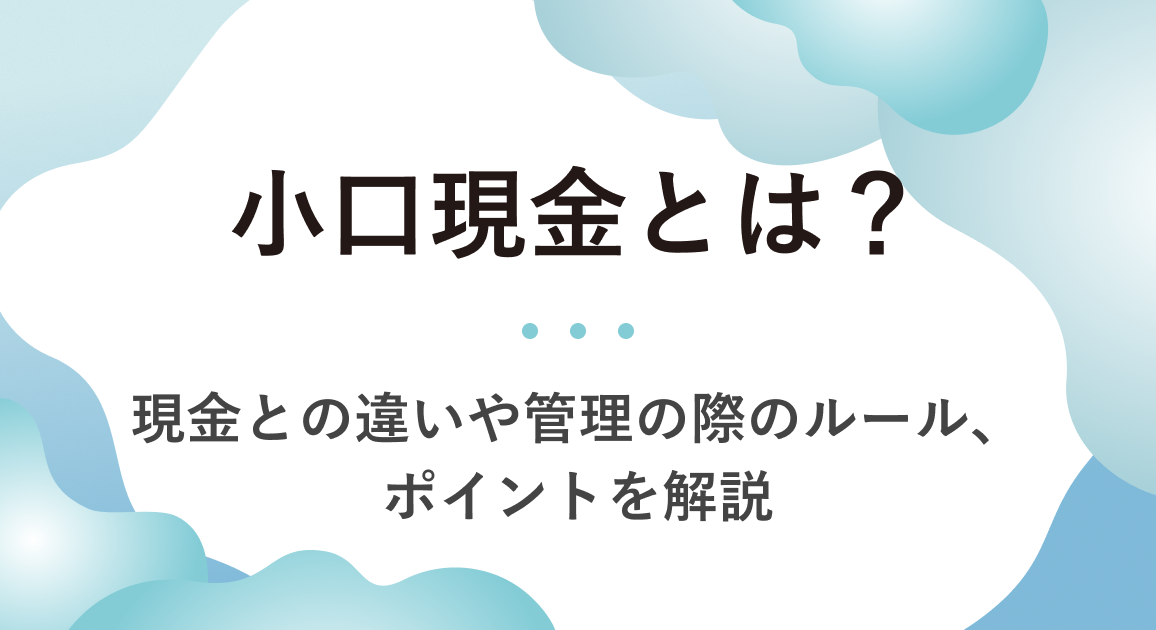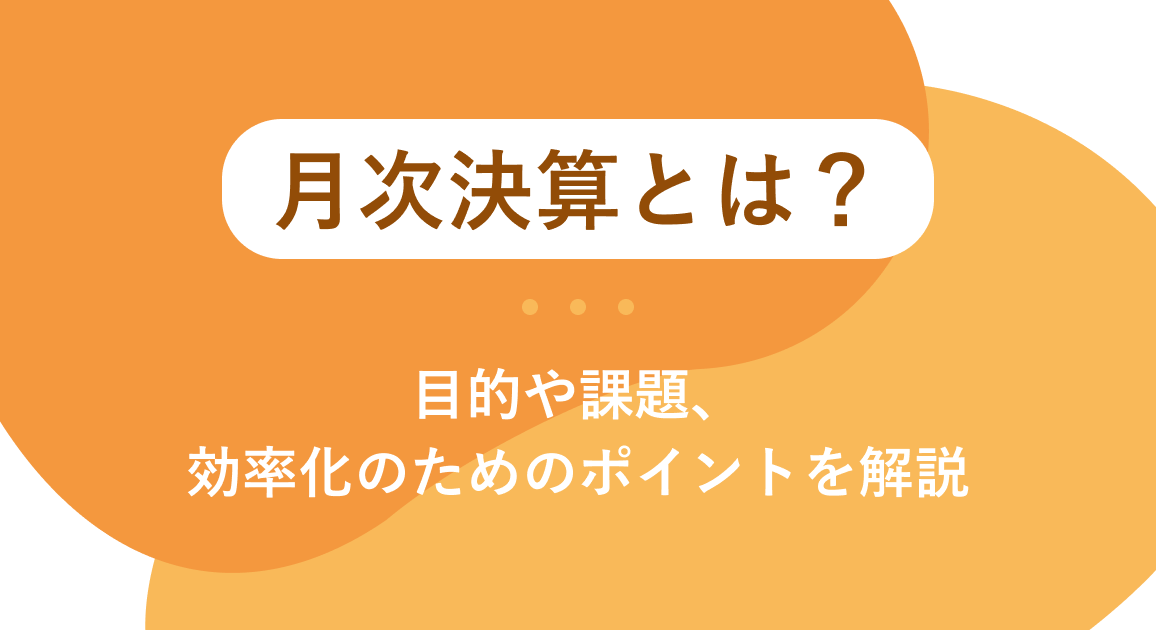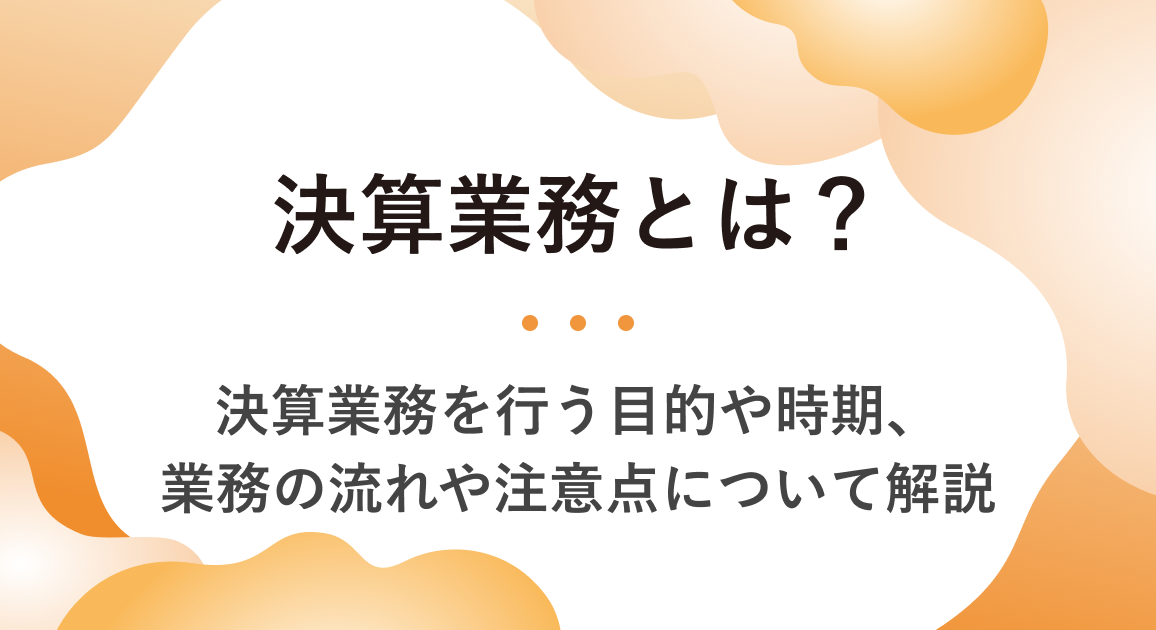- 経理・財務業務
経理処理とは?具体的な業務内容や効率化のポイントを解説
公開日:
更新日:
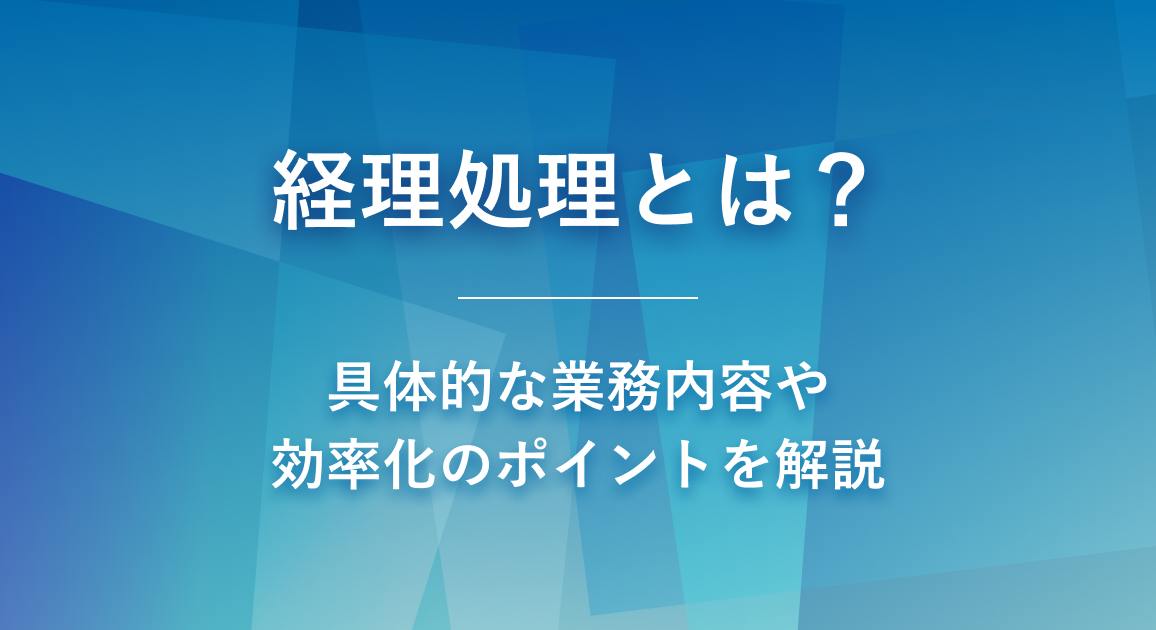
経理処理は、会社の資金の動き全般を扱う業務です。お金に関連する業務が多く、正確かつ迅速な処理が求められます。
この記事では、経理処理の概要や、具体的な業務内容を解説していきます。また、経理処理の効率化を図るための、5つのポイントについても見ていきましょう。
経理処理業務を効率化
経理処理とは

まずは、経理処理がどのようなものかを解説したうえで、混同しやすい「会計処理」「財務処理」との違いを見ていきましょう。
経理処理の概要
経理とは「経営管理」の略で、会社の資金の動き・業績を数字で明確にし、経営に役立てるまでの業務すべてを指すものです。
具体的には以下のような業務が含まれます。
- 伝票の作成
- 仕訳
- 現預金の管理
- 請求書の発行・受領
- 入金管理・消込
- 経費精算
- 給与計算
- 税金の管理
- 決算報告関連書類の作成
会計処理との違い
経理処理とは、前述したように会社の資金の動き・業績を数字で明確にし、経営に役立てるまでの一連の業務をすべて含みます。
一方で会計処理とは、帳簿への記帳業務のみを指しています。帳簿への記帳業務とは、お金の流れを始めとして業務取引を仕訳として計上することです。
よって、会計処理は、経理処理に含まれる多くの業務のうちの一つだといえます。
財務処理との違い
経理処理と財務処理は、業務内容も役割も異なります。
会計処理を含む経理処理では、会社の資金の動きや財政状態・経営成績を数字で明確にし、帳簿やデータを作成します。一方財務処理は、経理処理によって作成された帳簿やデータの内容を活用し、資金の確保や管理を行う業務です。
よって、会計処理や経理処理は、財務処理を行うための前段階という捉え方もできるでしょう。
経理処理の具体的な業務内容

経理処理における主な業務内容として、以下の9つを紹介します。
- 伝票の作成
- 仕訳
- 現預金の管理
- 請求書の発行・受領
- 入金管理・消込
- 経費精算
- 給与計算
- 税金の管理
- 決算報告関連書類の作成
それぞれ見ていきましょう。
1.伝票の作成
仕訳伝票は、請求書などの元資料から会社の取引を仕訳という形で記録する業務です。資料から取引内容や取引相手を把握し、伝票に「仕訳」として記載することで、会計帳簿に記帳できる状態になります。伝票を使用すれば帳簿への入力は誰でも可能となるため、入力の担当者を分散させることも可能です。
なお、伝票には以下のように、さまざまな種類があります。どの伝票を使用するかは、会社ごとに選択することが可能です。
伝票の種類 | 概要 |
|---|---|
振替伝票 |
|
入金伝票 |
|
出金伝票 |
|
仕入伝票 |
|
売上伝票 |
|
2.仕訳
仕訳は、会計帳簿に記帳する業務です。ここでは前項目で紹介した伝票上で仕訳を作成する業務の概要を説明します。
仕訳とは、取引を「借方」「貸方」の勘定科目に当てはめることです。一般的に「借方」は、資産の増加、負債の減少、費用の計上、「貸方」は資産の減少、負債の増加、収益の計上を表します。
具体例として、1個200円の商品を2個、現金で販売したケースにおける、仕訳の方法を以下で紹介します。
【仕訳】
借方 | 貸方 |
現金 / 400円 | 売上 / 400円 |
仕訳を記帳する際には、一般的に会計ソフト上で「現金」「売上」の勘定科目、400円という金額、取引日、消費税の課税区分、「現金にて販売」といった取引の内容等を入力します。
日々の取引を帳簿に記帳する業務が仕訳です。すべての仕訳を合計すると、最終的に「貸借対照表」「損益計算書」という、企業の財政状態・経営状況を示す書類が作成できます。
3.現預金の管理
現預金の管理業務では、主に以下のようなことを行います。
- 小口現金の入出金時に、領収書などを基に現金出納帳に記録
- 現金の残高と現金出納帳の残高が一致しているかをチェック
- 預金残高と会計帳簿(または出納帳)の残高が一致しているかをチェック
- 現預金残高と会計帳簿(または出納帳)との間に差異がある場合は、原因を調査
これらのチェックを行わないと、現金の盗難や預金の不正出金があったり、領収書を紛失していたりしても気付くことができません。現預金管理は、不正防止のためにも大切な業務です。
4.請求書の発行・受領
請求書は、サービスや商品の代金を請求する際に発行するものです。納品書とは別に発行されるか、納品書兼用とされる場合もあります。
請求書処理には「発行」と「受領」の2種類があります。
- 発行
- 取引先(購入側)への請求書作成・送付
- 受領
- 取引先(販売側)からの請求書受け取り・確認・支払い
【発行業務】
請求書の形式は、必要事項が記載されていれば自社で自由に決められますが、場合によっては取引先に指定されることもあります。請求書を発行し忘れると、取引先から入金されないため、漏れのないように注意が必要です。
発行した請求書の保管は税務上義務づけられており、税務調査時に提示が必要な重要書類であるため、整理しておきましょう。
【受領業務】
請求書を受け取ったら、内容を確認した上で支払いが漏れないように処理します。
受領した請求書も、税務調査時に提示が必要な重要書類であるため、整理しておきましょう。
5.入金管理・消込
入金管理・消込では、取引の相手から正確に入金が行われたかどうかの確認を行います。
具体的な業務内容は、以下の通りです。
- 請求書を確認し、期日通りかつ正確な金額で入金されたかをチェック
- 入金が正確であれば、売掛金を帳簿から消去する(入金消込)
- 過不足や入金漏れがあった場合には、相手方に連絡をとり、問い合わせや催促を行う
入金消込の具体的な業務は以下の通りです。
- 販売システムを利用している場合、システム上「入金」の処理をする
- 会計帳簿上で、入金があった旨の仕訳を計上する
入金遅れや入金漏れがあると、本来入るべき現金が少なくなり、資金繰りが悪化します。入金管理は、取引の対価の支払いが正常に行われているかを管理することで、企業のキャッシュフローを正常な状態に保つ、重要な業務です。
6.経費精算
経費精算は、従業員が一時的に立て替えた交通費や出張費などの経費を精算する業務です。
一般的な経費精算(実費精算)の流れは以下の通りです。
- 従業員が業務で発生した経費を立て替え、領収書を受け取る
- 従業員は経費精算書と領収書を、上長に承認を得た上で経理に提出
- 経理が領収書を確認し、費用を従業員の口座に振り込むための処理を行い、仕訳計上を行う
経理担当者は、従業員への支払いを遅滞なく行うだけでなく、精算業務が滞っていないかを確認しましょう。領収書の提出がないと、取引が仕訳として計上できず、タイムリーな会社の業績を帳簿上反映できません。
経費精算は、「立替精算」と「仮払い精算」の2種類に分けられます。
- 立替精算
従業員が経費を立て替えたあと、会社に対して精算を申請する方法
- 仮払い精算
会社が従業員に概算で経費を仮払いし、あとで実際の経費に基づいて調整を行う方法
7.給与計算
給与計算は、勤怠状況や手当などを基に給与の総支給額を計算し、社会保険料や税金を差し引いて手取り額を算出する業務です。年に一度、年末調整に関する業務もあります。企業と従業員間での労働契約を履行するための大切な業務であり、注意深く行う必要があります。
給与や手当の金額は従業員ごとに異なるため、正確に入力し、チェックしましょう。また、税金や社会保険料の計算についても、給与ソフトの設定の正確性を確認することが大切です。
また、所得税、住民税、社会保険料は、会社が従業員から預かったものを税務署、地方自治体、年金事務所に納付する義務があります。正確に漏れなく控除しましょう。
8.税金の管理
会社は、法人税、消費税、固定資産税、源泉所得税などさまざまな税金を支払う義務があります。これらの税金の管理も、経理担当者の仕事の一つです。
法人税、消費税を適切に納税するためには、税金の計算を正確に行い申告しなければなりません。また、源泉所得税は従業員などから預かったものを納付する義務があるため、正確に計算した上で期限までの納付が必要です。
経理では、税務調査の対応も行います。顧問税理士がいる場合には、税理士対応も業務の一つです。
9.決算報告関連書類の作成
決算期には、決算書を作成します。決算書は、会社の経営成績や財政状態を表すものであり、具体的には「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」などを指します。
決算書は税務申告時に必要になるだけでなく、会社の経営成績や財政状態を外部(銀行や取引先など)に説明するための重要な資料です。
また、決算書は決算日時点の業績を表すことから、自社の今後の経営判断の参考になります。決算書の作成は、税務申告時に添付するためなら年に一度で良いですが、経営判断の参考にするのであれば、1カ月単位で任意に行われる「月次決算」を行い、リアルタイムで数字を把握することが望ましいでしょう。
経理処理業務でよくある4つの問題点
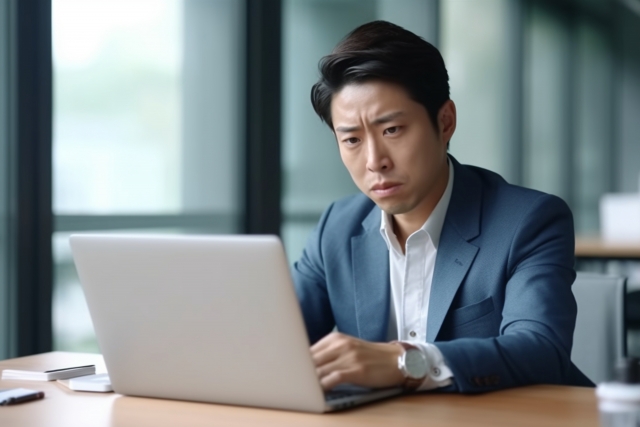
経理処理業務は幅広く作業も多いため、企業では下記のような4つの問題点がよく見られます。
- 専門知識が必要で業務が属人化する
- 精神的な負担などで作業の遅れが発生しやすい
- 紙のやり取りによる非効率が生じる
- 法改正への対応が求められる
それぞれ詳しく解説しましょう。
1.専門知識が必要で業務が属人化する
経理業務には、簿記や税務、資金管理など、さまざまな専門知識が必要です。このため、担当者が限定され、業務が特定の人に集中しやすくなります。特に小規模な組織では経理担当者が少ないため、担当者が急に休んだり退職した場合、業務が滞るリスクが高まります。
また、経理業務が属人化すると、他の社員が業務内容を把握できず、担当者の不在時に代替できず、業務が滞る恐れもあります。さらに、業務内容が不透明になりやすいため、不正行為が行われるリスクも増加します。
属人化を防ぐためには、業務の手順をマニュアル化するなどして複数の社員が同じ業務を共有・実行できる体制を整えることが重要です
2.精神的な負担などで作業の遅れが発生しやすい
経理業務には、会社の資金管理や決算書類の作成など、経営に直結する重要な業務が含まれます。このため、担当者には強いプレッシャーがかかりやすく、慎重に進めるあまり作業が遅れることが少なくありません。特に金額に関わる業務では、ダブルチェックや確認作業が必要で、業務のスピードが低下することがあります。
作業の遅延が発生すると、経営判断のタイミングにも影響を及ぼし、全社的な業務の進行に支障をきたす可能性があります。こうしたリスクを軽減するためには、業務プロセスの見直しなど経理業務の効率化が必要です。
3.紙のやり取りによる非効率が生じる
請求書・納品書・領収書などを紙でやりとりしている企業は今でも少なくありません。しかし、紙の書類を発行・管理することで業務が複雑化し、非効率なプロセスが生じやすくなります。
書類の数が膨大になると、データ入力や確認作業に多くの時間を要し、印刷コストも増加します。また、紙の書類は紛失リスクが伴うため、厳重な管理が必要です。さらに、大量の書類を保管するためのスペースの確保も企業にとって負担となります。
こうしたムダを減らすためには、ペーパーレス化の推進が重要です。電子化することで業務の効率化を図り、時間やコストの削減に役立ちます。
4.法改正への対応が求められる
会計基準や税法が改正されるたびに、経理担当者は最新のルールに基づいて業務を進める必要があります。例えば、2022年1月1日の電子帳簿保存法の改正により、領収書や請求書などの取引情報を電子的に受け渡す電子取引に対応することが求められました。
このため、現状の電子取引を確認し、データの保存方法や業務フローを再検討して法規に適合する形に整える必要があります。正しく対応できなければ、罰則を受けるリスクもあります。
通常の業務の上にルール変更に対応するのは容易ではなく、業務の負担が増える可能性もあります。
経理処理業務を改善するための4つのSTEP

経理処理業務の問題点を改善するためには、下記の4つのSTEPに沿って進めていくと良いでしょう。
- 業務内容を全て把握する
- 経理部門の業務フローを設計する
- 課題を特定し改善策を考える
- 具体的な改善プランを実行に移す
それぞれのSTEPについて解説します。
STEP1.業務内容を全て把握する
経理業務の改善を進めるには、まず現在行っている業務を全て把握することが重要です。各担当者が日々の業務内容を時系列で書き出し、全体を可視化することで、何が非効率を生んでいるのかを明確にします。この作業によって無駄な手順や重複作業がないかを確認し、どの部分が改善の対象になるかを特定しやすくなります。
STEP2.経理部門の業務フローを設計する</h3>
次のSTEPは、経理部門全体の業務フローの設計です。経理責任者が各担当者と連携し、それぞれの業務内容を確認しながら、全体の流れを整理し「見える化」することによって、どの業務がどのタイミングで行われているのか、どこでボトルネックが発生しているかを把握します。
業務の実施時期や順序、担当者の配置、必要な承認フローなどを整理し、経理部門全体の最適な業務フローを設計していきます。
STEP3.課題を特定し改善策を考える
業務内容を洗い出し、フローを見える化した後は、そこから具体的な課題を特定し、改善策を考えることが重要です。業務の中で無駄な作業や時間がかかりすぎている部分、ミスが発生しやすい箇所などを細かくチェックします。
例えば、手作業で行っている部分を自動化できないか、作業の重複を避ける方法がないかを検討します。
STEP4.具体的な改善プランを実行に移す
改善策が整ったら、実際にそのプランを実行に移します。例えば、重複していた業務を一元化したり、ITツールの導入で手動入力を減らすなど、効率化を図る具体的なアクションを取ります。
ただし、実行しただけでは十分ではありません。施策が適切に機能しているかを定期的に確認し、必要に応じて調整を加えることが重要です。状況に合わせた改善を繰り返し、PDCAサイクルを回して最適な業務フローを維持していくことが、経理処理業務を継続的に改善するための鍵となります。
経理処理業務の効率化で得られる5つのメリット

経理処理業務を効率化することで下記の5つのメリットが得られます。
- 業務負担が軽減し社員の満足度が向上する
- コストの削減が期待できる
- ミスが減り、数字の間違いがなくなる
- 時間的な余裕ができ、コア業務に専念できる
- 意思決定のスピードが向上する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.業務負担が軽減し社員の満足度が向上する
決算期などには通常の業務に加えて大量の作業が発生し、経理担当者の負担が増えるケースがよくあります。残業や休日出勤が続くと、担当者のモチベーションも低下しがちです。しかし、経理業務を効率化することで作業量を平準化し、残業や休日出勤を減らすことが可能です。これにより業務負担が軽減され、プライベートな時間を確保できるようになります。
業務負担が軽くなれば、従業員の満足度が向上し、離職率の低下にもつながります。特に単純作業や煩雑な書類処理を効率化することで、時間に余裕ができ、ストレスも軽減されます。結果として、社員の仕事への意欲が高まり、長期的な人材確保にもつながるでしょう。
2.コストの削減が期待できる
経理処理業務を効率化することでコスト削減が期待できます。効率化のためには、業務のデジタル化が不可欠です。これにより紙の使用や印刷にかかるコストが削減されます。また、デジタル化によって業務のスピードが向上し、従来の手作業で行っていたルーティンワークにかかる時間も大幅に短縮できます。
その結果、残業や休日出勤が減り、従業員に支払う賃金も抑えられるため、人件費の削減にもつながります。さらに、ペーパーレス化による資料管理の簡素化や保存場所の削減なども、全体的なコストダウンに貢献します。
3.ミスが減り、数字の間違いがなくなる
経理業務の効率化による大きなメリットの一つは、ミスの削減です。経理作業では、入力や計算といった単純な作業が多く、手作業で行うとヒューマンエラーが発生しやすくなります。特に大量のデータを短時間で処理しようとすると、数字の間違いや計算ミスが避けられないことがあります。
しかし、ITツールや自動化システムを活用することで、これまで手作業で行っていた部分を自動化し、ミスを大幅に減らすことが可能です。自動化によってダブルチェックが不要になり、業務の効率が向上するだけでなく、数字のズレや二重請求など、取引先の信頼を損なうリスクも低減できます。経理業務の正確性が高まれば、業務負担も軽減されるだけでなく、取引先からの信頼もより高まるでしょう。
4.時間的な余裕ができ、コア業務に専念できる
経理業務を効率化することで、時間的な余裕が生まれ、コア業務に専念できるようになります。コア業務とは、企業の利益に直結する重要な業務で、主に営業活動やマーケティング戦略の実行、または株主総会向けの報告書作成などが含まれます。これらの業務は企業の成長に不可欠であり、優先して取り組むべき内容です。
経理業務にかかる時間を削減すれば、従業員がこうした重要な業務に多くの時間とエネルギーを割けるようになります。特に、効率化によって雑務が減ることで、従業員の集中力も向上し、結果的に企業全体の生産性向上にもつながるでしょう。効率的な業務環境を整えることで、企業が成長する基盤をしっかりと築けるのです。
5.意思決定のスピードが向上する
経理業務の効率化によって、企業の意思決定スピードが向上します。経営環境が目まぐるしく変わる現代において、経営陣が迅速かつ的確に意思決定を行うことは、企業の存続や成長に不可欠です。その際、判断材料として重要なのが経理で作成される月次決算書です。業務の効率化が進むと、決算書を作成するまでの時間が短縮され、経営陣は早い段階で自社の経営状況を把握できるようになります。
それによって重要な経営判断を迅速かつ余裕をもって行えるようになり、適切なタイミングでの戦略的な意思決定が可能となるのです。結果として、企業が市場の変化に柔軟に対応しやすくなり、経営の安定と成長につながるでしょう。
経理処理を効率化するポイント
経理処理は、日々の伝票作成や仕訳の記帳、請求書の発行・受領、入金管理、税金の管理、決算関連書類の作成など、会社のお金に関する重要な業務を行うため、正確さが求められます。
ミスが許されないうえに、提出に期限があったり、処理すべき対象が膨大であったりするため、手作業中心担当者の負担が大きくなりがちです。以下、経理処理を効率化するポイントを紹介していきます。
会計関連書類フォーマットを統一する
経理処理で使用する書類のフォーマットを統一すると、記載すべき必要事項やチェックすべきポイントも統一して設定できます。マニュアルを用意し、誰でも作成、チェックができる状態になれば、分業などの効率化が図れるだけでなく、業務の属人化の防止にもつながるでしょう。
例えば経費計算の申請書や、自社で発行する請求書など、社内で作成する書類は、会社として統一することが望ましいでしょう。
関連書類を電子化する
経理処理に使用する書類は、実務上、紙面で運用しているケースが多くありますが、書類を電子化すると工数を大幅に効率化できます。
例えば請求書発行を電子化すると、プリントアウトや押印、封入・封かん・郵送といった手間が不要になります。これにより、プロセスが簡略化され、他の重要な業務に時間を割くことができるでしょう。
また、電子化すると検索や管理がしやすくなり、文書の保管にかかる手間やリスクも低減されます。
ツールやシステムの導入
経理業務に関するツールやシステムを導入すると、画像データの自動読み込み機能で入力作業が減少し、業務効率の向上が見込めます。また、金額などの入力ミスを防ぐことができ、正確性も保てるでしょう。
一般的な表計算ソフトでは、複雑な処理に限界があったり、手入力が必要な箇所があったりして、人為的ミスが起こりやすい環境にあります。計算式を壊してしまう、保存せずに削除してしまうといったトラブルも、よく発生するところです。
一方でツールやシステムの場合、データを壊したり削除したりするリスクはほぼない上に、基の画像データを自動読み込みし、システム間でのデータ移行や、データからの仕訳計上が可能です。また、クラウドシステムなどを導入すれば、社内の情報共有もしやすくなります。
キャッシュレス化の推進
小口現金の取引が多いと、出金(現金精算)の手間がかかる上、現金を多額に保有する必要がでてくるため、紛失・盗難のリスクも高まります。
法人カードを導入してキャッシュレス化を進めれば、現金で経費精算をする必要がなくなります。特に従業員数が多く、現金精算の件数が多い会社では、大幅に業務を削減でき効率化できるでしょう。社内に保有する現金を減らすこともでき、両替や補充、金庫管理などの管理作業が不要になります。
また、法人カードを利用すると、取引の日付や取引先、金額などのデータを入手できます。データであれば明細の参照がしやすいだけでなく、会計システムなどへの自動連携が可能になるため、記帳作業の時間を短縮でき、正確性も確保できるでしょう。
アウトソーシングの活用
経理業務を部分的にアウトソーシングすれば、担当者の負担を軽減することができます。アウトソーシングには、以下のようなさまざまなメリットがあります。
- 社内の人員が、経理以外の本業に注力できる
- 経理処理を行う方の雇用コスト、育成コストを削減できる
- 内部不正やミスの防止が期待できる
- 専門の方に依頼するため、正確な処理だけでなく法律や税制の改正にも迅速に対応できる
- 従業員の急な退職での引き継ぎ不足や採用の難航により、経理処理が遅延するリスクを軽減できる
とはいえ、経理処理は、会社の資金の動き・業績を数字で明確にして経営に役立てるという、経営に欠かせない業務です。すべての業務をアウトソーシングすると、ノウハウが社内に残らず、後々苦労する可能性があります。また、情報漏えいリスクや、アウトソーシングに係るコストが多額になるリスクもあります。
そのため、すべての経理業務ではなく、給与計算や請求書作成といった特定の業務だけアウトソーシングする、繁忙期のみ活用する、といった利用も検討すると良いでしょう。
まとめ
ここまで経理処理の概要や具体的な業務内容を解説しました。経理処理には、伝票作成や仕訳、現預金の管理、請求書の発行・受領、給与計算、税金管理など幅広い業務が含まれます。
経理処理業務は専門知識が必要であることから属人化が発生し、ミスが許されないため作業の遅れが発生します。特に、紙の書類を使用した経理処理は、ミスが起こりやすく、手間もかかります。
経理処理を正確かつ効率的に進めるためには、アナログからデジタルへのシフトが有効です。
「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。
請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。
債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。
経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。
これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。
Bill One(請求書受領)の特長
- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する
- 受領した請求書データを一元管理できる
- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック
- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合
- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管
- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One(債権管理)の特長
- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行
- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理
- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能
- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能
- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結
Bill One(経費精算)の特長
- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる
- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結
- 99.9%*の精度で領収証をデータ化し、自動で利用明細と突合
- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応
- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止
- 1カ月あたりの利用限度額が最大1億円
- カードごとの利用限度額設定が可能
- 年会費・発行手数料無料
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。


3分でわかる
Bill One請求書受領
請求書受領から、月次決算を加速する
クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。




3分でわかる Bill One債権管理
リアルタイム入金消込で、現場を強くする
クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。




3分でわかる Bill One経費
立替経費をなくし、月次決算を加速する
クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。



執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。