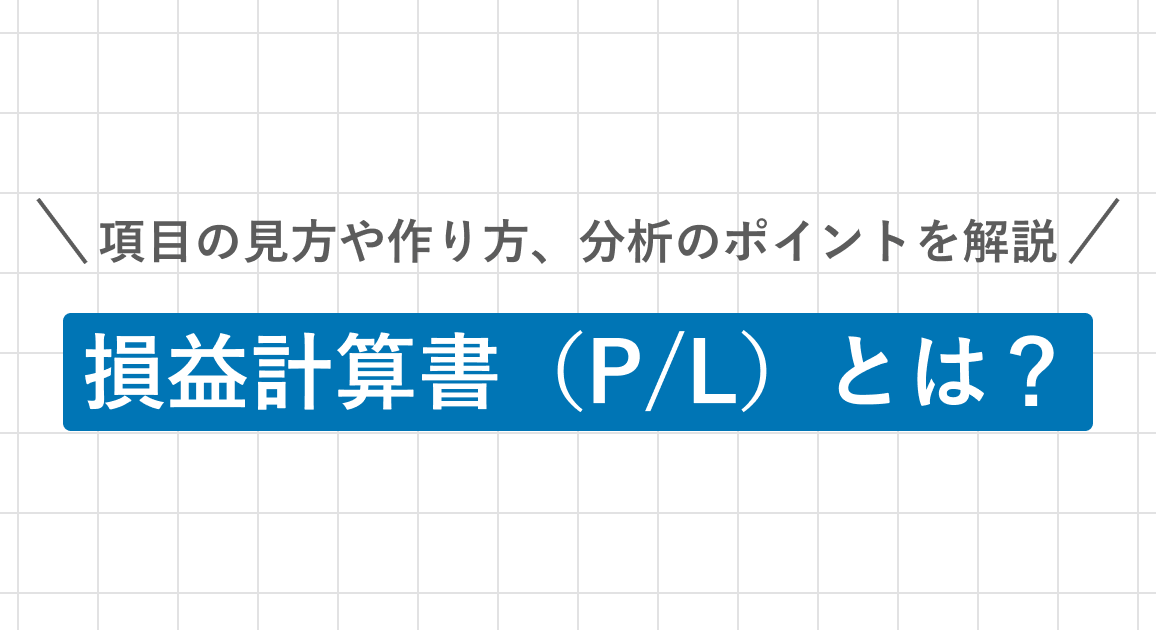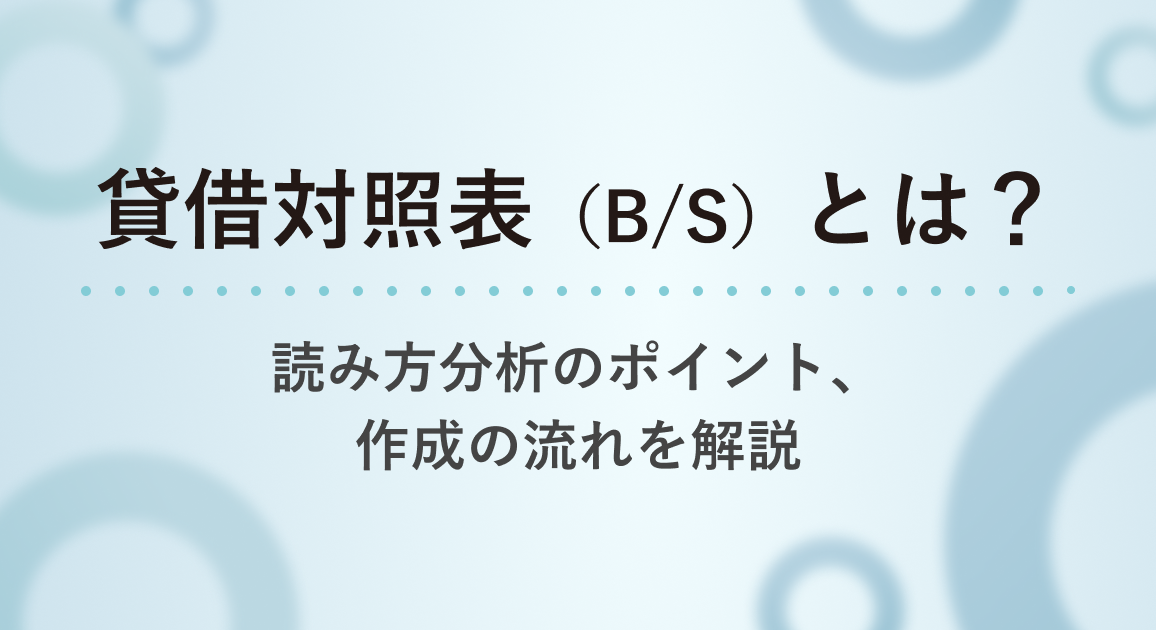- 経理・財務業務その他
売上の仕訳を正しく行う方法とは?勘定科目や計上基準を詳しく解説
公開日:
更新日:
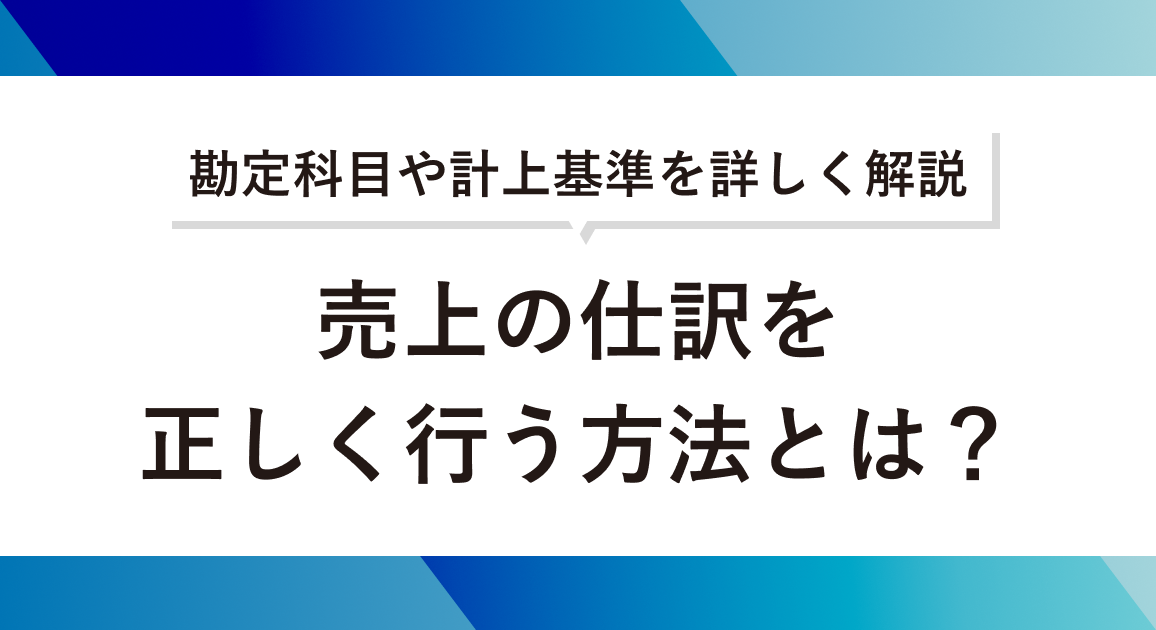
売上の仕訳処理は、企業会計において非常に重要なプロセスのひとつです。売上を正しく計上しないと、企業の財務状態や税務処理に深刻な悪影響を与える可能性もあります。
本記事では、売上の仕訳方法とその計上基準について、わかりやすく解説します。基本的な知識から具体的な仕訳例までを学ぶことで、売上仕訳への理解を深めることができるでしょう。
ぜひこの記事を参考に、正しい売上仕訳を目指してください。
経理のDXで業務を効率化
売上仕訳の基本

企業の経営活動を記録し、財務諸表を作成するための基礎となるのが「仕訳」です。ここではまず、売上に関する仕訳の基本について解説します。
売上高と売上の違い
売上と売上高の違いを理解することは、適切な仕訳処理の第一歩です。
売上とは、商品やサービスの提供によって得られた収益を指します。一方、売上高は、売上を合計した金額であり、期間ごとに管理することで業績を把握できます。
- 売上:個々の取引における商品やサービスの販売による収益
- 売上高:一定期間(通常は1年間)における、企業の営業活動によって得られた収益の総額
売上高は企業の経営成績を評価するうえで重要な指標です。期間別に売上を管理し、売上高を正確に把握することが必要です。
売掛金の仕訳方法
売掛金とは、企業が商品やサービスを提供した際に、まだ現金で支払われていないが、将来的に受け取る予定の代金を指します。主に掛け売りの際に発生し、売上計上の段階で売掛金として仕訳することで、取引の未回収分を示します。
売掛金の仕訳方法は、現金取引と掛け売りで異なります。たとえば、現金での取引では、売上と同時に「現金」勘定に仕訳しますが、掛け売りの場合には「売掛金」勘定に仕訳します。
- 現金取引時:「現金」を借方に、「売上」を貸方に記入
- 掛け売り時:「売掛金」を借方に、「売上」を貸方に記入。代金を回収した際に「現金」を借方に、「売掛金」を貸方に記入
このように売掛金の仕訳処理を適切に行うことで、売上と未回収分が明確になり、企業の正確な財務状況を把握できます。
売上仕訳が重要な理由
売上仕訳の正確さは、企業の財務および税務に多大な影響を及ぼします。
財務諸表への影響
売上仕訳は、損益計算書や貸借対照表といった財務諸表の作成に利用されます。売上と売掛金、売上原価などの関係を正確に仕訳すれば収益の見通しが明確になり、戦略的な資金運用が可能です。
一方で、仕訳が誤っている場合、財務諸表の内容が正しく反映されず、企業の経営判断を誤らせるリスクがあります。
税務処理への影響
売上仕訳は、法人税などの税額計算の基礎となります。不適切な売上計上は税務調査において指摘される可能性が高く、最悪の場合には罰金や修正申告が必要となる場合もあるため、売上に関連する仕訳は特に慎重に行うことが重要です。
このように、正確な売上仕訳を行うことは企業の財務健全性を保つだけでなく、法的リスクを避けるための基本的な要件でもあるのです。
損益計算書、貸借対照表は以下の記事もお読みください。
売上計上基準の種類

企業が売上を計上するタイミングは、「売上計上基準」によって定められています。売上計上基準は、企業の業種や取引内容によって適切なものを選択する必要があります。ここでは主要な売上計上基準の種類とそれぞれの特性について詳しく解説します。
まず、費用と収益を認識するための会計の考え方としては以下の3つがあります
- 実現主義
- 発生主義
- 現金主義
実現主義
実現主義とは、収益を獲得する権利が確定した時点で売上を計上するという考え方です。実現主義に基づく主な計上基準として、以下の3つがあります。
- 出荷基準
- 引渡基準
- 検収基準
出荷基準
出荷基準は、商品が出荷された時点で売上を計上する方法です。商品の発送が完了すると「売掛金/売上」の仕訳を行い、後日、現金での回収を行う際に「現金/売掛金」として処理します。この方法は製造業や卸売業で頻繁に利用されています。
引渡基準
引渡基準は、商品が取引先に引き渡された時点で売上を計上する方法です。引渡し完了時に「売掛金/売上」として仕訳し、後の支払い時に「現金/売掛金」と記録します。小売業や不動産業などで主に採用されています。
検収基準
検収基準は、商品やサービスが検収され、取引先による確認が完了した時点で売上を計上する方法です。検収完了時に「売掛金/売上」と記録し、支払いが実行され次第「現金/売掛金」と仕訳します。建設業やシステム開発業など、品質管理が厳しい業界で活用されます。
発生主義
発生主義とは、現金の受け渡しに関わらず、収益が発生した時点で売上を計上する方法です。企業は取引の発生時に「売掛金/売上」として記録し、実際の現金回収時には「現金/売掛金」として処理します。
発生主義は取引の発生と収益認識のタイミングが一致するため、会計の期間性を重視した考え方です。長期にわたる取引やサービス提供の際に採用されることが多く、たとえば継続的なサービスを提供するサブスクリプション型のビジネスモデルなどで利用されています。
現金主義
現金主義は、現金が受領された時点で売上を計上する方法です。たとえば、顧客が支払いを行ったタイミングで「現金/売上」として記録します。
現金主義は実際に入金された収益を売上と認識するため、シンプルでわかりやすい会計方法です。この方法は主に小規模な事業やサービス業など、現金取引が多い業態で利用されています。
税務上では限定された場合にしか認められていません。
各業種に適した計上基準
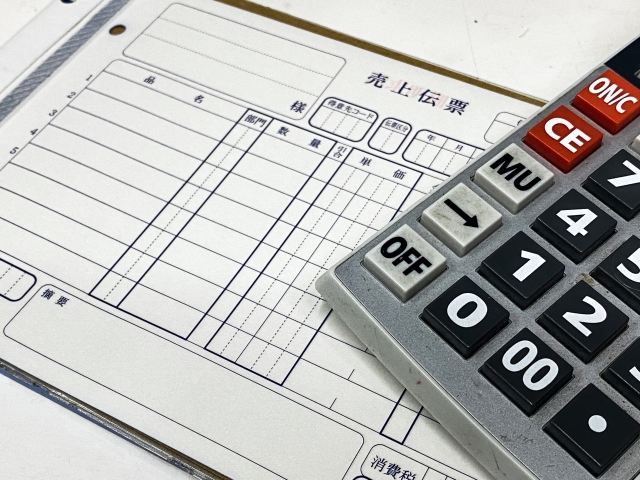
適切な売上計上基準は、業界ごとに異なります。
たとえば製造業では、工場で製造した製品を顧客へ出荷した時点で売上を計上する「出荷基準」が一般的ですし、サービス業では、実際のサービス提供完了後に売上が確定(たとえば美容院で施術が完了した時点で売上を計上)するため「引渡基準」が多用されます。
また建設業で一般に採用されるのは、建物の建設が完了し、顧客の検収が終了した時点で売上を計上する「検収基準」です。
このように業界に適した売上計上基準を選択することは、企業の財務状況を正しく反映するうえで非常に重要です。
特殊なケースの売上仕訳

売上取引においては、標準的な取引以外にも、値引や返品といった特殊なケースが発生することがあります。これらのケースでは、通常の売上仕訳とは異なる処理が必要となります。
売上値引の仕訳方法
売上値引とは、販売した商品やサービスの価格を特定の理由により割り引くことです。たとえば売上が100,000円で、値引が10,000円だった場合、以下のように続けて仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
売掛金 | 100,000 | 売上 | 100,000 |
売上値引 | 10,000 | 売掛金 | 10,000 |
このように値引をその都度正確に記録することで、売上高の過大計上を防ぎ、企業の収益状況を適切に示すことができます。
返品時の仕訳方法
返品が発生した場合は、売上高の減額処理と在庫の調整が必要です。たとえば100,000円の商品が返品された場合、以下のように仕訳します。
販売時の仕訳
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
売掛金 | 100,000 | 売上 | 100,000 |
返品・返金時の仕訳(その1)
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
売上戻 | 100,000 | 売掛金 | 100,000 |
なお「売上戻」を使用せず、「売掛金」と「売上」の勘定科目を入れ替えて仕訳することも可能です。
返品・返金時の仕訳(その2)
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
売上 | 100,000 | 売掛金 | 100,000 |
返品処理は、売上の過大計上を防ぐためにも重要な手続きです。売上高に対する正確な把握ができるように、返品が発生した際は速やかに仕訳処理を行い、企業の財務状況を正しく示す必要があります。
売上と消費税の処理

売上に伴う消費税の処理も、適切な会計処理のために欠かせません。ここでは消費税の計上基準、仕訳方法、非課税取引の処理について解説します。
消費税の仕訳方式
消費税の仕訳方式は「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類です。
税込経理方式では、取引金額に消費税を含めた金額で仕訳を行います。たとえば1,000円の商品を販売し、消費税100円を預かった場合、売上として1,100円を計上します。この方式は、仕訳が簡便であるというメリットがありますが、消費税額を明確に把握できないことがデメリットです。
一方、税抜経理方式では、取引金額から消費税を除いた金額で仕訳を行います。上記の例の場合、売上として1,000円を計上し、消費税100円は「仮受消費税」という勘定科目で処理します。この方式では消費税額を明確に把握できるため、税務申告の際に便利です。
どちらの方式を採用するかは、企業の規模や業種、取引内容などを考慮して決定した方がよいでしょう。
非課税取引等の仕訳方法
消費に負担を求める税として課税になじまないもの(土地等)、社会政策的な配慮から課税することが適当でないもの(医療等)は、消費税は非課税とされています。
また、消費税は国内での消費に課税されるものであることから、国外で消費される輸出物品は、消費税は免除されています。
このうち輸出取引では売上に対する消費税が免除され、仕入にかかった消費税が還付されます。売上時には消費税の仕訳が不要です。また医療や教育などの公益事業も非課税取引に該当し、これらの取引は「非課税売上」として記録されます。
たとえば非課税取引で売上が100,000円の場合、仕訳は「売掛金100,000円/売上100,000円」となり、消費税に関する仕訳が発生しません。
非課税取引等は税務上の扱いが異なるため、課税取引と区別して管理することが重要です。間違えて課税対象として計上すると税務上の問題が発生する可能性があるため、非課税取引等は注意が必要です。
会計システムを活用した仕訳の効率化

会計システムを導入することで、仕訳処理を自動化し、業務を効率化できます。たとえば銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、仕訳を生成する機能や、過去の仕訳データを基に自動で仕訳を提案する機能などがあります。これらの機能は人為的なミスを減らし、業務時間の大幅な削減に役立ちます。
会計システムを導入する際は、自社の規模や業種、業務内容に合ったシステムを選ぶことが重要です。また、導入前に十分な検討を行い、既存の業務フローとの整合性を確認する必要があります。
さらに、システム導入後も定期的なメンテナンスやバージョンアップを行うことで、常に最新の状態でシステムを利用することが大切です。
仕訳のミスを防ぐためのチェックポイント

仕訳のミスを防ぐためには、定期的なチェックが重要です。月次決算時には、以下の項目をチェックしましょう。
月次決算時のチェックリスト
- 売上高と入金が一致しているか
- 売上原価が正しく計算されているか
- 消費税の処理に誤りがないか
- 未払金や未収金などの残高が正しいか
また年次決算時には、より詳細なチェックが必要です。
年次決算時のチェックリスト
- 勘定科目ごとの残高に異常な値がないか
- 貸借対照表と損益計算書の整合性が取れているか
- 税務申告に必要な書類がそろっているか
なお、複数の売上計上基準が混在していると仕訳ミスが発生しやすくなるため注意が必要です。社内で統一した基準を設け、それに基づいて仕訳を行うようにしましょう。また、不明な点がある場合は、会計の専門家に相談することが大切です。
まとめ
この記事では、売上仕訳の基本から、消費税や特殊なケース、会計システムの活用まで、仕訳処理に関する重要なポイントを解説しました。
正確な売上仕訳処理は、企業の財務状況を正しく反映し、経営判断や税務対応に欠かせない要素です。また、会計システムの導入により、仕訳の自動化と業務効率化が実現し、ミスの削減や迅速な意思決定が可能になります。
会計システムを活用すれば、複雑な仕訳が簡略化され、定期的なチェックが容易になります。正しい知識とシステムの活用で、効率的かつ正確な仕訳処理を目指しましょう。
「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。
請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。
債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。
経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。
これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。
Bill One(請求書受領)の特長
- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する
- 受領した請求書データを一元管理できる
- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック
- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合
- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管
- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One(債権管理)の特長
- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行
- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理
- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能
- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能
- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結
Bill One(経費精算)の特長
- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる
- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結
- 99.9%*の精度で領収証をデータ化し、自動で利用明細と突合
- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応
- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止
- 1カ月あたりの利用限度額が最大1億円
- カードごとの利用限度額設定が可能
- 年会費・発行手数料無料
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

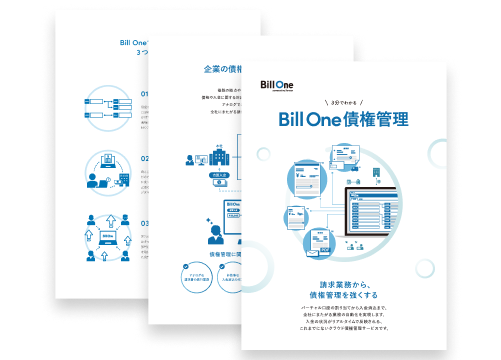
3分でわかる Bill One
「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える
経理AXサービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。



執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介
税理士 松崎 啓介
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
保有資格:税理士
昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務
税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)
その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。