- 経理・財務業務その他
月次決算チェックリストで業務を効率化する方法とポイントを解説
公開日:
更新日:
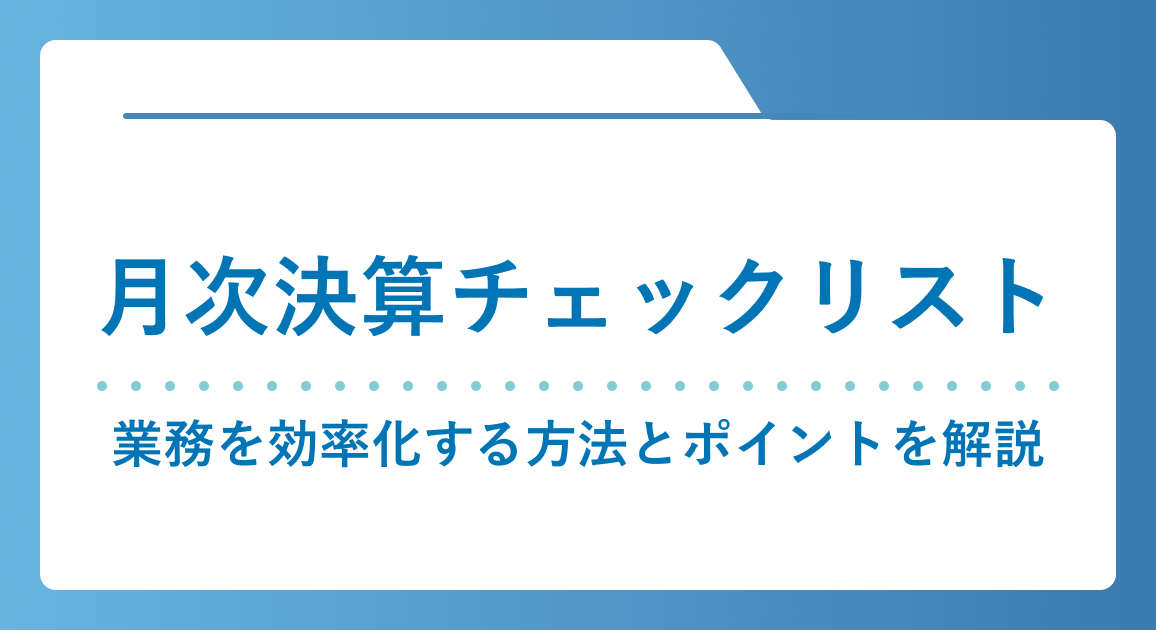
経営における意思決定のスピードを上げるために欠かせない月次決算。しかし、経理担当者にとっては膨大な業務量と確認作業が負担となり、ミスのリスクがつきまといます。本記事では、月次決算を効率化するための具体的な方法として『チェックリスト』に注目し、その活用法や作成時のポイントを解説します。
そこで注目したいのが、月次決算業務を効率化するためのチェックリストです。本記事では、月次決算の基本的な流れから、チェックリストによる確認事項まで、実践的なポイントを解説します。
月次決算を効率化するヒントが分かる!
月次決算とは

月次決算は、企業の財務活動を月単位で整理・分析することです。1カ月間の経理データを収集して経営状況を正確に把握することで、適切な改善策を早期に講じるための基盤となります。
月次決算については、こちらの記事にも詳しくまとめています。ぜひご参照ください。
月次決算を行う目的
月次決算を行う最大の目的は、企業の財政状況や経営状態を毎月的確に把握することです。
月単位で収益や支出の管理を行うことで、経営陣は迅速な意思決定が可能になり、課題へ早期に対策を取れます。
収益性の低い事業や部門を特定して改善策を早急に講じたり、支出の過多を早期に発見してコスト削減や予算の見直しをしたりすることで、企業全体の健全性を維持することにもつながります。
また、月次決算は年次決算の準備としても役割を果たし、会計データの精度向上や業務の効率化に貢献します。
年次決算との違い
年次決算は法律に基づいて行われるのに対し、月次決算は企業が任意で実施するものです。
また、年次決算が外部向けの情報提供を重視するのに対し、月次決算は内部の経営活動の改善や効率化を目的として行われる点が異なります。
年次決算は主に外部への報告を目的とし、株主や取引先、金融機関などのステークホルダーに対して企業の財務状況を説明するために行います。
一方、月次決算は経営陣が迅速かつ正確な経営判断を行うための内部情報として活用されるのが特徴です。
月次決算を行うメリット
月次決算を行うことで毎月の財務情報が明確になり、予算との差異や業績の変動をタイムリーに把握できます。これによって売掛金の未回収や在庫過不足、支出の増加といった課題を早期に発見できるようになり、迅速に対策を講じることが可能です。
また、月次での確認・修正を繰り返すことで年次決算の準備が進み、作業負担が軽減されるとともに正確性も向上します。
さらに、最新の財務データを金融機関に提供することで融資審査がスムーズに進み、企業の信用力も向上します。
月次決算チェックリストの確認事項

ここからは、具体的な確認事項を挙げて解説します。
チェックリストで下記の確認項目を一覧化し、作業手順を具体的に記すことで、作業内容を整理し、進捗状況を一目で把握できます。このリストを活用することで、各作業の確認が効率化され、担当者間での情報共有もスムーズになります。また、作業の精度が向上し、ミスのリスクを大幅に軽減できます。
事前準備
事前準備は、月次決算をスムーズに進めるための基盤となる作業です。
まず、小口現金出納帳を集計し、残高と照合して不一致がないか確認します。
次に、小口現金の精算仕訳や口座仕訳を確認し、未登録や誤りを防ぎます。給与に関する仕訳も見直し、正確性を確保します。
さらに、売上や仕入れなどの月末一括仕訳、在庫仕訳の確認も行い、全体の整合性を確認することが重要です。
現金・預金
現金や預金の残高確認を行い、帳簿に記録された金額と銀行口座の残高が一致しているかをチェックします。この作業では、通帳や銀行取引明細書と帳簿を照合し、不一致があればその原因を調査します。
差異が発生するのは、未処理の振込手数料や未記帳の取引などが主な原因です。原因を特定したら正確な修正仕訳を行い、帳簿と実際の残高を一致させます。
現金についても、実際に手元にある金額を確認し、帳簿上の記録との整合性を確認する必要があります。
売掛金・買掛金
月次決算では、売掛金と買掛金の確認が欠かせません。具体的には、未回収の売掛金がないかをチェックし、必要に応じて担当者に回収を依頼します。同時に、未払いの買掛金がないかも確認し、取引先への支払いが滞っていないかを確認します。
こうした作業を通じて、帳簿上のデータと実際の状況が一致しているかを確認し、差異がある場合は修正仕訳を行うことが重要です。
売掛金が放置されると回収不能リスクが高まり、買掛金の遅延は取引先との関係悪化につながる可能性があります。
仮払金・仮受金
仮払金は、社員が出張費や経費などを一時的に受け取った際に記録されるものです。実際の使用内容が判明した段階で正しい費用項目に振り替える必要があります。同様に、仮受金も一時的な入金として記録された項目です。その用途や返済状況を確認し、適切な勘定科目に振り替えることが求められます。
これらの処理が未完了のままだと、帳簿の正確性が損なわれ、財務状況の把握に支障をきたす恐れがあります。未清算の項目がないよう定期的に確認し、必要に応じて担当者に精算を依頼する必要があります。
在庫・棚卸資産
帳簿に記録された在庫数と実際の在庫が一致しているかをチェックし、差異がある場合はその原因を特定します。
不良品や納品ミス、棚卸時の記録ミスなどが差異の主な要因となるため、必要に応じて返品処理や修正を行い、正確な在庫データを反映させることが必要です。在庫確認を徹底することで、月次決算の正確性を保つだけでなく、適切な在庫管理を通じて経営の健全化にもつながります。
固定資産
月次決算では、固定資産に関する項目の確認も欠かせません。まず、減価償却費が適切に計上されているかを確認します。これは、資産の使用状況に基づいて正確に処理されていなければ、利益計算に影響を与える可能性があるためです。また、引当金が必要な場合は、その金額や計上方法が正しいかもチェックします。
さらに、10万円以上の購入資産は、固定資産としての会計処理が適切に行われているかを確認する必要があります。
借入金
借入金の管理も重要な確認事項の一つです。具体的には、短期借入金・長期借入金の返済予定表と帳簿に記録された残高を照合し、一致しているかを確認します。また、毎月の返済に伴う元金と利息の仕訳が正確に行われているかもチェックが必要です。
こうした確認が不十分だと、返済計画の遅れや帳簿の不整合が発生し、企業の財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
未払金・預り金
月次決算では、未払金や預り金の確認も忘れずにしなければなりません。
まず、月末時点での未払金や預り金が帳簿と一致しているかを確認します。
特に、所得税や住民税といった法定義務のある項目については、その金額が正確であることを入念にチェックする必要があります。
これらの金額に誤りがあると、税務申告や支払期日に影響を与え、場合によってはペナルティーのリスクを伴う可能性があります。また、未払金や預り金の処理が遅れると、取引先や従業員との信頼関係にも悪影響を及ぼしかねません。
経過勘定
経過勘定の処理として、次月以降に支払いや受取が予定されている項目を当月分の未払費用や未収収益として適切に計上します。この作業を怠ると、期間損益が正確に把握できず、財務報告の信頼性を損なう可能性があります。
損益科目
損益項目の確認は、月次決算で収益性や費用構造を正確に把握するために重要です。
売上高は、計上漏れや誤った金額がないか確認し、特に月末の締切処理に注意します。仕入や外注費などの費用項目では、計上ミスや未計上がないかをチェックし、費用配分が適切かを見直します。販管費や一般管理費では、特に広告費や交通費などの細かい項目を確認し、不適切な経費が含まれていないか精査します。
また、減価償却費についても計算が正確か確認が必要です。
貸借対照表
貸借対照表の確認では、帳簿全体の整合性をチェックすることが重要です。まず、各勘定科目でマイナス残高がないか確認します。万が一マイナス残高が発生している場合、その原因を特定し、適切に修正を行う必要があります。また、借方と貸方が一致しているかを必ず確認し、不一致があれば直ちに修正します。
チェックリストを作って月次決算を行うメリット

チェックリストを作って月次決算を行うことには、下記の3つのメリットがあります。
- ミスの防止と正確性の向上
- 効率的な業務進行
- 属人化の防止
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.ミスの防止と正確性の向上
チェックリストにより、確認すべき項目が標準化されるため、担当者に依存せず、業務漏れを防止できます。また、具体的な手順が明確になることで確認作業が効率化され、精度の高い処理が実現します。さらに、誰がどの段階で作業を完了したかを可視化できるため、業務の進捗管理も容易です。
このように、チェックリストを活用することで月次決算業務のミスを防ぎ、正確性を高められます。
2.効率的な業務進行
チェックリストには必要な業務が具体的に整理されているため、担当者は自分が行うべき作業を明確に把握でき、無駄なく作業を進めることが可能です。優先順位がわかりやすくなり、重要なタスクに集中しやすくなります。
また、業務フローが可視化されることで、各工程の進捗状況が共有され、チーム全体でのスムーズな連携が実現します。複数人での作業が必要な場合でも、担当範囲が明確になることで、作業の重複や漏れを防げます。
3.属人化の防止
チェックリストを活用することで業務手順が明確になり、特定の担当者の経験やスキルに依存せず、チーム全員が進行状況を共有できるようになります。
そのため、万が一担当者が不在となった場合でも、他のメンバーがスムーズに業務を引き継ぐことが可能です。
さらに、チェックリストを活用して業務内容を標準化することで、新しい担当者が業務を習得しやすくなり、引継ぎ作業も効率的に行えます。
このように、業務を誰でも実行可能な状態にすることで、業務の停滞を防ぎ、組織全体の安定した運営を実現できます。
月次決算業務の業務フロー

月次決算業務は、下記の業務フローで進めます。
- 現金・預金の残高確認
- 月次棚卸しの実施
- 仮勘定の整理
- 経過勘定の計上
- 月次試算表の作成
- 経営層への報告
それぞれの業務内容について解説します。
1.現金・預金の残高確認
月次決算業務の最初のステップは、現金や預金の残高確認を行うことです。具体的には、帳簿に記載された残高と銀行口座の残高が一致しているかをチェックします。一致しない場合は、その原因を特定し、必要に応じて修正仕訳を実施します。
また、社内で現金を保管している場合は、実際に金額を確認し、帳簿上の金額と整合性が取れているかの確認が必要です。
2.月次棚卸しの実施
月次決算業務の一環として、月末時点で棚卸しを行い、在庫数や評価額を確定します。帳簿上の在庫と実際の在庫に差異がないかを確認し、必要に応じて調整を行います。
棚卸しは、在庫の正確な状況を把握し棚卸資産を適正に管理するために重要です。
過剰在庫は資金繰りに影響を及ぼし、在庫不足は販売機会の損失につながるため、月末のタイミングで在庫状況を確認することは経営上大きな意味があります。
3.仮勘定の整理
月次決算では仮払金や仮受金といった仮勘定の内容を詳細に確認し、適切な勘定科目に振り替えます。
仮払金などが未処理のまま残ると、実際の経費が正確に反映されないことにつながるため、確実に処理することが重要です。整理を徹底することで、帳簿の透明性が向上し、財務管理の精度が高まります。
4.経過勘定の計上
経過勘定の計上は、月次決算で正確な期間損益を把握するために欠かせない作業です。具体的には、前払費用や未払費用、未収収益といった経過勘定を、当月の費用や収益の発生状況に応じて処理します。この作業によって費用や収益が発生したタイミングに基づいて適切に計上されるようになり、期間損益の整合性につながります。
5.月次試算表の作成
取引や費用が整理された後に、月次試算表を作成します。この試算表は企業の財務状況や収益性を示す基本的な帳票であり、貸借対照表や損益計算書の作成に向けた基礎資料です。
6.経営層への報告
月次決算書が完成したら、速やかに経営層に報告を行います。この報告は、財務状況や収益の現状、課題点を経営陣が把握するための重要なプロセスです。経営層はこの情報を基に、経営戦略の調整や意思決定を行います。
月次決算業務時によくある課題

企業経営に多くのメリットがある月次決算ですが、作成に課題があるケースも少なくありません。
ここでは、月次決算業務時によくある課題を2つ取り上げて紹介します。
各部署での処理業務が滞る
月次決算を進める際、各部署での処理が滞ることはよくある課題です。請求書や伝票の処理、経費精算といったデータが期限内に揃わないと、経理部門での作業が遅れ、決算全体に影響が及びます。
特に月末に業務が集中しやすい環境では、忙しさから処理が後回しになったり、情報共有が不足する状況が発生しがちです。
こうした課題に対し、システムを活用して各部署の業務進捗を可視化し、データの一元管理や自動化を取り入れることで、スムーズな処理を実現できます。
経理処理に時間がかかる
月次決算は迅速かつ正確に進める必要がありますが、膨大な手作業や確認作業が発生し、経理担当者の負担が大きいことが課題です。取引データの入力や書類の照合作業、帳簿整合性を保つためのダブルチェックなどは時間を要します。
このような煩雑な作業は、システムを導入することで効率化が図れます。データの自動入力やリアルタイム更新により手間を削減し、締切直前の作業集中を防ぐことでミスのリスクを軽減できます。
まとめ
本記事ではチェックリストを活用した月次決算のチェックリストについて解説しました。
月次決算には、リアルタイムで業績管理が可能になることや課題を早期に発見しやすくなるなど、多くのメリットがあります。そのため、健全経営を行う上で重要な役割を果たします。
ただし、限られた人数で通常の経理業務をこなしている企業にとって、月次決算業務は経理担当者にとって大きな負担となりがちです。このため、重大な見落としや処理ミスが発生するリスクも否めません。
こうしたリスクを低減するために、チェックリストを活用することは有効な手段の一つです。チェックリストを用いることで、作業の抜け漏れを防ぎ、業務の正確性を高めることができます。
しかし、チェックリストの活用だけでは限界がある場合もあります。さらなる効率化を目指すには、システムを導入して業務を自動化し、経理業務全体をスムーズにすることが不可欠です。
「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。
請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。
債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。
経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。
これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。
Bill One(請求書受領)の特長
- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する
- 受領した請求書データを一元管理できる
- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック
- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合
- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管
- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One(債権管理)の特長
- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行
- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理
- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能
- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能
- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結
Bill One(経費精算)の特長
- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる
- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結
- 99.9%*の精度で領収証をデータ化し、自動で利用明細と突合
- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応
- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止
- 1カ月あたりの利用限度額が最大1億円
- カードごとの利用限度額設定が可能
- 年会費・発行手数料無料
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。


3分でわかる
Bill One請求書受領
請求書受領から、月次決算を加速する
クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。




3分でわかる Bill One債権管理
リアルタイム入金消込で、現場を強くする
クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。




3分でわかる Bill One経費
立替経費をなくし、月次決算を加速する
クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。



執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部


