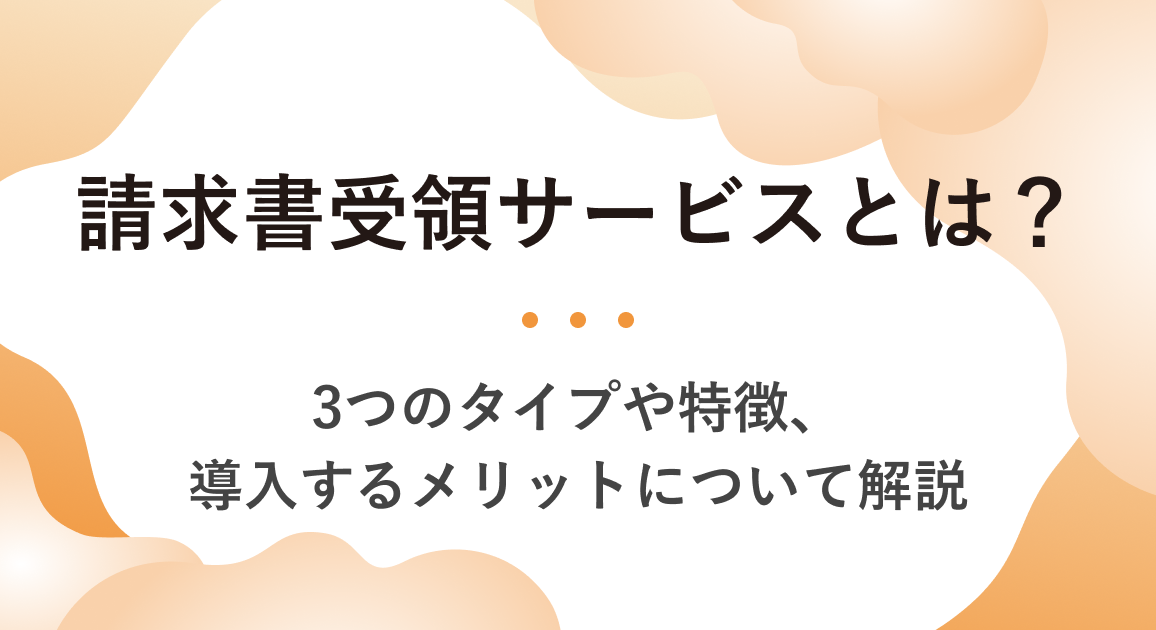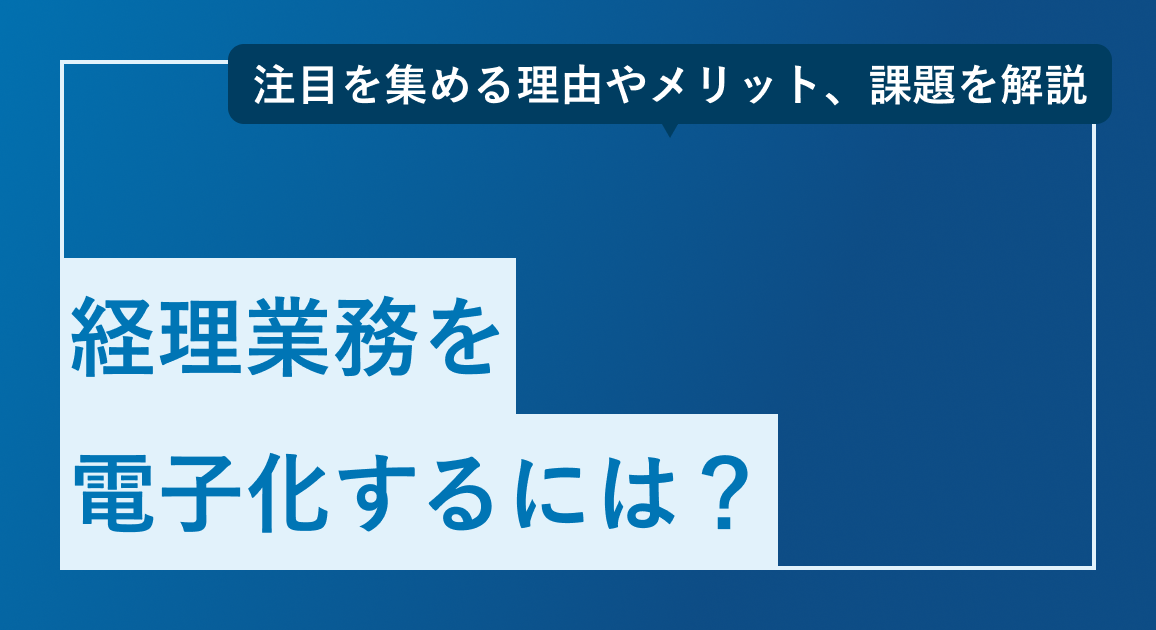- 請求書
請求書の催促方法とは?トラブルを防ぐポイントとメール文面をシーン別に紹介
公開日:
更新日:
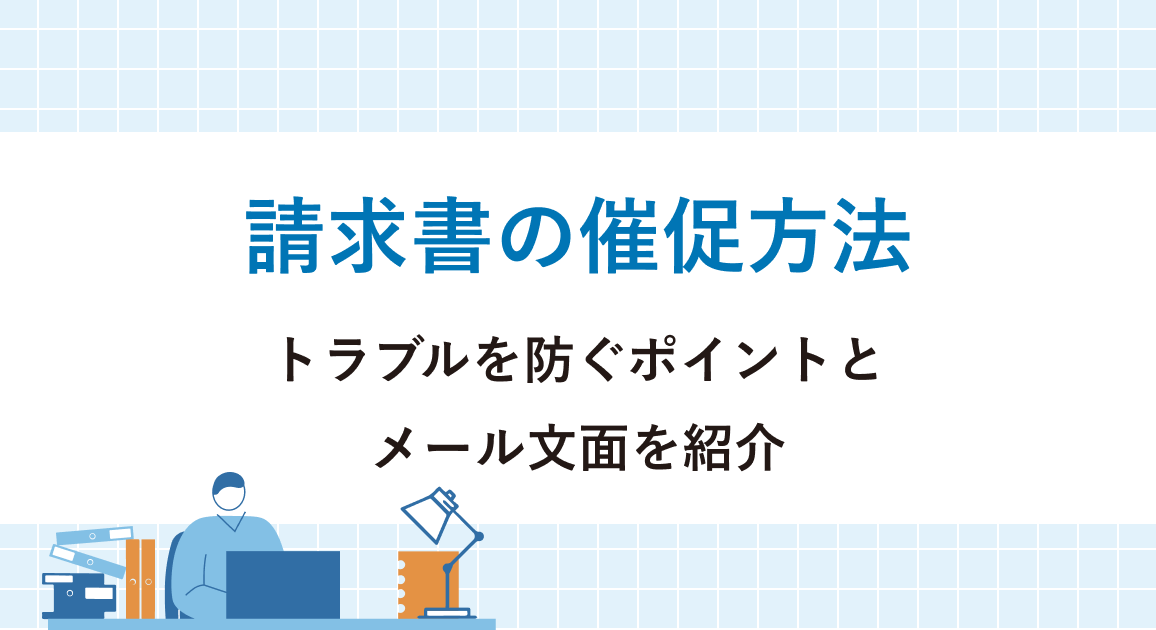
請求書は取引の重要な証となる書類です。しかし「締め切りが迫っているのに請求書が届かない」というトラブルは意外と多く、請求書の催促が必要となる場合もあります。
請求書が届かなくても契約に定められた支払い条件が満たされていれば支払いの義務は発生しますが、もし請求書が届かないまま支払いが遅れると、取引先に迷惑をかけるだけでなく、自社の信用問題に発展する可能性もあります。適切な対応をしなければ、信頼関係が損なわれるリスクも考えられるでしょう。
そこで本記事では、請求書が届かない場合の適切な催促方法を解説します。具体的な催促メールの文例やトラブルを防ぐためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
請求書の一元管理で債務管理を効率化
請求書を催促するときの基本ルール

請求書の催促をする際は、適切なタイミングと丁寧な表現が重要です。ここではまず、催促時の基本ルールをご紹介します。
早めに確認・連絡をする
請求書の受取状況は常に把握することが重要です。月末や締め日のタイミングで慌てて確認するのではなく、日常的に請求書の受領状況を管理しておきましょう。特に重要な取引先や金額の大きい請求書は、自社の支払いスケジュールを考慮して早めの確認を心がけてください。
また、いつもの発行タイミングより請求書の到着が遅いと感じた場合は、支払い期限が迫る前にリマインドメールを送ることをおすすめします。「いつも●日頃に頂いておりますが、まだ届いていないようです」といった形で状況確認を促すことで、先方も気づきやすくなります。
強い口調を避け、柔らかい表現を使う
催促する際は、相手に不快感を与えないよう配慮した表現を使うことが重要です。「請求書が届いていません!」といった強い口調ではなく「お手数ですが、請求書の発行状況をご確認いただけますでしょうか」など、穏やかな表現を心がけましょう。
また「ご多用のところ恐れ入りますが」「ご都合のよろしい際に」などのクッション言葉を活用することで、相手への配慮を示すことができます。催促はあくまでも業務上の確認であり、責めているわけではないというスタンスを保つことで、円滑なコミュニケーションにつながります。
催促のタイミングを見極める
効果的な催促には、適切なタイミングの見極めが欠かせません。一般的には、締め日の3~5日前に最初のリマインドメールを送り、状況確認を行います。この段階では「念のための確認」という軽めのトーンで構いません。
締め日当日~翌日になっても請求書が届かない場合は、やや具体的に催促メールを送りましょう。支払い日程への影響に触れながら、対応の必要性を伝えます。
さらに締め日を過ぎた場合は、メールだけでなく電話での確認も効果的です。直接会話することで状況把握がしやすくなります。必要に応じて督促メールを送付することで、迅速な対応を促すことができるでしょう。
【シーン別】請求書の催促メールの例文

請求書の催促は状況によって適切な表現やアプローチが異なります。ここでは、よくある3つのケースに応じた催促メールの例文をご紹介します。各社の状況に合わせてカスタマイズしながら、テンプレートとして活用してください。
パターン1.通常の催促メール
想定シチュエーション:締め日が近いが、請求書がまだ届いていないケースなど
件名:【ご確認のお願い】2月分請求書について ○○株式会社 経理部 △△様 お世話になっております。 □□株式会社の●●でございます。 いつもお取引ありがとうございます。 2月分のお取引(発注番号:12345)に関する請求書がまだ届いていないようです。 当社では今月の支払い処理を◇月◇日に予定しておりますので、それまでに請求書をいただけますと幸いです。 既にご送付いただいている場合は、大変恐れ入りますが、再度ご送付いただけますようお願い申し上げます。 ご多用のところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 □□株式会社 経理部 ●● ●●(担当者名) TEL:03-XXXX-XXXX |
この例文では、丁寧な表現を用いながらも具体的な情報(発注番号や支払い予定日)を明記することで、相手が確認しやすいように配慮しています。また、「既にご送付いただいている場合」の対応についても触れておくことで、コミュニケーションの行き違いを防ぎます。
パターン2.支払い期限が迫っている場合
想定シチュエーション:請求書が未着のまま支払い期限が迫っているケースなど
件名:【緊急】2月分請求書ご送付のお願い ○○株式会社 経理部 △△様 お世話になっております。 □□株式会社の●●でございます。 2月分のお取引(発注番号:12345)に関する請求書について、まだ弊社に届いていない状況です。 当社の支払い処理の締め切りが明日(◇月◇日)となっており、このままですと、今月の支払いに間に合わない可能性がございます。 大変恐縮ではございますが、本日中に請求書をメール添付(またはFAX)にてお送りいただけないでしょうか。 既にご送付いただいている場合は、お手数ですが再度ご送付いただけますと助かります。 何卒よろしくお願い申し上げます。 □□株式会社 経理部 ●● ●●(担当者名) TEL:03-XXXX-XXXX |
この例文では「緊急」という言葉を件名に入れ、支払いへの影響を具体的に説明することで、対応の優先度を高めています。また「本日中」という具体的な期限と「メール添付またはFAX」という送付方法を提案することで、スピーディな対応を促しています。
パターン3.催促メールを送ったのに返信がない場合
想定シチュエーション:1回目の催促メールに返信がないケースなど
件名:【再送・ご確認ください】2月分請求書について(2回目のご連絡) ○○株式会社 経理部 △△様 (CC:営業担当 ◎◎様) お世話になっております。 □□株式会社の●●でございます。 先日(◇月◇日)にもご連絡いたしました、2月分のお取引(発注番号:12345)に関する請求書について、まだ受領できておりません。 誠に恐れ入りますが、弊社の月次決算処理の都合上、◇月◇日までに請求書をいただけないと、今月の支払い処理が完了できない状況となっております。 つきましては、下記いずれかの方法で、至急ご対応いただけますようお願い申し上げます。 1. PDF形式の請求書をメールに添付してご送付 2. FAX(03-XXXX-XXXX)にてご送付 3. ご対応が難しい場合はその旨をご一報 ご多用の折、大変恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 □□株式会社 経理部 ●● ●●(担当者名) TEL:03-XXXX-XXXX |
この例文では「再送」や「2回目のご連絡」を明記し、CCに営業担当者も含めることで対応の緊急性を伝えています。また「月次決算処理」という業務上の重要性に触れながら、相手が取るべき具体的な行動を箇条書きで示すことで明確な対応を促しています。
状況を明確に伝えつつも、最後は丁寧な締めくくりで相手への配慮を忘れないようにしましょう。
請求書が届かない主な原因

請求書が期日までに届かない状況はさまざまな要因で発生します。適切な催促を行うためには、まずその原因を理解することが重要です。ここでは、請求書が届かない代表的な原因について解説します
取引先の担当者の送付忘れ
最も一般的な原因の一つが、取引先担当者の単純な送付忘れです。多くの企業では経理担当者が複数の取引先の請求書処理を同時に行っているため、業務の繁忙期には一部の処理が後回しになることがあります。
特に月末や四半期末、年度末などの決算期は業務量が急増するため、請求書の発行・送付が遅れやすくなります。担当者の休暇や急な欠勤、人事異動なども影響することがあるでしょう。また、一回限りの取引や新規取引の場合は、定型業務化されていないため忘れられるリスクが高まります。
社内処理の遅延
請求書が発行されていない別の原因としては、取引先の社内承認プロセスの遅延が挙げられます。多くの企業では請求書発行前に複数の部署や上司の承認が必要となり、その過程でボトルネックが生じる場合が少なくありません。
例えば、営業担当者が必要情報を入力していない、上司が多忙で承認作業が滞っている、経理システムの不具合で処理が遅延しているなどの理由が考えられるでしょう。特に大企業や官公庁では、承認フローが複雑で多層的なため、1つのステップで止まると全体の処理が大幅に遅れることがあります。
郵送・メールのトラブル
請求書が正しく発行・送付されているのに、途中で紛失や遅延が発生するケースもあり得ます。郵便の場合は配達の遅れや誤配、社内での仕分けミスなどが主な原因です。
電子メールの場合でも、添付ファイルのサイズ制限によるエラー、メールアドレスの入力ミス、または受信側のセキュリティー設定によって迷惑メールフォルダに振り分けられてしまうことがあります。サーバートラブルやネットワーク障害が原因で、送信者側では「送信済み」と表示されているにもかかわらず、実際には相手に届いていないケースも考えられるでしょう。
そもそも請求書が発行されていない
何らかの原因により、システム上で請求書が発行されていない状況も考えられます。たとえば注文書や発注書の不備、契約内容の食い違い、取引コードの未登録などが原因として考えられるでしょう。
また、請求サイクルの勘違い(月次請求と思っていたが実際は四半期ごとなど)も考えられます。取引先によっては、特定の条件が満たされた時点で請求書を発行する仕組みになっているかもしれません。
請求書が届かないときの具体的な対処方法
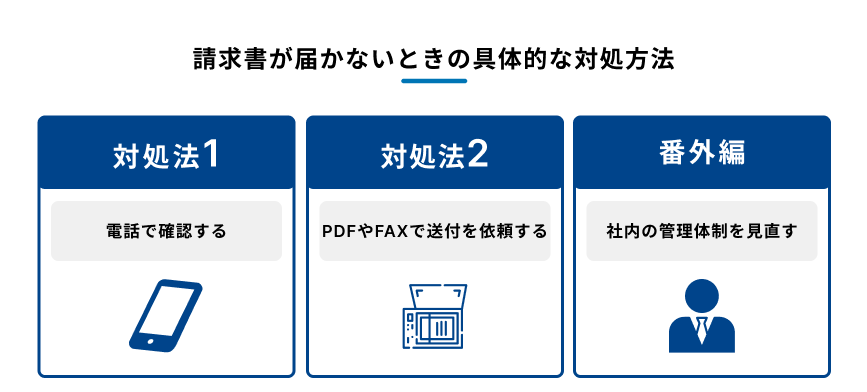
請求書が届かない状況に直面したとき、迅速かつ効果的に対応することがビジネスの円滑な運営には欠かせません。ここでは、実際に請求書が届かない場合の具体的な対処法をご紹介します。
電話で確認する
メールでの催促を行っても反応がない場合や、支払い期限が迫っている緊急性の高いケースでは電話による直接確認が効果的です。電話では即時に状況を把握できるため、問題解決までの時間を大幅に短縮できます。
電話で確認する際のポイントは、まず自己紹介と用件を簡潔に伝えることです。「○○株式会社の△△です。先日お取引いただいた案件の請求書についてお問い合わせしております」といった具合に、相手が状況を理解しやすいよう心がけましょう。
また、電話では担当者と直接会話することで、請求書が届かない原因(処理中、送付済み、発行前など)をその場で確認できます。「いつ頃発送される予定か」「どのような方法で送付されるのか」など、具体的な情報を引き出すことで、その後の対応がスムーズになります。
なお、電話でのやりとりの内容はメールで記録に残しておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。
PDFやFAXで送付を依頼する
郵送による原本の到着を待っていると支払い処理が間に合わないケースでは、PDFやFAXによる先行送付を依頼するのが有効です。多くの企業では内部承認用に電子データやFAXコピーでの処理も認められているため、原本到着前に支払い準備を進めることができます。
依頼する際は「支払い処理の都合上、原本到着前にPDF版(またはFAX)をいただけないでしょうか」と目的を明確に伝えましょう。送付先のメールアドレスやFAX番号を正確に伝え「受領後、確認のご連絡をいたします」と一言添えると、送付後の確認もスムーズです。
また、PDFやFAXでの先行受領により内容の事前確認ができるため、金額や明細の誤りがあった場合も早期に対処できます。社内での支払い申請手続きを先行して進めておくことで、原本が届いた時点ですぐに支払い処理を完了させることができるでしょう。
番外編:社内の管理体制を見直す
請求書の未着トラブルが頻発する場合は、自社の請求書管理体制そのものを見直す良い機会かもしれません。まずは、取引先ごとの請求書受領予定日をリスト化し、未着の場合にアラートが出るような仕組みを構築することをおすすめします。
受領した請求書の保管方法も重要です。紙の請求書をファイリングするだけでなく、スキャンしてデータとしても保存することで、紛失リスクを軽減できます。請求書受領から支払いまでの進捗状況を可視化するワークフローを整備すれば、処理漏れを防止できるでしょう。
より抜本的な解決策としては、請求書受領サービスや請求書管理システムの導入が効果的です。特にクラウド型の請求書管理システムであれば、請求書の受領状況をリアルタイムで把握でき、支払い期限管理や承認フローの効率化も実現できます。
請求書受領サービスの詳細については、以下の記事をお読みください。
請求書管理システムの導入(経理業務の電子化)の詳細については、以下の記事をお読みください。
請求書が未着でも支払いを遅らせてはいけない理由

請求書が届いていないからといって、支払いを無期限に遅らせることはできません。請求書は支払いのきっかけとなる書類ですが、支払い義務そのものは取引の成立時点で発生しています。ここでは、請求書未着であっても支払いを適切に行うべき理由を解説します。
法的義務があるため
取引における支払いは単なるビジネス上のマナーではなく、法的な義務です。特に下請取引の場合、下請代金支払遅延等防止法(下請法)によって、発注者は原則として納品後60日以内に下請代金を全額支払うことが義務付けられています。この支払い期限は請求書の有無にかかわらず適用されるため「請求書が届いていないから」という理由だけでは支払い遅延の正当な理由にはなりません。
民法上も、約定の期日または取引慣行に基づく期日に代金を支払う義務があります。請求書が届いていない場合でも、契約書や発注書に記載された条件通りの支払いが必要です。支払いを怠った場合、遅延損害金の請求や、最悪の場合は取引停止や法的手続きに発展する可能性もあります。
取引先との関係維持のため
請求書未着を理由に支払いを遅延させることは、取引先の資金計画に悪影響を及ぼし、信頼関係を損なう原因となりかねません。
また、支払いの遅延が常態化すると「入金が滞りがちな取引先」というレッテルを貼られるリスクがあります。こうした評判は業界内で広まりやすく、一度失った信頼を取り戻すのは容易ではありません。最悪の場合、優良な取引先からの取引を断られるなど、ビジネスチャンスの損失にもつながります。
支払いの適切な管理は、自社の経営管理能力を示す重要な指標にもなります。請求書の有無にかかわらず、約束した期日に支払いを行うことで「信頼できるビジネスパートナー」としての評価を高めることができるでしょう。取引先との良好な関係維持は、安定した調達や柔軟な取引条件の交渉など、長期的なビジネスメリットをもたらしてくれます。
まとめ
この記事では、請求書の催促方法から具体的な対処法、そして支払い遅延を避けるべき理由まで、請求書の未着問題に関する包括的な対応策を解説しました。
請求書を催促する際は、早めの確認・連絡、柔らかい表現の使用、適切なタイミングの見極めが重要です。一方で、請求書が未着の場合でも支払いが遅延すると法的義務違反となるリスクがあり、取引関係にも悪影響を及ぼします。こうした問題を根本的に解決するためには、社内の請求書管理体制の見直しが必要です。
特に請求書管理システムの導入は、受領状況のリアルタイム把握や支払い期限管理の自動化、電子保管による紛失防止など、多くのメリットがあります。「Bill One」を活用して、健全なキャッシュフロー管理と取引先との良好な関係を維持しましょう。
クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。
受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。
Bill One請求書受領の特長
- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する
- 受領した請求書データを一元管理できる
- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック
- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合
- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管
- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている
※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。


3分でわかる
Bill One請求書受領
請求書受領から、月次決算を加速する
クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。



記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部