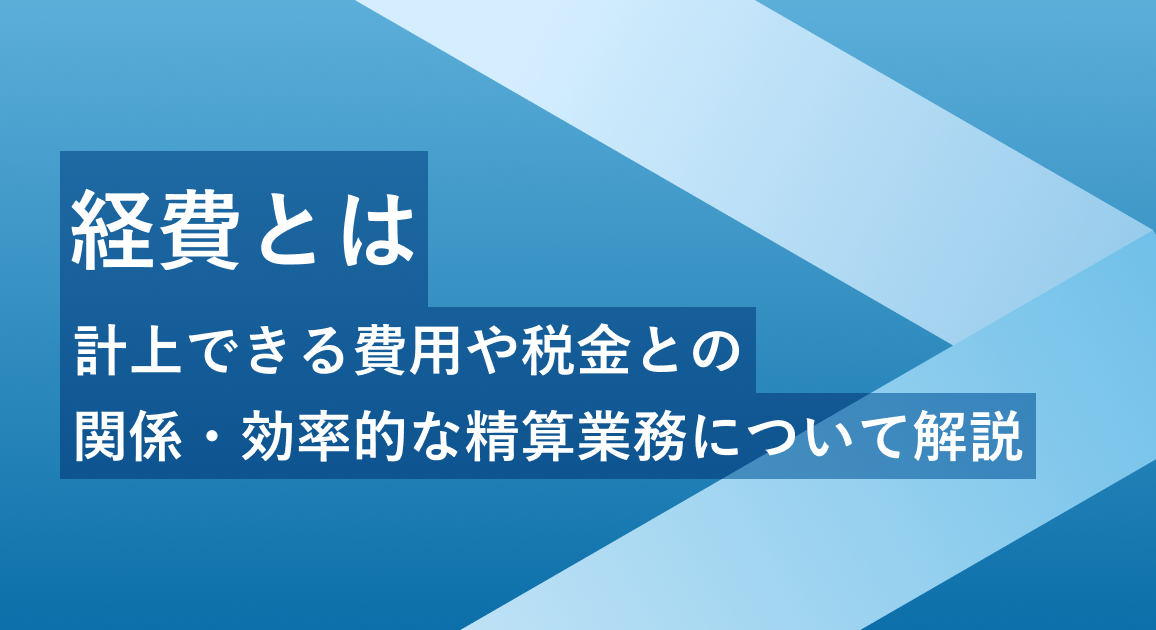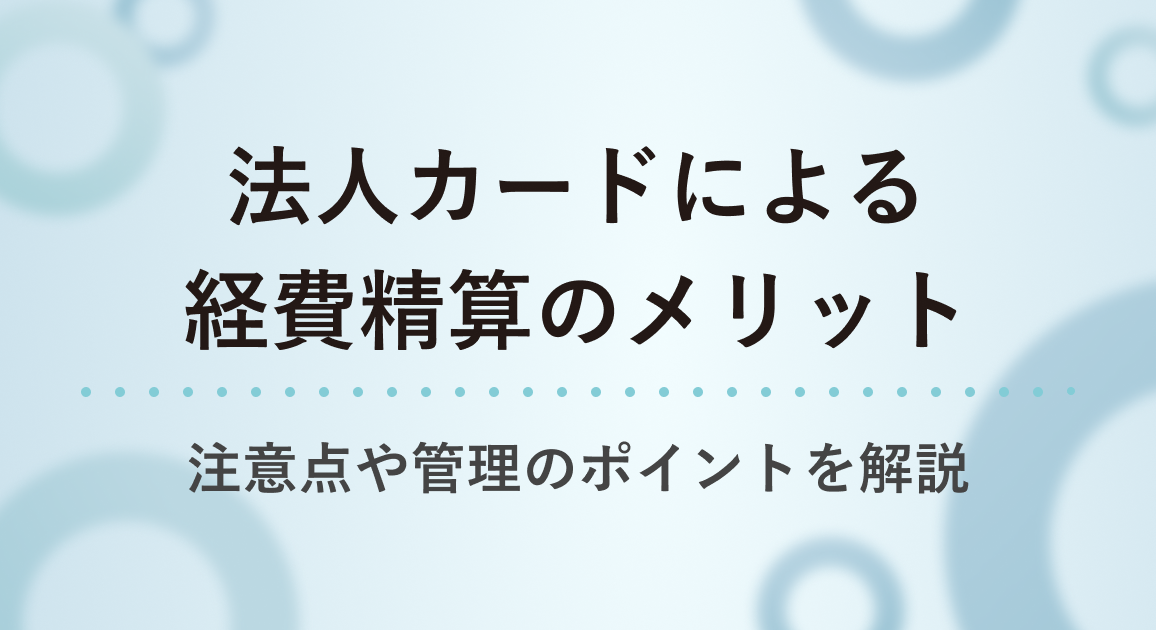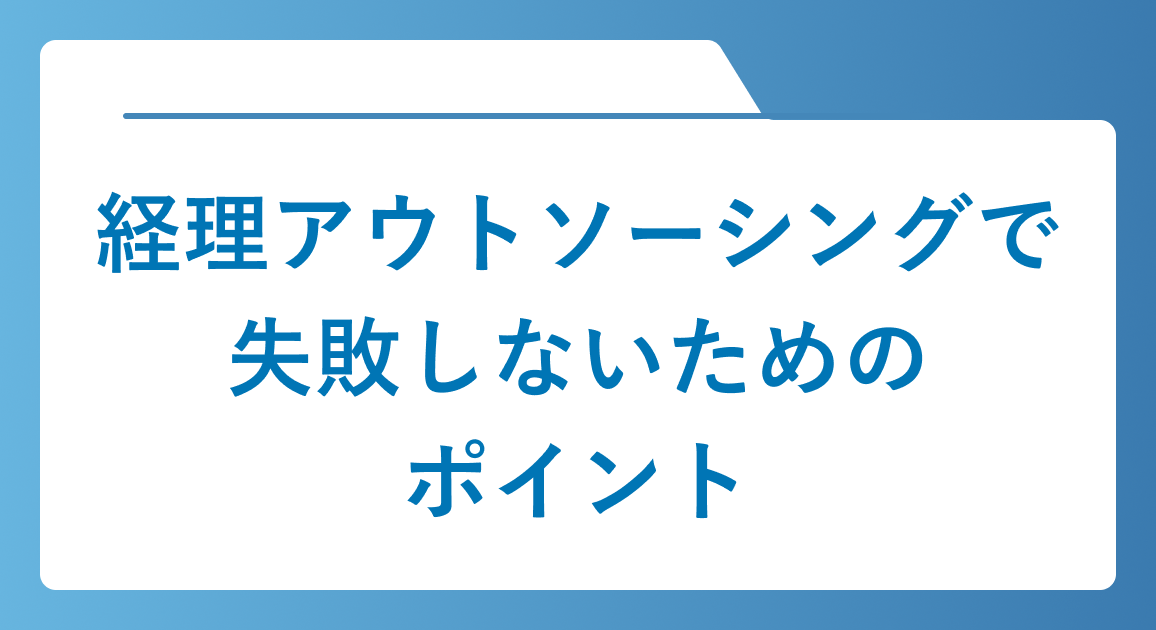- 経費精算
高額な経費立替は違法になる?いくらまでが適切?負担を減らす解決策
公開日:
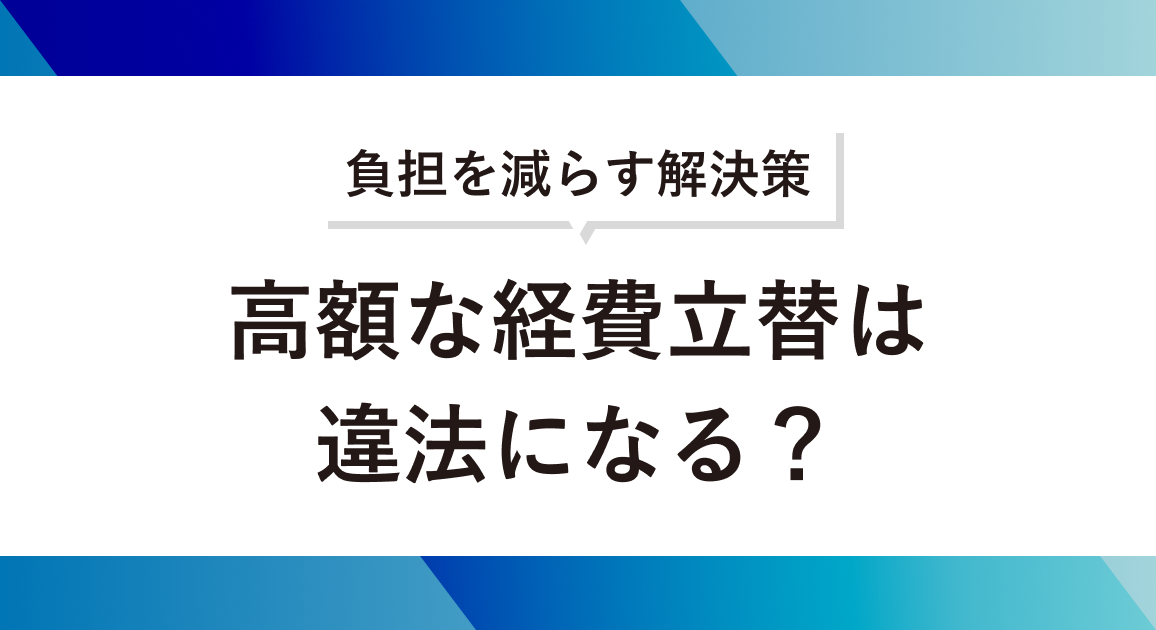
経費の立替精算は、多くの企業にとって課題です。特に、高額な経費立替は従業員の金銭的な負担を増やし、モチベーション低下や離職につながることも少なくありません。Sansan株式会社の調査によると、実に会社員の4割が立替経費の負担を懸念しており、高額な立替は企業と従業員双方にとって大きな課題となっています。
この記事では、経費立替の高額化がもたらすリスクと、その解決策を詳しく解説します。経費精算の効率化、従業員満足度の向上、そして企業の健全な発展を目指し、高額な経費立替の課題を克服するための参考にしてください。
高額な経費立替の実態と問題点

多くの企業で行われている経費立替は、特に高額になると従業員と企業双方にさまざまな課題をもたらします。現実の数字から見える実態と潜在的なリスクを理解することが、効果的な対策の第一歩です。
経費立替の現状
Sansan株式会社が2024年8月に実施した調査によると、会社員の平均立替額は毎月約3.1万円に上りました。これは、一人当たりの平均収入(約32.2万円)の1割に相当します。さらに、調査対象となった1000人のうち約4割が、立替経費の金銭負担によって「会社に不満を感じたことがある」と回答しています。
立替の対象となる経費はさまざまです。コピー代のような安価なものはもちろん、車両代、イベント会場費、海外出張費のように、数百万円に上るものもあります。
こうした高額な経費立替の実態を正確に把握し、企業内での実情を分析することが、適切な対策を講じるための出発点です。
参照:Sansan株式会社|立替経費負担に関する実態調査」を実施〜会社員の平均立替金額は月3万円で、月収の1割に相当。4割が金銭負担を懸念して接待や出張を躊躇した経験あり〜
高額な経費立替が引き起こすリスク
高額な経費立替は従業員と企業の双方にリスクをもたらします。
従業員側のリスクは、個人の家計への直接的な影響です。月に数回の立替が重なると生活費が圧迫され、特に給与水準が高くない若手社員にとっては深刻な問題となります。また、クレジットカードの利用限度額に達してしまい、プライベートでの利用ができなくなるケースも少なくありません。
企業側のリスクとしては、経理処理の複雑化やキャッシュフロー管理の煩雑さが挙げられます。特に月末や決算期に多額の立替精算が集中すると、資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。さらに、高額な経費立替はチェック体制の不備から不正経理の温床となるリスクもはらんでいます。
高額な経費立替は違法?いくらまでが適切?

経費立替の金額に関して、法的な上限は特に定められていません。適切な立替額は、企業ごとの経営状況や業務内容に応じて異なります。
一方で、従業員が立て替えた経費を企業が支払わない場合は法的な問題が生じます。立替金は従業員が企業のために支出したものであり、企業は通常、就業規則や労働契約に基づき、合理的な期間内に精算することが求められます。
企業が正当な経費の精算を長期間放置したり拒否したりした場合、従業員は立替金請求訴訟を起こすことも可能です。そのような事態を避けるためにも、企業は明確な経費精算規程を設け、適切な金額設定と迅速な精算プロセスを確立することが重要です。
なぜ経費立替が高額になるのか?

経費立替が高額になる背景には、特定の業務内容や企業の制度設計に起因する要因があります。効果的な対策を講じるためには、まずこれらの原因について理解することが大切です。
出張費・接待交際費の立替が多い
経費立替が高額になりやすい典型的なケースは、出張関連費用です。特に数日間の出張では、往復の交通費、宿泊費、現地での移動費、会食費などが累積し、一度に数万円から数十万円の立替が発生します。また海外出張ともなれば、航空券代や長期滞在のホテル代などにより、さらに高額になりがちです。
接待交際費も高額立替の主要因です。取引先との会食や接待ゴルフなどは一度に数万円の支出となることが多く、複数の取引先との接待が重なる営業担当者にとっては大きな負担となります。
経費に計上できる費用についての詳細は、以下の記事をお読みください。
社内制度・精算フローの問題
経費立替に関する社内制度の不備も、高額化の原因です。
たとえば出張や大型の取引が予定されている場合、事前に必要経費を概算で支給する仮払制度があれば従業員の負担を大幅に軽減できます。しかし制度が整備されていない、あるいは利用されていない企業では、全額を従業員が立て替えることになります。
加えて経費精算のルールが不明確だと、どこまでが企業負担で、どこからが個人負担なのかの線引きがあいまいになり、後から問題が発生するリスクもあります。
精算フローの問題も見過ごせません。申請から承認、支払いまでのプロセスが複雑だったり、承認者の確認が遅れたりすると、立替金の精算が2カ月以上遅れることがあります。その間に新たな立替が発生すれば、従業員の負担額は雪だるま式に増加していくことになるでしょう。
高額な経費立替が招くトラブルとその影響
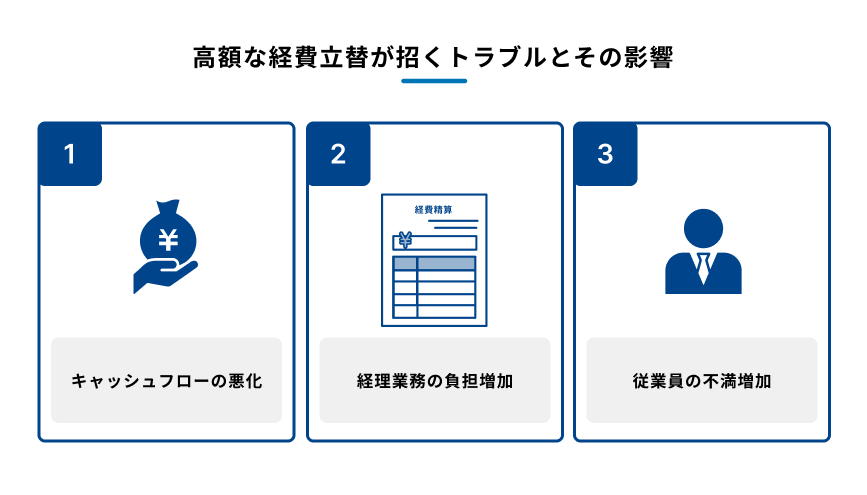
高額な経費立替は、単なる従業員の金銭的負担にとどまらず、企業全体の業務効率や組織風土にまで影響を及ぼします。ここでは、その具体的例をみていきましょう。
キャッシュフローの悪化
高額な経費立替が企業財務に与える影響は見過ごせません。多数の未精算立替金が存在すると、企業の将来的な支出予定額としての把握が困難になり、キャッシュフロー管理や経費予測の精度が低下するおそれがあります。
特に中小企業や資金繰りがタイトな企業では、月末や四半期末に一斉に立替精算の申請が集中すると想定外の資金流出が発生し、運転資金の確保に支障をきたすケースもあります。
また、決算期に未精算の経費が多くなると、経費の発生時期との対応関係が不明確となり、実態に即した損益把握が困難になる場合があります。こうした事態は、企業の信頼性や透明性を損なう要因にもなり得ます。
経理業務の負担増加
高額な経費立替は経理担当者の業務負担を著しく増加させます。高額な立替は複数の承認者による確認が必要になることが多く、より複雑な承認フローを経ることになるためです。
また、領収書や証憑の確認作業も、金額が大きくなるほど慎重な確認が求められるため、一件当たりの処理時間が増加します。限られた人員で多くの高額経費を処理しなければならない状況では、業務効率の低下やミスの増加につながりやすくなります。
さらに、経理担当者は単に書類の処理だけでなく、立替金の精算スケジュール管理や資金繰りへの影響も考慮しなければなりません。こうした業務負担の増加は、経理業務全体の遅延やミスの増加というリスクをもたらします。
従業員の不満増加
冒頭で紹介したSansanの調査によると、立替経費の金銭負担によって企業に不満を感じたことがある従業員は43.5%に上ります。この数字は、経費立替が従業員の企業に対する満足度に大きく影響することを示しています。
特に、経費精算の遅延が常態化している企業では、従業員が「自分のお金で企業の事業を支えている」という不満を抱きやすく、モチベーションの低下につながります。立替額が大きくなればなるほど、この不満は大きくなる傾向にあります。最悪の場合、経費立替の負担が転職の検討理由になるケースも考えられるでしょう。
このように、経費立替の問題は直接的に従業員の満足度や定着率に影響し、長期的な企業価値を損なう要因となりえます。
不正利用のリスク
高額な経費立替は不正利用のリスクも高めます。多額の経費が日常的に発生する環境では、個人的な支出を業務経費として申請する不正が発生しやすくなるためです。
具体的な事例としては、家族との食事を取引先との会食として申請したり、プライベートでの旅行の一部を出張費として計上したりするケースが挙げられるでしょう。社内行事やチーム活動の費用を、業務上必要な経費として不適切に申請するといった事例も見られます。
さらに、高額な経費立替が多数ある環境では、経理担当者の確認が行き届かなくなりがちです。結果として同一経費の二重申請や、必要書類が不足した不完全な申請が承認されてしまうリスクが高まります。
こうした不正や誤りは、企業の財務的損失だけでなく、コンプライアンス上の問題や社内の公平性を損なう要因となり、組織文化にも悪影響を及ぼします。
高額な経費立替によるトラブルを防ぐ方法

高額な経費立替がもたらすさまざまな問題を解決するには、根本的なシステムや運用方法の見直しが必要です。従業員の負担軽減と企業経営の効率化を両立させる効果的な対策を以下に紹介します。
法人カードの導入
法人カードは、従業員の経費立替問題を解決する最も効果的な手段の一つです。法人カードとは企業などの法人向けに発行されるクレジットカードで、以下のようなメリットがあります。
- 立替負担の解消:従業員は自己資金を使わずに必要な経費を支出できるため、金銭的負担がなくなる
- 経費の可視化:カード会社から提供される利用明細により、いつ、どこで、いくらの支出があったかを正確に把握できる
- 経理業務の効率化:カード利用データは電子的に管理されるため、手入力の手間が省け、ミスも減少する
- キャッシュフロー管理の改善:支払いサイクルが一定となるため、資金繰り計画が立てやすくなる
法人カードの導入に際しては、利用限度額の設定や利用可能店舗のカテゴリ制限など、適切な管理ルールを設けることが重要です。責任者による定期的な利用状況の確認体制を構築すれば、不正利用のリスクをさらに低減できるでしょう。
法人カードの詳細については、以下の記事をお読みください。
経費精算システムの活用
経費精算システムとは、経費の申請から承認、精算までのプロセスをデジタル化し、効率化するためのソフトウエアです。紙の領収書や申請書に依存した従来の方法と比べ、大幅な業務効率化と正確性の向上が期待できます。
経費精算システムの主な機能と特長は以下の通りです。
- オンライン申請・承認:従業員はスマートフォンやPCから簡単に経費申請ができ、承認者もオンラインで迅速に確認・承認できる
- ワークフローの自動化:あらかじめ設定された承認ルートに沿って自動的に申請が回覧され、承認プロセスの滞留や漏れを防止できる
- データ連携:会計システムや人事給与システムとのデータ連携により、二重入力の手間が省かれ、データの正確性が高まる
- 分析機能:経費データの集計・分析が容易になり、コスト管理や予算策定に役立つインサイトを得ることができる
たとえばクラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、OCR技術による領収書の読み取りや、専用のビジネスカード(法人カード)との連携などにより、経費精算に必要なあらゆる作業をオンラインで完結できます。
経理業務のアウトソーシング
経費精算業務を含む経理機能の一部または全部を外部にアウトソーシングすることも、効果的な解決策の一つです。特に経理スタッフが少ない中小企業や、コア業務に集中したい成長企業にとって有効な選択肢となります。
経理業務アウトソーシングの主なメリットは以下の通りです。
- 専門知識の活用:会計・税務の専門家が業務を担当するため、法令遵守や最新の会計基準への対応が確実になる
- 内部リソースの最適化:経理担当者が定型的な経費精算業務から解放され、より付加価値の高い財務分析や経営判断のサポートに注力できるようになる
- コスト削減:専任の経理スタッフを雇用するよりも、必要な業務量に応じたサービスを利用することでコスト効率が高まる場合がある
- 不正防止:第三者による業務の監査が入ることで、経理業務のブラックボックス化が防がれ、不正防止につながる
経理に関する情報は、企業にとって機密情報の一つです。アウトソーシングを検討する際は、信頼性の高いパートナーを選ぶことが重要です。
経理アウトソーシングについての詳細は、以下の記事をお読みください。
まとめ
高額な経費立替は、従業員の金銭的負担や不満の増加、企業のキャッシュフロー悪化、経理業務の複雑化、さらには不正利用リスクの高まりなど、多くの問題を引き起こします。
こうした問題を解消する方法のひとつが、企業の口座から直接引き落としができる法人カードの活用です。また、法人カードに連携した経費精算システムを利用すると明細の反映などが自動化され業務の効率化につながります。
クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。
全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。
Bill One経費・Bill Oneビジネスカードの特長
- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる
- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合
- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応
- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円
- カードごとの利用限度額設定が可能
- 年会費・発行手数料無料
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。


3分でわかる Bill One経費
立替経費をなくし、月次決算を加速する
クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。



記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部