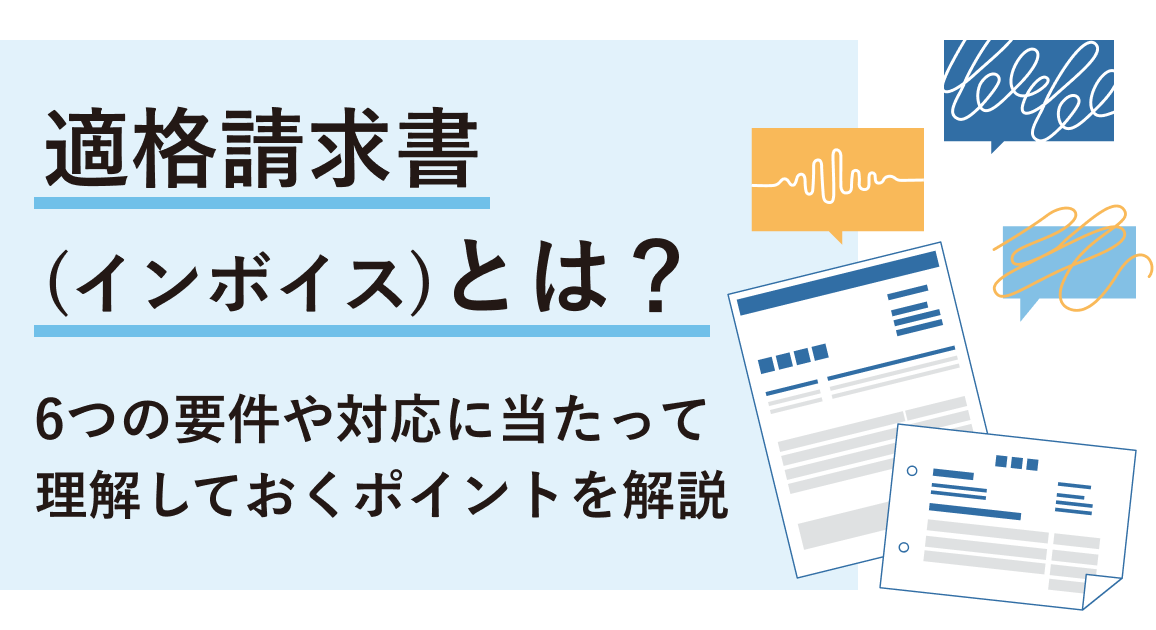- 法人カード
法人カード利用時の領収書は不要?経費精算に使える証憑や、取り扱う際の注意点を解説
公開日:
更新日:
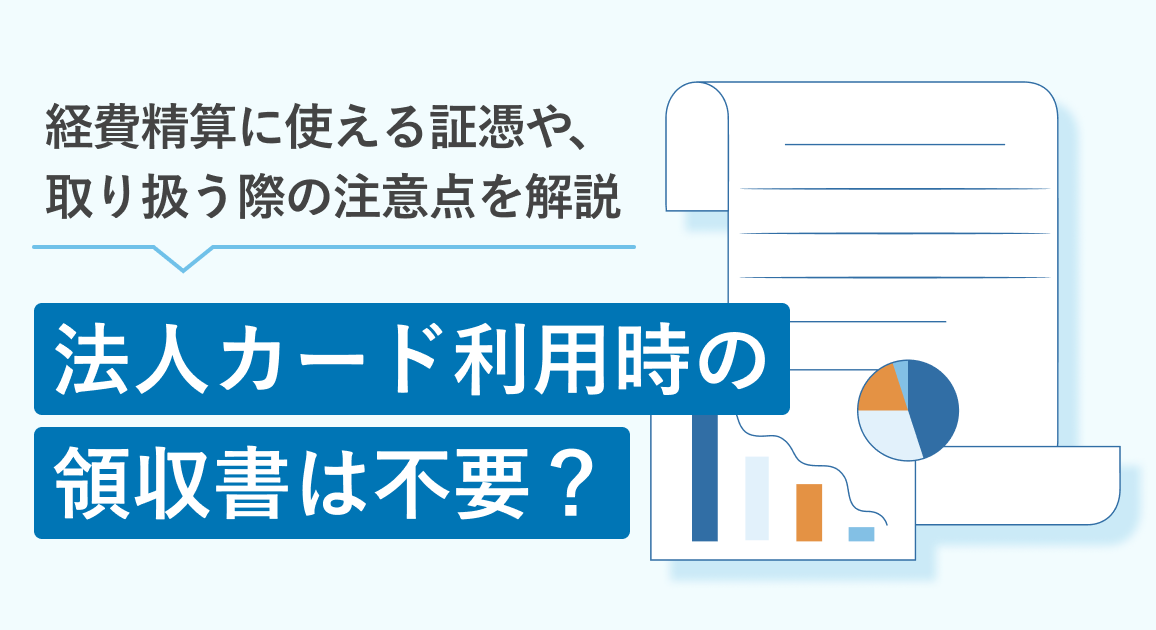
法人カードを利用すると、複数の書類が発行されます。カードで支払った接待交際費やネットショッピングでの買い物の領収書が、経費精算をするうえで必要なのかどうか、迷われている方もいらっしゃるでしょう。なかには、法人カード利用時の領収書を紛失したと焦っている人もいるかもしれません。
そこで本記事では、法人カードで支払った際に発行される領収書が、経費精算に必要か否かを詳しく解説します。領収書の取り扱いについて注意すべきポイントにも触れますので、経費管理の担当者様は、最後までご参照ください。
法人カードで経費精算を効率化
法人カードで決済した場合の領収書は、決済完了の証憑(しょうひょう)として扱えません。
証憑とは、取引や契約の正当性を証明する書類のことです。つまり、領収書は不要ともいえます。クレジットカードの決済は、あとで支払いが行われる「信用取引」のため、決済が完了したことを証明する書類としては使用できないのです。
法人カードで支払った場合でも、領収書自体を発行してもらうことは可能です。
ただし、現金払いとの区別のために「クレジット払い」と表記され、会計処理には使用できません。とはいえ、法人カードで受け取る領収書が、国税庁の税務調査に役立つ可能性はあります。
法人カードの領収書では支払いを証明できない

法人カードで決済した場合の領収書は、決済完了の証憑(しょうひょう)として扱えません。
証憑とは、取引や契約の正当性を証明する書類のことです。つまり、領収書は不要ともいえます。クレジットカードの決済は、あとで支払いが行われる「信用取引」のため、決済が完了したことを証明する書類としては使用できないのです。
法人カードで支払った場合でも、領収書自体を発行してもらうことは可能です。
ただし、現金払いとの区別のために「クレジット払い」と表記され、会計処理には使用できません。とはいえ、法人カードで受け取る領収書が、国税庁の税務調査に役立つ可能性はあります。
法人カードの証憑となるのは領収書ではなく売上票

では、何が法人カードの証憑として扱えるのでしょうか。
法人カードでの経費利用で決済証憑として使えるのは、領収証ではなく「クレジットの売上票」になります。クレジットの売上票とは、カードの支払い内容が詳しく記載されている書類のことです。
前述の通り、法人カードで決済した際の領収証は、証憑として認められていません。しかし、クレジットの売上票にプラスして領収書を提出することで、経理担当者はより詳細な取引内容を確認できるというメリットがあります。
法人カードについて、さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクを参考にしてください。
法人カードの領収書の取り扱いに関する注意点

ここからは、法人カードの領収書を扱う際の注意点として、以下の5つを紹介します。
- 二重計上に注意する
- 書類を適切に保管しておく
- 利用明細書は証憑として扱うことができない
- 必要に応じて領収書の発行を依頼する
- インボイス制度では領収書が必須となる
いずれも重要なことですので、一つずつ理解していきましょう。
1.二重計上に注意する
法人カードを利用すると、複数の書類が発行されるため、二重計上してしまう恐れがあります。
特に、法人カード利用に関する「領収書」と「クレジット売上票」を別々に保管するのは、おすすめしません。経費処理のミスにつながる可能性が高まるためです。
経費の利用内容に誤りがあれば、税務署からペナルティーを課されることになるので注意しましょう。
二重計上を防ぐには、提出された証憑と、クレジットカード会社から発行される利用明細を照らし合わせ、同じ取引を重複して処理していないか確認することが大切です。同一の取引は、ホチキスなどで一つにまとめておくと良いかもしれません。
2.書類を適切に保管しておく
法人カードの利用時に発行された書類は、必ずすべて保管するようにしましょう。前述の通り、経費精算時により詳細な内容を確認できるほか、税務調査の際にも信頼性を高めることができるためです。発行された書類は、一式保管するようにルールを定め、従業員に周知すると安心です。
請求書の保存について詳しく知りたい方は、下記のリンクをご覧ください。
3.利用明細書はインボイス制度の証憑としては不十分
クレジットカードを利用して発行される利用明細書には、決済の履歴が記載されています。ただし、利用明細書は、インボイス制度における仕入税額控除のための正式な証憑として扱うことができません。
クレジットカード会社が発行する利用明細書は、店舗や取引先が発行した適格請求書または適格簡易請求書ではないため、必要な要件を満たさないためです。
利用明細書はあくまで、支出の概要を把握するための参考書類です。税務調査には役立ちますが、税務上の正式な書類としては扱えないので注意してください。
4.必要に応じて領収書の発行を依頼する
先述したように、クレジットで取引を行った場合は「信用取引」に該当するため、原則として領収書は発行されません。しかし、会社のルールによっては、領収書の回収が求められる場合もあります。必要に応じて、手書きの領収書を作成してもらえるか確認してみましょう。
手書きの領収書を発行してもらう場合は、以下の内容が記載されているかの確認が欠かせません。
- 購入した日付
- 購入者の氏名・会社名
- 購入金額(税抜額又は税込額)
- 購入した商品・サービスの内容(但し書き)
- 領収書を発行した会社・人物・住所・登録番号
- 税率ごとに区分した消費税額等及び適用税率など
領収書に必要な項目が記載されているかを必ず確認し、足りなければ、追記してもらいましょう。
請求書について、より詳しく知りたい方は、次の記事をご参照ください。
5.インボイス制度では領収書が必須となる
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が施行され、法人カードの決済においては、領収書等の受領が必須となりました。
法人カードの経理処理には領収書が不要ですが、仕入れ税額控除を受けるためには、インボイス制度の要件に従って領収書等が必要です。経費処理時の領収書の扱いと、インボイス制度における必須書類としての領収書の扱いを混同しないよう、気を付けましょう。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために、適格要件を満たした証憑の受領・保管が欠かせません。クレジットカード決済の際に発行される書類のなかで、売上票と明細書には、適格要件の一部が記載されていません。そのため、適格請求書として扱うことができないのです。
インボイス制度に対応するためには、別途、領収書等の発行を依頼しましょう。法人カード利用の領収書やレシートが発行されたら、「適格請求書」または「適格簡易請求書」の必要項目を満たしているか、必ず確認しなければなりません。
また、受領した証憑は電子帳簿保存法の要件を満たしたうえで、一定期間(法人で基本7年、個人事業主は原則5年)保存しなければならないと、法律で定められています。回収はもちろん、紛失しないように適切に保管することが求められます。
インボイスの請求書や、法人カードにおけるインボイスについては、下記のリンクで詳しく紹介しています。興味のある方は、ぜひご覧ください。
まとめ
法人カードの利用には、以下のようなメリットがあります。
- 業務の効率化
- 法制度への対応
- 不正利用、紛失・盗難の防止
- 立替経費精算を廃止できる
ただし、法人カードのメリットを享受するためにも、領収書の扱いについて正しく理解することが大切です。
クラウド経費管理サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。
全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。
Bill One経費・Bill Oneビジネスカードの特長
- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる
- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合
- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応
- 1カ月あたりの利用限度額が最大1億円
- カードごとの利用限度額設定が可能
- 年会費・発行手数料無料
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。


3分でわかる Bill One経費
立替経費をなくし、月次決算を加速する
クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。



執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。