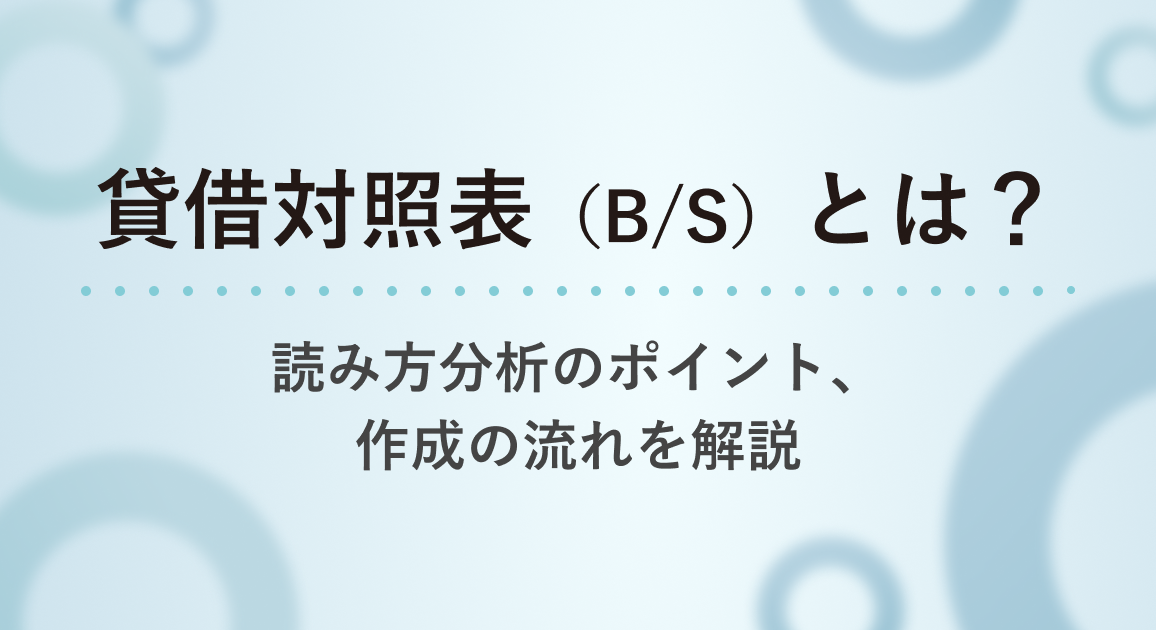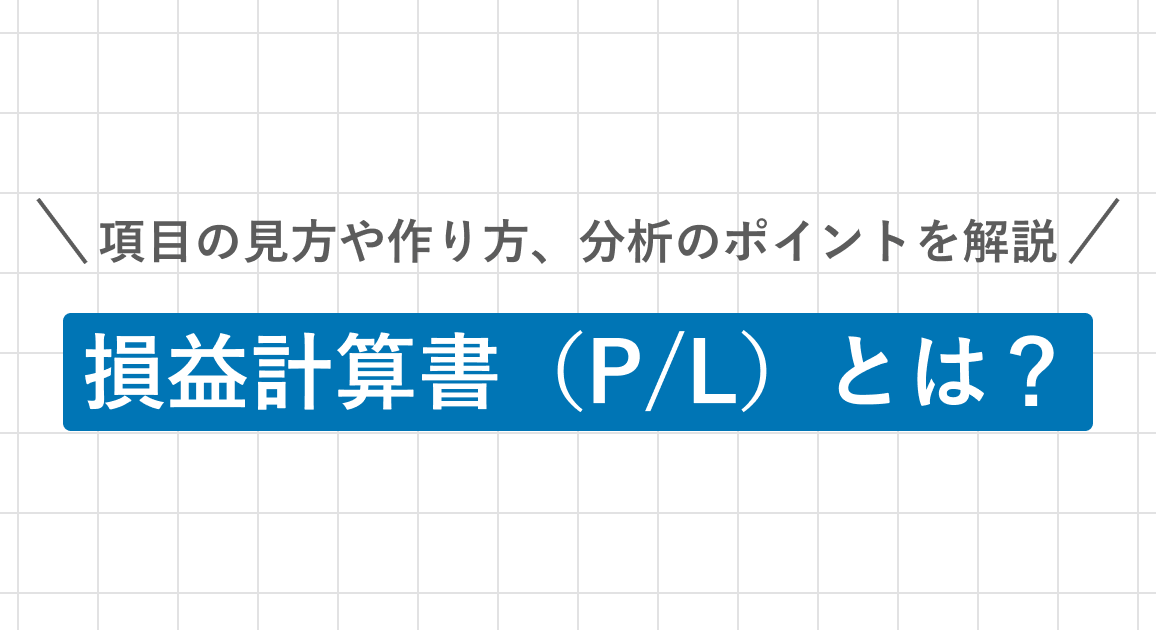- 経理・財務業務その他
連結決算とは?基本からメリット、作成手順をわかりやすく解説
公開日:
更新日:
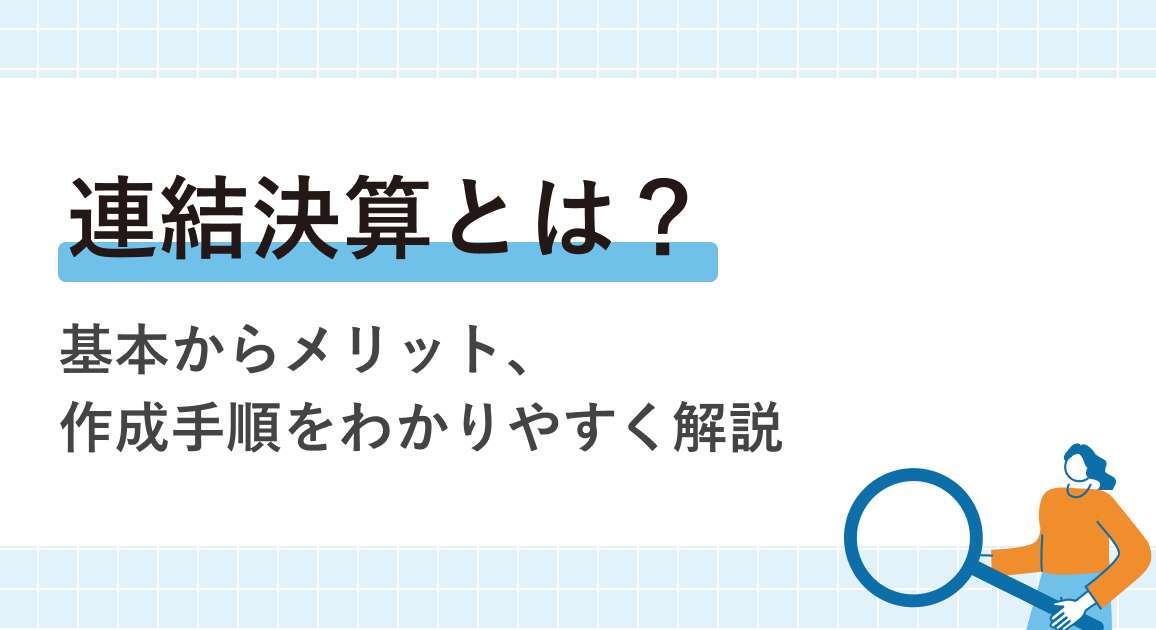
連結決算はグループ全体の財務状況を把握し、投資家やステークホルダーに信頼性の高い情報を提供する重要な会計プロセスです。しかし連結決算には複雑な手続きが必要となるため、多くの企業担当者にとって理解が難しい分野でもあります。
この記事では、連結決算の基本から対象企業の判断基準、メリットや手順を丁寧に解説し、さらに効率的に進めるためのシステム導入のポイントについても触れていきます。
経理のDXで業務を効率化
連結決算とは

連結決算とは企業グループ全体を1つの企業体として捉え、その経営成績や財務状況を明らかにする会計処理のことです。まずは、その概要や目的から見ていきましょう。
連結決算の定義
連結決算とは、親会社と子会社の財務情報を一体化した財務諸表を作成する会計手続きのことです。
企業グループとして事業を展開する場合、通常は親会社だけでなく、子会社の財務状況も含めた全体の経済活動を把握することが求められます。
連結決済はグループ全体の資産、負債、収益、費用などの経営状況を包括的に示し、より正確な財務情報を提供するものです。
連結決算の目的
連結決算の主な目的は、企業グループ全体の財務状況を一目で把握できるようにし、投資家や取引先などのステークホルダーに対して透明性を高めることです。
個別の企業のみの財務状況では見えにくいグループ全体の健全性や収益力を明らかにし、外部からの信頼を確保します。
これにより、資金調達や経営戦略の策定、リスク管理にも役立つことができます。
単体決算との違い
単体決算は企業ごとの個別の財務状況を示すものであり、親会社または子会社単体での決算内容に限定されます。一方、連結決算は親会社とその子会社を統合し、企業グループ全体の財務状況を把握するために作成されます。
この違いにより、単体決算では見えにくいグループ全体の債務や収益の分布が明確になり、より包括的な経営情報を提供できるようになるのです。
連結決算の対象となる企業

連結決算は、子会社を持つすべての企業が対象となるわけではありません。法律で定められた一定の要件を満たす企業に、連結決算の作成が義務付けられています。
会社法第444条の「大会社」
会社法第444条第3項では「大会社」と定義される上場企業に対して連結決算を義務付けています。
事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。
引用:会社法第444条第3項
ここでいう「大会社」とは、最終事業年度に係る貸借対照表に計上した資本金が5億円以上、または負債総額が200億円以上の企業のことです。
この基準を満たす企業は、子会社を含めたグループ全体の財務状況を開示することで、経営の透明性を高めることが求められます。
連結対象となる子会社とは

連結決算において、親会社と財務を統合する「連結対象の子会社」には、一定の基準が設けられています。ここでは、子会社の判断基準や例外について解説します。
子会社の基準
連結決算で子会社と認められる基準は、親会社の「支配」の程度に基づきます。この「支配」とは親会社が子会社の財務および経営方針を決定する力を有している状態のことで、主に以下の要素で判断されます。
議決権の保有割合
一般的には、親会社が子会社の議決権の過半数(50%超)を保有している場合、支配が認められます。
取締役の派遣
親会社が子会社に取締役を派遣し、経営に重要な影響力を持っている場合も支配とみなされます。
その他
契約による支配、技術的な支配など、株式保有率以外の要素も考慮されます。
重要なのは、形式的な支配だけでなく、実質的な支配も考慮される点です。たとえ議決権が50%に満たなくても、上記の要素を総合的に判断し、親会社が子会社を実質的に支配していると認められる場合には、連結の対象となります。
連結範囲に含めない子会社
原則として、支配関係にある子会社は連結決算の対象となりますが、例外的に連結範囲に含めないケースがあります。
支配が一時的な場合
たとえば、親会社が子会社を短期間で売却する予定がある場合など、支配が一時的であると判断される場合は、連結の対象外となります。
支配が困難な場合
法的な規制や地理的な要因、政治的な不安定さなどにより、実務上、親会社が子会社を支配することが困難な場合も、連結の対象から除外されることがあります。
重要性が乏しい場合
子会社の規模が非常に小さく、グループ全体の財務状況に与える影響が無視できる程度である場合、連結の対象から除外することが認められています。
これらに該当するかどうかは、ケースごとに個別に判断されます。
連結決算のメリット

連結決算を行うことによって、企業グループはさまざまなメリットを享受することができます。ここでは主なメリットとして、以下の5つを紹介します。
- 財務透明性の向上
- グループ全体の財務健全性の把握
- 資金調達力の強化
- 企業グループ全体でのリスク分散
- 経営戦略の一元化とシナジー効果
1.財務透明性の向上
連結決算により、親会社と子会社の財務を一体化して開示することで、投資家や金融機関からの信頼性が向上します。
グループ全体の資産や負債、収益状況が明らかになるため、各企業が単体で決算を行う場合には見えにくかったグループ全体の経営実態が把握しやすくなるでしょう。
これにより、外部のステークホルダーに対して企業の健全性や収益力を透明性高く伝えることにつながり、企業価値の向上にも寄与します。
2.グループ全体の財務健全性の把握
連結決算は、企業グループ全体の財務健全性を把握する上で有効です。
親会社と子会社を含むグループ全体の資産や負債を統合することで、経営者は全体のリスク状況を一目で把握できます。
これにより、各子会社の財務状態に基づいたリスク管理が可能になり、適切な対策を講じるための情報を提供できるようになるでしょう。
3.資金調達力の強化
連結決算によって、グループ全体の財務状況が明確に示されることで、より有利な条件での資金調達が可能になります。
親会社だけの財務力ではなく、子会社を含めたグループ全体の収益性や資産の規模が考慮されるため、金融機関からの信頼も増し、融資の選択肢が広がるでしょう。
このように、連結決算は資金調達力を強化し、企業の成長や新たな投資機会を実現する上で重要な役割を果たします。
4.企業グループ全体でのリスク分散
連結決算を通じて作成されるグループ全体のバランスシートは、リスク分散にも寄与します。
たとえば、ある子会社が一時的に損失を出した場合でも親会社や他の子会社の利益で補うことが可能となり、グループ全体で損失を分散できるようになるでしょう。
こうしたリスク分散は、個別の事業の失敗が全体の経営に与える影響を軽減し、企業グループの安定性を高める効果があります。
5.経営戦略の一元化とシナジー効果
連結決算により、企業グループ全体の経営戦略を一元化することで、シナジー効果を高めることが可能です。
経営者は統合された財務情報に基づき、グループ内のリソース配分を最適化することで、効率的な経営を実現できるでしょう。たとえば各子会社の強みを活かした連携や、共通する資源の共有によってコスト削減を図り、グループ全体の競争力を高めることができます。
これにより、経営の効率化と成長の加速が期待されます。
連結決算の課題

連結決算には多くのメリットがある一方で、実務上の課題も少なくありません。ここでは主に、以下の3つの課題について解説します。
- 作業が複雑
- コストと手間が増える
- 会計基準の統一が必要
1.作業が複雑
連結決算は単体決算と異なり、グループ企業間の内部取引を消去したり、複数の子会社間の取引を調整したりする必要があるなど、作業が複雑です。
たとえば親会社と子会社間で商品を売買した場合、その取引はグループ内での取引であるため、連結決算上では相殺する必要があります。
2.コストと手間が増える
連結決算を行うには、専用の会計システムを導入したり、連結決算に関する専門知識を持つ人材を確保したりする必要があるため、コストと手間が増加します。
特にグループ企業が多い場合や、海外に子会社がある場合は、システムの構築や運用、人材の確保に多大な費用と労力がかかる可能性があるでしょう。
3.会計基準の統一が必要
子会社が異なる会計基準を採用している場合、連結決算にあたり、会計基準を統一するための調整作業が必要となります。近年では、国際会計基準(IFRS)の導入が進んでおり、IFRSと日本の会計基準との整合性を取るための対応も求められます。
これらの課題を克服するためには、連結決算システムの導入や専門家への相談、従業員への研修など、適切な対策を講じる必要があります。
連結決算のポイントと手順

連結決算はいくつかの段階を経て作成されます。ここでは重要なポイントと、基本的な手順について説明します。
内部取引の消去
連結決算では、親会社と子会社間で行われた内部取引を消去する必要があります。
貸借取引の消去
親会社と子会社間で貸し借りがある場合、連結財務諸表上では相殺します。
商品取引の消去
親会社が子会社に商品を販売した場合、その売上と仕入は連結財務諸表上では相殺します。
有価証券取引の消去
親会社が子会社の株式を保有している場合、その株式の評価益は連結財務諸表上では消去します。
これらの内部取引を消去することで、グループ全体の純粋な経営成績を把握することができます。
連結財務諸表の作成プロセス
内部取引の消去後、連結財務諸表を作成します。主な財務諸表は、連結貸借対照表(連結BS)と連結損益計算書(連結PL)です。
個々の企業の財務諸表を作成
まず、親会社および各子会社が、単体決算に基づいた財務諸表を作成します。
連結調整
次に、親会社は、子会社から提出された財務諸表を基に、連結調整を行います。具体的には、内部取引の消去、子会社株式の評価、税効果会計などの調整を行います。
連結財務諸表の作成
連結調整が完了したら、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュフロー計算書などの連結財務諸表を作成します。
監査
作成された連結財務諸表は、監査法人による監査を受けます。
提出
監査済みの連結財務諸表を株主総会に提出し、承認を得た後、法定期間内に所轄官庁に提出します。
連結決算のプロセスは複雑なため、専門的な知識や経験が必要です。必要に応じて、会計専門家やコンサルタントへ相談すると良いでしょう。
連結決算をシステムで効率化する

連結決算を効率化するためには、専用のシステムの導入が効果的です。ここでは、システム導入による業務効率化の効果と選定のポイントを解説します。
システム導入による業務効率化の効果
システムを導入することで、データ収集、内部取引の消去、連結財務諸表の作成などのプロセスを自動化できます。
これにより大幅な時間短縮とコスト削減が実現できるだけでなく、人為的なミスの防止や軽減につながり、決算業務の精度が向上するでしょう。
システム選定時の重要ポイント
システムを導入する際は、以下のポイントを考慮しましょう。
- 使いやすさ:システムの操作方法が分かりやすく、従業員がスムーズに使いこなせるかどうかは重要なポイントです。
- コスト:システムの導入費用だけでなく、運用費用や保守費用なども考慮して、自社の予算に合ったシステムを選ぶ必要があります。
- 機能:必要な機能が揃っているか、自社の業務フローに合致しているかを確認しましょう。
- 導入後のサポート体制:システム導入後、トラブルが発生した場合のサポート体制が充実しているかを確認しましょう。
- セキュリティー:重要な財務情報を扱うため、セキュリティー対策が万全なシステムを選ぶ必要があります。
これらのポイントを踏まえ、自社のニーズに最適なシステムを導入することで、業務効率化と正確性の向上、そしてコスト削減を実現できます。
まとめ
連結決算は企業グループ全体の財務状況を正確に把握し、外部のステークホルダーに透明性を提供するために非常に重要です。親会社と子会社の財務を統合することで、投資家や取引先からの信頼が高まり、スムーズな資金調達にもつながるでしょう。
しかし連結決算は手間がかかるうえ、正確性が求められるため、担当者にとって大きな負担がかかるプロセスでもあります。そのため、ミスなく効率的に対応するためには、連結決算に特化したシステムの導入が効果的です。
「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。
請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。
債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。
経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。
これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。
Bill One(請求書受領)の特長
- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する
- 受領した請求書データを一元管理できる
- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック
- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合
- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管
- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One(債権管理)の特長
- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行
- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理
- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能
- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能
- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結
Bill One(経費精算)の特長
- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる
- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結
- 99.9%*の精度で領収証をデータ化し、自動で利用明細と突合
- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応
- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止
- 1カ月あたりの利用限度額が最大1億円
- カードごとの利用限度額設定が可能
- 年会費・発行手数料無料
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

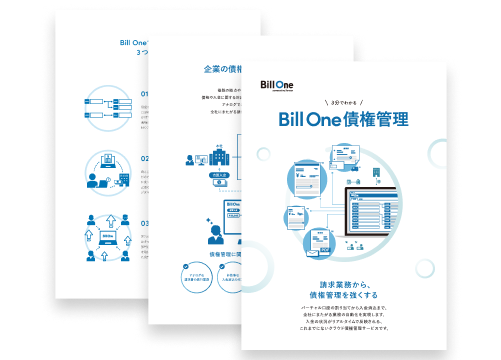
3分でわかる Bill One
「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える
経理AXサービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。



執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。