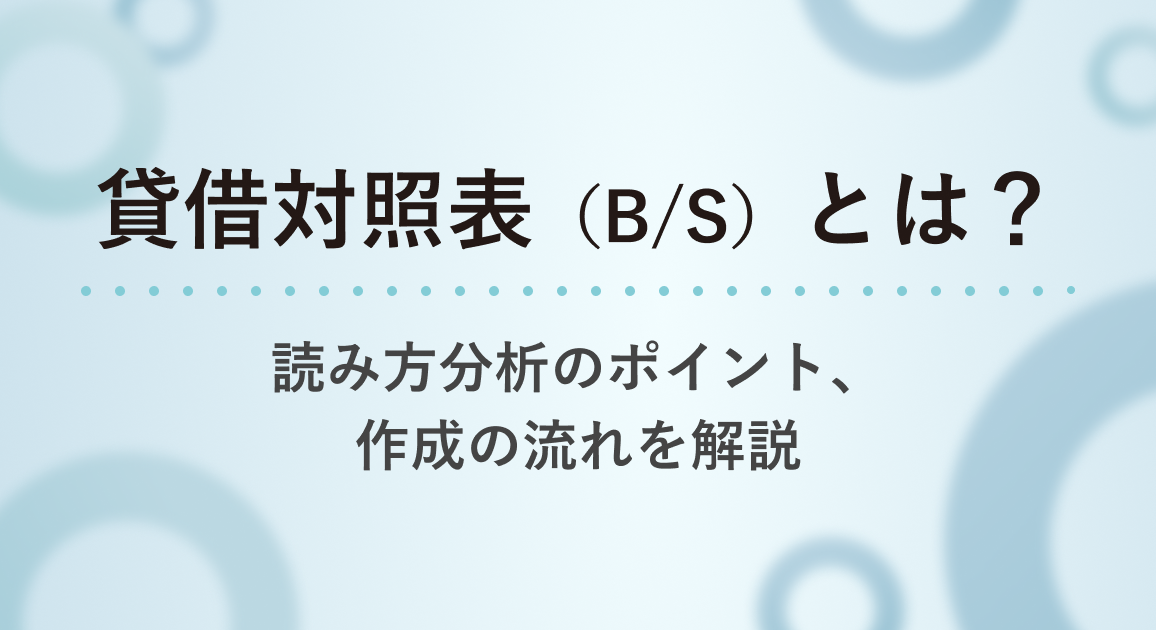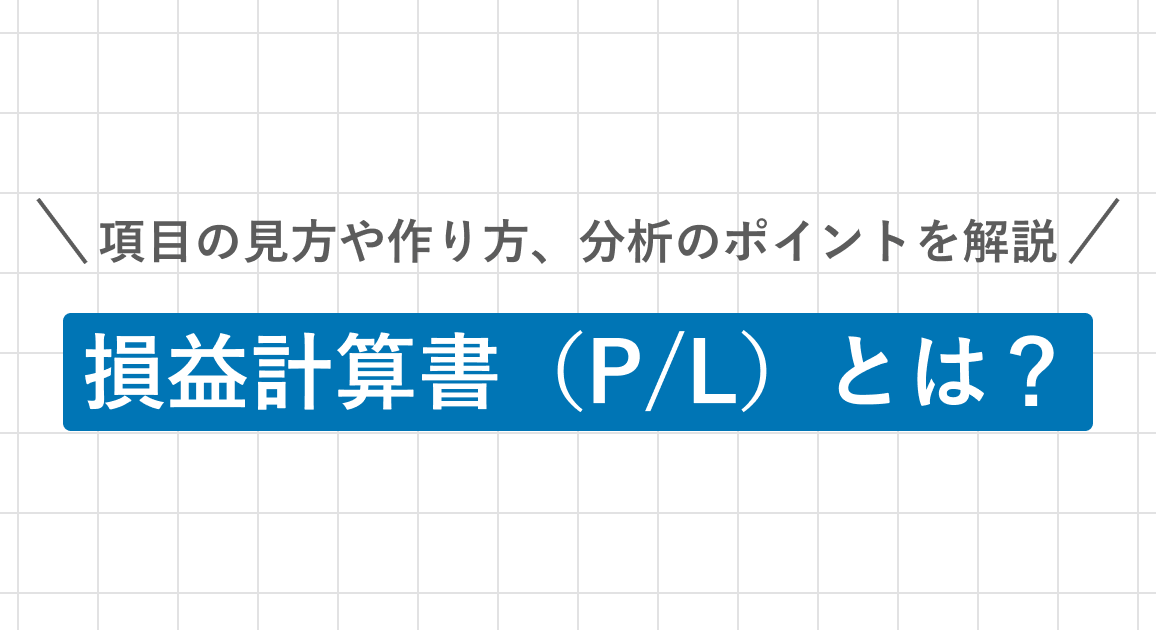- 経理・財務業務その他
経理と会計の違いとは?それぞれの業務内容と効率化の方法を紹介
公開日:
更新日:
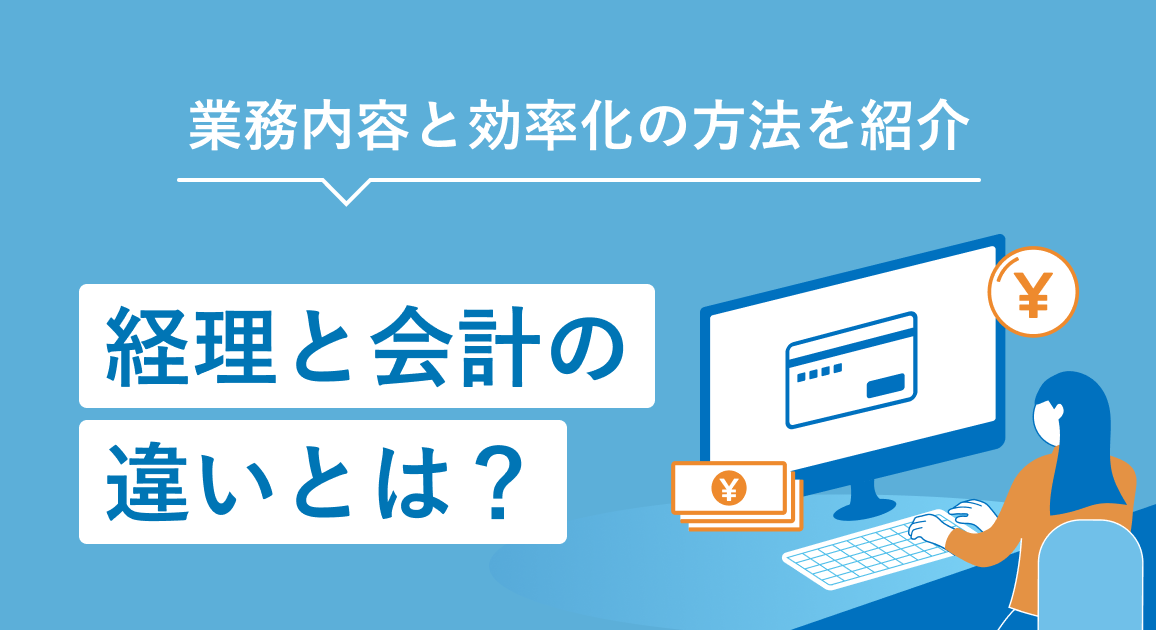
経理と会計は、どちらも企業のお金に関する業務を扱うことから混同されやすい言葉です。しかし、それぞれの業務内容にははっきりとした違いがあります。
この記事では経理と会計の違いを分かりやすく解説するとともに、それぞれの具体的な業務内容や、企業における重要性について説明します。経理・会計業務を効率化するためのポイントも紹介しますので、ぜひ自社の業務効率化にお役立てください。
経理のDXで業務を効率化
経理と会計の違いとは

「経理」と「会計」はどちらも企業のお金の流れに関わる業務です。まずはそれぞれの役割と範囲の違いに注目してみましょう。
まず経理は、企業の日々の資金の流れを記録・管理します。具体的な業務内容は、請求書の作成、支払い業務、伝票起票、帳簿記帳などです。また税金の申告・支払い、決算書の作成、企業内のお金に関する情報収集なども経理が担当します。
一方、会計の役割は資金全体の流れを記録・管理することです。具体的には、企業の経営状態を示す会計帳簿を作成します。また国や株主などに提出する報告書の作成も、会計の重要な役割です。
例えば、税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場で、備え付けて記録し保存されている帳簿とその取引関係書類を基に確定申告書等の税務関係書類を作成して提出し、税務署に対する説明の代理を行うことにより、納税義務の適正な実現を図ることを任務としています。
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場で、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図ることを任務としています。
このように職業会計人の中でも、経理と会計で役割分担が決められています。
「経理」の業務内容を理解する

企業の心臓部ともいえる「経理」。その業務内容は多岐に渡りますが、いずれも企業活動の根幹を支える重要なものです。日々の取引から年間を通した資金の流れまで、経理担当者の仕事は企業の安定的な運営に欠かせません。
経理業務の概要
経理業務には、現金出納帳の入力、伝票処理、請求書処理、支払い処理など、企業のお金の流れに関わるさまざまな業務が含まれます。これらの正確な記録と管理は、企業の信頼性を高め、健全な経営を維持するために不可欠です。
経理担当者は、これらの業務を日次・月次・年次という3つのサイクルごとに実施します。
経理業務のサイクル
経理業務は企業活動のあらゆる場面で発生します。日々の細かな取引から、月ごと、そして年ごとの大きなイベントまで、常に企業の財務状況を把握し、管理することが経理の役割です。
日次業務
日次業務は、企業の日常的な活動を支える業務です。現金の入出金を管理し、取引が発生するたびに伝票を作成・整理します。
さらに、請求書や領収書の発行・整理、売掛金や買掛金の管理、銀行への振込手続きなど、資金の流れをスムーズにするための業務も経理の仕事です。
これらの業務を正確かつ迅速に処理することで、企業の資金繰りを円滑に進めることができます。
月次業務
月次業務は、月単位で発生する業務です。これには従業員の給与や社会保険料の計算、請求書の支払い、月ごとの財務諸表の作成などが含まれます。
経理の月次業務は、企業の財務状況を定期的に把握し、経営判断に必要な情報を提供するものです。経営者は予算と実績を比較することで、今後の経営計画の修正や改善にも役立てることができます。
年次業務
年次業務は、年に一度発生する業務です。企業の1年間の活動を締めくくるもので、次の年の計画を立てるための重要な業務となります。
具体的な業務内容は、法人税や消費税などの税務申告、決算書の作成、株主総会への準備などです。これらの業務には専門的な知識や経験が必要となる場合も多いため、税理士などの専門家と連携しながら進めることが重要です。
経理で扱う帳簿の種類
経理業務ではさまざまな種類の帳簿が使用されます。それぞれの帳簿の役割を理解し、正確な記帳を行うことが経理業務の基礎です。
帳簿には、収入と支出をシンプルに記録する単式簿記と、取引を「借方」と「貸方」という2つの側面から記録する複式簿記の2種類があります。一般的に、企業の経理業務でつかわれるのは複式簿記の方です。
なお近年では、会計ソフトの普及により手書きでの記帳が減ってきています。ただし帳簿の役割や複式簿記の仕組みを理解することは、経理業務を行ううえで不可欠な知識といえるでしょう。
主要簿
経理業務で扱う帳簿は、大きく「主要簿」と「補助簿」に分けられます。このうち主計簿とは、企業のすべての取引を体系的に記録したものです。
主要簿には「仕訳帳」と「総勘定元帳」という2種類の帳簿があります。
例えば、青色申告法人は仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(補助簿)を備え付けて記録しなければならないこととされており、仕訳帳と総勘定元帳は必須の帳簿となっています。
役割 | 内容 | |
|---|---|---|
仕訳帳 | 発生した取引を時系列に記録する | 取引が発生した日付、取引の内容(摘要)、借方・貸方の勘定科目、金額など |
総勘定元帳 | 仕訳帳に記録された取引を、勘定科目ごとに分類・集計して記録する | 勘定科目ごとの、借方・貸方の発生額、残高など |
仕訳帳の記入例:
(1月1日に100000円の商品Aを売り上げた場合)
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 現金 | 100000円 | 売上 | 100000円 | 商品A |
総勘定元帳の記入例:<科目名:現金>
(1月1日に100000円を売り上げ、1月15日に50000円の仕入を行った場合)
日付 | 相手勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
1/1 | 売上 | 100000円 | 100000円 | |
1/15 | 仕入 | 50000円 | 50000円 |
補助簿
補助簿とは、仕訳帳や総勘定元帳だけでは記録しきれない詳細な情報を、勘定科目別に分けて記録するための帳簿です。
補助簿は、事業者の業種や規模によって作成している帳簿はまちまちですので、事業に当たって必要な帳簿を備え付けて記録することになります。
補助簿には11の種類があります。
役割 | 内容 | |
|---|---|---|
現金出納帳 | 現金の入出金を記録し、現金残高を明確にする | 日付、摘要(取引内容)、入金額、出金額、残高など |
預金出納帳 | 預金の入出金を記録し、預金残高を明確にする | 日付、摘要、預入金額、引出金額、残高など |
小口現金出納帳 | 少額の現金取引(切手代、交通費など)を記録する | 日付、摘要、支出金額、残高など |
仕入帳 | 商品の仕入状況を記録する | 日付、仕入先、商品名、数量、単価、金額など |
売上帳 | 商品の売上状況を記録する | 日付、得意先、商品名、数量、単価、金額など |
支払手形記入帳 | 支払手形の発行状況を記録する | 日付、支払先、手形金額、満期日など |
受取手形記入帳 | 受取手形の受領状況を記録する | 日付、受取先、手形金額、満期日など |
商品有高帳 | 商品の在庫状況を記録する | 商品名、入庫数、出庫数、残高など |
仕入先元帳(買掛金元帳) | 仕入先ごとの取引状況を記録する | 仕入先名、日付、摘要、仕入金額、支払金額、残高など |
得意先元帳(売掛金元帳) | 得意先ごとの取引状況を記録する | 得意先名、日付、摘要、売上金額、入金金額、残高など |
固定資産台帳 | 固定資産の取得、減価償却、売却などを記録する | 資産名、取得日、取得価額、耐用年数、減価償却費、帳簿価額など |
企業はこれらの補助簿をすべて作成する必要はありません。主要簿を補完するツールとして、自社の必要に応じて作成・記録します。
「会計」の業務内容を理解する

企業の財務状況を分析し、経営判断の材料を提供する「会計」。その業務内容は企業の未来を左右する、重要な役割を担っています。
会計業務の概要
会計業務は企業の財務状況を分析し、財務諸表の作成、財務分析、原価計算、管理会計などを通して、経営判断や外部への情報開示に役立つ情報を提供します。
なお会計業務は、その目的によって「財務会計」「管理会計」「税務会計」の3つに分類されます。
財務会計
財務会計とは、企業の一定期間における経営成績や財政状態を投資家や株主、債権者、取引先など、外部の関係者に対して開示するための会計です。企業の透明性を確保し、外部からの信頼を得るために欠かせないものです。
主な業務内容としては、各種会計情報の入力、伝票の作成、帳簿や試算表の作成などが挙げられます。原価計算によって製品やサービスの正確なコストを把握し、固定資産管理と減価償却によって資産価値の変動も適切に記録します。
これらの情報を基に、貸借対照表や損益計算書などの決算書を作成し、企業の財務状況を明らかにするのも財務会計の役割です。加えて、在庫管理、債権管理、有価証券の管理なども行います。
管理会計
管理会計とは、経営者や責任者が自社の現状を把握し、意思決定や経営戦略に役立てるための会計情報です。財務会計が過去の情報を外部に開示するのに対し、管理会計は未来の経営活動を支援するための情報を提供します。
管理会計の主な役割として挙げられるのは、予実管理、原価管理、経営分析、資金繰り管理などです。
役割 | 内容 |
|---|---|
予実管理 | 予算と実績を比較し、問題点や改善点を発見する |
原価管理 | 製品やサービスの原価を分析し、コスト削減を目指す |
経営分析 | 企業の収益性や効率性を評価し、経営戦略の立案に役立てる |
資金繰り管理 | 資金の調達や運用を計画し、資金不足を回避する |
税務会計
税務会計とは、税法に基づいて課税所得を計算し、税務当局への申告・納税を行うための会計業務です。適正な納税は企業の社会的責任であるため、税務会計は法令遵守の観点からも重要な役割を果たしているといえるでしょう。
税務会計の主な業務内容としては、課税所得や法人税額の計算、税務当局への申告・納税などが挙げられます。また税務調査への対応や、節税対策の検討なども税務会計の重要な業務です。
会計で作成する財務諸表
会計業務の重要なアウトプットの一つが財務諸表です。財務諸表は企業の財政状態や経営成績をまとめたもので、主に以下の3つの種類があります。
これらの財務諸表は、経営者が企業の経営状態を評価し、今後の経営戦略を立てる際の重要な資料です。また投資家や金融機関なども、財務諸表を参考に投資判断や融資判断を行います。
貸借対照表(B/S)
企業のある時点における財政状態を表す書類です。「資産」「負債」「純資産」の3つの要素で構成され、常に「資産=負債+純資産」の関係が成り立ちます。
要素 | 内容 |
|---|---|
資産 | 企業が保有する財産や権利のこと。現金、預金、売掛金、建物、機械などが含まれる |
負債 | 企業が負っている債務のこと。借入金、買掛金、未払費用などが含まれる |
純資産 | 資産から負債を差し引いたもの。企業の自己資本を表す |
貸借対照表では、企業がどのような資産を保有し、どのように資金調達しているのか、財務構造は健全かなどを把握できます。
損益計算書(P/L)
企業の一定期間における経営成績を表す書類です。「収益」「費用」「利益」の3つの要素で構成され、「利益=収益ー費用」の関係が成り立ちます。
要素 | 内容 |
|---|---|
収益 | 企業の主な事業活動によって得られた収入のこと。売上高、受取利息、受取配当金などが含まれる |
費用 | 企業の主な事業活動のために費やされた支出のこと。売上原価、販売費及び一般管理費、支払利息などが含まれる |
利益 | 収益から費用を差し引いたもの。企業の収益力を表す |
損益計算書では、企業がどれだけの利益を上げているのか、収益構造はどうなっているのかなどを把握できます。
キャッシュフロー計算書(C/F)
企業の一定期間における現金の流れを表す書類です。「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つの活動によるキャッシュフローで構成されます。
- 営業活動によるキャッシュフロー
商品の販売やサービスの提供など、企業の本業による現金の増減を表す - 投資活動によるキャッシュフロー
固定資産の取得や売却、有価証券の売買など、将来の収益獲得のための投資による現金の増減を表す - 財務活動によるキャッシュフロー
借入金の返済や株式の発行など、資金調達や株主への利益還元による現金の増減を表す
要素 | 内容 |
|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 商品の販売やサービスの提供など、企業の本業による現金の増減を表す |
投資活動によるキャッシュフロー | 固定資産の取得や売却、有価証券の売買など、将来の収益獲得のための投資による現金の増減を表す |
財務活動によるキャッシュフロー | 借入金の返済や株式の発行など、資金調達や株主への利益還元による現金の増減を表す |
キャッシュフロー計算書を見ると、企業の資金繰りの状況や、資金調達・運用の方針などを把握できます。
経理・会計業務を効率化するには

経理・会計業務は、企業の規模が大きくなるにつれて複雑化し、担当者の負担も増大しがちです。しかし、業務フローの見直しやデジタルツールの活用によって、業務効率を大幅に向上できます。
業務フローの見直し
業務効率化の第一歩は、現状の業務フローを徹底的に見直すことです。無駄な作業や重複しているプロセスがないか、ボトルネックとなっている箇所はないかなどを洗い出し、改善策を検討します。
例えば承認プロセスが複雑で時間がかかっている場合は、権限委譲や承認フローの簡素化を検討できるでしょう。紙ベースでのやり取りが多い場合は、デジタル化によってペーパーレス化を進めることで業務効率を向上できます。
業務フローの見直しは、一度行えば終わりではありません。定期的に見直しを行い、改善を継続していくことが重要です。業務内容や環境の変化に合わせて、常に最適なフローを構築することで、経理・会計業務の効率化を図ることができます。
デジタルツールやシステムを活用する
業務フローの見直しに加えて、デジタルツールやシステムの活用は、経理・会計業務の効率化に大きく貢献します。近年ではさまざまなツールが登場しているため、業務内容に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。
請求書・領収書の電子化によるペーパーレス化
紙の請求書や領収書の電子データ化には、保管スペースの削減、紛失リスクの軽減、検索性の向上など、多くのメリットがあります。また承認プロセスも電子化することで、紙のやり取りにかかる時間や手間を大幅に削減できます。
クラウド会計システムによる経理作業の自動化
クラウド会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードの取引明細を自動で取り込み、仕訳や帳簿作成を自動化します。これにより経理担当者は、手入力の手間やミスを減らして、より高度な業務に集中できるようになります。
請求書受領システムによる請求書業務の迅速化
請求書受領システムを利用すれば、請求書の受領にかかわる業務を効率化できます。請求書を紙で受け取るとデータの手入力や目視による金額確認、郵送によるタイムラグなどが発生しますが、請求書受領システムならこうした手間を省けます。
オンラインバンキングを活用した入出金管理の効率化
オンラインバンキングを利用すれば、銀行口座の残高確認や振込手続きをインターネット上で行えます。時間や場所に縛られないため業務効率が向上し、また自動で入出金明細を取得できるため、手入力の手間やミスの発生を防げます。
まとめ
経理業務と会計業務は、どちらも企業の健全な経営に欠かせない重要な業務であり、相互に連携しながら企業活動を支えています。
一方で、これらの業務は企業の規模が大きくなるにつれて複雑化し、担当者の負担も増大しがちです。より効率的に業務を行うには、業務フローの見直しやデジタルツールの活用が欠かせません。
「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。
請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。
債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。
経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。
これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。
Bill One請求書受領の特長
- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する
- 受領した請求書データを一元管理できる
- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック
- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合
- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管
- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One債権管理の特長
- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行
- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理
- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能
- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能
- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結
Bill One経費精算の特長
- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる
- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結
- 99.9%*の精度で領収証をデータ化し、自動で利用明細と突合
- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応
- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止
- 1カ月あたりの利用限度額が最大1億円
- カードごとの利用限度額設定が可能
- 年会費・発行手数料無料
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

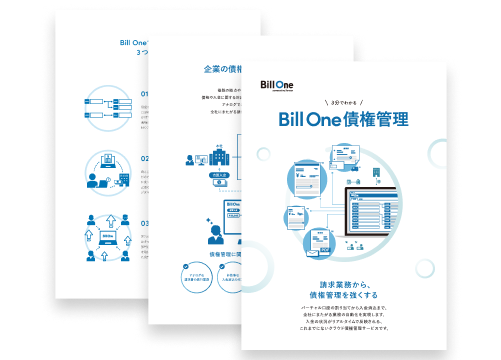
3分でわかる Bill One
「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える
経理AXサービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。



執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介
税理士 松崎 啓介
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
保有資格:税理士
昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務
税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)
その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。