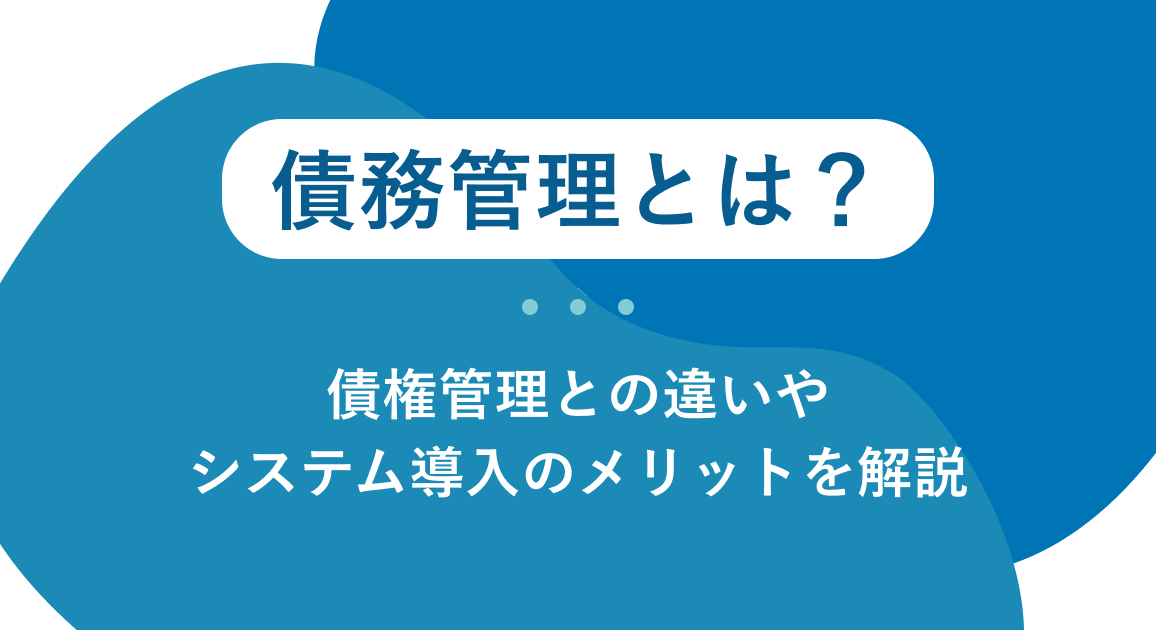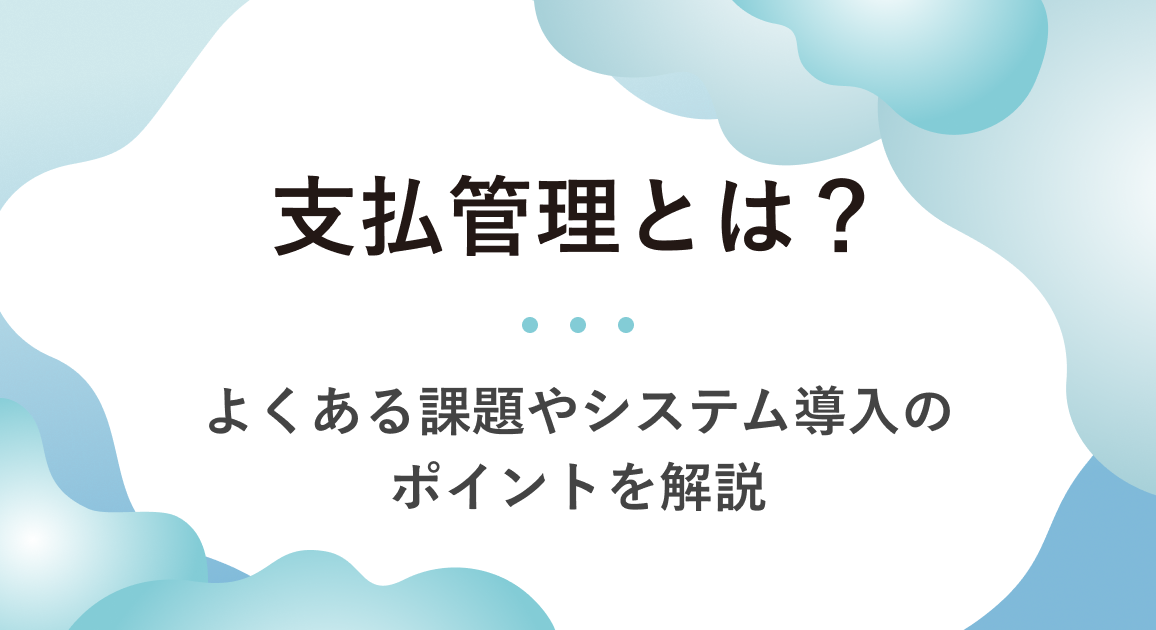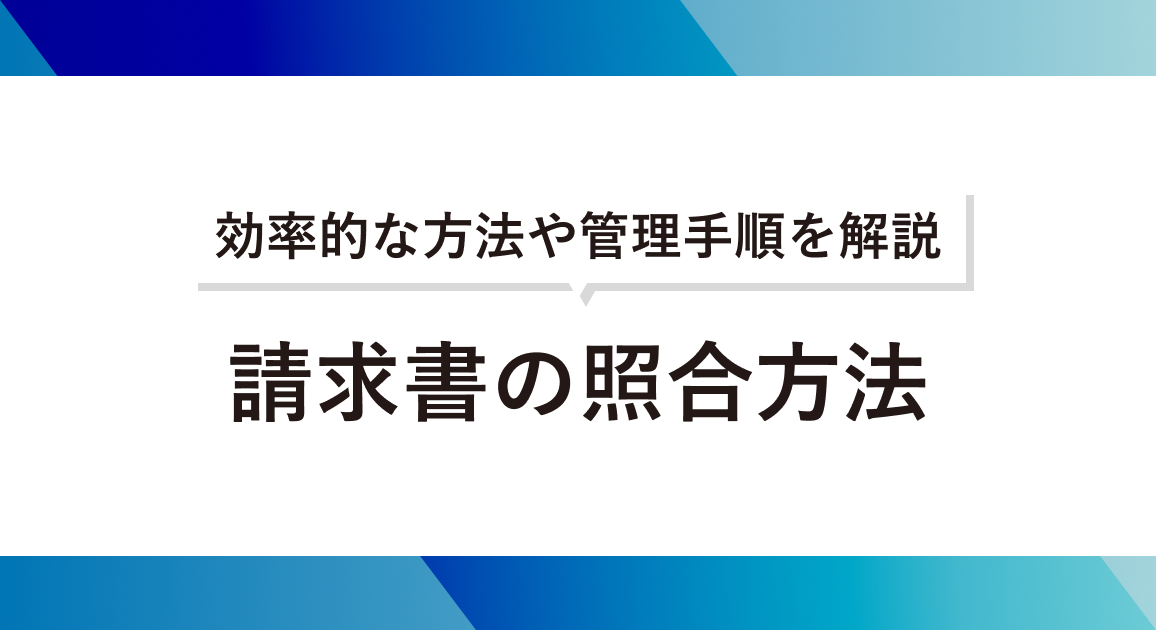- 請求書
買掛金管理とは?目的や管理方法、管理上の注意点について解説
公開日:
更新日:
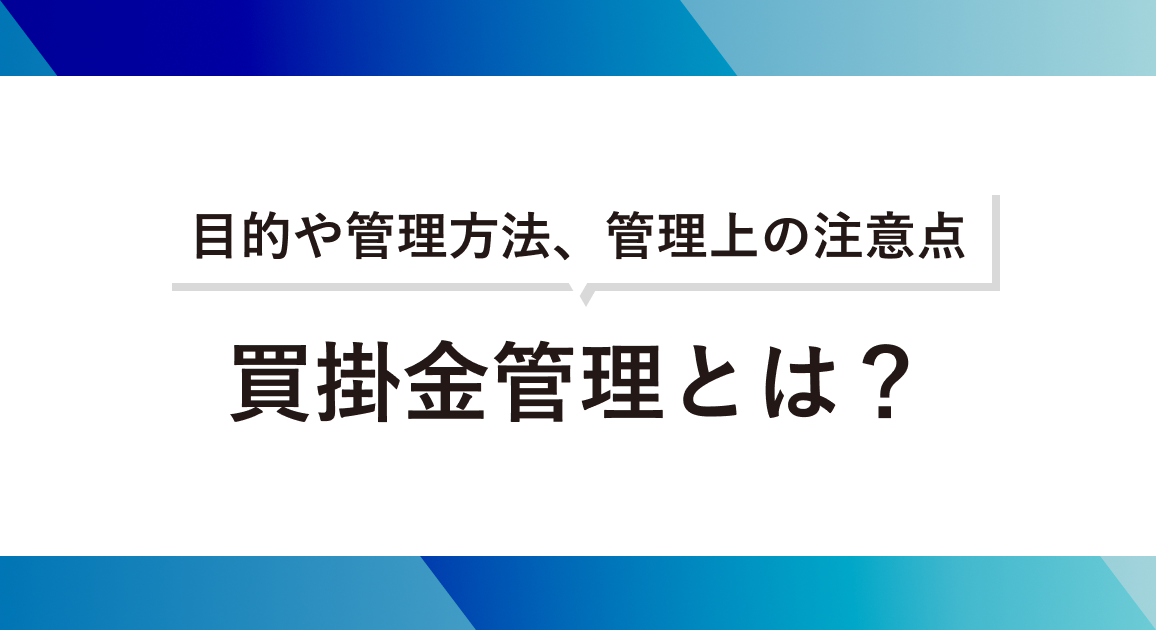
買掛金管理は、企業の資金繰りと信用を支える重要な経理業務の1つです。買掛金を適切に管理することは、支払い漏れを防ぐだけでなく、企業のキャッシュフローを把握する上でも重要です。
本記事では、買掛金管理の目的や方法、ポイントを解説し、支払い業務の効率化と財務の健全化につながるヒントをご紹介します。
請求書の処理業務をシステムで自動化
買掛金管理とは?

まず買掛金がどのようなものか、基本的な知識から説明します。似たような勘定科目との違いも理解することで、より正確な経理処理が可能になります。
買掛金とは商品やサービスの対価として将来的に支払うべき債務
買掛金とは、商品や原材料の仕入れ、あるいはサービスの提供を受けた際に発生する、後日支払いを約束した代金を指します。これは「信用取引(掛け取引)」と呼ばれる商習慣から生じるもので、将来的に金銭を支払う義務、つまり債務の一種です。
例えば、製造業の企業が部品メーカーから部品を100万円分仕入れた場合、一般的には「月末締めの翌月末払い」といった契約を結びます。この取引が成立した時点で、企業は100万円を後日支払う義務を負います。この「後日支払うべき義務」を、会計上では買掛金と呼びます。
会計上、買掛金は貸借対照表の「負債の部」に分類されます。具体的には、1年以内に支払い期限が到来する「流動負債」として計上されます。買掛金の残高は、企業の短期的な資金繰りや流動性を判断する上で重要な指標の一つです。
未払金との違い
買掛金と混同されやすい勘定科目に「未払金」があります。どちらも「後で支払う義務」という点では共通していますが、その発生原因には明確な違いが存在します。
買掛金が企業の主たる営業活動、つまり商品や原材料の仕入れから生じる債務であるのに対し、未払金はそれ以外の単発的な取引から生じる債務です。
具体例としては、事務用品の購入代金やオフィスの光熱費、外部に支払う広告宣伝費などが挙げられます。これらは事業運営に必要ですが、営業活動そのものには直接関係ありません。
このように、取引が本業に関わる継続的なものか、単発的なものかで勘定科目を使い分けます。
買掛金管理とは?
買掛金管理とは、仕入先から商品やサービスを仕入れた際に生じる買掛金を適切に管理する業務です。具体的には、請求書の内容を確認して支払いをしたり、会計処理を行ったりします。
買掛金は、将来的に支払う義務のある債務であるため、正確な管理が不可欠です。買掛金の管理を怠ると、企業の信用問題につながるだけでなく、資金繰りの悪化を招く可能性もあります。
このようなリスクを回避し、健全な経営を維持するためには、買掛金の発生から支払いまでのプロセスを明確にし、正確に記録・管理することが重要です。
買掛金を管理する3つの目的
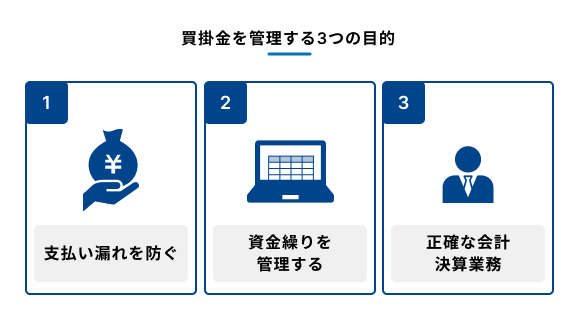
日々の業務で発生する買掛金を、なぜ正確に管理する必要があるのでしょうか。その目的は大きく分けて3つあります。
- 支払い漏れを防ぐ
- 資金繰りを管理する
- 正確な会計・決算業務
1.支払い漏れを防ぐ
買掛金を管理する最大の目的は、支払い漏れを未然に防ぐためです。特に、多くの仕入先と取引がある場合、管理が煩雑になりがちです。どの請求書に対して支払いが完了しているのかを正確に把握していないと、意図せず支払いが遅れたり、漏れてしまうリスクが高まります。
支払い遅延や漏れは、仕入先からの信用を損なう原因となり、最悪の場合には取引停止につながる可能性もあります。安定した事業活動を継続するためにも、支払い期日までに確実に支払いを完了できる体制を求められます。適切な買掛金管理は、企業の信用を守る第一歩です。
2.資金繰りを管理する
2つ目の目的は、企業の資金繰りを適切に管理することです。買掛金は将来必ず出ていくお金、つまりキャッシュアウトの予定を示しています。いつ、どの仕入先に、いくら支払う必要があるのかを正確に把握することで、将来の資金需要を予測できます。
この予測に基づいて、支払いのタイミングで手元の資金が不足しないように備えることが可能です。例えば、大きな金額の支払いが集中する月があれば、事前に資金調達を検討するなどの対策を講じることができます。
逆にこの管理ができていないと、突然の資金ショートに陥る危険性があります。健全なキャッシュフローを維持し、安定した経営基盤を築く上で、正確な買掛金の把握は不可欠です。
3.正確な会計・決算業務
買掛金は、将来的に支払い義務を伴う負債であるため、買掛金の管理は、会計や決算といった財務の正確性を保つ上で重要です。
買掛金の残高を常に正確に把握することで、企業の財務状況を正しく示せます。もし買掛金の計上漏れや金額の誤りがあると、貸借対照表上の負債が過小評価され、企業の財政状態を誤って認識してしまう恐れがあります。
また買掛金の適切な管理は、月次・年次の決算業務をスムーズに進めるためにも不可欠です。仕入先ごとに買掛金の残高を確認し、仕入先からの請求書と照合することで、計上ミスを防ぎ、監査にも耐えうる正確な決算書を作成できます。
このように、買掛金を適切に管理することは、企業の健全な経営を維持するために欠かせない、経理担当者の重要な業務です。
買掛金を管理する際のポイント

効果的な買掛金管理を実現するためには、日々の業務で意識すべきいくつかのポイントがあります。ここではミスを防ぎ、管理の精度を高めるためのポイントを紹介します。
請求内容の確認を徹底する
請求書を受け取ったら、支払い処理に進む前に必ずその内容を精査します。請求書に記載された内容が、発注内容と一致しているかを確認する作業は、過払いを防ぐ上で極めて有効です。
具体的には、請求書に記載されている商品名や数量、単価、合計金額などが、自社が持つ発注書や納品書、契約書と相違ないかを照合します。もし食い違いが見つかった場合は、すぐに仕入先に問い合わせて確認します。
仕入先ごとに買掛金元帳を作成する
買掛金の残高や取引履歴を正確に追跡するために、買掛金元帳を作成します。この元帳は、必ず仕入先ごとに分けて作成する必要があります。
取引件数が少ない場合でも、複数の仕入先の取引を1つの元帳にまとめて記録してしまうと、どの仕入先に対していくらの買掛金が残っているのかが不明瞭になります。結果として、支払い漏れや二重支払いの要因となり、管理の目的そのものを果たせなくなります。手間はかかりますが、1社ずつ個別の元帳を用意することが、正確な残高管理となります。
買掛金の回転率と回転期間を分析する
日々の残高管理に加えて、定期的に財務分析の指標を用いて自社の支払い状況を客観的に評価することも効果的です。その際に用いられるのが「買掛回転率」と「買掛回転期間」です。
買掛回転率は、仕入れの代金をどれくらいの効率で支払っているかを示す指標で、以下の計算式で求められます。
買掛回転率(回) = 売上原価 ÷ 買掛金残高
この数値が低いほど、支払いが完了するまでに時間がかかっていることを意味し、資金繰りに余裕がある状態と解釈できます。
一方、買掛回転期間は、商品を仕入れてから実際に代金を支払うまでの平均的な日数を示します。
買掛回転期間(日) = 買掛金残高 ÷ (売上原価 ÷ 365)
この期間が長いほど、支払いサイトが長いことを表します。ただし、一般的に60日を超えるなど、あまりに長過ぎる場合は仕入先の資金繰りを圧迫し、取引条件の見直しを求められる可能性もあるため注意が必要です。
定期的に買掛金残高を仕入先と照合する
自社で記録している買掛金の残高が、仕入先が認識している売掛金の残高と一致しているかを確認します。この照合作業を定期的に行うことで、双方の認識のズレを早期に発見し、修正が可能です。
具体的には、四半期末や決算期末などのタイミングで、仕入先へ残高確認状を送付し、自社の買掛金元帳の残高と照合します。もし金額に差異があれば、その原因(計上漏れ、返品処理の反映タイミングのズレなど)を特定し、必要に応じて両社の合意の下で修正します。このプロセスを経ることで、会計記録の信頼性を高められます。
買掛金を管理する3つの方法

買掛金の管理に不可欠な買掛金元帳には、その作成・管理方法にはいくつかの選択肢があります。ここでは代表的な3つの方法について、それぞれの特徴を解説します。
- Excelで管理する
- テンプレートを使用する
- システムで管理する
Excelで管理する
最も手軽に始められる方法が、Excelなどの表計算ソフトを利用した管理です。
多くの企業で導入されているソフトであり、特別なコストをかけずに、すぐに運用を開始できるのが利点です。仕入先ごとにシートを作成し、取引日や取引内容、金額、支払い状況などを記録することで、簡易的な元帳として機能します。
しかしすべての入力や更新が手作業になるため、入力ミスや計算式の誤りといった人為的なミスが発生しやすいという弱点もあります。
テンプレートを使用する
インターネット上で公開されている買掛金管理用のテンプレートを活用する方法もあります。
必要な項目があらかじめ設定されたフォーマットを利用できるため、ダウンロードすれば、すぐに使い始められます。会計ソフトメーカーなどが無料で提供しているケースも多く、手軽さが魅力です。
ただし、テンプレートは汎用的な作りになっているため、自社の特殊な取引形態や管理項目に対応できないなど、カスタマイズの自由度が低い側面もあります。
システムで管理する
近年、多くの企業で導入が進んでいるのが、会計システムや請求書受領システムを活用した管理方法です。
これらは請求書をデータで受け取ったり、紙の請求書をスキャンして読み取ったりすることで、取引内容を自動で会計システムに反映させることができます。
手入力の作業が減るため、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
買掛金管理のシステム化をおすすめする理由

買掛金管理を適切に行うために、システムの導入もおすすめです。システム導入によって買掛金管理にはどのようなメリットがあるのか、3つの観点からご紹介します。
請求書の受け取りから支払いまでを効率化
買掛金管理を手作業で行う場合、請求書の受け取り、内容の確認、担当部署への回付、上長の承認、そして経理部門での支払い処理と、多くのステップと人手を要していました。
しかしシステムを導入すれば、これらのプロセスをシステム上で一元管理できます。
請求書のデータ化から支払いデータの作成、会計ソフトへの仕訳連携までが自動化されるため、担当者は煩雑な手作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
人為的ミスを削減できる
手作業による管理では、元帳への転記ミスや支払い金額の入力誤り、支払い漏れなど、人為的ミスを完全になくすことは困難です。
これらのミスは、企業の資金を不必要に流出させたり、取引先との信頼関係を損ねたりする原因となります。
システムの導入によってデータ入力や消込作業を自動化することで、こうしたリスクを低減させ、管理の正確性を高めることが期待できます。
内部統制を強化できる
買掛金管理のシステム化は、不正行為のリスクを低減し、内部統制を強化できることも期待できます。
特に担当者による架空発注や、取引先と共謀した水増し請求、不当な値引き処理といった不正は、紙ベースの運用では発見が難しいです。
システムを導入すると、誰がいつどのような操作を行ったかの証跡がすべて記録されます。さらに発注データと請求データをシステム上で自動的に照合する仕組みを構築できるため、正当な取引に基づかない支払いを未然に防ぎ、不正が起きにくい環境を整備できます。
まとめ
本記事では、買掛金管理の基本から実践的なポイント、そして管理システム導入のメリットまでを詳しく解説しました。
買掛金は、単なる支払い義務の記録ではありません。その正確な管理は、支払い漏れを防いで取引先との信頼関係を維持し、さらには自社の資金繰りを安定させるために重要です。日々の業務においては、請求内容の確認や仕入先ごとの元帳作成、定期的な残高照合といった作業が、管理の精度を支えます。
そして手作業での管理に限界を感じている場合や、さらなる業務効率化と正確性を追求する場合には、システム導入が有効です。システムを活用することで、人為的ミスの削減や内部統制の強化にもつながり、経理部門全体の生産性を向上させることが期待できます。
クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。
受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。
Bill One請求書受領の特長
- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する
- 受領した請求書データを一元管理できる
- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック
- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合
- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管
- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている
※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。


3分でわかる
Bill One請求書受領
請求書受領から、月次決算を加速する
クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。



執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介
税理士 松崎 啓介
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
保有資格:税理士
昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務
税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)
その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。