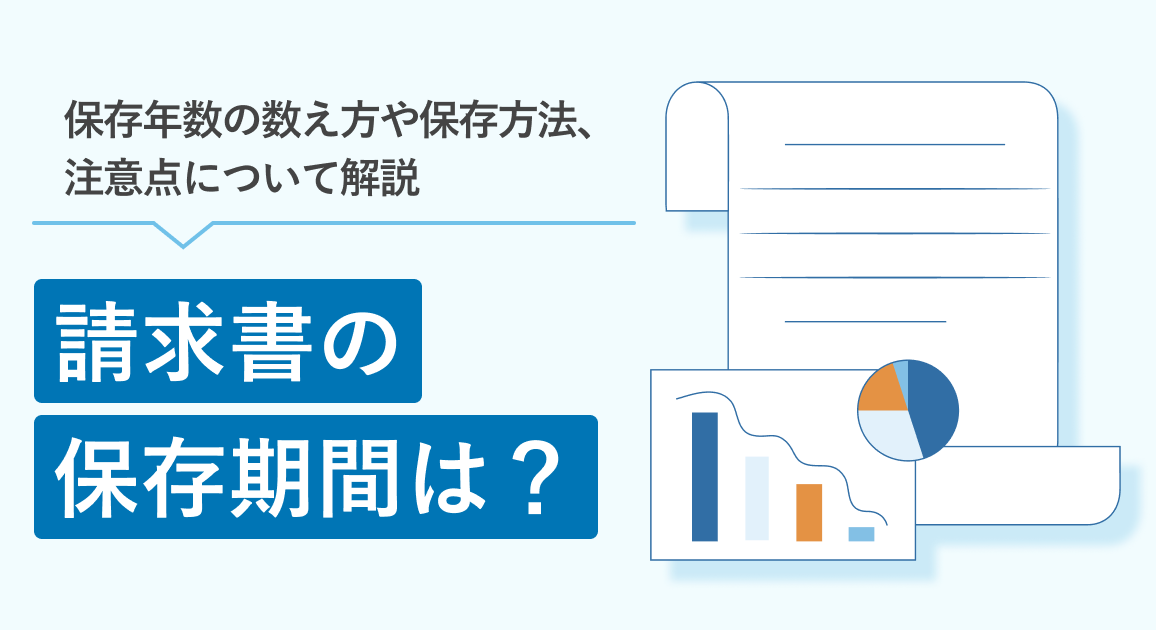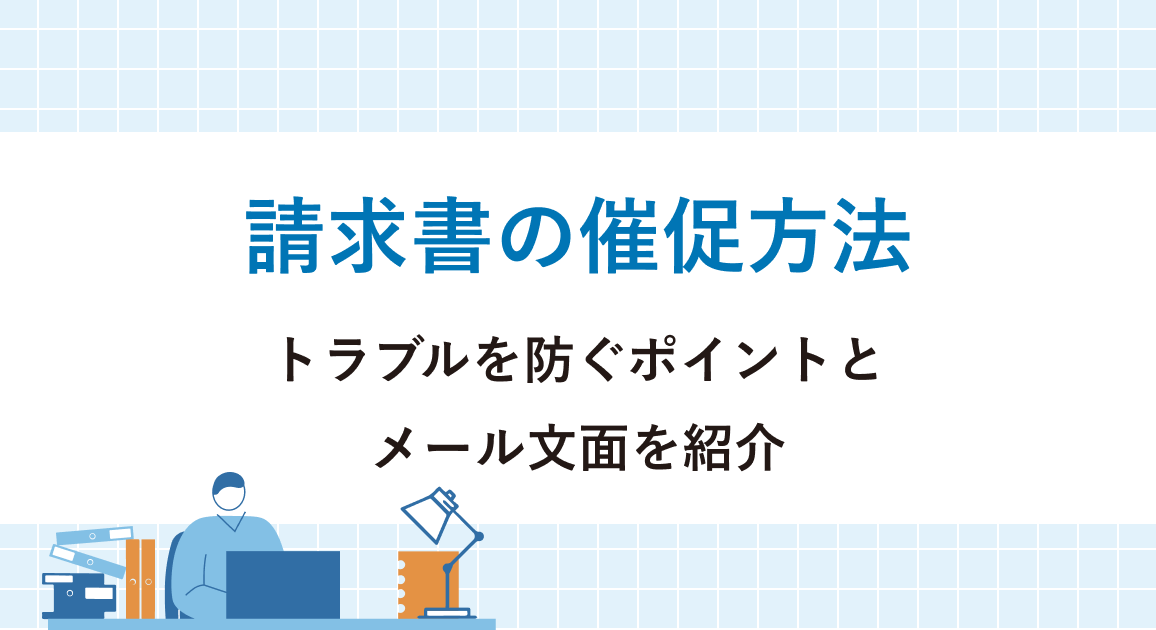- 請求書
請求書受領のメール文例はこれ【テンプレート付き】書き方・文例・マナーを解説
公開日:
更新日:
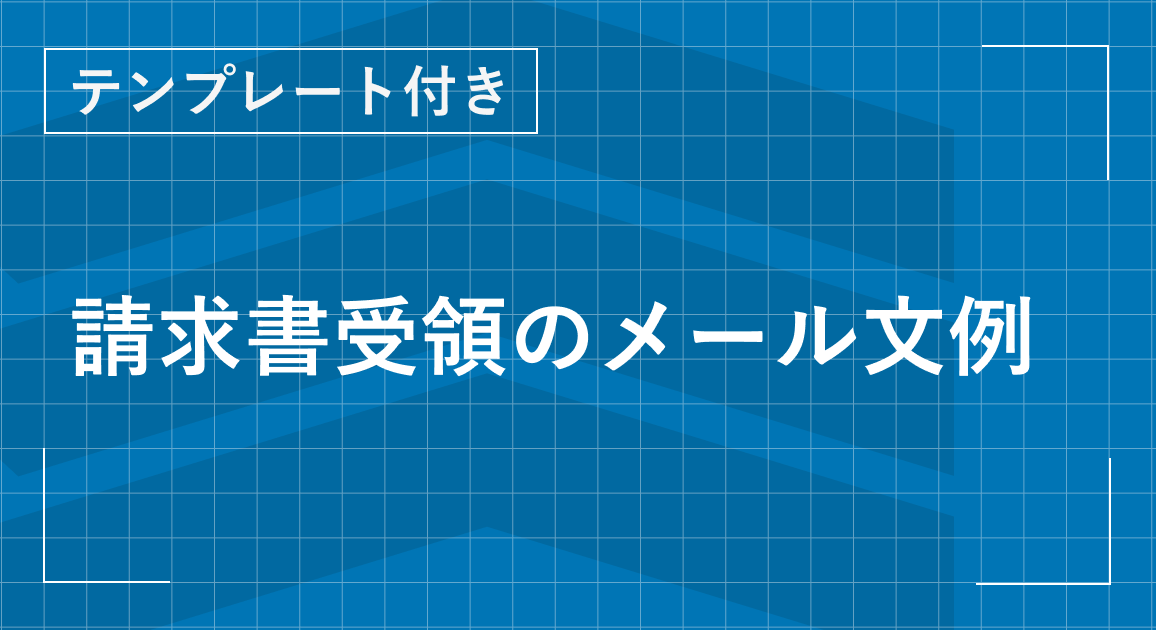
請求書を受領した際に「受領メールを送るべきか?」と迷ったことはないでしょうか。
受領メールは法律上の義務ではありませんが、送ることで取引先に安心感を与え、信頼関係の構築に役立ちます。また、請求内容の確認やトラブルを防止する上でも効果的です。
しかし、請求書受領のメールはすべてのケースで送る必要があるわけではなく、送る場合もタイミングや言葉の使い方に注意が必要です。
この記事では、請求書受領のメールの目的・必要性・書き方・具体的な文例・注意点まで詳しく解説します。正しい受領メールを送ることで、スムーズな取引を実現しましょう。
請求書受領をシステムで効率化
請求書受領のメールはなぜ必要?

請求書受領のメールは、取引の透明性を高め、スムーズなビジネスコミュニケーションを実現する重要なステップです。単なる形式的なやりとりではなく、取引先との信頼関係構築にも大きく貢献します。
受領メールの定義と目的
請求書受領のメールとは、取引先から請求書を受け取った際に「確かに請求書を受領した」という事実を伝えるためのメールです。主な目的は、取引先に請求書が届いたことを知らせ、安心感を与えることにあります。これにより、取引先は請求書の到達を確認でき、支払いプロセスが適切に進行していることが分かります。
法律上、受領メールを送る義務はありません。しかしビジネスマナーとしては送ることが一般的です。また受領メールは取引の記録としても機能するため、単なる確認連絡以上の価値があります。
受領メールを送るべきケースと不要なケース
請求書受領のメールは常に必要というわけではありません。状況によって判断すると良いでしょう。
送るべきケース
- 新規取引先との初めてのやりとりの場合
- 高額な請求書を受け取った場合
- 請求内容の確認が必要な場合(内容に不明点がある時など)
- 相手がはっきりと受領確認を求めている場合
- 重要なプロジェクトや特別な取引の場合
特に初めての取引や高額請求の場合は、受領メールを送ることで取引の透明性を高め、相互の信頼関係を構築するきっかけとなります。
送らなくてもよいケース
- 長期的な取引関係があり、相手が受領メールを期待していない場合
- オンラインシステムなど別の方法で受領確認ができる場合
- 請求書と同時に支払いも完了する場合(即時決済など)
- 日常的な少額取引で、取引先と「連絡は不要」と事前に合意している場合
- 社内ルールで不要と定められている場合
長期的な取引関係にある企業とは、事前に受領メールのルールについて確認しておくと良いでしょう。双方の業務効率化にもつながります。
請求書受領のメールを送る3つのメリット

請求書受領のメールは単なる事務作業ではありません。送ることで得られる具体的なメリットは多岐にわたります。長期的な取引関係の構築から日々の業務効率化まで、受領メールがビジネスにもたらす価値を見ていきましょう。
信頼関係の構築
請求書受領のメールを送ることは、取引先との信頼関係を築く上で重要な一歩です。「請求書を受け取りました」と伝えることで、取引先に安心感を与えることができます。特に新規取引先や重要な案件では、この小さなコミュニケーションが大きな信頼につながるでしょう。
相手の立場になって考えてみると、請求書を送ったのに何の連絡もない状況には不安を感じるものです。「本当に届いているのだろうか」「確認できているのだろうか」という疑問を抱かせないためにも、受領メールは効果的です。このような気配りが、長期的なビジネスパートナーシップの土台となります。
トラブル防止
受領メールを送るために請求書を確認することで、トラブルの回避にもつながります。請求金額や支払い期日などの重要事項に間違いや認識の違いなどがあれば、その時点で修正などを依頼できるため、後日の面倒な調整作業を避けられるでしょう。
また、送ったはずの請求書が実際には届いていないというケースもあります。普段から受領メールを送る習慣があれば、それが届かないことで、取引相手(送付元)がメールトラブルや送付ミスなどに気がつきやすくなります。
取引の透明性向上
受領メールはビジネスの透明性を高める重要な役割を果たします。メールという形で証拠が残るため「いつ請求書を受け取ったか」という事実を記録できるためです。この記録は、後日、支払いに関するトラブルが発生した際にも役立ちます。
また社内の経理処理においても、請求書の受領日が明確になることで、処理の優先順位付けや支払いスケジュールの管理がスムーズになります。特に月末や決算期など忙しい時期には、受領メールの記録を元に効率的な処理が可能になり、経理担当者の負担軽減につながるでしょう。
請求書受領のメールの基本構成
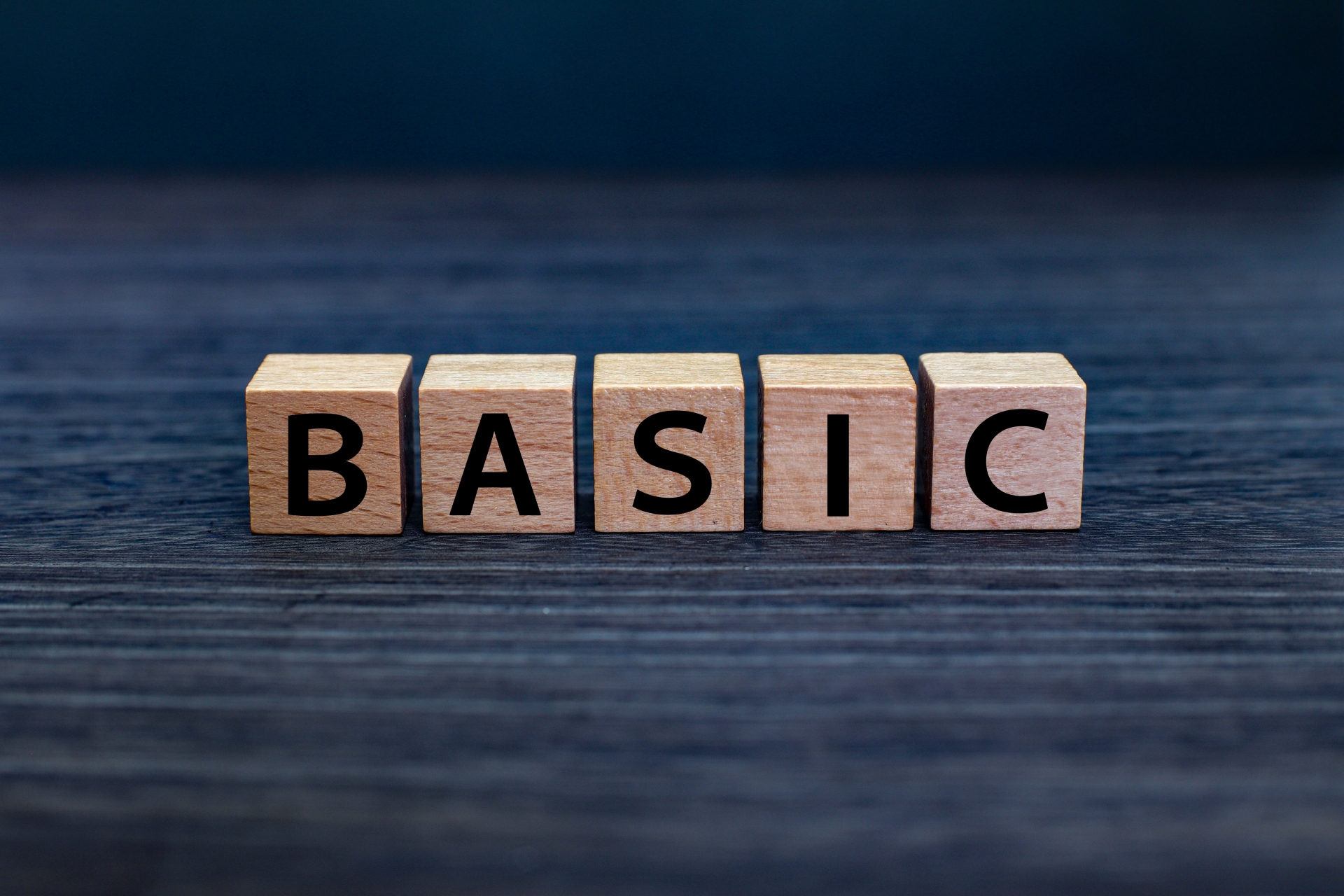
効果的な請求書受領のメールには一定の形式があります。適切な構成と表現を心がけることで、相手にプロフェッショナルな印象を与えるとともに、スムーズなコミュニケーションが可能になります。
件名の付け方
請求書受領のメールの件名は、一目で内容が分かるシンプルなものが理想的です。
効果的な件名の例
「請求書(No.12345)受領のご連絡」
「2023年6月分請求書受領のお知らせ」
「御社請求書(2023-06-15付)受領確認」
「プロジェクトA 請求書受領確認」
請求書番号や日付、プロジェクト名などの情報を含めることで、取引相手も内容を把握しやすくなります。ただし長い件名は避けて、簡潔さを心がけるようにしましょう。
本文に含めるべき要素
受領メールには、以下の要素を含めると効果的です。
- 宛名:取引先の会社名と担当者名を明記します。「株式会社〇〇 △△様」のように、丁寧に記載しましょう。
- 導入文:簡潔なお礼の言葉から始めます。「いつもお世話になっております。〇〇株式会社の□□です」などの挨拶を含めると良いでしょう。
- 確認内容:請求書の具体的な情報を明記します。
a.請求書番号
b.発行日
c.請求金額
d.対象期間/対象サービス
- 支払い予定:支払い予定日や方法について言及します。「支払い期日の〇月〇日までに指定の口座に振込みさせていただきます」など。
- 締めの挨拶:「引き続きよろしくお願いいたします」などの丁寧な締めくくりの言葉を添えます。
これらの要素を含めることで、相手に必要な情報を明確に伝えることができるでしょう。
避けるべき表現と言葉遣い
請求書受領のメールでは、ビジネス文書としてふさわしい表現を使用することが重要です。
たとえば「受信しました」という表現は避けるべきです。これはメールやデータを指す言葉で、書類の受け取りには適していません。同様に「ダウンロードしました」なども書類の受領には不適切です。
また、単に「受領」「確認」だけの表現も事務的な印象を与えるため避けましょう。適切な表現としては、以下のものが挙げられます。
「拝受いたしました」
「受領いたしました」
「確かに受け取りました」
加えて、「御社」「貴社」などの敬称を適切に使用することで、ビジネスマナーに則った受領メールになるでしょう。
【テンプレート】請求書受領のメールの文例

実際のビジネスシーンですぐに使える請求書受領のメールのテンプレートをご紹介します。
基本的な受領メール
日常的な取引先とのやりとりに適した、基本形のテンプレートです。請求書の重要情報を明確に記載することで、誤解を防ぎ、スムーズなコミュニケーションが可能になります。
件名:請求書(No.12345)受領のご連絡 株式会社〇〇 経理部 △△様 お世話になっております。 □□株式会社の◇◇です。 本日、貴社よりご送付いただきました下記請求書を確かに受領いたしました。 【請求書情報】 請求書番号:No.12345 発行日:2025年6月15日 ご請求金額:123,456円(税込) 対象:2025年5月分サービス利用料 ご請求金額については、支払い期日の2025年6月30日までに指定口座へお振込みさせていただきます。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 ------------------------------ □□株式会社 経理部 ◇◇ TEL:03-XXXX-XXXX MAIL:xxx@xxxx.co.jp ------------------------------ |
よりフォーマルな受領メール
官公庁や大企業、重要クライアントとのやりとりに適した、フォーマルなテンプレートです。「拝啓」「敬具」の挨拶や丁寧な表現を用いることで、敬意と誠実さを伝えられます。
件名:御請求書(整理番号:ABC-2023-06-123)受領のご連絡 株式会社〇〇 財務経理部長 △△様 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 このたび、貴社よりご送付いただきました下記御請求書を確かに拝受いたしましたのでご連絡申し上げます。 【御請求書詳細】 請求書番号:ABC-2023-06-123 発行日:令和7年6月15日 ご請求金額:金1,234,567円(消費税込) 対象:令和7年度第1四半期コンサルティング業務委託料 ご請求の金額については、支払い期日の令和7年6月30日までに貴社指定の金融機関口座へ遅滞なく振込手続きを完了させていただく所存です。 今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 敬具 □□株式会社 財務経理部 部長 ◇◇ TEL:03-XXXX-XXXX(直通) MAIL:xxx@xxxx.co.jp |
請求書に誤りがあった場合の返信例
請求書の内容に誤りがあった場合も、まずは受領の事実を伝え、その上で具体的な確認事項を丁寧に説明することが重要です。相手を責めるような表現は避け、事実確認を依頼する姿勢を保ちましょう。
件名:請求書(No.12345)受領と内容確認のお願い 株式会社〇〇 経理部 △△様 お世話になっております。 □□株式会社の◇◇です。 本日、貴社よりご送付いただきました請求書(No.12345)を受領いたしました。 内容を確認させていただいたところ、以下の点について確認させていただきたく存じます。 【確認事項】 請求書には5月分のサービス利用料として123,456円と記載されていますが、弊社の記録では5月分のご利用金額は98,765円となっております。 また、契約書上の合意金額とも相違があるようです。 お手数をおかけして恐縮ですが、内容のご確認をお願いいたします。 何卒よろしくお願い申し上げます。 |
請求書受領のメールを送る際の注意点

請求書受領のメールは単に送るだけでなく、送り方にも配慮が必要です。適切なタイミングや表現、取引先のルールへの理解など、細かな点に気を配りましょう。
適切なタイミングで送信する
請求書受領のメールは、基本的には受け取った当日中、遅くとも翌営業日までに送るのが望ましいです。長時間放置すると、取引先に「重要視されていない」という印象を与えかねません。
送信する時間帯にも配慮が必要です。早朝や深夜、休日などの業務時間外の送信は避け、できるだけ営業時間内に送るようにしましょう。取引相手とこちらの営業時間が異なる場合、相手の業務時間を考慮した送信タイミングを心がけることで、さらに良好な関係構築につながります。
取引先のルールを確認する
企業によっては、独自の請求書処理ルールを持っている場合があります。なかには「受領メールは不要」と明示している企業もあるでしょう。
新規取引を開始する際には、事前に請求書の受領確認に関するルールを確認しておくことをおすすめします。「請求書を受け取った際の確認方法について、御社のルールがあれば教えていただけますか」と尋ねることで、相手企業の方針に沿った対応が可能です。
明確なルールがない場合でも、長期的な取引関係にある相手とは、双方の効率化のために「特に言及がなければ受領メールは省略する」などの取り決めを行うことも一つの方法です。取引先のルールに合わせた柔軟な対応が、円滑なビジネス関係につながります。
受領メールを送らない場合のリスク
受領メールを送らないことで生じるリスクは想定以上に大きいかもしれません 。まず、取引先に「この企業は請求書の管理がずさんではないか」という不信感を与えかねません。特に新規取引先との関係では、この小さな不信感が取引継続の判断材料になることもあります。
また、請求書の未達や内容の誤りに気づかないまま支払い期日を過ぎてしまうと、取引先との関係が悪化するだけでなく、遅延損害金の発生や信用低下など実質的な不利益となる可能性もあります。さらに、内部監査や会計監査の際にも、請求書の受領から支払いまでのプロセスが明確に記録されていないことが問題視されることがあります。
請求書を受領した後の流れ

請求書を受け取った後の処理は、単に受領メールを送るだけでは終わりません。適切な社内フローに沿って処理を進め、期日管理や書類保管まで一連の流れを把握しておくことが重要です。
受領メールを送る
取引先への受領メールの送信は、請求書の処理フローの第一歩です。請求書を受け取ったらできるだけ早く、前述のテンプレートなどを参考に受領メールを送りましょう。
受領メールには、請求書番号や金額などの基本情報を記載します。支払い予定日についても触れると親切です。特に、初めての取引や高額請求の場合は、相手に安心感を与えるためにも丁寧な対応を心がけましょう。
社内承認フロー
受領メールを送った後は、社内での承認プロセスに移ります。一般的な流れとしては、まず請求書を経理担当者に渡し、内容確認を依頼します。大企業や組織的な承認フローがある場合は、決裁権限に応じた承認ルートに沿って処理を進めていきます。
主な社内承認フローは以下の通りです。
- 請求内容の確認(発注内容と相違がないか)
- 担当部署による承認(サービス・商品の納品確認)
- 管理部門や責任者による最終承認
- 支払い処理の準備
これらのプロセスをスムーズに進めるためには、社内での情報共有を徹底し、請求書の処理状況を可視化することが重要です。特に複数部署が関わる場合は、承認の遅延が支払い遅延につながらないよう注意が必要です。
支払い期日の管理
請求書の受領後、社内承認が完了したら、支払い期日の管理に移ります。支払い遅延は取引先との関係悪化や、場合によっては遅延損害金の発生につながるため、適切な期日管理が欠かせません。
未払いの請求書は、支払い期日順にファイリングするか、電子管理システムで整理し、定期的に確認する習慣をつけましょう。特に月末など、複数の支払いが集中する時期は注意が必要です。
また、支払い済みの請求書も適切に保管する必要があります。法人の場合は原則として7年間の保存が義務付けられています。
請求書の保存期間についての詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。
トラブル時の対応
請求書に関するトラブルは、早期発見・早期対応が重要です。特に、請求書が届かない場合や、期日が近づいているのに未着の場合は、積極的に取引先へ確認の連絡を取るべきです。
たとえば、通常なら月初に届くはずの請求書が10日経っても届かない場合は「いつも月初に頂いている請求書がまだ届いていないようですが、既に送付されていますでしょうか」といった丁寧な催促メールを送りましょう。
請求内容に不明点や誤りがある場合も、早めに確認の連絡を取ることで支払い遅延のリスクを回避できます。
請求書の催促メールについての詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
本記事では、請求書受領のメールの必要性から具体的な文例、送信する際の注意点まで詳しく解説しました。請求書受領のメールは、単なる形式的なやりとりではなく、取引先との信頼関係構築や業務の透明性向上に大きく貢献する重要なコミュニケーションです。
しかし請求書の数が増えるにつれて、受領確認から支払い管理までの一連の流れには多大な時間と労力が必要となってきます。ここで活躍するのが請求書受領システムです。Bill One請求書受領のようなシステムを導入することで、請求書の受領確認から支払いまでの流れをデジタルで完結でき、人為的ミスも大幅に減らせます。
クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。
受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。
Bill One請求書受領の特長
- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する
- 受領した請求書データを一元管理できる
- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック
- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合
- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管
- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている
※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。


3分でわかる
Bill One請求書受領
請求書受領から、月次決算を加速する
クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。



記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部