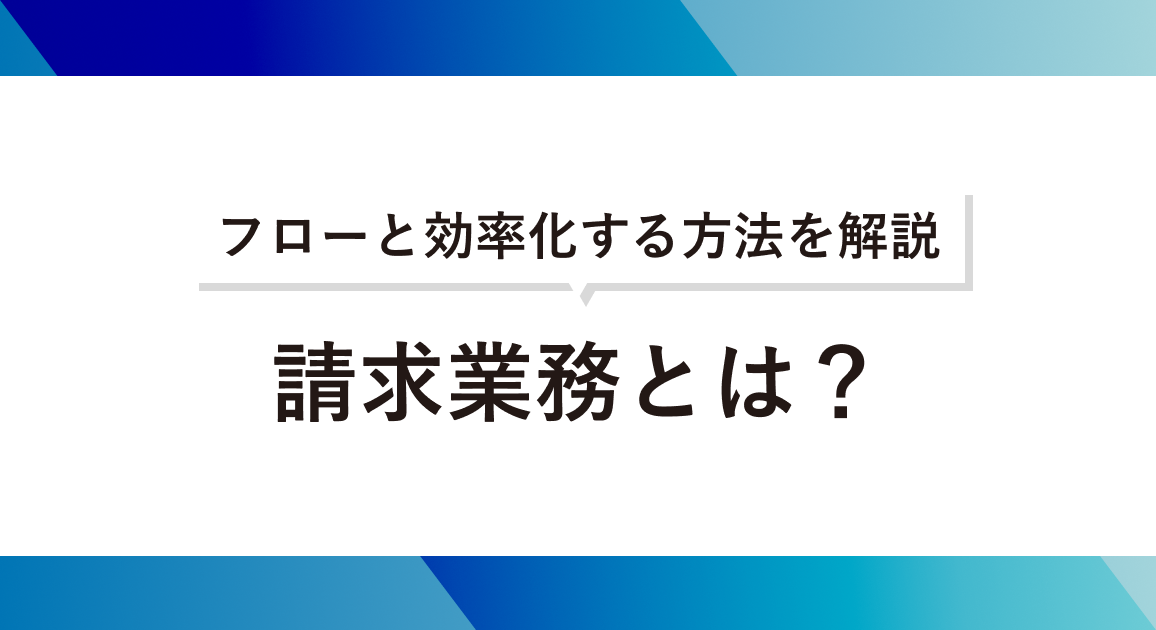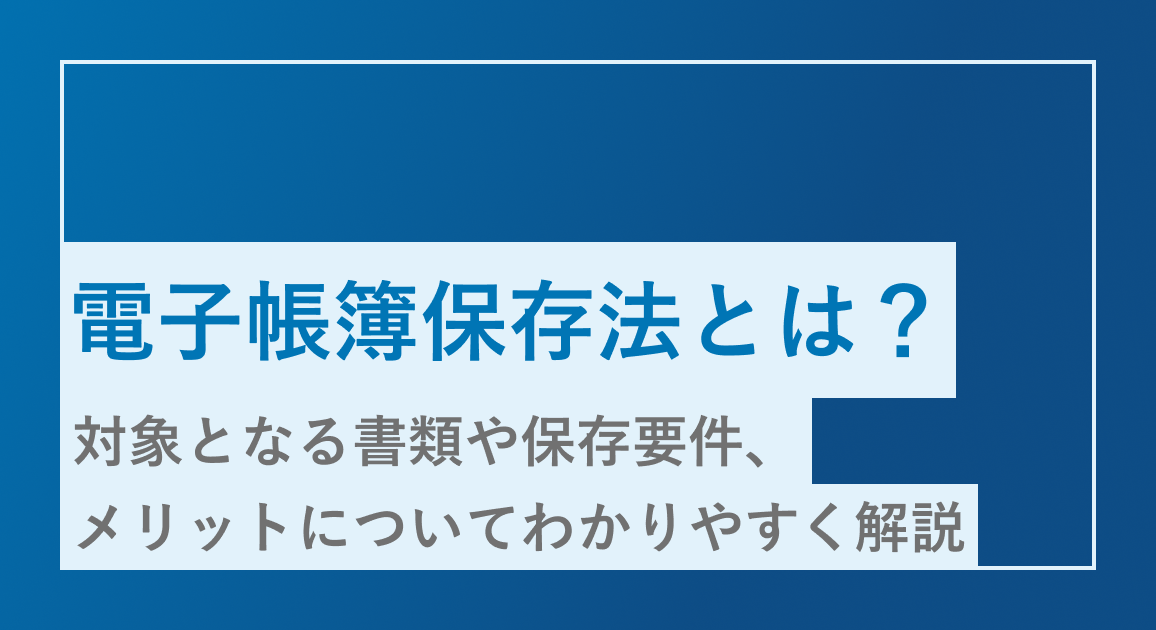- 請求書
請求書をペーパーレス化する方法 | メリットや導入時の注意点を解説
公開日:
更新日:
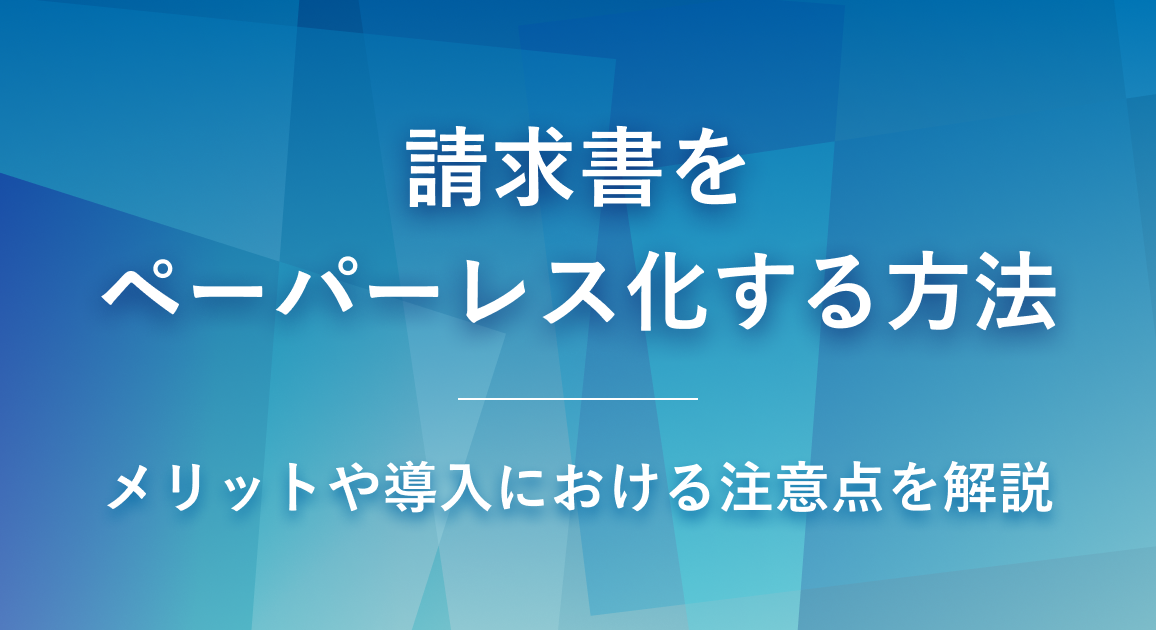
近年、請求書をペーパーレス化する企業が増えています。請求書のペーパーレス化には、多くのメリットがありますが、長年にわたり、紙の請求書を使用してきた企業にとって、既存の業務を遂行しながらペーパーレス化を推進するのは非常に困難であると言えます。
この記事では、請求書のペーパーレス化の概要やメリットをご紹介した上で、推進に当たっての注意点や手順を紹介します。電子請求書の保存要件についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
請求書をオンラインで管理しペーパーレス化
請求書をペーパーレス化する方法

請求書のペーパーレス化とは、紙の請求書を廃止し、電子化されたデータで発行から受け取り、保存、管理までを行う取り組みのことです。テレワークや働き方改革の推進に伴い、請求書のペーパーレス化を進める企業が増えています。
まずは、請求書をペーパーレス化する方法を見てみましょう。本記事では、「請求書発行におけるペーパーレス化」と「請求書受け取り・保存におけるペーパーレス化」に分けて解説します。
請求書発行におけるペーパーレス化
請求書発行におけるペーパーレス化では、紙ではなく電子データとして請求書を発行します。専用の請求書作成ソフトやクラウドサービスを導入すれば、電子請求書を簡単に作成できます。
請求書作成ソフトの中には毎月のルーティン業務を自動化できるものや、取引先への自動送信が可能なものなどがあり、業務効率を大幅に向上できることが魅力です。
なお、請求業務を効率化する方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
請求書受け取り・保存におけるペーパーレス化
請求書の受け取り・保存においては、受け取った請求書を電子データとして保存します。電子データで受領した請求書だけでなく、紙の形式で受け取った請求書をスキャンして電子保存することも可能です。
ただし、いずれの場合も電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。詳しくは後述しますが、要件を理解して適切に保管しましょう。
請求書をペーパーレス化するメリット
続いて、請求書をペーパーレス化するメリットを見てみましょう。請求書をペーパーレス化する主なメリットは以下の通りです。
- 請求書業務の効率化
- 請求書業務におけるコストカット
- テレワーク・在宅勤務への対応
- 請求書管理の一元化
- 紛失や情報漏えいのリスクの低減
1. 請求書業務の効率化
請求書を電子データで管理することで、請求書業務全般を効率化できます。
紙で請求書をやりとりする場合、印刷や郵送、承認作業などに時間がかかります。また、確認も手作業で行わなければならず、ミスのリスクも高くなってしまいます。
請求書システムを導入してペーパーレス化を実施すれば、各工程にかかる時間を大幅に短縮できます。作成した請求書をワンクリックで相手に送信できたり、承認もオンライン上で完結できたりと、担当者間の確認をリアルタイムで進められるようになります。
また、自動化を取り入れることで負担が少なくなるだけでなく、入力ミスも少なくなり、修正対応にかかる時間も削減できます。
2. 請求書業務におけるコストカット
紙の請求書を発行・管理するためには、以下のような費用が発生します。
- 印刷費用:用紙やインク代など
- 郵送費用:切手代や封筒代など
- 保管スペースの維持費:紙の書類を保管する倉庫やキャビネットの維持費
- 人件費:書類整理やデータ入力、ファイリングなどを行う人件費
請求書をペーパーレス化すれば、上記のようなコストを大幅に削減できます。特に郵送費用は取引先が多い企業ほど大きな負担となりますが、電子送付により郵送にかかる費用もゼロにできます。また、ペーパーレス化により、不要になった保管スペースを別の業務で有効活用することもできるでしょう。
3. テレワーク・在宅勤務への対応
テレワークや在宅勤務に対応できることも、請求書をペーパーレス化するメリットの1つです。
働き方改革やテレワークの推進を契機に、業務のオンライン化が進んでいます。しかし紙の請求書を前提とした業務フローでは、出社しなければ処理が進められないことも多いのが実情です。経理担当者が直接紙の請求書を確認したり、上長の承認を得るために押印してもらったりと、わざわざオフィスに出向かなければならないケースが多くあります。
ペーパーレス化を進めれば、オンラインで発行から承認、受け取り、保管までを完結できるため、場所を問わず業務が可能です。取引先からの問い合わせもリアルタイムで対応できるため、業務の停滞を解消できるでしょう。
4. 請求書管理の一元化
請求書管理を一元化できることも大きなメリットです。
紙の書類管理では、必要な書類を探すのに時間がかかる場合があります。特に過去の請求書を確認したい場合、膨大な書類の中から該当のファイルを探し出さなければなりません。
一方、ペーパーレス化で請求書を電子データとして管理すれば、検索機能を利用して瞬時に必要な情報を取り出せるようになります。取引先名や発行日を入力するだけで、関連書類を表示できるため、過去のデータの確認作業もスムーズです。
5. 紛失や情報漏えいのリスクの低減
請求書のペーパーレス化により、請求書の紛失や情報漏えいのリスクを低減できます。
紙の請求書は、物理的な紛失や盗難のリスクが伴います。特に外出先で書類を持ち歩く場合、置き忘れや紛失による情報漏えいも問題となります。また、災害時に書類が損傷・消失してしまう可能性もあるでしょう。
電子データとして管理することで、上記のようなリスクを最小限に抑えられます。請求書システムによっては、アクセス権限を細かく設定したり、万が一に備えてバックアップを取ったりすることも可能です。
請求書をペーパーレス化する手順

以下では、請求書をペーパーレス化する手順を解説します。
- ペーパーレス化の目的を明確にする
- 請求書システムを導入する
- 運用体制を整える
- 社内・取引先へ周知する
それぞれ詳しく見てみましょう。
1. ペーパーレス化の目的を明確にする
まずは、ペーパーレス化の目的を明確にしましょう。導入理由や目的が曖昧のままプロジェクトを進めても導入後に方向性がぶれてしまい、期待した効果が得られない可能性があります。
例えば、よくある導入目的には次のようなものがあります。
- 業務効率を改善したい
- テレワーク対応を強化したい
- 紙の保管スペースをなくしたい
請求書システムにはさまざまな種類があるため、目的によってシステムを選定する際の判断基準が変わってきます。各部署へのヒアリングも行いながら現状の課題を把握し、最も優先順位の高い目標を決めましょう。
2. 請求書システムを導入する
目的が明確になったら、自社に最適な請求書システムを選びましょう。1つのサービスだけでなく、複数のサービスを比較検討することが重要です。
プランや料金はもちろん、操作性や機能の充実性、セキュリティー対策、電子帳簿保存法への対応など、多角的に検討することがポイントです。中には無料のトライアル期間を設けているものもあるので、活用してみるのもよいでしょう。
3. 運用体制を整える
システムを導入したら、請求書業務をスムーズに行うための運用体制を整備します。紙の請求書とは処理内容や手順が異なるため、新たな担当者のアサインや役割の見直しなども検討しましょう。
請求書処理の各段階で誰が担当するかを決め、業務フローを明確にします。この際、エラー時の対応ルールを決めておくと、万が一トラブルが生じた際もスムーズです。
なお、運用開始後も不便な点があれば洗い出し、改善を重ねることが大切です。
4. 社内・取引先へ周知する
最後に、社内や取引先へ周知しましょう。導入決定後、早ければ早いほど良いでしょう。
取引先によっては紙での請求書を希望してくる可能性もあり、そういった場合は個別に対応する必要があるかもしれません。
また、社内担当者や取引先も対応準備を進める必要があるため、できるだけ早く案内を出すことが理想です。
請求書をペーパーレス化する際の注意点

請求書をペーパーレス化する際の注意点は以下の通りです。
- 導入・運用コストを考慮する
- すべての取引をペーパーレス化できるとは限らない
- 電子帳簿保存の要件を満たす必要がある
- 取引先・社内への周知を徹底する
- スモールスタートで段階的に移行する
1. 導入・運用コストを考慮する
ペーパーレス化を進める際は、導入前に総額のコストを確認しましょう。
紙の削減で経費が節約できる一方、システムの導入や運用に費用がかかる点は押さえておきましょう。特に、自社向けにカスタマイズしたり、開発をしたりする場合は、初期費用が高額になることもあります。
とはいえ、単に価格が「安い」「高い」といった基準だけで決めるのではなく、自社の業務に適しているかを慎重に見極めることが大切です。導入により発生するコストと、削減できる工数・コストを照らし合わせて、費用対効果を検証しましょう。
2.すべての取引をペーパーレス化できるとは限らない
請求書の電子化が進んでいるとはいえ、すべての取引先がデジタル対応しているわけではありません。
自社でペーパーレス化を進めた場合も、取引先の中には紙の請求書を希望する企業や、電子請求書の受領に対応していないケースもあります。取引先ごとの事情に応じて個別の対応が求められる可能性もあるため、無理にすべてを電子化しようとするのではなく、イレギュラーの対応手段も柔軟に検討しておきましょう。
3.電子帳簿保存の要件を満たす
請求書を電子データとして保存する場合、法律に基づいた管理を行わなければなりません。日本では「電子帳簿保存法」により、法人は原則7年間の書類保存が義務付けられています。
また、電子帳簿保存法の規定にもとづき、電子化された請求書は以下の要件を満たす必要があります。
- 真実性の確保…電子データが改ざんされていないことを証明できる状態であること
- 可視性の確保…ファイルへのアクセスが容易であること
請求書システムを導入する場合は、上記を満たしているサービスを選びましょう。
なお、電子帳簿保存法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
4. 取引先・社内への周知を徹底する
請求書のペーパーレス化を円滑に進めるには、社内外への十分な周知と説明が不可欠です。社内では、導入目的や新しい業務フローを全社員に理解させる必要があります。
システムの操作方法が分からない状態では、せっかく導入しても利用してもらえません。経理部門以外の部署でも、請求書の発行や受領に関わる部門や担当者へ操作方法やルールをしっかり共有しましょう。マニュアルの作成やレクチャーの実施も効果的です。
また、取引先への案内も重要です。急な運用変更を通知すると、取引先が混乱し、クレームの原因となる可能性もあります。できるだけ早い段階で、電子化の方針と導入スケジュールを説明しましょう。
5. スモールスタートで段階的に移行する
ペーパーレス化を成功させるには、一度にすべての移行を目指すのではなく、スモールスタートで段階的に進めていくことが現実的です。
いきなり全社規模で導入すると、予期せぬトラブルが生じた際に、業務に支障をきたす恐れがあります。特に大規模な企業では関係部署が多いため、一度にシステムを浸透させるのは時間がかかります。
まずは請求書の発行頻度が高い部署や、比較的業務がシンプルな部門でテスト導入を行ってみると良いでしょう。小規模な運用で課題を洗い出し、課題が解消された段階で次のフェーズへ進むとスムーズです。
まとめ
本記事では、請求書のペーパーレス化について解説しました。請求書のペーパーレス化により請求書業務全般の効率化につながることはもちろん、紙の請求書管理にかかるコスト削減も実現できます。
請求書のペーパーレス化を進める際は、自社に適した請求書システムを導入することが大切です。一口に請求書システムといってもさまざまなサービスがあるため、自社のニーズに合ったものを導入しましょう。
「Bill One」は、請求書の受領・発行などの経理業務を効率化できるサービスです。
請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。
債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。
これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。
Bill One請求書受領の特長
- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する
- 受領した請求書データを一元管理できる
- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック
- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合
- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管
- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One債権管理の特長
- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行
- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理
- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能
- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能
- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結
Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。


3分でわかる
Bill One請求書受領
請求書受領から、月次決算を加速する
クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。




3分でわかる Bill One債権管理
リアルタイム入金消込で、現場を強くする
クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。



記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部