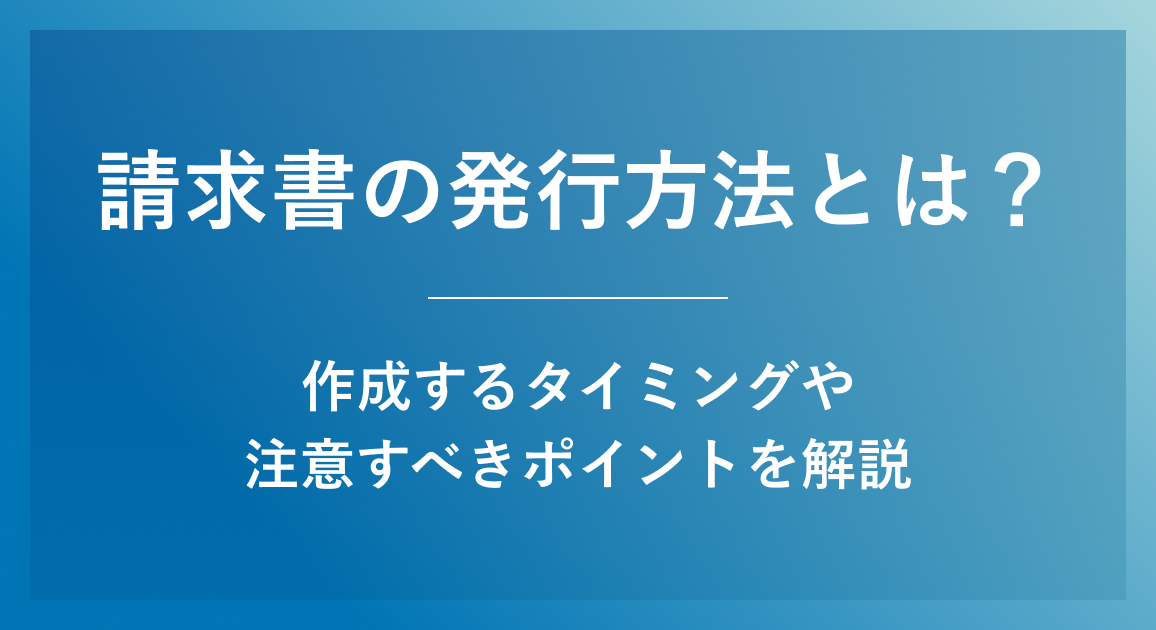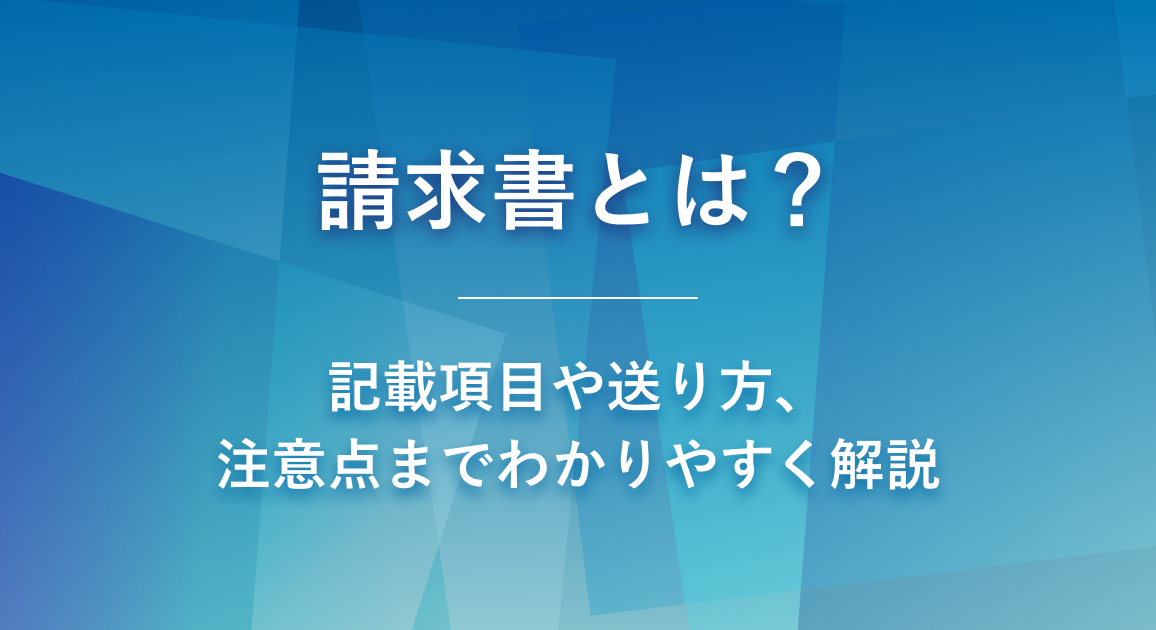- 請求書
請求書の支払期限を徹底解説!設定方法や期限を過ぎたときの対処法
公開日:
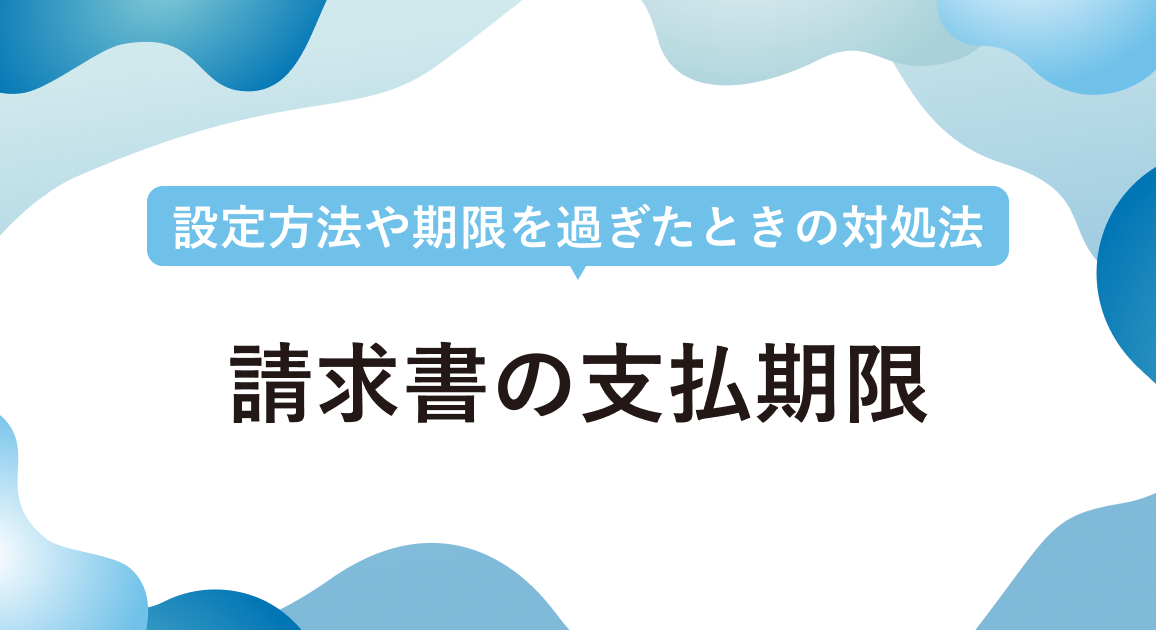
請求書の支払期限は、取引先との信頼関係を築く上で重要なポイントです。しかし、支払期限の意味や、支払期日・締め日との違いがあいまいなまま運用しているケースも少なくありません。
本記事では、請求書における支払期限の基本ルールや設定時のポイントを整理するとともに、支払期限を過ぎた場合の対応方法や、注意点についても解説します。適切な請求書管理の運用と、未然のトラブル防止にお役立てください。
受領も発行も対応!請求書業務を効率化
請求書の支払期限とは?
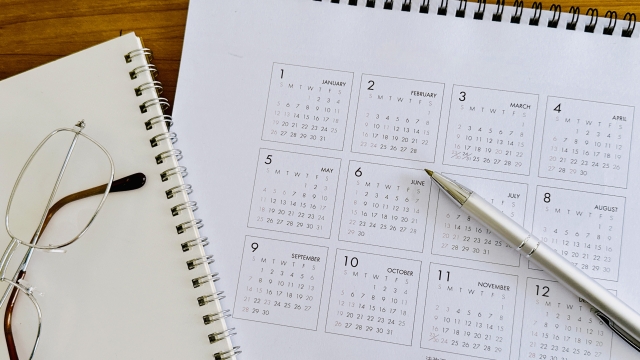
請求書の支払期限とは、取引先に対して「いつまでに金額を支払う必要があるか」を明示する日付のことです。
支払期限を明確に示すことで、取引先とのやり取りがスムーズになり、未入金のリスクを減らせます。経理業務や資金繰りの計画にも影響するため、請求書を発行する際には事前に支払期限を決めておくことが一般的です。
支払期限と支払期日の違い
請求書における「支払期限」と「支払期日」については、厳密には以下のような違いがあります。
- 支払期限:いつまでに支払う必要があるかを示した日付
- 支払期日:支払いを行うべき具体的な日付
たとえば、支払期限を「5月末までに支払う」と定めている場合、「5月31日が支払期日」ということになります。
とはいえ、上記を区別して使用するケースは少なく、どちらも同じような意味合いで使われることが一般的です。
支払期限と締め日の違い
「支払期限」と「締め日」も混同されやすい用語ですが、両者については意味がまったく異なります。
- 支払期限…「いつまでに支払う必要があるか」を示したもの
- 締め日…取引期間の区切りとなる最終日
支払期限が請求金額を支払う期日であるのに対して、締め日は取引期間の区切りとなる日付であり、請求金額を確定するための基準日です。たとえば「月末締め・翌月末支払い」のように、締め日をベースに発行日や支払日を決める形が一般的です。
締め日は売上の管理や請求金額を確定するための基準となる日であり、支払いそのものの期限とは異なります。
請求書に支払期限は必要?

請求書に支払期限を記載することは、法律上の義務ではありません。しかし実際には、多くの企業が支払期限を設けています。
ここで押さえておきたいポイントは、以下の通りです。
- 請求書への支払期限の記載は義務ではない
- トラブルを避けるために記載することが一般的
- 入金遅延のリスクを低減しやすくなる
請求書の支払期限は義務ではない
請求書の記載内容には明確な法的ルールがなく、フォーマットも企業ごとに異なります。そのため、支払期限を記載するかどうかは、発行側の判断に委ねられています。
ただし、期限を明示しないと、受領側が支払日を勘違いする可能性もあります。特に、取引の内容が複雑になるほど支払タイミングのすれ違いが発生しやすくなるため、注意が必要です。
トラブルを避けるために記載することが一般的
支払期限の記載は義務ではないものの、トラブルを避けるために記載することが一般的です。
期限が明記されていない場合、取引先が支払いを後回しにしてしまう可能性もあります。こうした行き違いを防ぐためにも、期限の記載は基本といえます。
また、支払期限を記載しておくことで、業務の進行が可視化されやすくなります。経理担当者がスムーズに処理できるようになり、支払状況の確認や催促の対応もしやすくなります。
入金の遅れを回避しやすくなる
支払期限を明記することで、入金遅延に早期に気づくことができ、速やかな対応につながります。取引先も期限を意識するため、支払いを後回しにされにくくなる効果が期待できます。
また、支払期限が明記された請求書の方が内容を確認しやすく、受領側の処理負荷の軽減にもつながります。
請求書の支払期限は自由な取り決めが可能

請求書の支払期限は、法律で一律に定められているものではありません。基本的には、発行側と受領側の合意があれば、自由に取り決めることが可能です。
支払条件としてよく見られる形式としては、「月末締め・翌月末払い」など、毎月の経理処理や資金繰りのサイクルに合わせた支払条件が一般的です。こうしたスケジュール設定により、取引双方の業務負担を軽減することにもつながります。
また、契約書などで支払サイト(支払条件の取り決め)をあらかじめ明確にしておくことで、請求書を発行するたびに調整する手間も省けます。こうした合意がない場合は、請求書に明記した支払期限が事実上の基準となるため、日付の設定は慎重に行う必要があります。
請求書を作成するタイミングについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
請求書の支払期限を設定するときのポイント
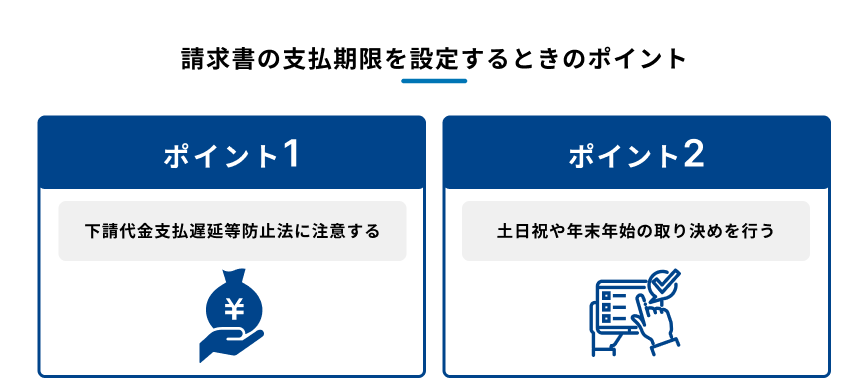
ここでは、請求書の支払期限を設定するときのポイントについて解説します。
下請代金支払遅延等防止法に注意する
取引当事者の資本金規模や取引内容によっては、下請事業者の利益保護を目的とした下請代金支払遅延等防止法の適用対象となる場合があります。
下請代金支払遅延等防止法では、親事業者が下請事業者に対して支払うべき代金について、「商品やサービスの受取日から60日以内」に支払うことを原則としています。
たとえば、納品日が4月1日の場合、「毎月末日納品締切、翌月末日支払」の支払制度を採用していなければ、支払期限は5月30日までに設定する必要があります。
一方、「毎月末日納品締切、翌月末日支払」の支払制度採用している場合には、『受領後60日以内』のルールが『受領後2か月以内』として運用されますので、4月1日に納品を受けた場合、5月31日に支払ったとしても下請法上差し支えありません。
これに違反すると、監督官庁からの指導や勧告を受ける可能性があります。
一般的な「月末締め・翌月末払い」のような慣例的な支払条件であれば、同法の範囲内に収まるケースが多いですが、支払期限の設定時には取引先の区分を確認しておくことが重要です。
土日祝や年末年始の取り決めを行う
支払期限を設定する際には、カレンダー上の休日にも注意が必要です。期限が土日祝日や年末年始と重なる場合、金融機関が営業しておらず、期日通りの支払いが難しくなることがあります。
このような場合に備え、契約書や請求書に「支払期限が休業日に当たる場合は前営業日とする」といったルールを明記しておくと安心です。たとえば、「5月31日が日曜日であれば、前営業日の5月29日(金曜日)を支払期限とする」といった形です。
このような取り決めがないと取引先との間で認識のずれが生じやすくなるため、事前に土日や年末年始の対応方法を決めておきましょう。
請求書の支払期限の書き方

支払期限の記載方法や、土日祝日や年末年始の取り決めは、発行する企業の裁量で記載場所や文言を自由に設定できます。ただし、取引先が見落とさないよう、必要な情報を明確かつ視認性の高い形式で記載することが重要です。
実務では、請求書の上部や下部に「支払期限:2025年5月31日」といった形式で記載されることが一般的です。日付は西暦表記に統一するとわかりやすいでしょう。また、支払方法(銀行振込、口座名義など)とセットで記載すると、受領側のスムーズな支払いにつながります。
【受領側】請求書の支払期限を過ぎてしまったときの対処法
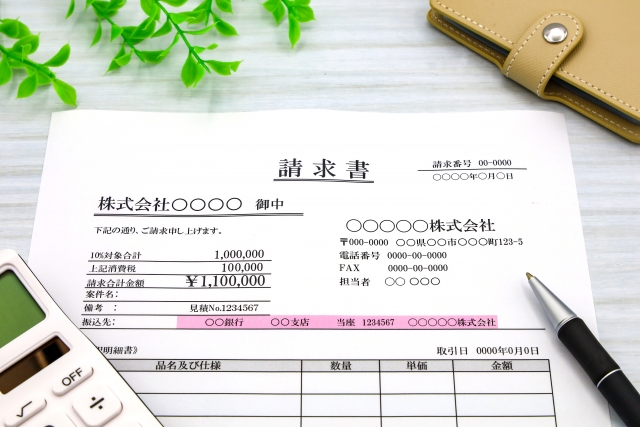
受け取った請求書の支払期限が過ぎてしまった場合、取引先へできるだけ早く連絡し、誠意をもって事情を伝えましょう。放置すると信用の低下や取引停止につながる可能性があるため、迅速な対応が求められます。
まずは請求元の企業に連絡を入れ、謝罪の意を示したうえで、具体的な支払予定日を伝えるようにしましょう。明確な日付を提示することで、相手に安心感を与えることができます。
また、期限が短すぎて対応が間に合わない場合や、請求書に支払期限の記載がない場合などは、事前に連絡することでトラブルを防ぎやすくなります。支払期限があいまいな場合は、希望する支払日を伝えて、事前に了承を得られるように進めましょう。
なお、支払期限以外の記載項目や送り方については、以下の記事も参考にしてみてください。
【発行側】請求書の支払期限を過ぎても入金がないときの対処法

自社が発行した請求書の入金が期日までに確認できない場合、順を追って対応を進めましょう。いきなり強く催促すると、取引関係に悪影響を及ぼす可能性もあります。誤解や行き違いの可能性も含めて、ひとつずつ確認することがポイントです。
- 自社にミスがないか確認する
- 取引先に連絡する
- 内容証明を送付する
- 支払督促を申し立てる
1. 自社にミスがないか確認する
自社が発行した請求書の支払が遅れている場合、まず行うべきは「自社側に原因がないかどうか」の確認です。
支払期限や金額、振込先情報に誤記がある場合、取引先が対応を保留している可能性があります。送信済みの請求書が正しい宛先に届いているか、PDFの添付忘れなども含めて確認します。
2. 取引先に連絡する
自社側に問題がなかった場合は、取引先に連絡を取り、未入金の状況について丁寧に確認しましょう。
たとえば「〇月〇日支払予定の件について、入金の確認が取れておりません」といった形で、事実ベースで伝えることが重要です。
大手企業などでは、経理部門が請求内容を把握していない可能性もあるため、営業窓口の担当者に直接確認するとスムーズです。
3. 内容証明を送付する
メールや電話での連絡を入れたにも関わらず入金が確認できない場合は、内容証明郵便の送付を検討しましょう。内容証明とは、相手に対して「請求の意思があること」を法的に示す手段です。記録が残るため、万が一トラブルが生じた際の証拠としても活用できます。
とはいえ、相手方が必ずしも悪意があるとは限りません。「〇日までにご対応いただけますようお願いいたします」といったように、事実をベースにした表現を使いましょう。
4. 支払督促を申し立てる
内容証明を送付してもなお入金がない場合は、最終手段として裁判所に「支払督促」を申し立てることが可能です。これは相手方に対して法的に支払義務を認めさせるための手続きであり、相手が異議を申し立てなければ、強制執行も可能になります。
ただし、関係が完全に決裂するリスクもあるため、最終手段として検討するのが一般的です。社内での検討や、顧問弁護士との相談を経たうえで進めるようにしましょう。
請求書の支払期限に関するよくある質問
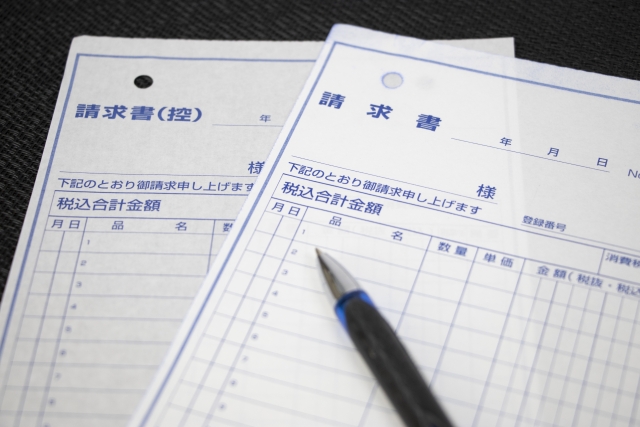
最後に、請求書の支払期限に関するよくある質問をまとめました。
- 支払期限の法律は?
- 支払期限を過ぎるとどうなる?
支払期限の法律は?
下請代金支払遅延等防止法など特定の法律を除き、請求書の支払期限を記載すべき義務や記載方法について明確に定める法律はありませんが、「債権をいつまで請求できるか」という観点では、民法で時効期間が定められています。
2020年の民法改正により、商取引における債権の消滅時効は「債権の行使ができることを知ったときから5年」もしくは「(債権を知らない場合)債権を行使できるようになったときから10年」とされました。
参照:法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
支払期限を過ぎるとどうなる?
支払期限を過ぎても入金が確認できない場合、契約内容に基づき遅延損害金(延滞利息)が発生する可能性があります。利率は契約書に明記されていることが多く、記載がない場合は年3%の法定利率(民法で定められた遅延損害金の利率)が適用されます。
また、長期にわたって支払われない場合は、内容証明の送付や法的手続き(支払督促、訴訟など)に発展することもあります。
※2025年4月時点
まとめ
請求業務では、請求書の発行から入金確認、消込処理までの一連のプロセスを正確かつ効率的に運用することが重要です。また、請求書を受領した発注者も、支払漏れの有無や原因に応じて請求書を適切に管理する必要があります。特に、複数の請求先がある場合や入金のタイミングが取引先ごとに異なる場合は、支払管理が煩雑になりやすいため注意が必要です。
「Bill One」は、請求書の受領・発行などの経理業務を効率化できるサービスです。
「Bill One」を活用することで紙の請求書を電子化し、請求書の受領及び発行における業務の削減につながります。
請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。
債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。
Bill One請求書受領の特長
- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する
- 受領した請求書データを一元管理できる
- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック
- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合
- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管
- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One債権管理の特長
- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行
- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理
- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能
- 発行済み請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能
- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結
Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。


3分でわかる
Bill One請求書受領
請求書受領から、月次決算を加速する
クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。




3分でわかる Bill One債権管理
リアルタイム入金消込で、現場を強くする
クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。



記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部