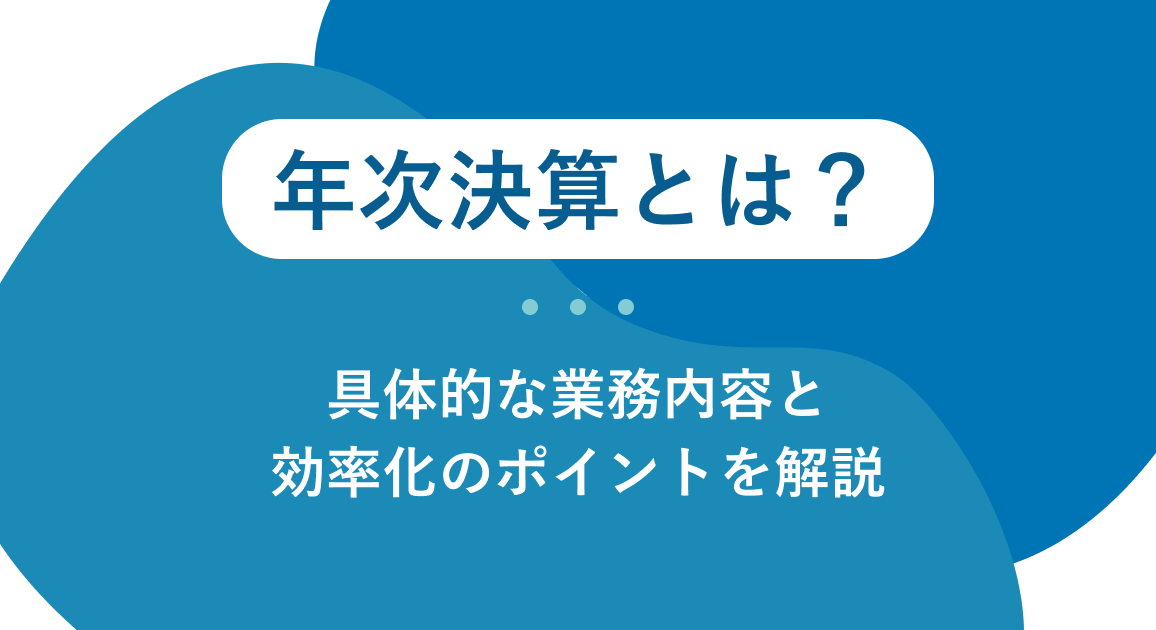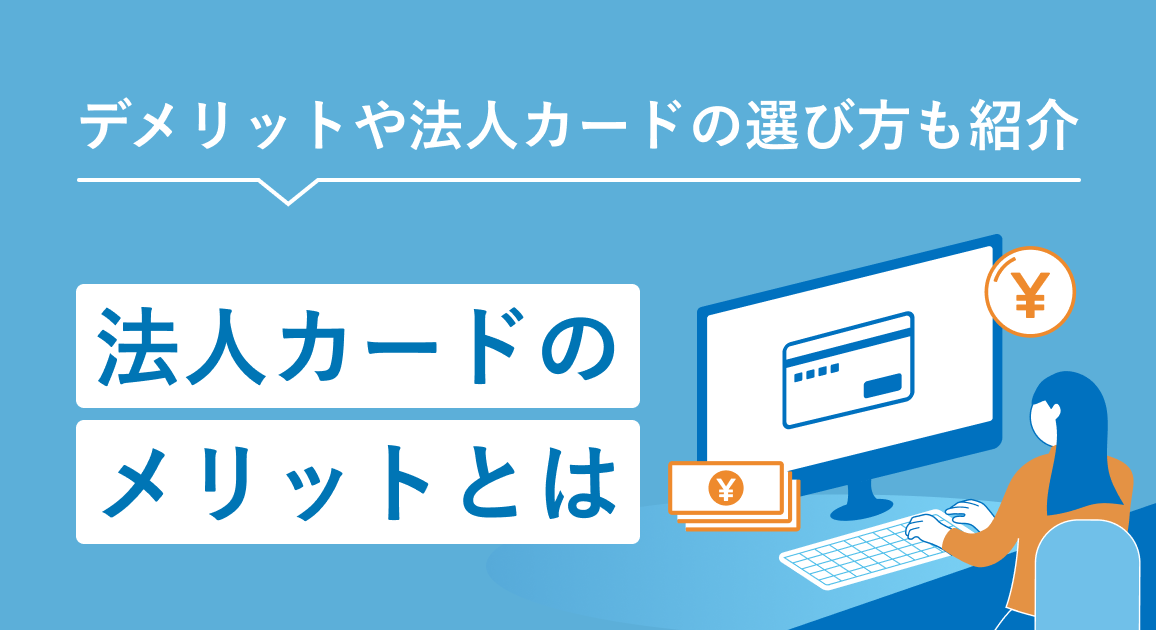- 経費精算
経費精算の振込はいつ行うべき?法律上の期限と振込遅れを防ぐ方法を解説
公開日:
更新日:
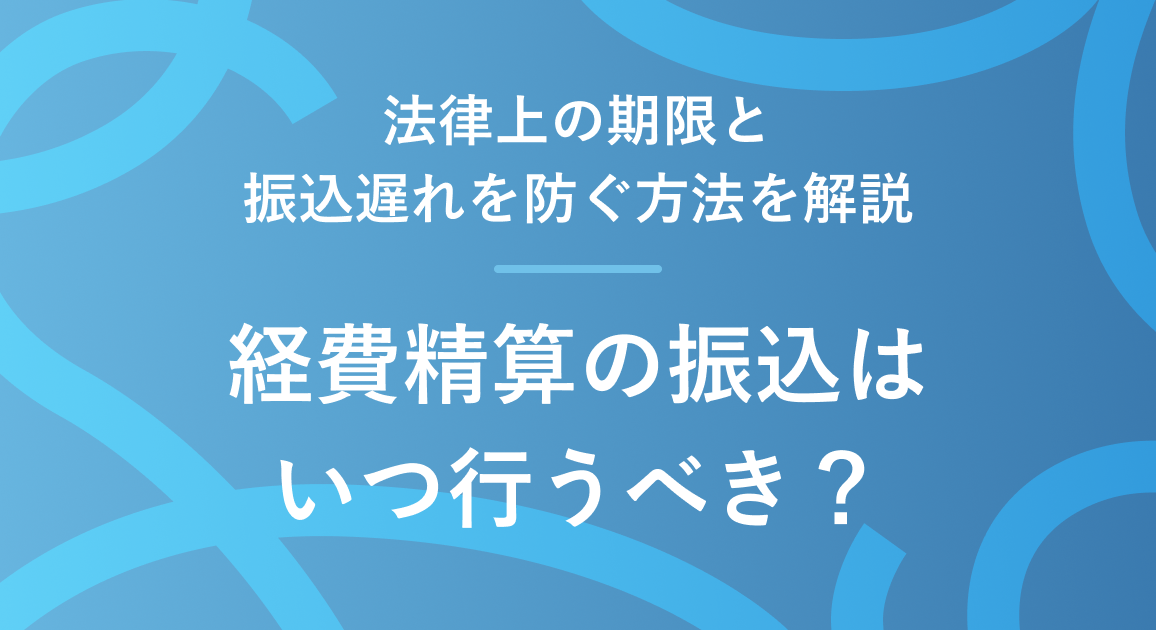
「経費精算の振込はいつ?」といった社員の何気ない疑問であっても、経費精算の振込が遅れることで実務上の課題に発展する可能性があります。振込タイミングが不明確だったり遅延が発生したりすることで社員の不満や不信感を招き、モチベーションの低下につながりかねないためです。
また、経費精算が適切に行われていない企業というイメージを持たれることで、社会的な信用低下を招くリスクもあります。
この記事では、経費精算における一般的な振込タイミングの考え方や法的な注意点、振込遅延の対策などを整理してご紹介します。
立替経費をなくす新しい経費精算スタイル
経費精算の一般的な振込タイミングはいつ?
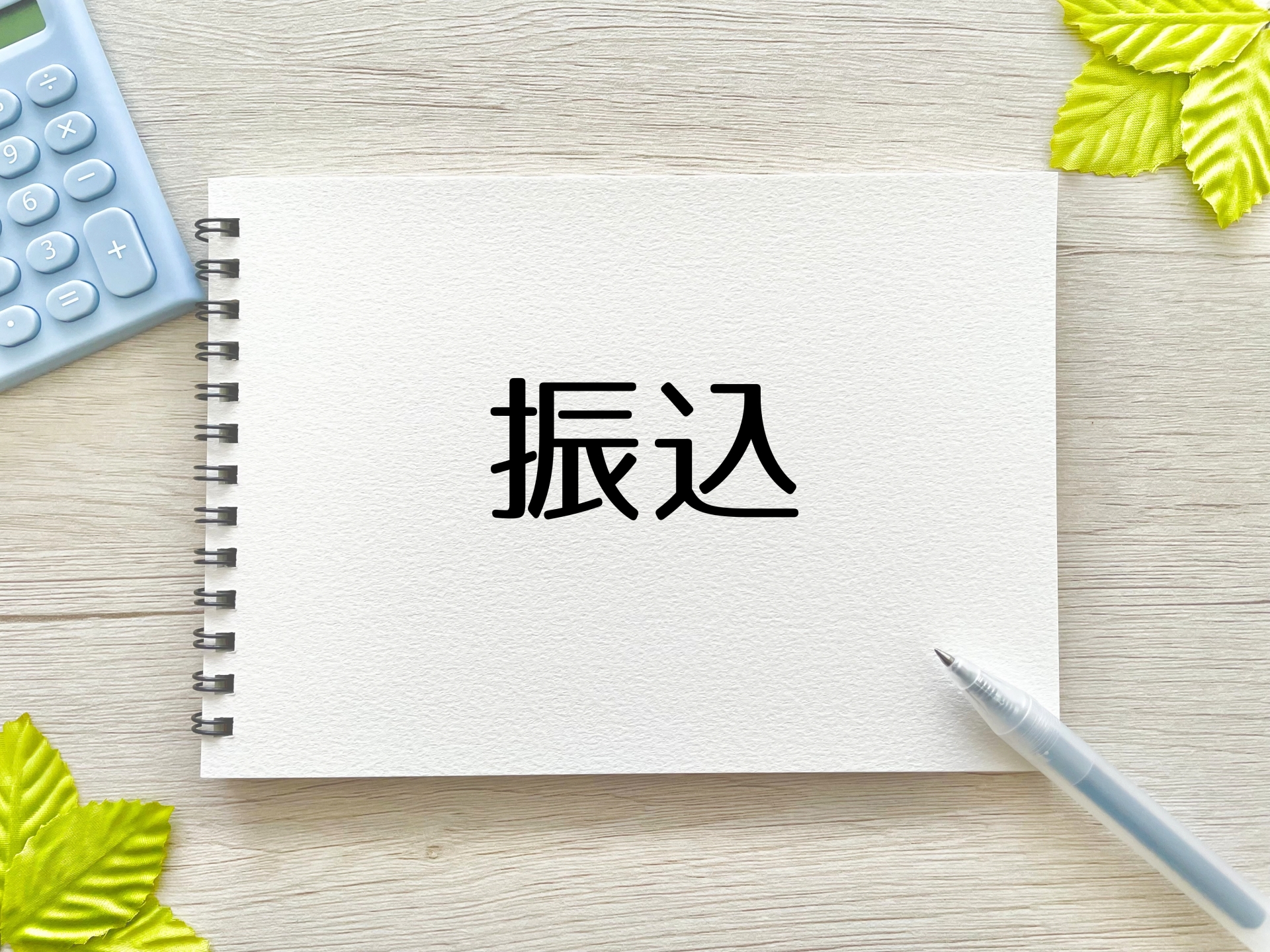
経費精算の振込タイミングは企業ごとに異なりますが、業務効率や社員の満足度、企業の財務状況などを考慮して最適な方法を選ぶことが大切です。ここでは、一般的な振込パターンを見ていきます。
給与と同時
多くの企業では、経費精算の振込を給与支払いと同じタイミングで行っています。月末締めの翌月25日払いなど、給与の支払い日に合わせることで、振込業務を一度にまとめることができます。
メリット
- 振込手数料の削減が可能で、コスト効率が高い
- 社員にとって分かりやすく、いつ振り込まれるか予測しやすい
- 経理部門の業務効率化につながり、作業の集中管理ができる
デメリット
- 給与計算との兼ね合いで処理が煩雑になる可能性がある
- 締め日が早まり、月末近くの経費が翌々月の精算になる場合もある
- 社員の立替期間が長くなり、不満が生じる可能性がある
月1回、特定の支払い日を設定
給与日とは別に、月に1回特定の日(例:15日)を経費精算の支払い日として設定する方法です。例えば「前月末締め当月15日払い」というルールを設けることで、担当者は計画的に振込業務を進めることができます。
メリット
- 経理部門が処理スケジュールを立てやすく、業務の集中を防げる
- 給与計算とは別のタイミングで処理できるため、業務の分散化が図れる
- 社員にとっても、いつ振り込まれるか予測しやすい
デメリット
- 給与振込と別に行うため、振込手数料が余分にかかる
- 月に一度の支払いのため、月初に発生した経費は立替期間が長くなる
- 締め日と支払い日の間に十分な処理期間を確保する必要がある
月2回など、複数回の支払い日を設定
経費精算の振込を月に複数回(例:10日と25日)設定する方法です。例えば「15日締め当月25日払い、月末締め翌月10日払い」といったルールを設定します。これにより、社員の立替負担を軽減することができます。
メリット
- 社員の経費立替期間が短縮され、金銭的負担が軽減される
- 経費発生から還付までの期間が短くなり、社員満足度が向上する
- 経費精算業務が分散されるため、月末の業務集中を防げる
デメリット
- 経理担当者の作業回数が増加し、業務負担が大きくなる
- 振込手数料が複数回分かかるため、コストが増加する
- 締め日や支払い日が複数あり、管理が複雑になる可能性がある
申請受付後に都度
経費申請を受け付けた後、一定期間内(例:3営業日以内)に都度振り込む方法です。この方法は、社員の立替負担を最小限に抑えることができる反面、経理担当者の負担が大きくなります。
メリット
- 社員の立替期間を最小限に抑えられ、経済的負担が少ない
- 経費精算に対する社員の満足度が高くなる
- 急な出張や高額な立替に対して柔軟に対応できる
デメリット
- 経理担当者の業務負担が著しく増加する
- 振込手数料が頻繁に発生し、コスト増加につながる
- 処理のタイミングが不規則になり、業務の計画が立てにくい
経費精算でいつ振り込むかを決めるポイント

経費精算の振込タイミングを決める際には、自社の状況や業務の効率性、社員の満足度などを総合的に考慮する必要があります。以下のポイントを参考にして、最適な振込タイミングを設定しましょう。
社員数と申請件数
経費精算の申請件数は、社員数や業務の特性によって大きく異なります。例えば営業部門が多い企業や出張が頻繁にある企業では、申請件数が多くなるのが一般的です。
社員数や申請件数が多い場合は、月1回など定期的なタイミングでまとめて処理する方が効率的です。申請が多すぎると都度払いでは経理担当者の負担が大きくなりすぎるため、ある程度まとめて処理するのが現実的な選択といえます。
一方、少人数の企業や申請件数が少ない場合は、都度払いや複数回の支払いを選択しても経理の負担は比較的小さく抑えられるでしょう。
経理部門の体制・リソース
経費精算の処理能力は、経理部門の人員体制やリソースによって制限されます。専任の経理担当者がいる企業と、兼任で経理業務を行っている企業では対応力が異なります。
経理部門の人員が限られている場合は、月1回など処理業務を集中させる方が効率的です。逆に、十分な人員やシステムが整っている場合は、より頻繁な支払いスケジュールを組むことも可能でしょう。
重要なのは、経理部門に過度な負担をかけず、無理のないスケジュールを設定することです。業務が集中して処理が遅延する場合は、振込タイミングの見直しを検討する必要があります。
キャッシュフロー
経費精算のタイミングを決める際には、企業のキャッシュフローを考慮することも重要です。特に成長中の企業や季節変動のある業種では、資金繰りが厳しい時期があります。
経費の支払いが集中すると一時的に資金需要が高まるため、企業の入金サイクルと支出タイミングのバランスを考慮して振込日を設定しましょう。例えば、主要顧客からの入金後に経費精算の振込を行うといった工夫も有効です。
ただし、キャッシュフローを理由に経費精算を過度に遅らせることは社員の不満につながる可能性があるため、バランスの取れた判断が求められます。
社員のニーズ
経費精算の最大の目的は、業務のために立て替えた社員への適切な還付です。社員の立場からすれば、立替期間は短いほど経済的負担が軽減されます。
特に高額な出張費や交際費が発生する部門では、立替負担が大きくなりがちです。社員の経済状況や不満の声を考慮して、可能な限り立替期間を短縮する工夫が必要でしょう。
経費精算の法的な振込期限は?

経費精算の振込タイミングについて明確な法的期限はありません。一方で、税法や民法には振込期限を決める際の参考となる規定があります。それらの内容をしっかり理解して、適切な経費精算プロセスを構築しましょう。
税法上は「事業年度内精算」が原則
税法上、経費は発生した事業年度に計上することが基本原則です。例えば4月から翌年3月までが事業年度の企業であれば、その期間内に発生した経費は原則としてその年度内に精算することが望ましいとされています。
これは法人税法上の「債務確定主義」に基づくもので、費用は債務が確定した事業年度に計上するという考え方です。経費が発生した時点で企業の債務は確定しているため、その事業年度に経費として計上するのが原則となります。
ただし、実務上は「月またぎ」の経費精算は十分にあり得ます。例えば3月末に発生した経費を4月に精算するケースでは、決算のタイミングによって、以下のように対応が異なるでしょう。
- 決算前:未払費用として計上し、当年度の経費として処理
- 決算後:翌年度の経費として処理
このように決算期をまたぐ経費精算は、取り扱いに特に注意が必要となります。決算が確定した後は遡って修正することが難しいため、決算期末に発生した経費については、未払費用計上などの適切な会計処理を行うことが重要です。
また、月またぎの経費精算が多発すると、会計処理が煩雑になるだけでなく正確な財務状況の把握が難しくなる点にも注意が必要です。
年次決算についての詳しい内容は、以下の記事をお読みください。
立替金の消滅時効は5年
社員が企業に経費精算を請求できる期間は、民法上、原則として5年間とされています。民法第166条第1項には「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき」に時効により消滅すると規定されています。
つまり、社員は経費が発生してから5年間は原則として企業に対して精算を請求することができます。これは企業が定める経費精算の期限(例:発生から1カ月以内など)とは別の、法律上の権利です。
経費精算に関する社内ルールを設ける場合は、社員の権利を不当に制限するようなものではなく、業務効率化や会計処理の適正化のためであることを明確にした上で、十分な周知と理解を得るようにしましょう。
経費精算の振込が遅れるとどうなる?

経費精算の振込が遅れると、想像以上に多くの悪影響を企業にもたらします。単なる事務処理の遅延と捉えるのではなく、組織全体にかかわる重要な問題として認識することが必要です。
社員の不信感を招く
経費精算の振込が遅れると、最も直接的な影響を受けるのは立替をした社員です。自分のお金を企業のために使ったにもかかわらず、その返金が遅れることで不満や不信感が生まれます。
特に「経費がいつ返ってくるのか?」という疑問は社員のストレスとなります。経費の金額が大きい場合や、頻繁に立替が発生する部門の社員にとっては、個人の家計にも影響を及ぼす重大な問題です。
このような状況が続くと企業への信頼が低下し、業務へのモチベーションも下がってしまいます。最悪の場合、優秀な人材の流出にもつながりかねません。また、経費精算の遅れが常態化すると、社員が経費を立て替えることに躊躇するようになり、必要な業務活動(営業訪問や取引先との会食など)が滞る可能性もあります。
社会的信用力が低下する
経費精算の振込遅延は、以下のような面で企業の社会的信用力の低下につながることもあります。
まず考えられるのは、決算情報の信頼性が低下する恐れです。経費の計上が適切なタイミングで行われないと、財務諸表の正確性に疑問が生じます。このことは、取引先や金融機関に対して悪い印象を与える可能性があります。
また、経費精算という基本的な業務の期限が守れない企業は、他の事項についても管理がずさんではないかという印象を与えかねません。結果として、契約期限や納品期限などの重要な約束事も守れないのではないかと取引先に疑念を抱かせるおそれがあります。
さらに、税務調査の際に経費精算の遅延や不適切な処理が見つかると、企業全体の経理体制への信頼性が問われ、より詳細な調査の対象となる可能性があります。
経費精算の振込が遅れる原因と対策
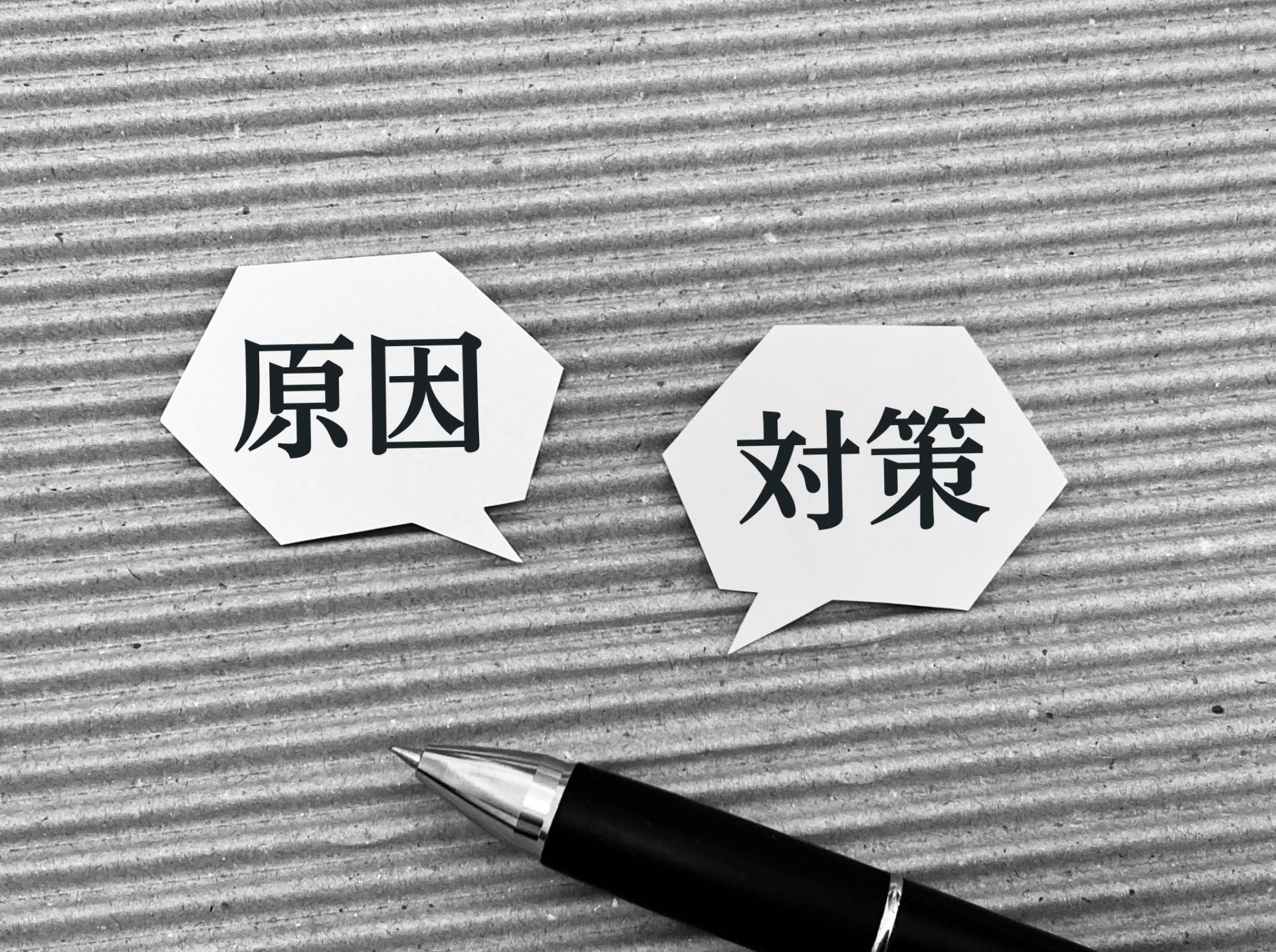
経費精算の振込遅延は、さまざまな要因から発生します。根本的な原因を理解し、適切な対策を講じることで、効率的かつ正確な経費精算プロセスを構築しましょう。
振込が遅れる主な原因

経費精算の振込が遅れる背景には、いくつかの典型的な原因があります。これらについてしっかりと理解することが、効果的な対策の第一歩です。
申請ミス
経費精算の申請段階でのミスは、処理の遅延を引き起こす一般的な原因の一つです。具体的には以下のようなミスが挙げられます。
- 金額の記入ミスや計算間違い
- 領収書の紛失や不備
- 必要書類の添付漏れや記入漏れ
- 申請項目の分類ミス
また、社内で定めた申請期限に遅れることも問題です。特に月末や決算期末の申請遅れは、会計処理の複雑化を招き、結果として振込の遅延につながります。
非効率な処理
多くの企業では、いまだに紙ベースやExcelベースの経費精算プロセスを採用しています。これらの方法では以下のような手間やミスが生じやすく、処理の遅延につながります。
- 手入力による転記ミスやデータ入力の手間
- 申請書の紛失や混在によるトラッキングの難しさ
- 経理システムとの連携不足による二重入力
こうした非効率な処理は、単に時間がかかるだけでなく、エラーの発生確率も高める要因となります。
承認フローの遅延
経費精算は通常、上長や経理部門などによる複数の承認ステップを経て処理されます。このフローにおける以下のような遅延も、振込遅れの大きな原因です。
- 上司の承認の遅れ
- 申請書類のたらい回し
- 複雑すぎる承認ルート
特に管理職が出張や休暇で不在の場合、承認プロセスが停滞してしまうことは珍しくありません。
振込の遅れを解消する方法
経費精算の振込遅延を解消するためには、プロセス全体を見直し、効率化を図る必要があります。以下に効果的な対策を紹介します。
ルールの整備と明文化
経費精算に関するルールを以下のように明確にして、全社で共有することが基本です。
- 経費申請の提出期限を明確に設定する(例:経費発生から2週間以内)
- 承認者の承認期限も設ける(例:申請から3営業日以内)
- 振込予定日を明確に定める(例:毎月15日と末日)
- 高額経費や緊急性の高い経費に対する特別ルールも検討する
これらのルールをマニュアル化し、社内のネットワークで常に閲覧できるようにしておくことで、全社員の理解と協力を得やすくなります。
クラウド経費精算システムの導入
経費精算プロセスを抜本的に改善するには、専用のクラウドシステムの導入が効果的です。これにより、以下のようなメリットが得られます。
- ワークフローの自動化により、申請から承認、経理処理までがスムーズになる
- スマートフォンでの領収書撮影や電子保存により、紙の管理が不要になる
- 承認プロセスの可視化と自動リマインド機能で、遅延を防止できる
- 会計システムとの連携により、二重入力などのミスを避けられる
- 振込データの自動生成や自動仕訳により、処理時間を短縮できる
クラウドシステムは初期投資が必要ですが、長期的には業務効率化とコスト削減につながります。また「電子帳簿保存法」や「インボイス制度」など、最新の法対応が容易になる点も大きなメリットです。
法人カードの活用
法人カードの活用は、社員の立替負担を根本的に減らす方法として非常に効果的です。
- 立替が不要になるため、社員の金銭的・心理的負担が軽減する
- カード明細と連携した経費精算システムで申請の手間も削減できる
- 使用履歴が明確になり、経費の透明性と管理が向上する
法人カードは適切な利用ルールを設けることで、経費精算の効率化だけでなく、経費の可視化や不正防止にも役立ちます。
法人カードについての詳細は、以下の記事をお読みください。
まとめ
経費精算の振込は、社員の不信感を招くとともに、企業の社会的信用力の低下にもつながる重要な問題です。一方、振込のベストなタイミングは、企業規模や業務特性、経理体制によって異なります。重要なのは、明確なルールを設定・周知し、一貫した運用を行うことです。
さらに、クラウド経費精算システムの導入や法人カードの活用も、経費精算の効率化と社員満足度向上に効果的です。クラウド経費精算サービス「Bill One経費」を活用して、経費精算の課題解決を図りましょう。
クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。
全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。
Bill One経費・Bill Oneビジネスカードの特長
- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる
- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合
- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応
- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円
- カードごとの利用限度額設定が可能
- 年会費・発行手数料無料
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。


3分でわかる Bill One経費
立替経費をなくし、月次決算を加速する
クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。



記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部