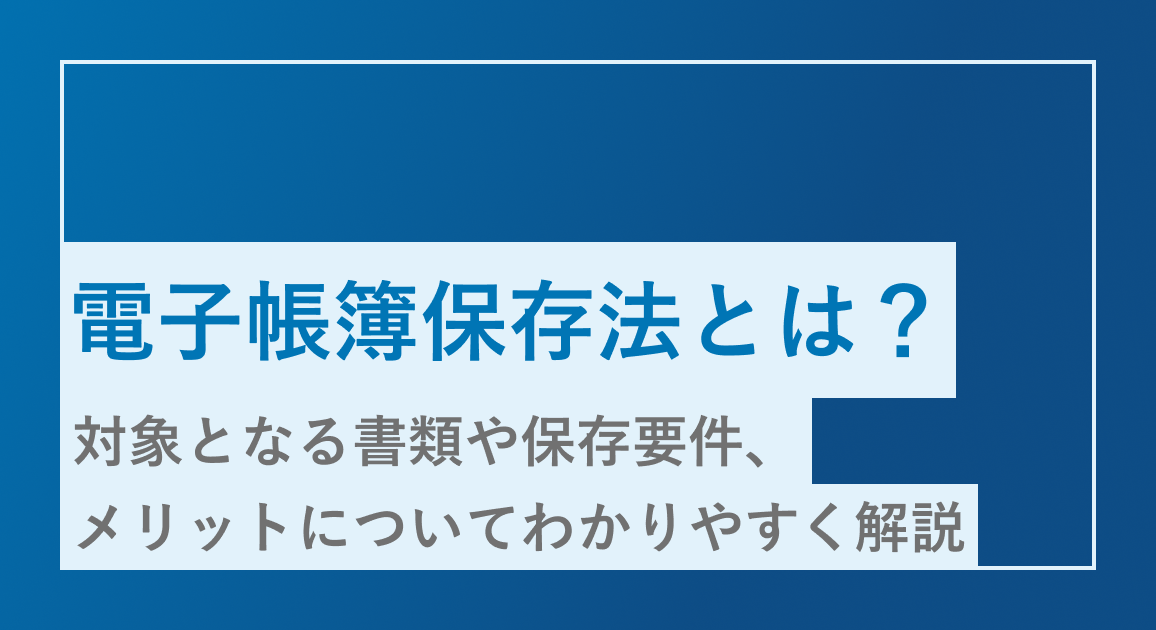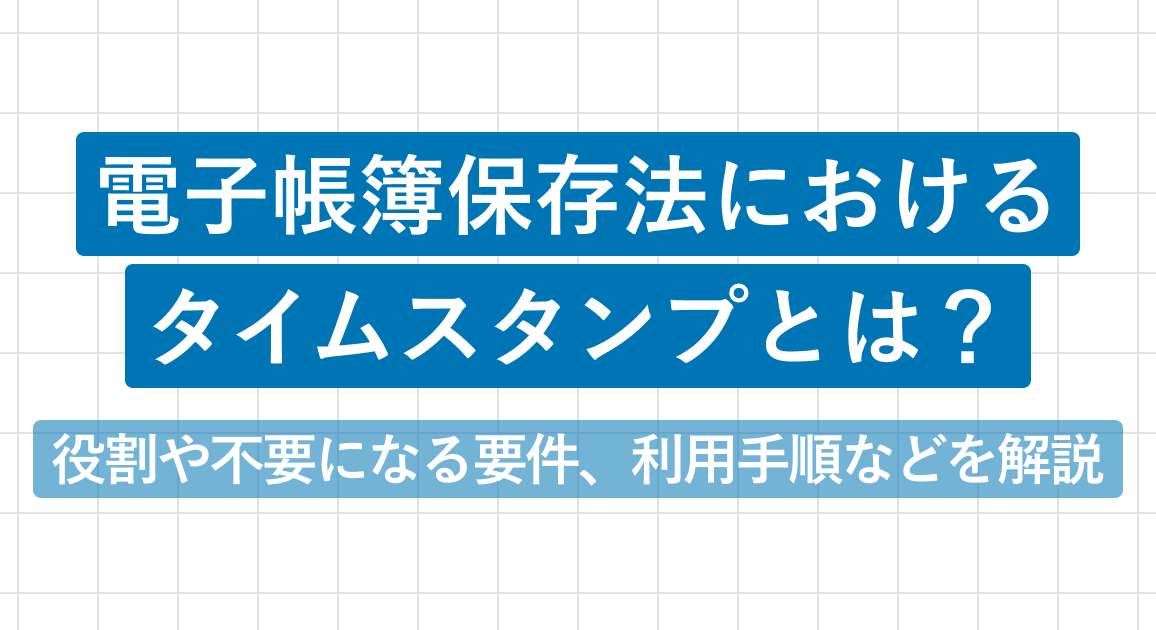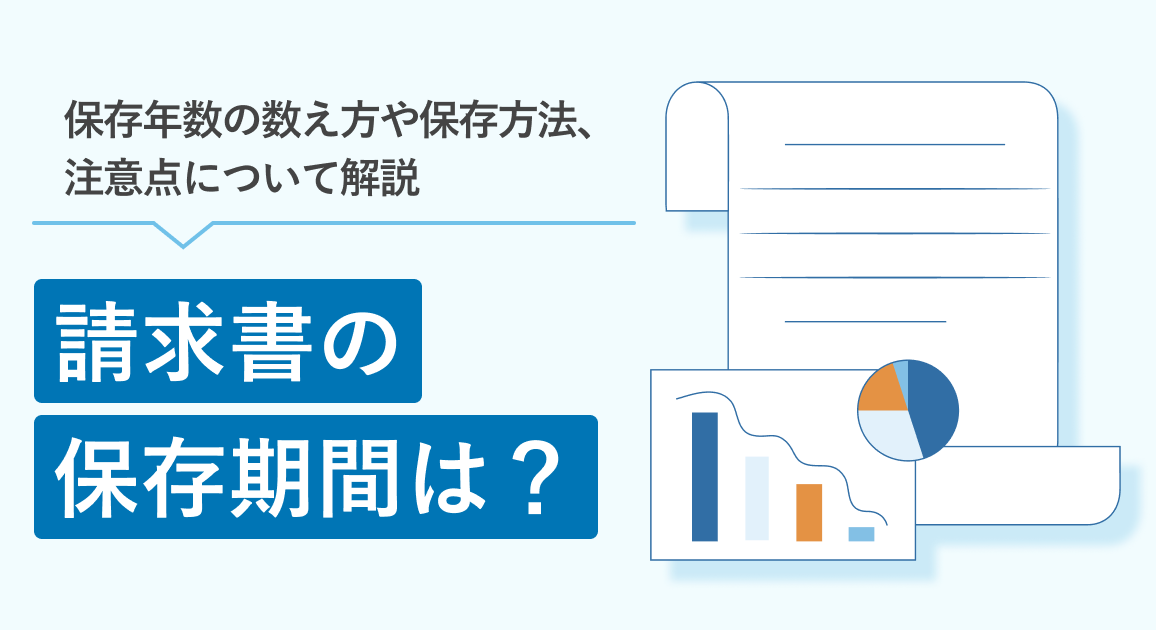- 請求書
電子帳簿保存法に則った請求書控えの保存方法は?発行側が押さえるべきポイントを解説
公開日:
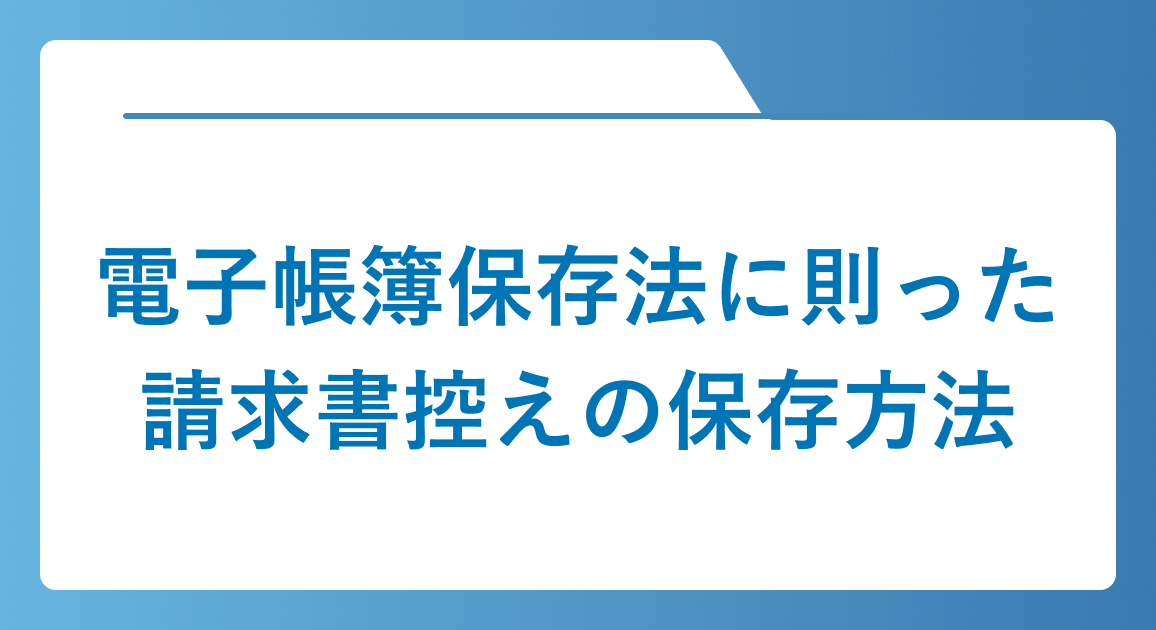
電子帳簿保存法の改正により、多くの企業が請求書の電子化を進めています。その中で、発行済みの請求書の保管方法にお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、電子帳簿保存法における請求書控えの保存方法について解説します。発行側が押さえるべき法律や保管期限、注意点などをわかりやすく整理してまとめました。請求書控えの管理に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
自社で発行した請求書の控えは保存が必要?
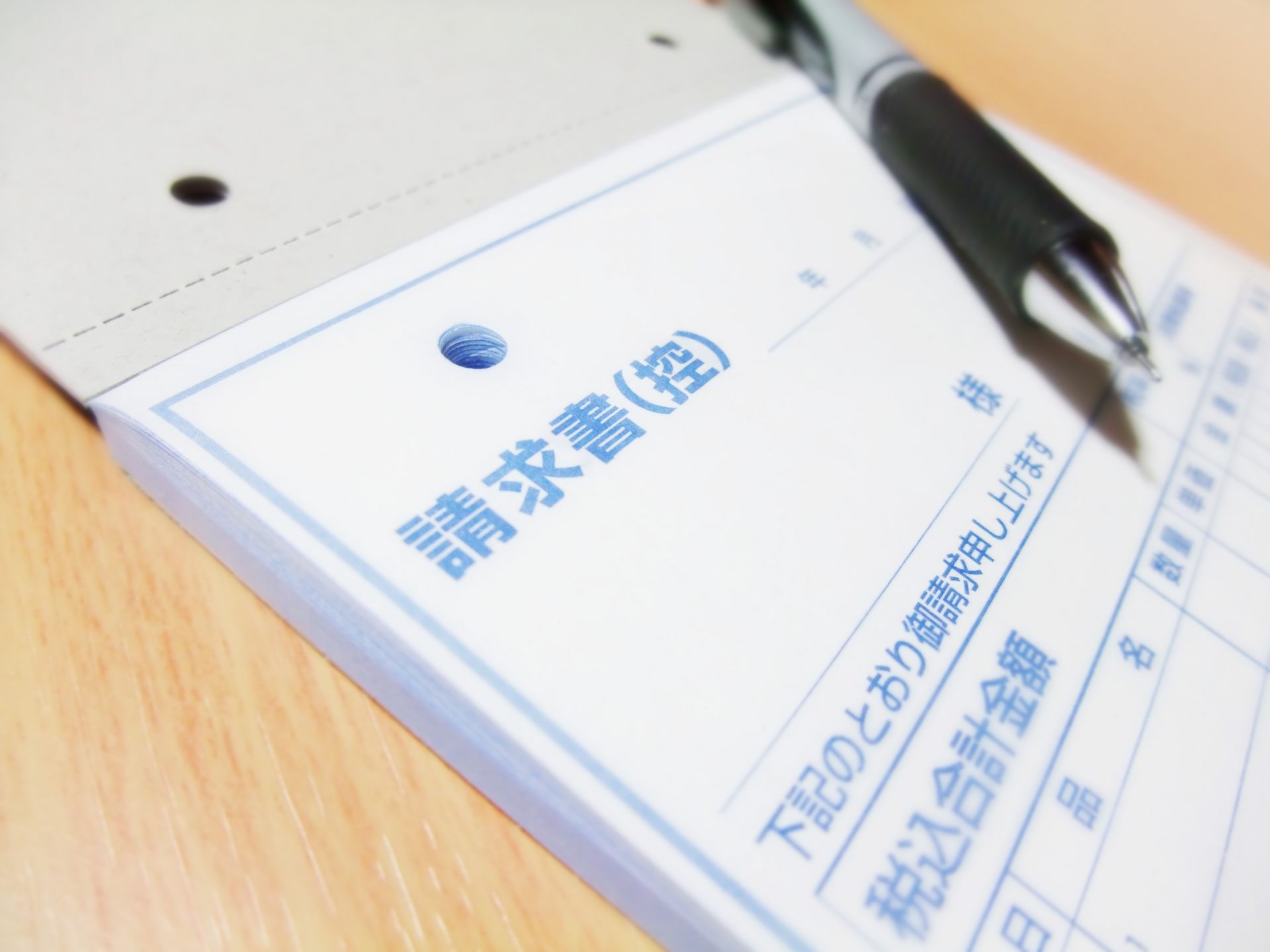
請求書を発行した企業には、請求書の保存義務は法律上明確には定められていません。また、請求書の控えを作成すること自体にも義務はありません。ただし、一度控えを作成した場合には、それが取引の記録として扱われるため、保存義務が生じます。
控えを作成した場合のみ保存義務が生じる
自社で請求書を発行した場合、その控えを作成する義務はありません。ただし、控えを作成した場合は保存義務が発生します。法人は7年間、個人事業主は5年間の保管が必要です。
具体的な保存方法については後述しますが、紙で発行した場合と電子データで発行した場合で方法が異なるため注意が必要です。
適格請求書(インボイス)の控えは7年の保管が必要
控えの保存が適切に行われていないと、税務調査で問題になる可能性もあります。インボイス制度に対応している企業は注意しましょう。
電子帳簿保存法に則った請求書控えの保存方法

続いて、電子帳簿保存法に則った請求書控えの保存方法を見てみましょう。以下では、紙で発行した場合と電子データで発行した場合に分けて解説します。
- 紙で発行した場合
- 電子データで発行した場合
1. 紙で発行した場合
紙で発行した請求書の控えは、紙のまま保存するか、スキャナーで電子化して保存します。
紙のまま保存する場合は、原本またはコピーをファイルに綴じて保管しましょう。見つけやすいように、日付や取引先ごとに分類して整理すると便利です。
一方、スキャナーを使用する際は、電子帳簿保存法におけるスキャナー方式での保存が必要です。
紙で保存する場合はいずれか一方に統一して、適切な方法で行いましょう。
2. 電子データで発行した場合
電子データで発行した請求書は、控えも電子データのまま保存しなければなりません。改正前は、電子データを印刷して保存することも認められていました。しかし、現在は電子帳簿保存法の改正にともない、電子データを紙に印刷して保存することは認められていません。
紙に印刷をしても、もととなる電子データを削除することはできないため、注意しましょう。電子化した請求書の控えの保存要件については、次の項で詳しく解説します。
【電子帳簿保存法】電子化した請求書の控えの保存要件
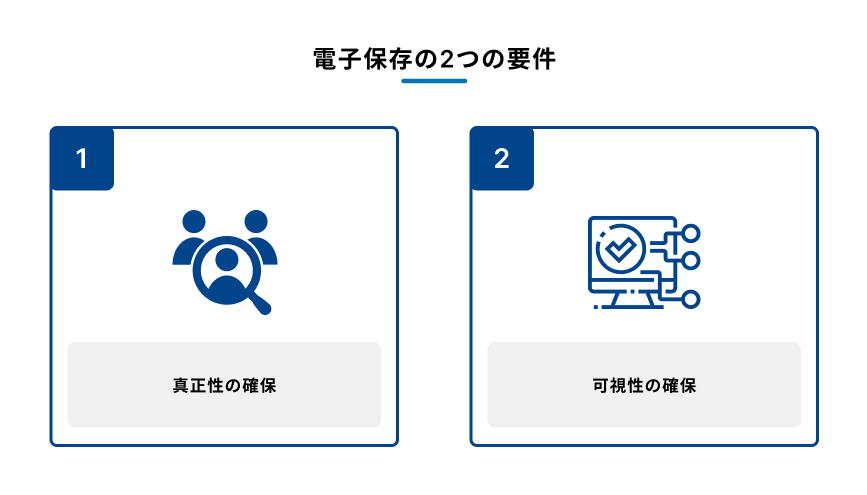
以下では、電子化した請求書の控えの保存要件について解説します。電子化した請求書の控えを保存する場合は、特に真実性の確保と可視性の確保が重要です。
なお、電子帳簿保存法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
真実性の確保
電子化された請求書の控えが改ざんされていないことを証明するためには、「真実性の確保」が重要です。そのためには、次のような措置を講じる必要があります。
- 発行側は、タイムスタンプを付与した上で電子取引データを授受する
- 受取側は、電子取引データの授受後、最長で約2カ月かつ概ね7営業日以内にタイムスタンプを付与する
- 電子取引データの訂正や削除の履歴が確認できるシステム、または訂正・削除ができないシステムを使用する
- 不当な訂正・削除の防止するための社内規程(事務処理規程)を制定し、遵守する
なお、タイムスタンプについては以下の記事もご覧ください。
可視性の確保
「可視性の確保」とは、請求書の控えを誰でもすぐに確認できる状態にしておくことを指します。自社の体制が以下の要件を満たしているか確認しましょう。
- 請求書の内容を確認できるモニターや操作マニュアルを備え付けている
- 自社開発のシステムを使用している場合、システムの概要書を用意している
- 請求書データを日付や金額、取引先で検索・表示できる状態にある
なお、二期前の売上高が5000万円以下の事業者、または請求書データを印刷して、日付や取引先ごと整理がされている場合、税務署のダウンロードの求めに応じられる場合は検索要件の対応は不要です。
請求書の控えの保存期間

法人の場合、請求書の控えの保存期間は7年間です。ただし、請求書の種類や企業の決算月によって、カウントの開始時期が異なります。
- 通常の請求書:確定申告書の「提出期限の翌日」から起算
- 適格請求書:その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から起算し、7年間保存
※ただし例外として、2018年4月以後に発生した欠損金の繰越控除がある場合、保存期間が10年間となります。不安な場合は、念のため10年ほど保存しておくとよいでしょう。
発行した請求書や請求書の控えの保存期間については、以下の記事でも解説しています。
請求書の控えを保管するときの注意点
請求書の控えを保管する際は、以下の点に注意しましょう。
- 入出金の状態ごとに分けて管理する
- 改ざんができない形式で保管する
入出金の状態ごとに分けて管理する
未入金の請求書と入金済みの請求書が混在していると、誤って請求漏れが発生してしまう可能性があります。そのため請求書の控えは、入出金の状態ごとに分けて管理しましょう。
未入金のものと入金済みのものを分けて整理することで、取引先ごとの入金状況を把握しやすくなり、請求漏れの防止につながります。取引先からの入金が確認できるまでの期間は、未入金の請求書控えを日付順に整理して、支払い漏れがないか確認しましょう。
入金済みの請求書控えについては、月ごとや取引先ごとに分類しておくと、後から必要になった際にすぐに取り出せて便利です。
改ざんができない形式で保管する
WordやExcelで作成した請求書は、そのままの状態では金額が改ざんされてしまうリスクがあります。
改ざんを防ぐためには、PDF形式に変換して保存したり、訂正や削除の履歴が残るシステム、あるいは訂正・削除不可のシステムを活用したりしましょう。電子帳簿保存法に対応している請求書システムを活用すれば、データの変更履歴が記録されるため、万が一修正が必要になった場合も過去の記録を正しく確認できます。
電子帳簿保存法の請求書控えに関するよくある質問

最後に、電子帳簿保存法の請求書控えに関するよくある質問をまとめています。
- 請求書の控えは電子データで保存する義務がある?
- 電子帳簿保存法で請求明細書の保存は必要?
- 保存期間が過ぎたら請求書控えを破棄してもよい?
請求書の控えは電子データで保存する義務がある?
適格請求書(インボイス)に関しては、7年間の保存が必要です。請求書を電子データとして取引先に送付した場合、発行側もその控えを電子データのまま保存しなければなりません。
なお、紙で請求書の控えを発行した場合は、紙の状態で保存するか、スキャナーで電子化ことも可能です。
電子帳簿保存法で請求明細書の保存は必要?
請求明細書は、取引における真実性・正当性を証明する「証憑」にあたります。取引先に対して電子データで請求明細書を送付した場合は、電子データでの保存が必要です。
請求書の控えは保存期間が過ぎたらすぐに破棄してもよい?
保存期間が過ぎた請求書の控えについては、データや控えを破棄しても構いません。ただし、正確な保存期間を確かめた上で、税務調査や社内監査の観点から慎重に判断しましょう。税務調査の対象となる書類がある場合や、訴訟の可能性がある取引に関連する請求書の控えについては、保存期間を過ぎても保管しておくと安心です。
まとめ
本記事では、電子帳簿保存法における請求書の控えの保存方法について解説しました。請求書は紙の状態で保存することも可能ですが、保管スペースの確保や管理の手間がかかります。電子化する際には、電子帳簿保存法に対応する必要があります。
請求書業務の負担を軽減するためには、電子帳簿保存法に対応した請求書システムの導入がおすすめです。一口に請求書システムといってもさまざまなサービスがあるため、自社のニーズに合ったものを導入しましょう。
「Bill One」は、請求書の受領・発行などの経理業務を効率化できるサービスです。
請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。
債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。
これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。
Bill One請求書受領の特長
- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する
- 受領した請求書データを一元管理できる
- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック
- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合
- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管
- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている
*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度
Bill One債権管理の特長
- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行
- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理
- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能
- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能
- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結
Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。


3分でわかる
Bill One請求書受領
請求書受領から、月次決算を加速する
クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。




3分でわかる Bill One債権管理
リアルタイム入金消込で、現場を強くする
クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。



記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部